村上春樹「海辺のカフカ」読了。
本作「海辺のカフカ」は、2002年(平成14年)9月に新潮社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は53歳だった。
悩める少年たちの救済の物語
本作「海辺のカフカ」は、父子家庭で育ったマザコン少年の成長物語である。
テーマは、凶悪な少年犯罪を引き起こしかねない、不安定でキレやすい少年の心、つまり「危険な年齢」だ。
(ちなみに『危険な年齢』は、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』が日本で初めて翻訳されたときのタイトルだった)。
物語の背景となっているのは、1990年代後半に社会現象ともなった「キレる少年たち」による数々の凶悪な少年犯罪だろう(<酒鬼薔薇聖斗>による神戸連続児童殺傷事件は1997年)。
「僕にはそうなってしまうときがあるんだ」「自分ではおさえがきかなくなる」と大島さんは言う。「そして人を傷つけてしまうんだね?」(村上春樹「海辺のカフカ」)
著者は、文学を通して、不安定な少年の内面に潜む心の闇をえぐり出すとともに、主人公<田村カフカ>の成長を通して、少年たちの病んだ心を浄化したかったのではないだろうか。
つまり、本作『海辺のカフカ』は、悩める少年たちの救済の物語なのだ。
不安定な家庭環境、児童虐待、不登校。
現代を生きる少年たちの「砂嵐」は混沌としている。
そして、そんなカオスのような「砂嵐」を抜けてこそ、少年は成長していく。
それは、すべての少年たちが通らなければならない、一つの過程だった(少なくとも、かつて15歳を経験した大人たちの多くは、そう考えている)。
幼い自分を捨てて家を出た母親を許すことによって、カフカ少年もまた新しい自分へと成長していく。
「僕にあなたをゆるす資格があるんですか?」彼女は僕の肩に向かって何度かうなずく。「もし怒りや恐怖があなたをさまたげないのなら」(村上春樹「海辺のカフカ」)
少年に対する母親の強い影響力が、ここでは暗示されている。
もしかすると、この物語は、母親世代に向けて書かれた物語だったのかもしれない(あるいは、これから母親になる世代に向けて)。
もう一つの物語の主人公<星野さん>は、不思議な老人<ナカタさん>との共同行為によって、新しい自分を手に入れる。
「なぜおじさんが不思議かってえとだね、おじさんは俺という人間を変えちまったからだ。うん。このたった10日のあいだに、俺は自分がすごく変わっちまったみたいな気がするんだ」(村上春樹「海辺のカフカ」)
「カフカ少年の物語」とパラレルで進行する「星野青年の物語」もまた、かつて不安定な15歳だった青年の、もう一つの成長譚なのである。
星野青年の喪失と再生の物語は、人間がやり直しをするのに年齢は関係がないことを示しているし、再生のきっかけは些細なもので構わないことを暗示している(星野さんの場合は「喫茶店のBGM」だった)。
そして、星野青年とナカタ老人の関係もまた、家族の持つ大切さを暗示している。
つまるところ、この物語は「家族」の重要性を訴えかける小説なのだ。
少年たちの心の闇の原因は「家族」にあり、病んだ少年たちを救済できるのも、また「家族」である。
そう考えると、この物語が本当に伝えたかったことは、家族の関係性が希薄となった現代社会に対する警鐘だったのかもしれない。
著者が伝えたいと考えているメッセージ
「若者たちの成長物語」という主軸ストーリーの周辺に組み込まれているのは、著者が読者へ伝えたいと考えている様々なメッセージである。
無意味な戦争、ジェンダーギャップ、トランスジェンダー、知的障害者、児童虐待、教師による体罰、登校拒否(1999年からは「不登校」と呼ばれている)、行政や警察への不信感。
世の中にはびこる悪への怒りを、著者は『海辺のカフカ』という物語の中に、これでもかというくらいに盛り込んでいる(いささか盛り込み過ぎの感はあって、それがこの物語を難解に感じさせる理由のひとつとなっている)。
「まず第一に、僕は男性じゃありません」と大島さんは宣言する。すべての人々が言葉を失い、沈黙する。僕も息をのみ、となりの大島さんをちらっと見る。「僕は女だ」と大島さんは言う。(村上春樹「海辺のカフカ」)
メッセージは、ストーリーという骨格に付随する肉片みたいなものなので、こうしたメッセージこそが、『海辺のカフカ』という作品の形を構成しているとも言える(仮に、それ自体は主要なテーマではないとしても)。
夏目漱石『坑夫』や『源氏物語』『雨月物語』などの文学、ヴェートーベンの「大公トリオ」、シューベルトのニ長調のソナタなどの音楽を登場させているのは、著者の芸術観の発露。
もっとも、トランスジェンダーを採りあげる一方で、女子大生による売春行為を、男性目線から肯定的に描くなど、性差別に対する姿勢は安定していない。
15分後に女が現れた。カーネル・サンダーズが言ったとおり、素晴らしい体つきの美人だった。ぴったりとした黒いミニのドレスを着て、黒いハイヒールを履いて、黒いエナメルの小さなショルダーバッグを肩にかけていた。(村上春樹「海辺のカフカ」)
少年期の性欲を露骨に描いているのは、村上春樹的世界観としては、特に珍しいことではないんだけれど。
家族への期待をテーマとする一方で、学校に対する期待がまったくないのもまた、村上春樹の学校観を示したものだろう。
『海辺のカフカ』は現代の民話
僕は、この小説を「現代の民話」として楽しく読んだ。
ギリシャ悲劇『オイディプス王』の引用など、西洋的な色彩が濃く、心理学的なアプローチから考察したくなるが、実際には極めて日本的な物語であって、むしろ、現代版の「日本昔ばなし」と言っていいくらいだ。
例えば、不思議な老人・ナカタさんは、民話に登場する神様的な存在で、知的障害者が不可思議な能力を持つという発想自体、既に民話的である(猫と会話をするところなんて、いかにも昔話)。
作品中で、ナカタさんは、カフカ少年の内面を反映した神様としての役割を果たしている。
星野青年を援助してくれる<カーネル・サンダーズ>は神様の使いで、「入り口の石」が神社の祠の中にあるのも、かなり民話的な作りだ。
そもそも「石」に不思議な力を持たせるのは、日本の伝説では古来から見られるもので、星野青年が力を振り絞って「入り口の石」をひっくり返して入り口を閉めるというくだりは、『古事記』の「天の岩戸」を思い起こさせて楽しい。
森から戻るカフカ少年に、兵隊が「目的地に着くまで、君は二度とうしろをふりかえっちゃいけないよ」と声をかけるのも、神話からの引用(いわゆる「見るなのタブー」。黄泉の国でイザナギは振り返ってしまった。世界中に類似の伝承がある)。
佐伯さんの若き時代のヒット曲「海辺のカフカ」は、物語の未来を暗示する「わらべ唄」であり、歌が物語を暗示する手法も民話に由来するものだろう。
なお、父親が息子に呪いをかけるという基本設定は、ギリシャの古い戯曲からの引用である。
「君はいつか君の手でお父さんを殺し、いつかお母さんと交わることになる─そうお父さんが言ったわけだね」僕は何度かうなずく。「それはオイディプス王が受けた予言とまったく同じだ。そのことはもちろん君にはわかっているんだろうね」(村上春樹「海辺のカフカ」)
一つ一つ拾い上げていくとキリがないが、本作『海辺のカフカ』では、日本的民話が西洋文化のフィルターによって、巧妙にカモフラージュされている。
神話や民話に精通していれば、きっともっと楽しめるんだろうなあ。
当然だが、著者は入念に情報収集をした上で、ネタバレすることがないよう慎重に民話的モチーフを用いていると思われる。
カフカ少年の潜在意識を具象化した物語
本作『海辺のカフカ』は、随所に謎の多い作品だが、ミステリー小説のように、伏線を回収して謎解きをするのは難しいだろう。
この小説が「難解だ」「意味が分からない」と評されるのは、物事を理屈で整理しようとするからである。
昔話が理屈を超越しているように、この作品にも論理性はないので、伏線を回収することはできない。
というか、そもそも最初から伏線なんかないんだから、論理性を構築しようとする作業そのものが無意味なのだ。
僕は言う、「僕は夢をとおして父を殺したのかもしれない。とくべつな夢の回路みたいなのをとおって、父を殺しに行ったのかもしれない」(村上春樹「海辺のカフカ」)
あるのは、ワクワクするようなストーリー展開と、著者の明確なメッセージのみ。
むしろ、この小説は、著者による種々のメッセージを発信するために、複雑怪奇なストーリーによって構成されているのだ。
この小説が、海外でも人気を得たのは、本質的に日本的な文学作品だったから。
外国の読者にとって『海辺のカフカ』の独創性は「西洋的ではないところ」にあった
空から魚やヒルが降ってきたりするところに、意味性や象徴性なんかないし、メタファーでさえない(心理学者は意味を見出したがるかもしれないが)。
神の使いである<カーネル・サンダーズ>は「赤衣の童子」でもよかった(宮沢賢治の『オツベルと象』に登場してくる)。
わざわざ<カーネル・サンダーズ>であるのは、西洋的なフィルターで飾る必要があったからだ。
ちなみに、ナカタ老人に殺害された<ジョニー・ウォーカー>の本性である彫刻家<田村浩一>の芸術的テーマは「人間の潜在意識を具象化するというもの」とあり、これは、村上春樹の文学作品に共通するテーマでもある。
つまり、『海辺のカフカ』もまた、カフカ少年の潜在意識を具象化した物語だったのだ。
夢も森もみんな、カフカ少年の潜在意識を具象化したものである。
<カラスと呼ばれる少年>は、もちろんカフカ少年自身だが(いわゆる「メタ認知」)、森の中に現われる<二人の兵隊>もまた、カフカ少年の潜在意識に存在するカフカ少年自身だろう。
ここにある森は結局のところ、僕自身の一部なんじゃないか──僕はあるときからそういう見かたをするようになる。僕は自分自身の内側を旅しているのだ。(村上春樹「海辺のカフカ」)
<二人の兵隊>は、登場するタイミングといい、役回りといい、いかにも「羊男」的存在なので笑ってしまった(これが、村上春樹文学の予定調和である)。
まあ、それを言えば<さくら>は、いかにも「ユミヨシさん」的存在だけれども。
心の中に残る「遠い部屋」(「ずっと昔に失われてしまった懐かしい部屋」)は、トルーマン・カポーティ『遠い声 遠い部屋』へのオマージュ。
「あなたはきっと強くなりたいのね」「強くならないと生き残っていけないんです、とくに僕の場合には」は、レイモンド・チャンドラー『プレイバック』へのオマージュだろう(「強くなければ生きていけない。優しくなければ生きている資格がない」)。
まとめ
本作『海辺のカフカ』は、大人目線によって書かれた大人のための少年文学である。
15歳の少年が主人公だが、その主人公像は、古い倫理観を有する大人によって描かれた、旧式の少年像という感じが強い。
それは、この作品が実際には、大人に向けて書かれた物語であるからだろう。
かつて15歳だったすべての大人たちに向けて。
そして、現在の15歳を守る役割は、現代の大人たちに託された、重大な役割なのだ。
書名:海辺のカフカ
著者:村上春樹
発行:2014/12/20
出版社:新潮文庫

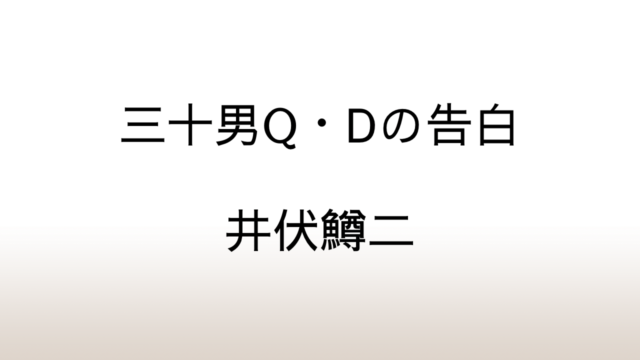

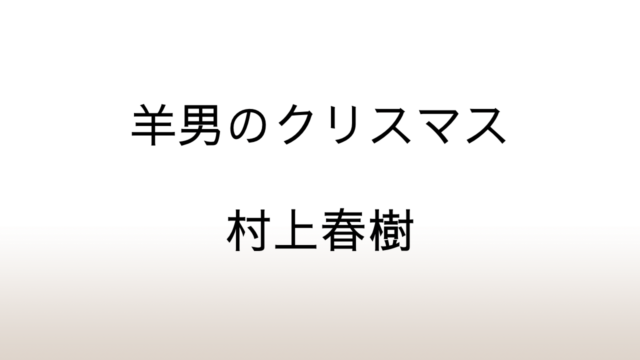
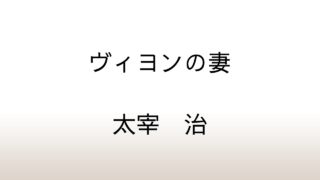
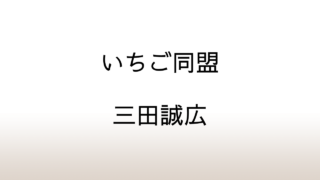
003-150x150.jpg)




