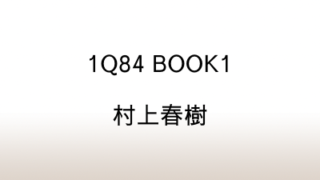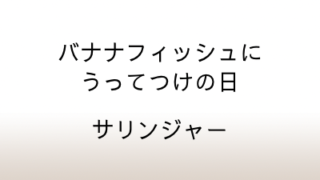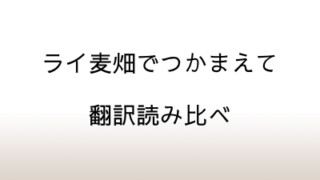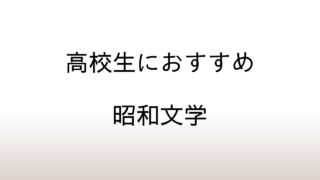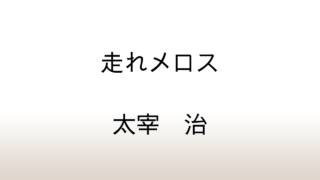井伏鱒二『人と人影』読了。
『人と人影』は、1972年(昭和47年)に毎日新聞社から刊行された随筆集である。
この年、著者は74歳だった。
1990年(平成2年)に講談社文芸文庫に入った。
庄野潤三や河盛好藏とウバメ樫の思い出
本書『人と人影』は、大きく三つの章から構成されている。
文壇仲間を題材とした「人と人影」、自然の鳥や草花を題材とした「小品博物誌」、そして、旅行と釣りを題材とした「旅と釣」である。
他の随筆集で読んだことのある作品も含まれているから、あるいは、精選随筆集だったのかもしれない。
どの随筆にも、井伏さんらしい味わいがあって楽しいが、昭和文学好きとしては、多くの文士の横顔を知ることができる「人と人影」はおすすめ。
仲良しの庄野潤三が登場するのは「ウバメ樫」という作品で、京都観光をしているとき、第三高等学校(現在の京都大学)の横を通ったとき、見事なウバメ樫の生け垣を見つけた。
それを卒業生の河盛好藏に言うと、河盛さんは「そんな生垣があったかしら」と、たよりない返事をする。
そして、生島遼一に聞いてみようとか、大宅壮一に聞いたらいいとか、それより河野与一の方がいいとか、そんな助言をしてくれたという話である。
ビンチョウ炭というのは、ウバメ樫で焼いた炭のことで、谷崎精二を囲む会の会場だった湯島の鳥屋で、このビンチョウ炭が出た。
井伏さんは、小林龍雄と二人で、ビンチョウ炭を見るために、再びこの鳥屋を訪れている。
この随筆の最後に出てくるのが、庄野潤三である。
小田急線の庄野潤三君は数年前に十本の苗木を庭に植え、玄関のわきに植えた一本は六尺以上の背丈になったと云っていた。しかしその苗木を植えて三年目に、庄野君自身の生れた大阪帝塚山の家の生垣と同じ木であったと漸く気がついたそうだ。(井伏鱒二「ウバメ樫」)
この話は、庄野さんの随筆でも読んだような気がする。
「小品博物誌」では「におい」がよかった。
子どもの頃の「におい」の記憶について綴ったものだが、最後に田山花袋が登場している。
においに敏感な人は、鼻が低くて先の方が尖っているという説をなす人がいます。だから小説「蒲団」を書いた田山花袋も高くない鼻の先がとんがっていて、こんな鼻は嗅覚にこだわる傾向が強いと云うのです。「蒲団」の主人公は、女の坐っていた蒲団を嗅いで興奮しています。不幸にして、私の鼻もどことなく田山さんに似ています。(井伏鱒二「におい」)
なんとも、ユーモアのある話だと思った。
太宰治は「人間は死ぬときが大事だ」と言った
「旅と釣」では、名作「釣人」が収録されている。
佐藤垢石との思い出を中心に書かれているが、太宰治夫妻や亀井勝一郎と釣りに行ったとき、伊豆の釣り宿で洪水に遭った話も出てくる。
太宰君はもう死ぬ覚悟だから「人間は死ぬときが大事だ」と云って、細君に向い「あのね、失礼して、ズロースをはいて来なさい。死ぬときが大事です」と云った。細君の方は、ただ俯向くだけで、不断と同じようにきちんとかしこまっていた。(井伏鱒二「釣人」)
このとき、水は既に宿の一階を浸していて、泊り客は二階へ避難していたのだから、ズロースなんかを探しに行く余裕なんてあるはずもないが、「人間は死ぬときが大事だ」というのは、いかにも太宰らしい言葉だと思った。
ところで、1990年刊行の講談社文芸文庫は、なんだか贅沢な作りをしている。
巻末に「人と作品」があって、井伏さんのスナップ写真がたくさん収録されている。
最近の文芸文庫では、こんなふうに写真を入れることは、あまりないのではないだろうか。
「年譜」を読むと、1990年当時の井伏さんは92歳。
作家本人が、まだ存命中だったのだ。
書名:人と人影
著者:井伏鱒二
発行:1990/2/10
出版社:講談社文芸文庫

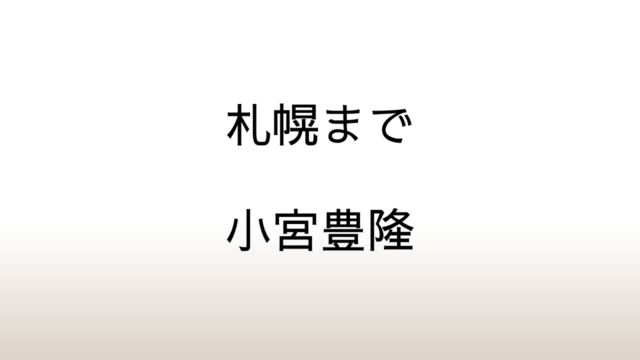
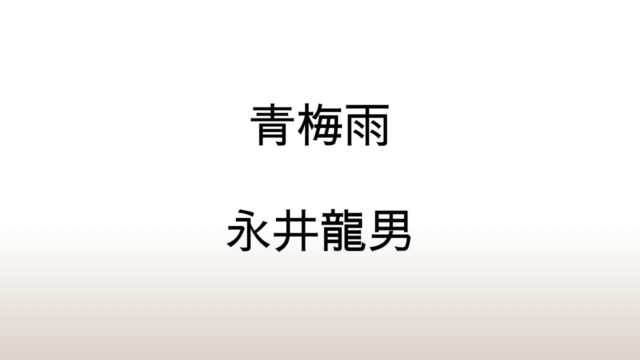
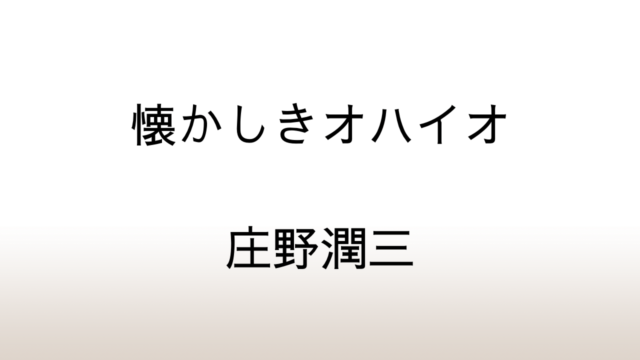
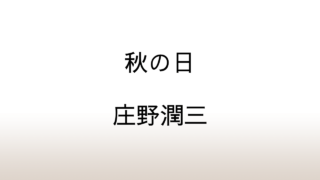
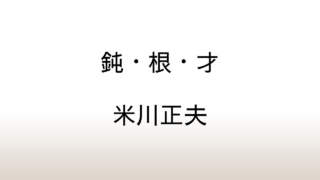
003-150x150.jpg)