村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」読了。
本作「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」は、1985年(昭和60年)6月に新潮社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は36歳だった。
第21回「谷崎潤一郎賞」受賞。
単行本の箱には「純文学書下ろし特別作品」の文字があり、「笑い・冒険・思想の三重奏」「小説の面白さが横溢した哀しくて楽しい恐怖小説」と帯に記されている。
心の傷痕からの逃避を願う男の物語
本作『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の鍵となっているのはカタツムリだ。
「ヨーロッパではかたつむりは神話的な意味を持っているのよ」と彼女は言った。「殻は暗黒世界を意味し、かたつむりが殻から出ることは陽光の到来を意味するの。だから人々はかたつむりを見ると本能的に殻をたたいてかたつむりを外に出そうとするのね。やったことある?」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
やみくろの支配する地底世界や夢読みが生きる夜の図書館を暗黒世界とするなら、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、まさしく、かたつむり的な構造を持った物語ということになる。
物語の主人公は、殻の外と中を行ったり来たりしなければならない。
「彼らは何をあれほどに憎んでいるんだろう?」と私は彼女に訊ねてみた。「光のある世界とそこに住む者をよ」と彼女は言った。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
つまり、世の中は、一匹のかたつむりみたいに、見えている部分と見えていない部分とで構成されているということで、そこに、複雑な世界の光と闇が見える。
さらに、かたつむりは、物語世界であると同時に、物語の主人公でもある。
「ハードボイルド・ワンダーランド」において、「組織(システム)」所属の「計算士」である主人公は、「組織(システム)」と「工場(ファクトリー)」との情報戦争に巻き込まれて、意識の核の中に自我を閉じ込められてしまう。
かつて「組織(システム)」の研究者だった時代に、シャフリング技術を開発した老博士によって映像化された主人公の意識の核(潜在意識=ブラックボックス)は「世界の終り」と名付けられた。
この作品では、現実世界の物語である「ハードボイルド・ワンダーランド」と(充分に非現実的だが)、主人公が意識の核の中で無意識的に作り出した物語である「世界の終り」という二つの物語が、交互に語られていく。
「(略)あんたは自分の意識の底にある象工場に下りていって自分の手で象を作っておったわけです。それも自分の知らんうちにですな」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
主人公が生きている世界と、主人公の心の中の世界はパラレルに展開していくが、現実世界の主人公は、脳回路のジャクションの誤作動によって、自身の意識の核の中(つまり「世界の終り」という物語)に閉じ込められてしまった。
これは、殻の外と中というふたつの世界を持つカタツムリが、殻の中に閉じ籠ったままで生きていくことに他ならない。
主人公の意識の核の中で、ほぼパーフェクトとも言える物語が創作されていたことについて、老博士は、主人公のパーソナリティを指摘している。
「いろんな要因があるです」と博士は言った。「幼児体験・家庭環境・エゴの過剰な客体化・罪悪感……とくにあんたには極端に自己の殻を守ろうとする性向がある。違いますかな?」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
つまり、この物語は、35歳の中年男性が、自分の殻の中(意識の核)に閉じ籠っていくまでの過程を描いた物語ということになる。
それでは、主人公は、どうして、自分の殻の中に閉じ籠ってしまわなくてはならなかったのだろうか。
その理由は、彼自身の心の中(つまり「世界の終り」という物語)に示されている。
「ここはとても静かな街よ」と彼女は言った。「だからもしあなたが静けさを求めてここに来たんだとしたら、あなたはきっとここが気に入ると思うわ」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
「ここ」は壁に囲まれた静かな街で、主人公の心の中だけにある、主人公自身が作り出した街だ。
街に閉じ込められそうになった主人公は、影と一緒に脱出を試みるが、土壇場になって、街に残ることを決意する。
「僕には僕の責任があるんだ」と僕は言った。「僕は自分の勝手に作りだした人々や世界をあとに放りだして行ってしまうわけにはいかないんだ。君には悪いと思うよ。本当に悪いと思うし、君と別れるのはつらい。でも僕は自分がやったことの責任を果たさなくちゃならないんだ。ここは僕自身の世界なんだ。壁は僕自身を囲む壁で、川は僕自身の中を流れる川で、煙は僕自身を焼く煙なんだ」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
ここで「君」と呼ばれている影は、主人公の自我であり、現実世界(つまり「ハードボイルド・ワンダーランド」の物語)を生きる主人公自身でもある。
主人公が、「街」に残る決心をしたのは、夢読みの仕事を手伝う図書館の女の子に恋をしたからで、この女の子の存在が、「世界の終り」では重要な鍵となっている。
図書館の女の子は、主人公が作りだした、主人公の心の中でだけ生きていくことのできる存在だが、主人公の意識の核は、この女の子に強い執着を見せる。
そもそも、主人公が影と別れて「街」に残る選択をしたのは、自分自身(つまり自我)と距離を置きたいという気持ちがあったからだ。
「いや、迷ってるんだ。本当に迷ってる」と僕は言った。「まずもとどおりの僕自身というものが思い出せない。果たしてそれは帰るだけの価値のある世界で、戻るだけの価値のある僕自身なんだろうか?」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
自分自身の自我に、「それは帰るだけの価値のある世界で、戻るだけの価値のある僕自身なんだろうか?」と疑問を持たなければならない理由が、主人公にはあった。
獣たち(一角獣)を殺すのは、冬の寒さでも食料の不足でもなく「街が押しつけた自我の重みなんだ」という影の言葉を読むと、主人公の心には、そもそも何らかの傷痕(つまりトラウマ)があったと考えることができる。
その心の傷痕に関係しているものが、図書館の女の子だったのではないだろうか。
それから僕は目を閉じたまま図書館の女の子について考えてみた。しかし彼女について考えれば考えるほど、僕の中の喪失感は深まっていった。それがどこからどのようにして生じるのか、僕には見定めることができなかったが、純粋な喪失感であることはたしかだった。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
つまり、この物語は、主人公が抱える喪失感をテーマにした物語だった、ということになる。
そして、その喪失感の救済こそが、この物語が求めるねらい(作品の意図)なのだ。
しかし、自分自身の喪失感を、主人公は把握できないでいる。
いったい私は何を失ったのだろう? と私は頭を搔きながら考えてみた。たしかに私はいろんなものを失っていた。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
物語の案内役として機能する太った娘は、主人公の喪失感を敏感に感じ取っていた(主人公が持つ課題の整理も含めて、彼女は優秀な交通整理役を果たしている)。
「あなたは愛する人をなくしたことがある?」「何度かね」「それでいまはひとりぼっちなのね?」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
主人公の喪失感を埋めるために必要だったのが「世界の終り」という(主人公の無意識の中にある架空の)物語だった。
「しかしあんたはその世界で、あんたが失ったものをとりもどすことができるでしょう。あんたの失ったものや、失いつつあるものを」「僕の失ったもの?」「そうです」と博士は言った。「あんたが失ったもののすべてをです。それはそこにあるのです」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
逆に言うと、「世界の終り」で主人公の得たものこそが、主人公の失ったものである、という仮説が成り立つ。
そして、「世界の終り」で主人公が手に入れたものは、紛れもなく、図書館の女の子の心だったのだ。
おそらくその喪失感は僕の失われた記憶とどこかで結びついているのに違いないと僕は推測した。僕の記憶が彼女の何かを求めているのに、僕自身がそれに応えることができず、そのずれが僕の心に救いがたい空白を残していくのだろう。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
「ハードボイルド・ワンダーランド」の太った娘は、主人公とセックスすることを望んでいるが、主人公は「本能とか直感とか、それに近いもの」に遮られて、彼女とセックスをすることができない。
太った娘も図書館の女の子も、おそらく同じ17歳で、そのことが、無意識的に主人公の行動を制限していたのだ。
「君の影のことを話してほしいな」と僕は言った。「ひょっとして僕が古い世界で出会ったのは君の影なのかもしれない」「ええ、そうね。私も最初にそのことを思ったの。あなたが私に会ったことがあるかもしれないって言ったときにね」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
四つのときに引き離された彼女の影は、彼女が17歳のときに戻ってきて「街」で死んだ。
影を失った彼女は、主人公の心の中でだけ生き続けている。
「あなたが言っているのはたぶん心のことですね?」老人は肯いた。「僕に心があり彼女に心がないから、それで僕がどれだけ彼女を愛しても何も得るところがないということですか?」「そうだ」と老人は言った。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
おそらく現実世界で主人公には、17歳の女の子を失った過去があるのだろう。
そして、その記憶は彼自身の中で封印されたが、意識の核の中で「世界の終り」と呼ばれる物語世界を創造してしまった。
そこに自我はなく、誰もが平穏に暮らしている。
なぜなら、主人公は、彼自身の自我にトラウマ(つまり後悔)を抱えていたからだ。
「たぶんそれがあなた自身の問題でもあるからじゃないかと私は思うの」と彼女は言った。「僕自身の問題?」「あなたはもっと心を開かなくちゃいけないと私は思うの。心のことはよくわからないけれど、私にはそれが固く心を閉じてしまっているように感じられるの。古い夢があなたに読まれるのを求めているように、あなた自身も古い夢を求めているはずよ」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
簡単に言えば、本作『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、心の傷痕からの逃避を願った男の物語ということになる。
そして、男の逃げ場所(あるいは避難場所)は、彼自身の心の中にあった。
つまり、意識の核の中にある物語をさらけ出すことで、主人公は過去の傷痕からの脱却を図ろうとしていたのだ。
傷だらけの自我を封印して、新しい自分を生きる
難しい精神分析を抜きにして、この物語は、心の中に潜む膿を洗い流すような小説として読むことができる。
「海から打ちあげられたものはどんなものでも不思議に浄化されているんだ。使いようのないがらくたばかりだけれど、みんな清潔なんだ。汚くて触ることのできないようなものは何ひとつとしてない。海というのは特殊なものなんだ」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
この作品の中で「海」として機能しているものが、つまり、この物語そのものである。
主人公は(つまり、おそらく著者は)、心の中の傷痕を清潔な物語として浄化し、自分自身の心を癒そうとしていたのだろう。
だからこそ、この物語は、不思議に心を癒してくれる作品となっている。
「ねえ」と太った娘が言った。「怖がらないでね。あなたがもし永久に失われてしまったとしても、私は死ぬまであなたのことを覚えているから。私の心の中からはあなたは失われないのよ。そのことだけは忘れないで」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
太った娘は、主人公の心の中に生きる図書館の女の子を具現化した存在だ。
「私の心の中からはあなたは失われないのよ」の一言が、おそらく主人公には必要だったのだ(過去の傷痕から救済されるためにも)。
彼女は、おそらく17歳で死んでいる(「あなたは愛する人をなくしたことがある?」)。
私は彼女が服を着ているあいだ居間のソファーに座って朝刊を読んだ。タクシーの運転手が運転中に心臓発作を起して陸橋の橋桁につっこみ、死んでいた。客は三十二歳の女性と四歳の女の子で、どちらも重傷を負った。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
「三十二歳の女性と四歳の女の子」は、「世界の終り」に登場する人々を暗示的に示したものだったのかもしれない。
そして、この物語が、カタツムリ的だと感じた、もうひとつの理由。
「洗濯屋の前でかたつむりを見たんだ」と私は言った。「秋にかたつむりがいるなんて知らなかった」(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
知られざる存在、それは、この世界で生きる我々自身のことでもある。
しかし誰も私がひと晩かけて地底の迷路をさまよい歩いていることは知らない。氷水の中を泳いだり、蛭にたっぷりと血を吸われたり、腹の傷の痛みを抱えて苦しんでいることも知らない。私の現実世界があと二十八時間と四十二分のうちに終ろうとしていることも知らない。TVのニュース番組では誰もそんなことを教えてくれないからだ。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
教えてくれなかったのは、この世界のどこかで、17歳の女の子が死んだことも同じだっただろう。
そして、彼女は世の中から忘れられていく。
その虚無感を描いたものが、本作『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』だったということもできる。
それでも、我々は、現実的に存在しているのだ(たとえ、世の中的には知られざるような、ちっぽけな存在であったとしても)。
この長篇小説を象徴する文章が、終わり近くに出てきた。
ボブ・ディランは『風に吹かれて』を唄っていた。私はその唄を聴きながら、かたつむりや爪切りやすずきのバター・クリーム煮やシェーヴィング・クリームのことを考えてみた。世界はあらゆる形の啓示に充ちているのだ。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
爪切りは「一生もの」であり、すずきのバター・クリーム煮は、永遠に変わらないものを象徴し、シェーヴィング・クリームは、はかない人生を意味している。
そのすべては、「風に吹かれて」いるのだ。
「メリー・ゴー・ラウンドの馬に乗ってデッドヒートをやっているような」僕たちの世界(「みんな昔に一度起ったことなのよ。ただぐるぐるとまわっているだけ。そうでしょ?」)。
心の傷痕を抱えた主人公は、しかし、そんな現実世界を受け容れてみせる。
しかしもう一度私が私の人生をやりなおせるとしても、私はやはり同じような人生を辿るだろうという気がした。何故ならそれが──その失いつづける人生が──私自身だからだ。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
おそらく主人公は、傷だらけの自我(喪失感を抱えた意識=つまりトラウマ)を、「世界の終り」という意識の核の中に封印して、新しい自分自身を生きていくはずだ。
そういう意味で、この作品は、救済の物語として読むことができるのである。
それにしても、この作品で引用されている文学作品は多い。
既成の文学作品がメタファーとしての役割を担うものだとしたら、この物語は、膨大なメタファーに充ち溢れている。
ウィリアム・シェイクスピア(「今年死ねば来年はもう死なないのだ」)、ツルゲーネフの『ルージン』と『春の水』、スタンダールの『赤と黒』、「世界が不要物で埋まって廃墟と化してしまう近未来のSF小説」、サマセット・モームの『剃刀の刃』、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』、J・G・バラード(大雨が一か月降り続く)、バルザックの『農民』(「ねえ、フランスにもかわうそはいたのね」)、『オズの魔法使い』、『緑色革命』、『異邦人』(ムルソーの「僕のせいじゃない」という口癖)、フローベール、トマス・ハーディー、ジョン・アップダイク(秋に最初に着るセーターの匂いの話)、J・D・サリンジャー(「どうして離婚したの?」「旅行するとき電車の窓側の席に座れないから」)、『カラマーゾフの兄弟』(「ねえコーリャ、君は将来とても不幸な人間になるよ。しかしぜんたいとしては人生を祝福しなさい」)、ジョン・コンラッドの『ロード・ジム』。
こうした文学作品の引用が、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という作品を、実に立体的で、奥の深い物語として仕上げているのは確かだ(そのすべてを理解できるかどうかは別として)。
おそらく、1985年(昭和60年)当時に村上春樹が持っていたもののすべてが、この小説に注がれているはずだ。
「どうして結婚しないのかね」ゾーイーは楽な姿勢に戻ると、ズボンの尻のポケットから畳んだリネンのハンケチを取り出し、さっと振ってひろげると、鼻を、一回、二回、三回、かんだ。彼はそのハンケチをしまいながら言った。「それはね、ぼくが汽車に乗るのが好きだからさ。結婚したらもう、窓側の席に坐れないだろう」(J.D.サリンジャー「フラニーとゾーイー」野崎孝・訳)
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』こそ、村上春樹の代表作品だと考えている人は少なくない。
たぶんだけれど、この作品には、著者自身も強い思い入れを持っているのではないだろうか。
テーマにもプロットにもストーリーにも文章にも、それだけの緊張感がある。
私はビング・クロスビーの唄にあわせて『ダニー・ボーイ』を唄った。「その唄が好きなの?」「好きだよ」と私は言った。(村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」)
夏は過ぎ、薔薇は枯れ、あなたは行ってしまう──。
「ダニー・ボーイ」も、また、喪失の歌だった。
書名:世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド
著者:村上春樹
発行:1988/10/05
出版社:新潮文庫

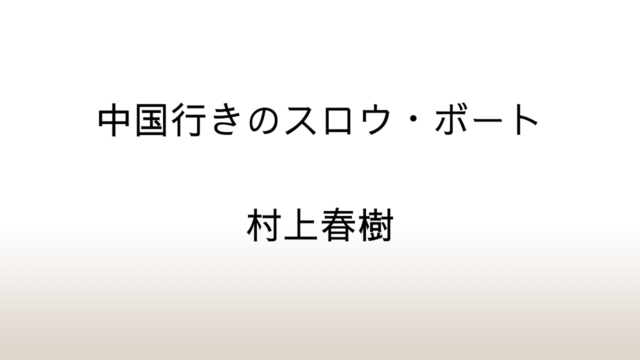
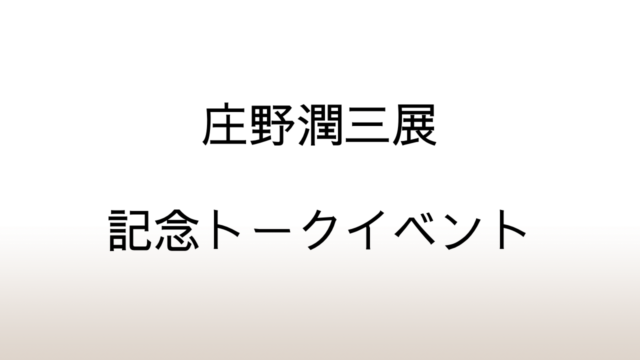

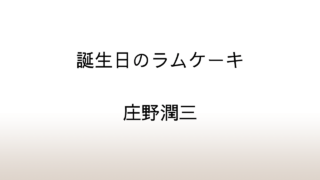

003-150x150.jpg)




