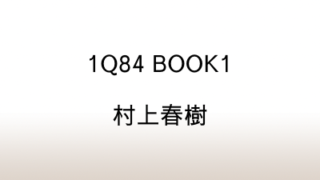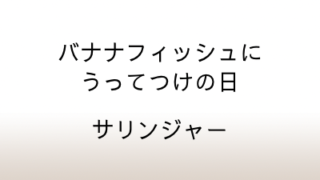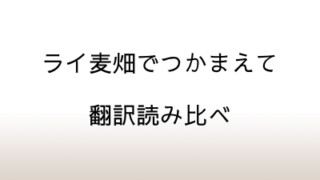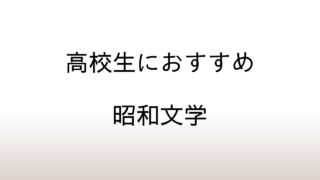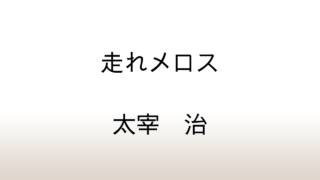小沼丹「埴輪の馬」読了。
本作「埴輪の馬」は、1976年(昭和51年)3月『文芸』に発表された短編小説である。
この年、著者は58歳だった。
作品集としては、1986年(昭和61年)9月に講談社から刊行された『埴輪の馬』に収録されている。
井伏鱒二と旅行した日の思い出
本作「埴輪の馬」は、埴輪の馬を買おうと突然に思いたった<僕>が、埼玉県の<弘光寺>まで出かける話だが、「埴輪の馬」そのものは重要なテーマではない。
かつて、仲間たちと弘光寺へ出かけたことを思い出すというのが、この物語の大きな柱となっている。
それは、もう二十五六年前のことで、小説家の<清水町先生>と一緒に総勢五人で、上野から汽車に乗って行った。
<清水町先生>とあるのは、もちろん井伏鱒二のことで、この小説は、井伏鱒二と旅をしたときの回想記でもある。
このとき、小さな停車場まで、弘光寺の住職が迎えに来てくれたのだが、送迎の自動車というのが、なんと真新しい消防車だった。
真面目そうな若い運転手が直立不動の姿勢でお辞儀をすると、先ず清水町先生が衆人環視の裡に俯き加減に運転席の隣に坐った。途端に見物人の一人の子供が大声で、──あっ、村長さんだ。と叫んだ。(小沼丹「埴輪の馬」)
戦後間もない頃のことで、新しい消防車と都会からの来客が珍しかったらしく、多くの村人たちが、駅前まで集まってきたというからおかしい。
運転席の隣に座った井伏さんを見て、途端に見物人の一人の子供が大声で「あっ、村長さんだ」と叫んだというくだりには、思わず声を出して笑ってしまった。
小沼さんの小説には、こういうおかしさがある。
その裡に漸く車が動き出したら、子供達は一斉に両手を挙げて、万歳、万歳と大声で叫んだ。大人のなかにも、それにつられたのか、万歳、と叫んだ者が何人もいたようである。(小沼丹「埴輪の馬」)
まるで井伏さんの小説の一場面を思わせるような、楽しい光景である。
まだのどかだった時代の田舎のスナップ写真の一枚だろう。
ちなみに、年譜の1951年(昭和26年)10月のところに「井伏鱒二らと埼玉県岡部町針ヶ谷の弘光寺を訪ね、出迎えた消防自動車に乗る」と記されている。
人間同士のささやかな奇縁
そんな昔話から始まって、物語は、現代の弘光寺行きへと、時間軸を戻してくる。
このとき、自動車を運転してくれたのが<夏川君>で、<夏川君>は最初に清水町先生と一緒に弘光寺へ行ったときのメンバーの一人の弟だった。
夏川君の兄を思い出しているうちに、<僕>は弘光寺へ行った後のことも、いろいろと思い出す。
本堂の奥に古ぼけたかごが二挺置いてあったことや、座敷で宴会をしている最中に住職が行方不明になったこと。
懐かしい記憶が、次から次へと思い出されてきて、それが、この物語の主要な要素となっている。
一言で言えば、この物語は懐旧の念で書かれた短編小説ということになるだろう。
ただ、その昔話が、酔っぱらいの昔話のようにベタベタとくどくなく、センチメンタルでもないところに、小沼丹の文学の特徴がある。
著者は、あくまでも感傷を抑えて、あえて思い出と距離を置きながら、懐かしい昔話を物語へと置き換えている。
読みようによっては、随筆とも小説とも受け取れる作品だが、埴輪の馬をきっかけとして、現代と過去を自在に行ったり来たりする構成に、文学性の高さが感じられる。
無職の某君と書いた兄の夏川君は、現在では或る会社の社長で、なかなか忙しいらしく長いこと会っていない。しかし、兄の夏川君を想い出したら、昔、一緒に消防自動車に乗った人の弟の運転する車で同じ弘光寺へ行く、それは別に偶然ではない筈だが、そのときは何だか偶然のように思われて面白かった。(小沼丹「埴輪の馬」)
「それは別に偶然ではない筈だが、そのときは何だか偶然のように思われて面白かった」とあるのが、この短篇小説の核心ということになるのだろう。
著者は、昔のことを思い出しながら、人間の奇縁ということに感慨を感じている。
読み終わった後に残る、この微かな切なさはなんだろうか。
関係ないけど、講談社文芸文庫の背表紙に「表題作『埴輪の馬』では、埴輪様式の土器の馬を購入のため、師井伏鱒二や友人と出かける」とあるのはおかしい。
井伏鱒二と出かけたのは昔のことで、埴輪の馬を購入のため一緒に出かけるのは夏川君ただ一人だったのだから。
念のため、年譜を参照すると、1975年(昭和50年)12月として「弘光寺を訪ね、和尚の紹介で名人の工房から埴輪の馬を買い持ち帰る」と記されている。
小沼丹が弘光寺を訪れるのは、年譜によると、これが三度目で、二度目は1960年(昭和35年)4月に「井伏らと弘光寺を再訪、長瀞に遊ぶ」とあった。
作品名:埴輪の馬
著者:小沼丹
書名:埴輪の馬
発行:1999/3/10
出版社:講談社文芸文庫

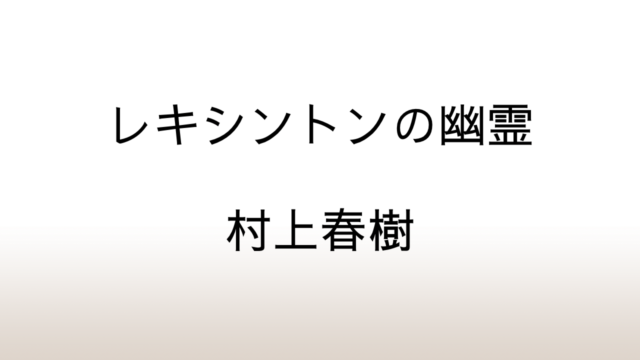
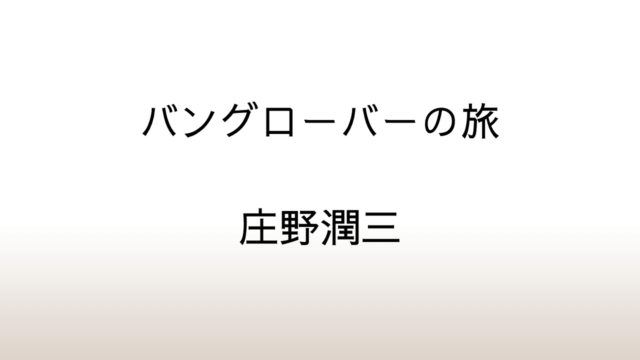
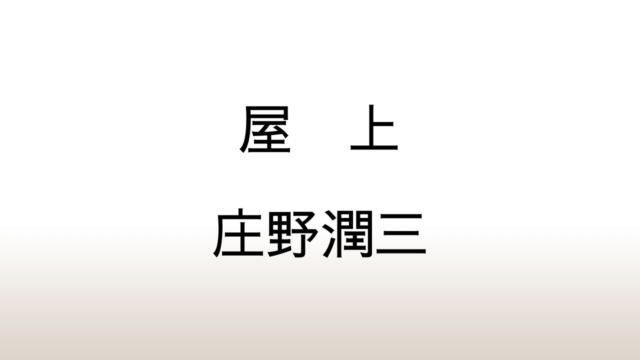
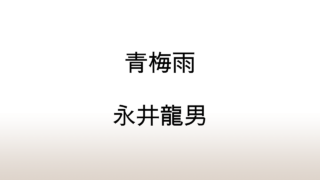
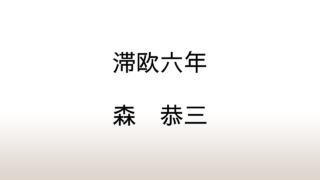
003-150x150.jpg)