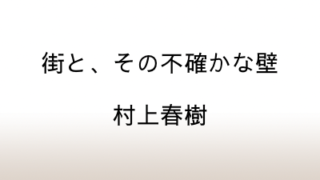川西蘭『春一番が吹くまで』読了。
本作『春一番が吹くまで』は、1979年(昭和54年)11月に河出書房新社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は19歳だった。
初出は、次のとおり。
「春一番が吹くまで」
1979年(昭和54年)5月『文藝』
文藝賞最終選考作品(受賞はならず)
「ブラック・ボックスを背負って」
1979年(昭和54年)9月『文藝』
「著者ノート 芸事はじめ、小説はじめ」
文庫書き下ろし
若者たちが、大人になることをためらう時代
本作『春一番が吹くまで』は、川西蘭の第一作品集である。
河出文庫版あとがきとも言える「芸事はじめ、小説はじめ」によると、デビュー作「春一番が吹くまで」は、文藝賞応募作品だった。
そんな時、本屋で『文藝』を立ち読みした。高橋揆一郎氏の『伸予』が載っている号だ。パラパラとめくっていると、『文藝賞』原稿募集の太い文字が目についた。(川西蘭「芸事はじめ、小説はじめ」)
後に芥川賞を受賞する『伸予』(高橋揆一郎)は、1978年(昭和53年)6月『文藝』に発表された。
川西蘭の応募作は最終選考まで残りながら受賞には至らなかったものの、『文藝』編集長の連絡により、本作「春一番が吹くまで」は(書き直しの上)1979年(昭和54年)5月『文藝』に発表されることになる。
※ちなみに、当時の『文藝』では、庄野潤三の『ガンビアの春』が連載中だった。
ペンネームの「川西蘭」は、人気アイドルグループ・キャンディーズの「伊藤蘭」に由来する。
1960年(昭和35年)生まれで、1970年代後半に高校を卒業する著者も、「キャンディーズ世代」と呼ばれる若者の一人だった(キャンディーズの解散は1978年4月)。
19歳のデビュー作となった「春一番が吹くまで」は、大学受験を控え、夏休みの間だけ東京の予備校へ通う、17歳の少年(藤村健)の物語である。
この夏休み、主人公は、一人の美しい女性(縞埼夕子)と出会い、恋をし、彼女をめぐる二人の男女と知り合いになる。
この物語は、つまり、大学受験生を主人公とするひと夏の恋愛物語なのだ。
本作「春一番が吹くまで」最大の魅力は、登場人物のキャラクター設定に尽きる。
地方都市の高校生が、東京の予備校で出会った美少女に恋をする(そして別れる)というプロットそのものに、さしたる意味はない(あまりにも凡庸すぎる)。
たった四人の登場人物が、この中編小説を支えているのだ(150枚一挙掲載だった)。
主人公(ケン)は、通学電車から一生懸命に海を見ている、繊細な男子高校生だった。
大学受験のために生きているような連中を「参考書とお友だち」と皮肉る彼は、受験生という自分の状況に、うまく馴染むことができない(一応、法学部志望だった)。
一体、一流と呼ばれる大学、予備校、高校へ行くことが、自慢することなんだろうか。”優秀な”という奇怪な形容動詞がつけられる人間になることなんだろうか。意味のあることとは思えなかった。(川西蘭「春一番が吹くまで」)
受験戦争に懐疑的な気持ちから逃れられない青春像は、当時『週刊少年マガジン』で人気を博していた『翔んだカップル』(柳沢きみお)にも通じる、1980年代前夜の空気感に満ちている。
「大学受験ってなんだろう?」という主人公の疑問は、本作「春一番が吹くまで」の大きな背景として効果的に機能するものだ。
東京都内の大学で、主人公は美しすぎる女子高生(ユウコ)と出会う。
ユウコは、病弱で、情緒不安定な女の子だった。
首を軽く振ったユウコは、目をそっと閉じて体から力を抜いた。陽に焼けていないユウコの白い胸に顔を近づけながら、僕は雪の中に埋もれていくような気がしていた。(川西蘭「春一番が吹くまで」)
二人が仲良くなったとき、ユウコの元カレ(佐藤)が現れ、「ユウコとは半端な気持ちで付き合うな」と忠告する。
医学部を目指して浪人中(三浪)の佐藤は、自身の勝手な行動から、ユウコ(元カノ)をダメにしてしまったと後悔していた。
「オレが彼女を引きずり回しているうちに、変わったんだな。自分勝手かもしれないけど、ユウコに魅力を感じなくなって、自然に離れていったんだな、オレ達は……。それ以来、ユウコは殻にこもってしまって……」(川西蘭「春一番が吹くまで」)
佐藤は、現在、ファッション・モデルのようなオシャレ女子(弥生)と交際している。
弥生は、「佐藤を誤解してほしくない」と、主人公に告げる。
「佐藤クンとユウコはすごく仲良しだったのね。それがさあ、彼、三回だっけ、大学落っこって、急に弱気になったのよ。”オレはもう駄目だ”って、別れちゃったのよ。でも、彼、まだユウコが好きで、ずっとそうなんだ、うん」(川西蘭「春一番が吹くまで」)
3人の話を聞いた主人公は、何が正解なのか、分からなくなってしまう。
この「何が正解なのか分からない」という主人公の気持ちは、そのまま、この物語の大きなテーマとなっている。
「何が正解なのか分からない」もの、それが、つまり、青春ということなのだ。
ひたすら献身的に佐藤につくす弥生の姿を見て、「彼女は人一倍真剣に生きている傷つきやすい女の子なのかもしれない」と、主人公は考える。
寂しかったり、苦しかったりして、世の中に目をやった時に、余りに尖ったイメージしかそこにはないから、わざとふわふわしたイメージで自分をくるんで守っている。固いものに固いままぶつかった時に、勝つのは力のある方に決まっているから。(川西蘭「春一番が吹くまで」)
傷付きやすい若者だったという意味では、佐藤も例外ではない。
「実際、今のオレには何もないからね」と彼はグラスを右手で軽く握って言った。「このアパートだって、生活費だって、オレのまわりにあるものは全部オレのオヤジのものさ。もしかすると、君と話しているオレ自身だってそうかもしれない」(川西蘭「春一番が吹くまで」)
将来に悩む佐藤の姿は、あるいは、将来の主人公自身の姿でもあったかもしれない。
「学生の間というのは、温室の中にいるのと同じらしいんだな。外は木枯しが吹いててね。オレなんか学生止めてるんだから、もう外に出てなきゃならないんだけど、出口のところでオヤジに貰った分厚い毛皮のついた防寒コートを着こんで、外が春になるのを待ってるのさ」(川西蘭「春一番が吹くまで」)
「外が春になるのを待ってるのさ」という佐藤の言葉は、作品タイトル「春一番が吹くまで」に、直接つながるものだ。
つまり、この物語は、ユウコとの恋愛を通して、<冬の時代>を生きる受験生の孤独を描いたものとして読むことができる。
一流大学へ入学し、一流企業へ入社した者だけが、人生の成功者だった(と信じられていた)1980年代的幻想への問題提起が、そこにはある。
「僕は社会学をやりたいんだ。つまり、どういうことかって言うと、僕は出来れば”大人”になりたくないんだ。だから、甘いかもしれないけど、一枚膜を隔てて社会というものを見つめていたいんだ」(川西蘭「春一番が吹くまで」)
「僕は出来れば”大人”になりたくないんだ」という言葉は、J.D.サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』の主人公(ホールデン・コールフィールド)を思わせるが、主人公は「だから、社会学をやりたい」と言う。
「一枚膜を隔てて社会というものを見つめていたい」という永井荷風的哲学は、夏目漱石『それから』の主人公(長井代助)が標榜する「高等遊民」にも通じる人生観だった。
若者たちが、大人になることをためらう時代。
あるいは、それが、1980年前後という時代だったのかもしれない。
若者の自殺と仲良しチームの崩壊
同時収録「ブラック・ボックスを背負って」は、ミニコミ誌『イエロー・プレス』を発行する男子大学生の仲良し四人組が崩壊していく過程を描いた青春小説である。
「春一番が吹くまで」に続く、デビュー2作目の作品。
溜まり場となっている喫茶店Sのマスターも含めて、登場人物のキャラクター設定は、デビュー作同様に魅力的だ。
マスターはもう五十に近いのだが感覚だけは若く、僕たちのやってることを理解してくれる。他の客に迷惑をかけない限り、大声で話してもいくら長居をしても文句を言わない。(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
1980年前後、喫茶店のマスターは、若者たちの後見人的な役割を担うことが多かったような気がする。
『週刊少年チャンピオン』連載の『750ライダー』(石井いさみ)や『すくらっぷ・ブック』(小山田いく)など、少年青春漫画には、優しくて頼りになる喫茶店マスターが、必ず登場していたものだ。
大抵の場合、コーヒーを淹れる技術は素晴らしくて、なぜか独身という設定。
そういう喫茶店のマスター像まで含めて(そもそも馴染みの喫茶店をたまり場にしていることまで含めて)、本作「ブラック・ボックスを背負って」は、1980年代前夜の雰囲気に満ちた青春小説だ。
「土曜の夜はフィーバーだって言うじゃないか」「じゃあね、バイなら」「ガチってるぜ、全く」「ポパイ・ザ・セーラーマン。くっくうーっ」など、文章表現にも、時代を反映したものが随所で眼を惹く。
一方で、軟派な若者文化を背景としたビジュアルを呈しつつ、作品テーマは、非常に重いものとなっている。
本作「ブラック・ボックスを背負って」の大きなテーマは、仲良しの四人組大学生チームの崩壊だが、彼らの崩壊の原因となったのは「若者たちの自殺」だった。
「そうだ」手を合わせて、ギュッと握り締めた政が熱っぽい口調で言った。「自殺をやろうよ。今流行ってるからちょうどいいし、ジュンちゃんの場合を書いていけば、正確な記事になるじゃない、やろうよ」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
「今流行ってるからちょうどいいし」とあるように、若者の自殺は、当時の大きな社会的課題のひとつで、少年漫画誌でも採りあげられるほど、青年層の関心も高かった(柳沢きみお『翔んだカップル』でも、自殺する女子高生が描かれている)。
「自殺」を一周年記念号の特集記事とするか否かということで、彼らは、それぞれの倫理観を主張するが、それが、この物語の大きなメッセージとなっていく。
「時々思うのよ。普通意識しないじゃない、生きてることなんか。どうして生きてるんだろうとか、これからどうなるんだろうとか。時々ね。……やっぱり、恐いよ」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
主人公(キヨシ)の恋人(ジュン)も、また、自殺願望を口にする高校2年生の女の子だった。
「オレか、オレは生きていたい。はっきり言って、まだ当分は死なないだろうし、今は死ぬことよりも生きることを考えていたいからね。とにかく、意地汚く生きるんだよ」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
かつて、目の前で、女の子が自殺した経験を持つ敏満は、「自殺」を採りあげるなら『イエロー・プレス』を抜けると言う。
「オレたちはさ、自分がいつ死ぬとか、いつ死にたいと思うかとか、全然分からないんだよ。それなのに、他人が死んだ原因や意味を捜したって仕方ないじゃないか」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
ポップな文章表現で80年代的に軽薄な印象を与えつつも、彼らの議論は、やはり1970年代的だ(時代の変わり目だった)。
ジュンが大切にしている飼い猫(ゴードン)が死んだことで、リアルな死に触れた彼らは、浅はかな自殺議論に終止符を打つ。
深く出来るだけ深く穴を掘ってゴードンを埋めたかった。それは、地表に近いと腐乱した死骸が何かの拍子に顔を出す恐れがあったからとも言えるが、決してそれだけの理由からではない。土の中深く封じこめてしまいたい、という思いの方が強かった。(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
そして、「自殺」をめぐる議論の中で、彼らは、『イエロー・プレス』の活動が中途半端だったことに気づく。
「政、オレたちはもう駄目かもしれない」と皮肉っぽく顔をゆがめた。「オレたちがこれやってさ、何になったかって言うと堕落したくらいのことだよ。もう、止めるよ。……いっさい止める」「お前は何んで逃げようとするんだ」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
「若者たちの自殺」というフィルターを通して、彼らは、自分たちの活動と正面から向き合うことができたのだ。
彼らは、それぞれの葛藤を抱えながら、何とか妥協点を見つけて『イエロー・プレス』を存続させようと努力する。
「酷いこと言ってるけどね、キヨシ。ボクは本当は死にたくなんてないんだよ。こんなに真面目な話だってしたくないんだ。分ってよ、みんなでずっとやって行こうよ」(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
この物語の優れたところは、『イエロー・プレス』の再生という安易な妥協で終わらなかったことだろう。
これからどうなるんだろう、と思った。今までのように冗談ばかりではやって行けない。そうかといって、確かなものを作り上げていく自信は全くない。でも、もう僕は歩き始めなければならなかった。(川西蘭「ブラック・ボックスを背負って」)
思うに、『イエロー・プレス』は、彼らの成長に必要な、一つの踏み台だったのだ(もちろん、前向きな意味で)。
そして、自殺騒動を通して、主人公(キヨシ)とジュンとの絆も深まった。
終わりが始まり──。
この物語は、『イエロー・プレス』という一つの集団の崩壊を描きながら、次のステップへと向かう若者たちの姿を描き出している。
非公認サークルで活動する男子大学生たちの物語というところも、80年代の細野不二彦的に好感が持てる(『あどりぶシネ倶楽部』『うにばーしてぃBOYS』)。
つまるところ、1980年前後の少年漫画誌が持つ雰囲気が好きだという人たちには、この作品は受け入れられるのではないだろうか。
不器用だけれど一生懸命に生きている若者たちの姿には、何かしら共感するものを見つけられるはずだから。
書名:春一番が吹くまで
著者:川西蘭
発行:1984/02/04
出版社:河出文庫

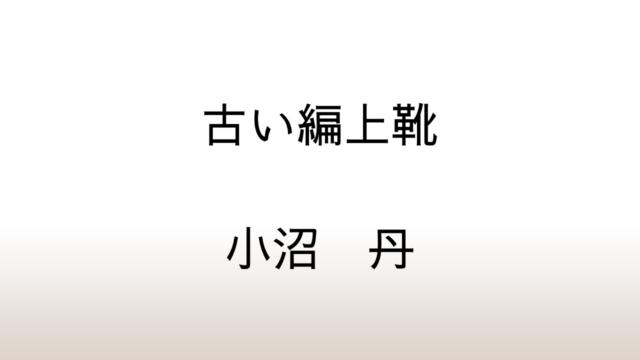


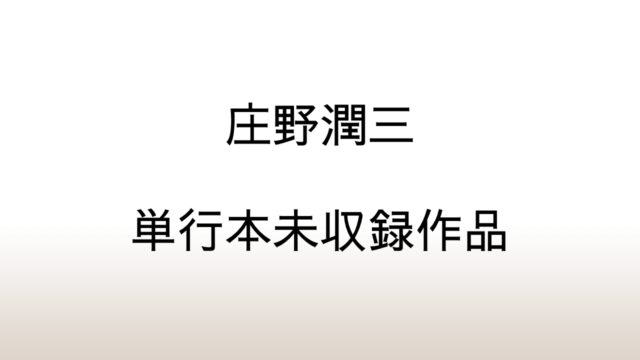
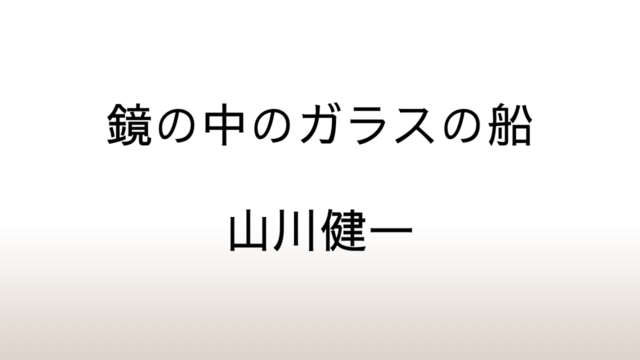

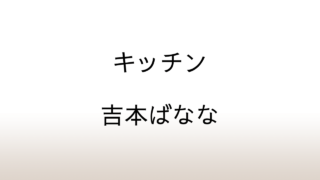

003-150x150.jpg)