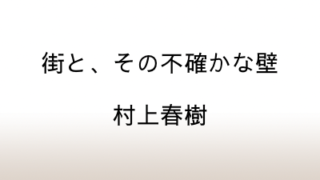庄野潤三には、雑誌に発表しながら、作品集には収録されていない、いわゆる「単行本未収録作品」が多い。
単行本未収録となった背景は、作者の意図によるものだろうが、未収録作品の中に貴重な発見をする場合もある。
今回は、古い雑誌の中で見つけた、庄野潤三の単行本未収録作品を紹介したい。
(以下、発表順)
(作品は随時追加していきます)
スカランジェロさん(1956年)
本作「スカランジェロさん」は、1956年(昭和31年)5月『小学六年生』に発表された短編小説である。
父と長女と長男の三人が、特急つばめ号に乗って大阪のおばあちゃんのところへ向かう。
特急列車の中で出会った外国人夫妻のことを書いた物語が、本作「スカランジェロさん」で、小学三年生の長女<あたし>の視点による一人称で書かれている。
あたしたちは持って来たおべんとうを食べました。おかあさんが入れてくれた折箱は、おとうさんのが大きくて、あたしと弟のは小さい折箱です。おとうさんはあせをいっぱいかきながら食べています。時々、ポケットからハンカチを出して顔のあせをふき、それから頭をくしゃくしゃとふいて、また食べています。そんなことをするので、おとうさんの髪の毛はぼうぼうです。ほのおがもえている時のように、全部の毛が上をむいています。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
こんな姿を見られたら恥ずかしいから、食堂車に行った外国人夫妻が戻ってくる前に、お弁当を食べ終わってくれればいいのに、と願うところまで含めて、少女の言葉がおかしい。
母親抜きで実家へ帰るのは、母親が次男の出産を控えていたからだ。
赤ちゃんは四月に生まれました。桃子という名前です。あたしは弟の信夫があまりいうことを聞かないので、女の赤ちゃんが生まれたらいいのになあと思っていたら女の赤ちゃんだったので、大よろこびでしたが、このごろではとてもやんちゃであたしは困っています。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
この夏、長女・夏子は小学三年生、長男・龍也は幼稚園(三歳)で、次男・和也は、翌1956年(昭和31年)の2月に誕生している。
本作「スカランジェロさん」が学習誌『小学六年生』五月号に発表されたとき、次男・和也は、まだ生まれたばかりだったのだ。
家族旅行の楽しさ(1956年)
本作「家族旅行の楽しさ」は、1956年(昭和31年)12月『旅』に発表されたエッセイである。
表題のとおり、家族旅行の楽しさについて綴ったもので、庄野家の場合、最初に家族旅行をしたのは、結婚してから七年目のことだった。
庄野夫妻の結婚は、1946年(昭和21年)のことだから、七年目というと、1952年(昭和27年)ということになる。
私たちの家では長女が五つになり、二番目の男の子がヨチヨチ歩きが出来るようになっていた。それで下の子供は、家内の母親の家に預かってもらって、三人で出発した。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
長女・夏子は、1947年(昭和22年)10月生まれ、長男・龍也は、1951年(昭和26年)9月生まれ。
庄野さんは、妻子を連れて、朝日放送の同僚に紹介された三重県の青山高原へ旅行した。
旅館は沸かし湯の温泉宿だったが、夕食を運んできた女中が美人で、庄野さんは一人でかなり多くの酒を飲んだ、とある。
ホールがあると聞かされて行ってみると、蓄音機のそばに女性が一人いた。
私はこの女性と一緒に踊ったが、真夏のことであり、その上に大分お酒を飲んでいるので、汗が流れた。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
他に客はいないから、庄野さんと女性は二人だけで踊り続ける。
妻は、庄野さんが汗を拭くためのハンカチを、部屋まで取りに行かねばならない。
その間、妻と長女とは誰もいない広いホールの壁際の椅子に坐って、父のダンスを見物していた。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
家族旅行に出かけて、父親だけ酒を飲んで酔っ払って、ホールの女と踊り続けているんだから、現在だったら騒動になりそうな話である。
昭和20年代のこととはいえ、何とものんびりした話だ。
翌日、一家は赤目ノ滝を見学して帰阪する。
両親がもう生きていないので私のことを心配したりしないから、私は将来出来れば子供たちを連れて外国の土地を旅行してみたいと考えている。無論、万障繰り合わせての旅行であるが、夢は大きく持つ方がいい。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
ロックフェラー財団の招きを受けた庄野さんが、千壽子夫人と一緒にアメリカへ留学するのは、1957年(昭和32年)のことである。
子どもたちを連れての外国旅行は、どうやら実現することがなかったらしい。
四対一(1958年)
本作「四対一」は、1958年(昭和33年)『洋酒天国』29号に発表されたエッセイである(副題「オハイオ州ガンビアの話」)。
アメリカの人たちはバーボンを好んで飲んだ。
庄野さんも最初はバーボンを飲んで「何というまずいウイスキーだろう」とがっかりするのだが、どこの教授の家に呼ばれても国産のバーボンばかり出されるので、やがてバーボンの味にも親しみ馴れてしまったという。
本場のスコッチは、当時のアメリカでも高級品で、大学の教授くらいでは簡単に買うことができなかったものらしい。
ガンビアにいる間に覚えた酒として、もうひとつ、カクテルのマーティニがある。
近所に住んでいる飲み仲間のエディノワラ氏(ミノー)はマーティニが好きで、「どうしてマーティニを飲まないのか」「わしがつくって上げるから一回ためしてみろ」と、庄野さんに勧めたのがきっかけだった。
エディノワラ氏は「大事なことは、ジンを四、ヴァームースを一の割合でやることだ。三と一の割合でやる家が多いが、これは絶対、四と一でなくてはいかん」と主張した。
つまり、「四対一」という作品名は、エディノワラ氏が教えてくれたマーティニのレシピのことだったのだ。
エディノワラ氏は、「ジンとヴァームースを入れたあと、食塩をほんの少し、入れること。これがコツだ」と言いながら、左の掌にこぼした食塩を右手でつまんで、グラスの中に落とした後で、さらに「大事なことは、残りの塩を左の肩から後ろへ投げ捨てることだ」と言った。
庄野さんがアメリカで撮影してきた写真が、数カット掲載されているのも貴重。
若き芥川賞作家たち房総へゆく(1959年)
本作「若き芥川賞作家たち房総へゆく」は、1959年(昭和34年)3月『旅』に発表されたエッセイである。
この時期、庄野さんは、多くの紀行文を書いた。
ついでに云えば、現代の自分の文学が小説ばかり追い求めて、紀行文を忘れていることも私はかねがね不満に思っている。内容空疎な小説を読んでも、味気なくなるばかりだ。この文学界に活を入れるのは、すぐれた紀行文しかないと私は思っている。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
1959年(昭和34年)といえば、アメリカ留学の記録『ガンビア滞在記』を刊行した年である。
リアルな体験に、庄野さんが新しい道を見出していたことは想像に難くない。
私はスティーヴンスンの紀行文が好きだ。「旅は驢馬をつれて」などは大好きだ。中でもあの星空の下で野宿をするくだりは絶妙だと思う。あんな旅行を私はやってみたいと前から考えている。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
庄野さんの盟友・小沼丹が、R.L. スティーヴンソンの『旅は驢馬をつれて』の翻訳を家城書房から刊行したのは、1950年(昭和25年)のことだった。
1953年(昭和28年)8月、安岡章太郎が「悪い仲間」で芥川賞を受賞した年の夏、毎月一回集まって飲んでいた作家仲間たちが、千葉県鴨川に住んでいる近藤啓太郎の誘いで房総の旅館へ出かけた。
当日、両国の駅へ来たのは、安岡章太郎、島尾敏雄、三浦朱門、私の四人だけであった。行くと云っていた小島信夫はその頃教えていた高等学校の生徒の母親に頼まれて、その子の監督として軽井沢へついて行くことになり、欠席した。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
このとき、仲間の吉行淳之介は、肺結核の外科手術を受けるために清瀬病院に入院していたが、友人たちのためにビール1ダースを寄贈してくれたという。
作家たちは、町の飲み屋で一緒になった空軍基地のアメリカ兵たちと騒ぎ、一度も砂浜を踏むことなく、房総を去ってゆく(紀行文というよりも、飲み会の記録だ)。
荒々しい売文生活に負けずに作品の健康を守るためには、我々は旅に出なければならない。グループ旅行は難しいから、めいめい一人で、スティーヴンスンのやったように各自の驢馬を引き連れて旅行に出かけようではないか。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
当時、庄野さんは、作品を書くことができなくて苦悩の時期にあった。
名作「静物」を発表するのは、翌1960年(昭和35年)の6月のことである。
土人の話(1960年)
本作「土人の話」は、「小説中央公論」1960年(昭和35年)7月号臨時増刊に発表された短編小説である。
学校友だちの<桑木>に関する思い出を綴った作品で、戦争中、彼の部隊が駐屯している近くには、人食い人種のダイア族が住んでいたという。
私は桑木とほぼ同じ頃に海軍に入隊したが、外地へは到頭一度も出なかった。そのため、彼が味わったような怖しい経験もしなかった代り、人食人種のダイア族にもお眼にかからなかった。十人目まで数えると、もう一度始めから数え直す英印軍の土人の兵隊も見ることが出来なかった。(庄野潤三「土人の話」)
復員後、桑木は東京の神学校へ入って、牧師の試験に合格し、それから四年近くかかって、焼け跡にバラックの教会を建てた。
旅費節約の方法(1960年)
本作「旅費節約の方法」は、1960年(昭和35年)10月『旅』に発表されたエッセイである。
サンフランシスコからニューヨークまで大陸横断の鉄道旅行で節約しようと思ったら、食費を節約するしかない、と庄野さんは言っているが、この方法を庄野さんは、自分より一年前にアメリカへ行った阿川弘之夫妻に教えられたらしい。
そういう金持のことを羨む必要はない。もしそういう旅行がしたければ、金持になった時にやればいいので、金持になるつもりがなく、またいくら頑張ってもとてもなれないと分っているなら、最初から羨むことはないのである。そして、金持が自分の金でもって楽しんでいる旅行について、「ああいうのはつまらない」などとよけいな口をさしはさむこともないわけだ。(庄野潤三「旅費節約の方法」)
旅行に対する姿勢が、そのまま、庄野さんの生き方となって表れている。
王様とペンギン(1960年)
「王様とペンギン」は、1960年(昭和35年)の「婦人之友」(11月号・12月号)に連載された中編小説である。
中学一年の<和子>の弟<四郎>は小学三年生で、ある日、テレビの野球放送を聴いて「あ、ピッチャーはペンギンだって」と言った。
アナウンサーが「ピッチャーは辺見」と言ったのを「ピッチャーはペンギン」と理解したものらしい。
さらに、別のときには「あ、一塁のランナーは王様だって」と言ったこともある。
物語の後半では、四郎が、<私>に向かって「はい、パチリ8」と声をかける場面がある。
「8チャンネルを付けてくれ」と言っているのだが、これは、名作『夕べの雲』に出てくるものと、まったく同じだ。
<私>は、子どもたちが楽しみにしている漫画の放送を苦々しく思っているが、<ラビット>という名前の兎と<タイガー>という名前の虎が登場する五分間の外国漫画は、おもしろいと思うようになった。(庄野潤三「王様とペンギン」)
あるいは、この作品は『夕べの雲』のプロトタイプとなったのかもしれない。
湖中の夫(1961年)
本作「湖中の夫」は、1961年(昭和36年)2月号『新潮』に発表された短編小説である(雑誌の目次には「新潮賞受賞第一作」とある)。
「湖中の夫」というタイトルは、レイモンド・チャンドラーの『湖中の女』(1943)を連想させるが、本作はミステリーでもハードボイルドでもなく、不動産屋で聞いた会話を再現しただけのミニマルな物語である。
舞台は不動産屋のテーブルで、家を売る<男>と、家を買う<婦人>が向かい合っている。
婦人の隣には、不動産屋の<業者>が座っていた。
「実はこちらの方の御主人はアメリカの方で、最近まで基地に勤務して居られました。ところが、二ヶ月前に友達と一緒に湖へ釣りに出かけられて、遭難されました。そこでこの方はもうすぐ基地の住宅を出なければならなくなったわけです」(庄野潤三「湖中の夫」)
婦人は、死んだ夫の生命保険を使って、この住宅を買おうとしているものらしい。
契約が成立して有頂天になっている不動産屋だけが、婦人の夫が死んだときの様子を推測してみたり、自分の故郷で潜って死んだ男の話をしてみたりする(まるで空気が読めていない)。
同じ空間で同じ時間を共有していながら、この三人はまったく何の共通点も持ち合わせていない。
そこに人生の奇妙な瞬間がある。
セーラの話(1961年)
本作「セーラの話」は、1961年(昭和36年)4月『小学六年生』に発表された短編小説である。
アメリカ・オハイオ州のガンビア滞在中の体験を素材とした物語だから、『ガンビア滞在記』の落穂拾い的な作品と言ってもいい。
主人公は、ケニオン大学の英語の先生<サトクリッフ>さんの長女<セーラ>で、『ガンビア滞在記』をはじめとする一連の「ガンビアもの」にも、もちろん登場している。
初対面のとき、セーラは、フィンランド式のおじぎをして挨拶をしてくれる。
おとうさんが、「日本から来られた庄野さんですよ」と言うと、その子は手をさし出し、片方の足をうしろに引いて、ちょっとからだを下げるようにして、「はじめまして、ミセス庄野」と、私の妻に、それから私にあいさつをしました。(庄野潤三「セーラの話」)
このとき、セーラは8歳の少女だった。
保険会社(1961年)
本作「保険会社」は、1961年(昭和36年)『文学雑誌』第三十号に発表された短篇小説である。
「ガンビアにいた時の日記を見ると、七月九日(昭和三十年)に私と妻はミノーと一緒にコロンバスへ出かけている」という一文から始まっている。
一年間の留学生活を終えて、七月末に日本へ帰ることになっていた庄野夫妻は、「セイリング・パーミット」(収入証明書)を用意するため、ミノーと一緒にコロンバスにある保険会社まで出かけた。
「ブルー・クロス」という小さな保険会社へ入ると、入口に近いところに、横山隆三の漫画に出て来る人物のように胸がとんがっている女性が座っていた。
奥のデスクに座っているのは、少し男ぶりのいい三十代の男性で、彼はずっと電話中で、胸のとんがっている女性が椅子を滑らせてやってきても、全然相手にいない。
ところが、反対側に座っている、ちょっと美人の、背の高い女性がやって来たとき、男性は立ち上がって、彼女の話を聞き始めた。
最後に、彼女は「立ち上がった男に話しかけながら、ひょいと手を伸して男の顎のところを逆さに撫でた」。
きっと、庄野さんは、美人の部下が、男性上司の顎を撫でた場面に惹かれていたのだろう。
庄野夫人が後で言うには、胸のとんがっている女性は、ドアのガラスに映っている二人の様子を見逃さずにいたそうである。
リッチソン夫妻(1961年)
本作「リッチソン夫妻」は、1961年(昭和36年)10月『群像』に発表された短篇小説である。
ケニオン大学で出会ったたくさんの教授群像を紹介しながら、特にリッチソン夫妻に焦点を当てて作品化している。
ハイライトは、リッチソン夫人が交通事故に遭って大怪我をしたという知らせが届くラストシーンだろう。
夫人重症のニュースは、ガンビア時代の親友ミノーのクリスマス・カードによって伝えられるが、その後に届いたリッチソン氏からのクリスマス・カードによって、夫人は一命を取り留めたことが伝えられる。
庄野さんがアメリカから帰国したのは1958年(昭和33年)で、リッチソン夫人が事故に遭うのは、その翌年の1959年(昭和34年)。
この小説は1961年(昭和36年)に書かれているから、小説の中に登場する人々は、まだ実在している人たちばかりであって、しかも、ガンビアにいる彼らと庄野さんとは、遠く離れていながらも、まだつながっている状態だった。
南九州への旧婚旅行(1968年)
本作「南九州への求婚旅行」は、1968年(昭和43年)10月『旅』に発表された紀行文で、交通公社の企画した<旧婚旅行ツアー>に夫婦で参加した際のルポルタージュとなっている(著者は47歳)。
「旧婚旅行」という言葉を最近は聞かない。
戦争中や戦後直後に結婚した人たちは、もちろん新婚旅行に行く余裕なんてなかった。
生活が落ち着いた今、改めて結婚記念の旅行に出かけようということで流行したのが、結婚後数十年経た熟年者たちによる「旧婚旅行」である。
結婚22年目の記念に、庄野夫妻も、この「旧婚旅行ツアー」に参加したのである(仕事を兼ねて)。
ツアーは、1968年(昭和43年)7月25日に東京を出発、大阪でツアー参加者と合流後、関西汽船で九州に入り、別府、宮崎、鹿児島、長崎を周遊しているが、庄野さんの紀行文は、風景描写ではなく人間描写である。
こうして今日、高波の寄せる日に、日向の国の鵜戸神宮へお詣りに来たのは、旅行の途中に立ち寄っただけのかりそめのことのように見えるが、或いはそれにはもっと深い意味があるのかも知れない。偶然のようで偶然でないかも知れない。(庄野潤三「南九州への旧婚旅行」)
掲載紙には、「開聞岳の中腹で記念植樹をする庄野夫妻」の写真が大きく紹介されている。
母と二人の若者(1968年)
本作「母と二人の若者」は、1968年(昭和43年)10月『群像』に発表された、J.D.サリンジャー『フラニーとゾーイー』(野崎孝・訳)についての書評である。
庄野潤三とサリンジャーには「家族をモチーフとした小説を書いている」という共通項があるが、サリンジャーは、家族の不幸せな部分に着目し、庄野さんは、家族の幸福な部分に着目した。
ベクトルがまったく異なる作家である庄野さんは、異常な子どもたちで構成されたグラース家の物語を、素直に受け入れることはできなかったらしい。
読者としての評価はなく、物語の梗概だけが延々と続く(多少の変換を加えながら)。
それに対してゾーイーは、ひとつひとつ反駁を加えてゆく。しまいにはフラニーは泣き出してしまうのだが、このあたりからおしまいへかけては、息もつがせぬといった風で、迫力がある。はじめはあんまり好きじゃないと思っていたゾーイーが、なかなかどうしていいところをみせるのである。(庄野潤三「母と二人の若者」)
庄野さんは、お母さんがつくった一杯のチキンスープを飲まないうちは、巡礼に出たって何になるかというゾーイーの台詞を引用して、「この言葉には確かに説得力がある。私はゾーイーの意見に賛成であった」という文章で、この書評を締めくくっている。

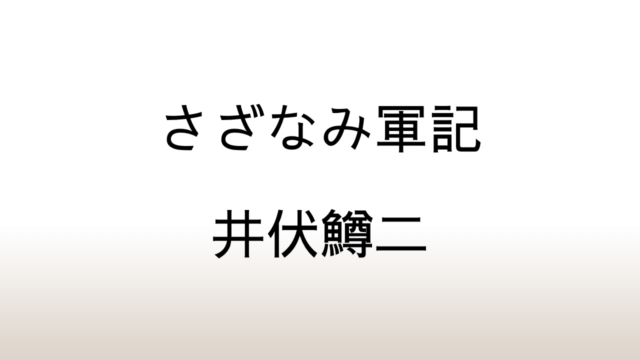



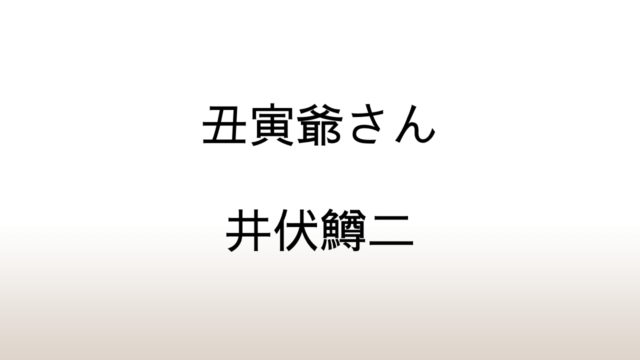
」-640x360.png)
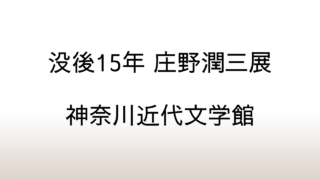
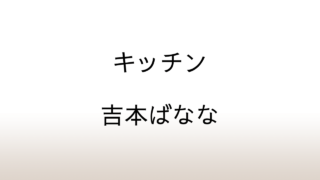
003-150x150.jpg)