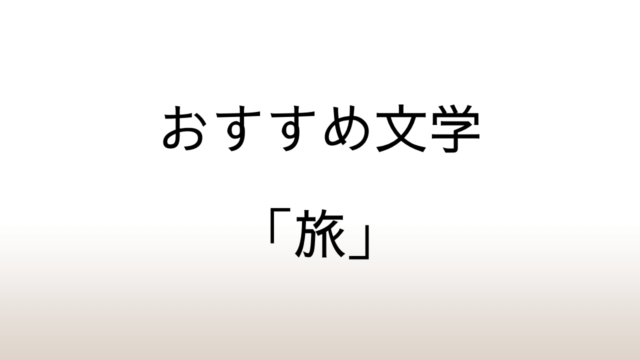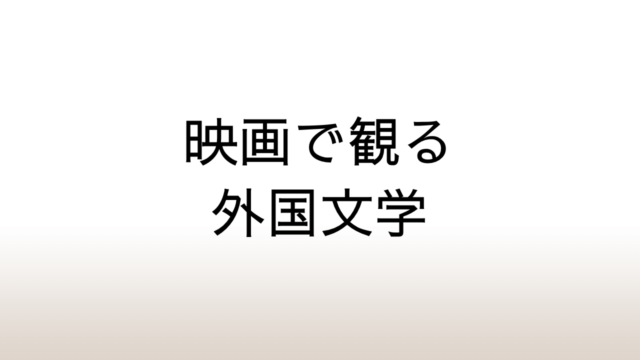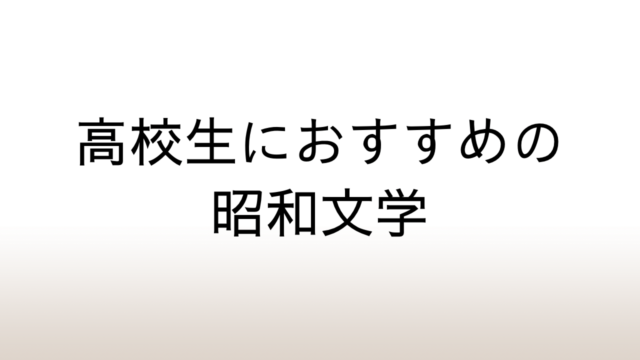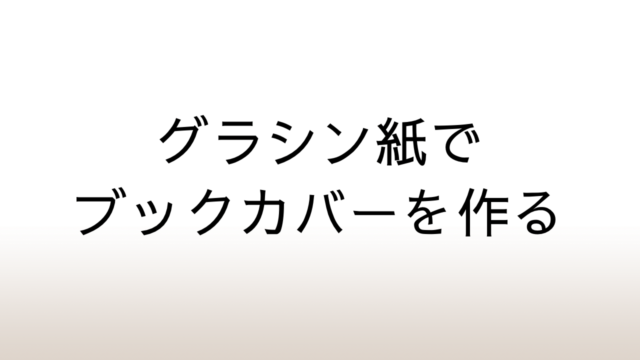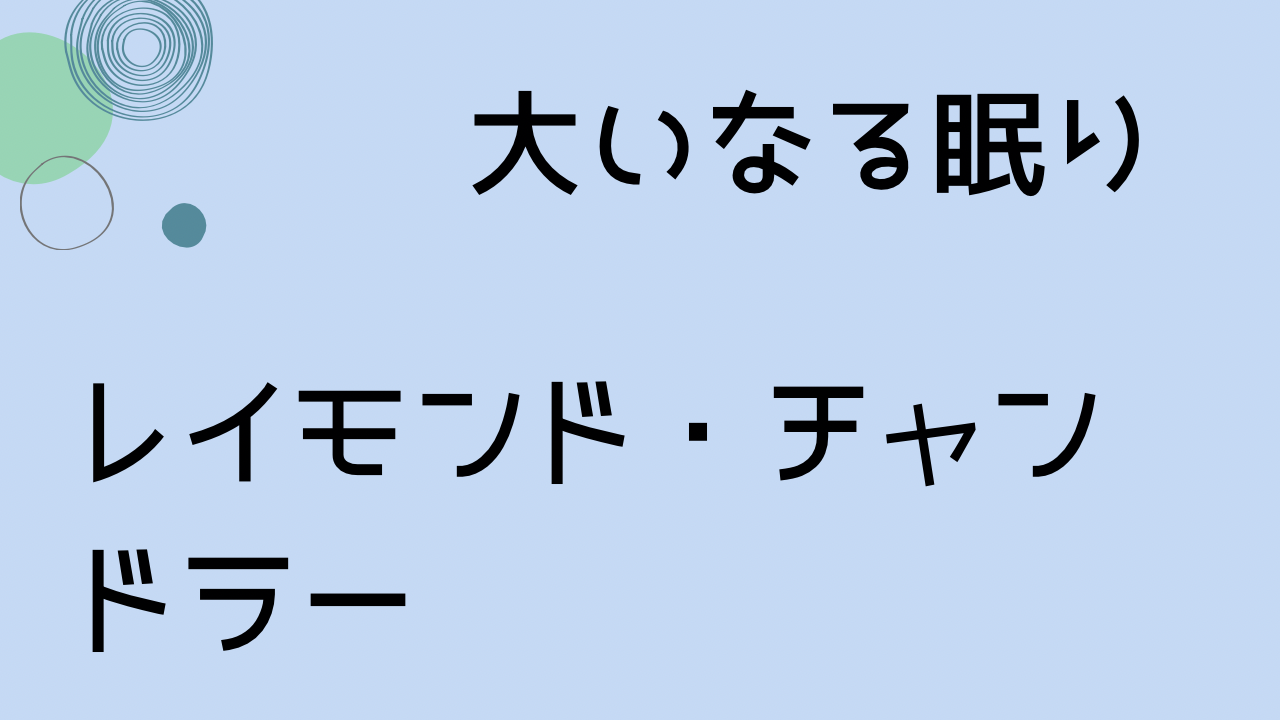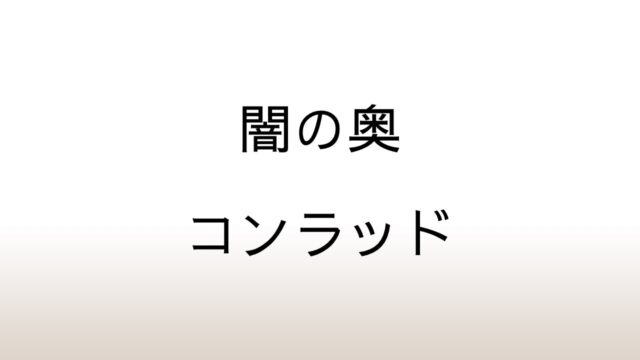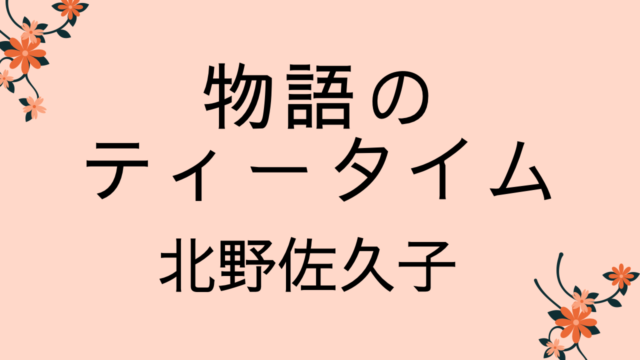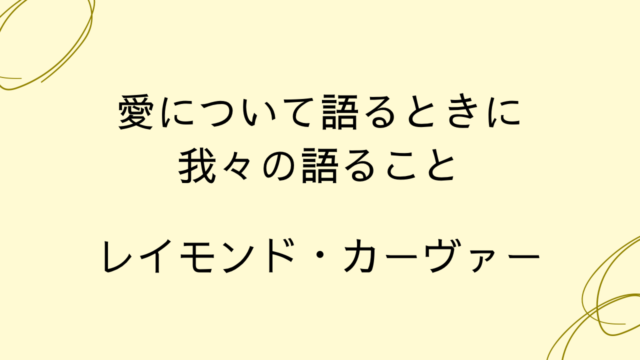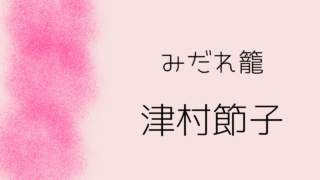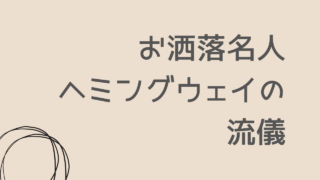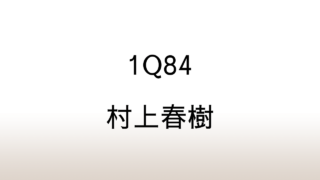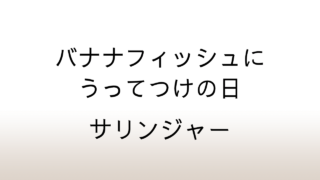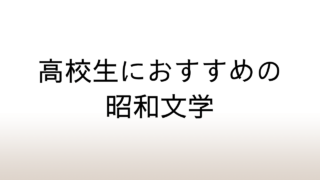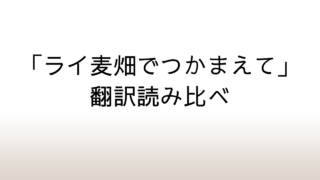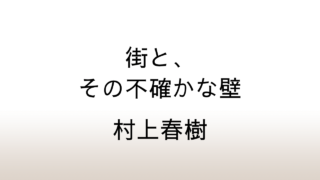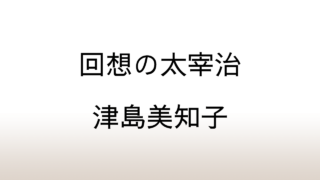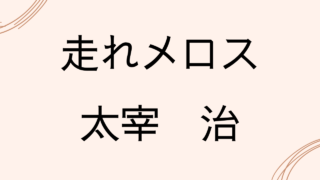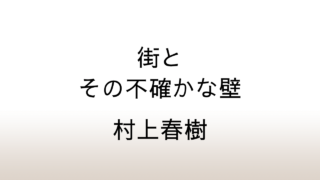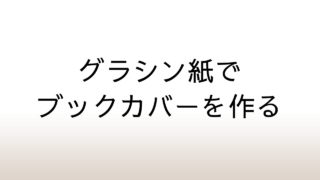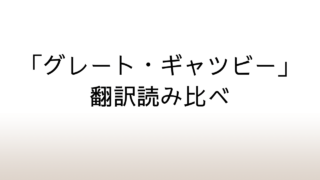レイモンド・チャンドラーの「大いなる眠り」を読みました。
読書の秋にぴったりのハードボイルド・ミステリーです。
書名:大いなる眠り
著者:レイモンド・チャンドラー、訳:双葉十三郎
発行:1959/8/14
出版社:創元推理文庫
作品紹介
「大いなる眠り」は、レイモンド・チャンドラーの長編推理小説です。
私立探偵フィリップ・マーロウが主役の長編小説シリーズ第1作目で、本国では1939年(昭和14年)に刊行されました。
原題は「The Big Sleep」。
日本では、双葉十三郎の翻訳によって1956年(昭和31年)に刊行されているほか、2012年(平成24年)には村上春樹による日本語訳版も刊行されています。
ちなみに、マーロウシリーズの長編小説リストは次のとおり。
①
本ブログでは「②さらば愛しき女よ」と「⑤かわいい女」「⑥長いお別れ」を紹介済みなので、よろしければ
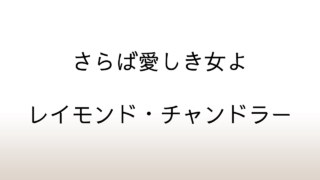
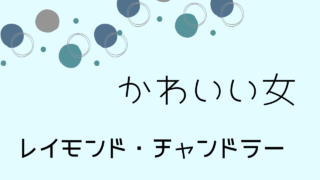
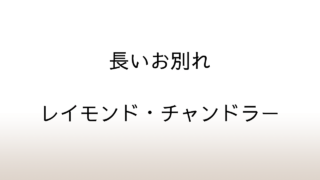
なお、本作「大いなる眠り」はハンフリー・ボガート主演で映画化もされています(邦題は「三つ数えろ」)。
あらすじ
スターンウッド将軍から恐喝に関する相談を受けたフィリップ・マーロウが、恐喝犯人を突き止めるべき捜査を開始したとき、最初の殺人事件が起きた。
次々と発生する殺人事件に巻き込まれつつも、マーロウはスターンウッド将軍の依頼に応えるべく、事件の解決に挑んでいくが、美しい女性たちの謎の誘惑とともに、事件は思わぬ展開を見せていく、、、
私立探偵フィリップ・マーロウ富豪スターンウッド将軍の邸宅へ招かれた。依頼の内容はゆすりの処理。将軍の次女カーメンが、賭博場でふり出した一千ドルの約束手形にからまる強迫状の件だった。マーロウは差出人のガイガーの家をさぐりに行った。ところが、突如として三発の銃声がとどろく。室内にとびこんだマーロウの前には二人の人間がいたが、それは猥褻な秘密写真撮影の現場だった。意表をつく新鮮な形容、会話の妙味、迫力ある描写、チャンドラーは処女作「大いなる眠り」によって、一流の批評家と読者を一挙に魅了し、ハメットにつづくハードボイルド派のチャンピオンとなった。翻訳権独占刊行!
なれそめ
レイモンド・チャンドラーの「大いなる眠り」は、秋の小説です(この長い小説が「十月の半ば、朝の十一時だった」で始まっているところからも、この作品が秋の小説であることが分かります)。
チャンドラーの小説で、季節感が重要な役割を果たすことはほとんどないのですが、秋の小説は、やはり秋に読んだ方が気分が出るような気がします。
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
彼は灰色の男だった。
彼は灰色の男だった。みがきのかかった黒い靴と、ルーレットの賭け台の仕切りみたいに、灰色のネクタイに刺された二個の真紅のダイヤモンド以外は、すべてこれ灰色だった。ワイシャツも灰色、やわらかな仕立てのいいフランネルのダブルの服も灰色だった。(レイモンド・チャンドラー「大いなる眠り」)
フィリップ・マーロウ・シリーズでは、登場人物のファションが非常に丁寧に描写されていることが多いようです。
いわゆるビジュアル的な表現が多いので、映画のようにキャラクターを楽しむことができます。
本作「大いなる眠り」では、賭博場の経営者であるエディ・マースの男っぷりが、すごく渋くてカッコイイです。
ファッションデザイナーとして著名なトム・ブラウンは、灰色(グレー)のスーツを愛用していることで有名ですが、一見定番のグレースーツは実は難易度が高いスーツでもあります。
グレーのスーツを着こなすということは、つまり、オシャレ上級者と言うことができるわけで、この「灰色の男」の登場は、この長編小説に刺激的なスパイスのような役割を果たしてくれています(そして、ストーリー上でも、マースは極めて重要な役割を担っています)。
僕はシャーロック・ホームズでもファイロ・ヴァンスでもない。
僕はシャーロック・ホームズでもファイロ・ヴァンスでもない。警察がすっかりさらった現場へいき、こわれたペンかなんかを拾い、それから事件を組み立てる、なんて器用なまねはできません。(レイモンド・チャンドラー「大いなる眠り」)
「大いなる眠り」は、フィリップ・、マーロウが登場する最初の長編小説ですが、マーロウのビジネスに対する哲学は、この作品の中で既に完成しています。
マーロウは依頼主から依頼金を得て働いている私立探偵であり、警察の協力者ではない。
「ぼくだって好きでやってるんじゃありませんが、ほかにすることがないからしかたがない。僕は事件をひきうける。つまり生活のために売るべきものを売ってるわけです。神様からちょうだいしたちょいとばかりの勇気と知恵と、依頼人を保護しようと歩き回る熱心さ、それだけですよ」という徹底的な依頼人第一主義は、到底警察と折り合いのつくものではありませんが、私立探偵の矜持を失うことなく、マーロウはビジネスに徹します。
仮に、それが自分に得なことではないと分かっていても「一日二十五ドルと雑費」(依頼料)のために生きる、それが私立探偵フィリップ・マーロウの哲学で、それは、私立探偵としてのマーロウが何があっても譲ることのできないアイデンティティだったようです。
「殺さなきゃならなかったの?」彼女は苦々しく言った。
「殺さなきゃならなかったの?」彼女は苦々しく言った。私は笑いだしたときとおなじように、とたんに笑いをやめた。彼女は私の背後へまわり、手錠の鍵をはずした。「そうね。殺さなきゃならなかったわね」彼女はやさしく言った。(レイモンド・チャンドラー「大いなる眠り」)
チャンドラーの小説は、その作品名に深い意味があるような気がします。
まるで読者へ挑戦しているかのように、謎に満ちたタイトルが、作品に対する興味をそそり、読む者の想像力を刺激します。
「大いなる眠り」とは、一体どのような意味だろうか。
永遠の眠りという言葉は、我々に「死」を連想させますが、それはいったい誰の「死」なのか。
タイトルの謎は、物語の最後まで解き明かされません。
「君は死んでしまった。大いなる眠りをむさぼっているのだ」という一文が登場するまでは。
それにしても、この日本語訳は、あの村上春樹版の翻訳でも継承されているあたり、ほとんど完璧な訳だったと言えるのかもしれませんね。
作者の啓示に満ちた、非常に素晴らしいタイトルだと思います。
読書感想こらむ
マーロウシリーズの長編小説は全部で7作品ありますが、2作目の「さらば愛しき女よ」から7作目の「プレイバック」までは清水俊二さんによる翻訳で、最初の「大いなる眠り」だけが双葉十三郎さんの翻訳です(村上春樹さんの翻訳は別として)。
翻訳者によって、小説の雰囲気って本当に変わるなあというのが、まず最初の感想で、それは、この小説が翻訳された時代性と大きな関係があるのかもしれません。
今となっては、かなり古くさい表現がたくさん登場するのですが、それも古典としてはやむを得ないところだと思います。
プロットは入り組んでいますが、きれいに整頓されているので、マーロウ初心者でも安心して読むことができるでしょう。
ただし、いわゆる本格ミステリーとは別物なので、トリックに期待をするのは筋違いです。
主人公フィリップ・マーロウの生き様を楽しむ。
それだけで、この小説を読む価値があると思いますよ。
まとめ
レイモンド・チャンドラーの「大いなる眠り」は、フィリップ・マーロウが登場する長編小説の最初の作品です。
世界的な評価も高い名作なので、読んで損はないです。
ただし、翻訳が古いということをお忘れなく。
著者紹介
レイモンド・チャンドラー(小説家)
1888年(明治21年)、アメリカ中西部のイリノイ州シカゴ生まれ。
1933年(昭和8年)、45歳のとき、探偵小説『脅迫者は撃たない』でデビュー。
『大いなる眠り』刊行時は51歳だった。
双葉十三郎(翻訳家)
1910年(明治43年)、東京生まれ。
映画評論家としても活躍した。
『大いなる眠り』刊行時は46歳だった。