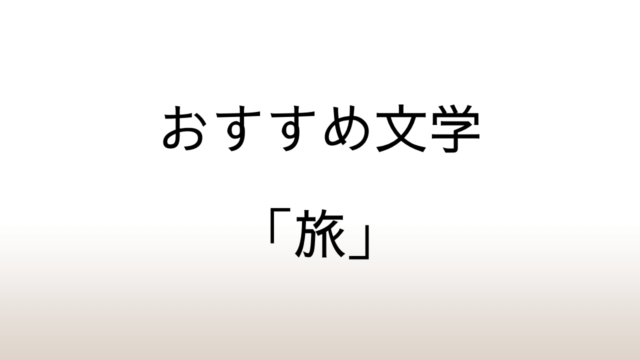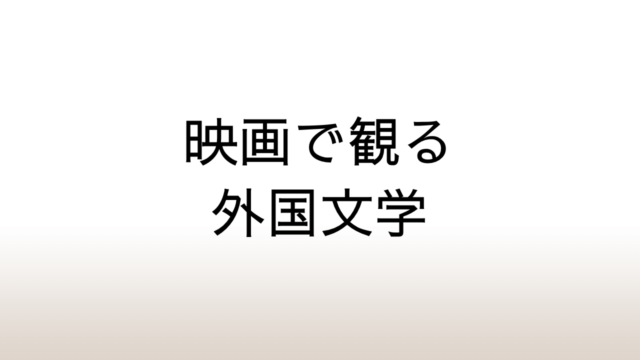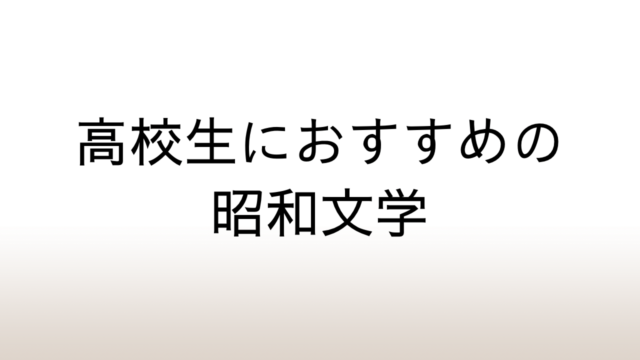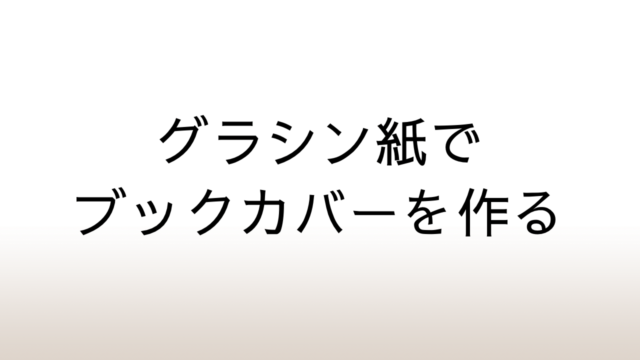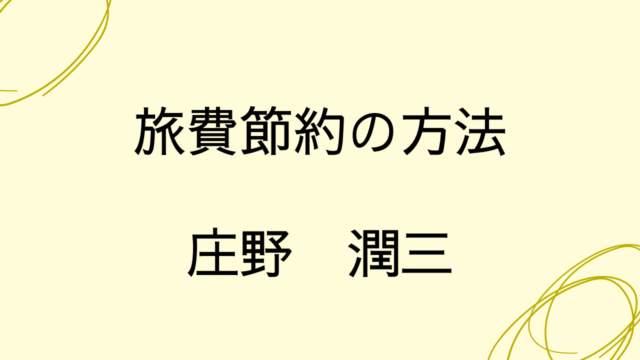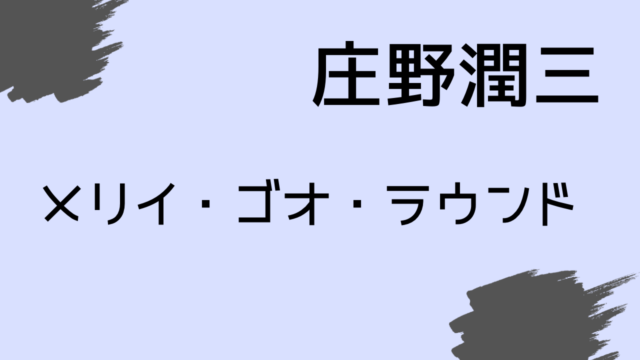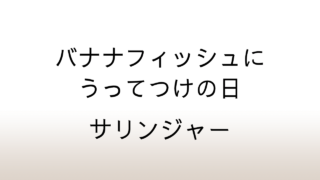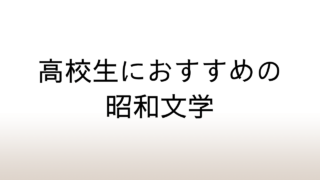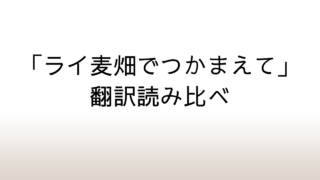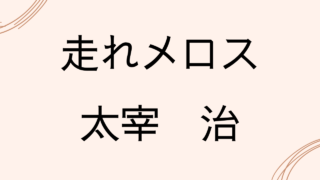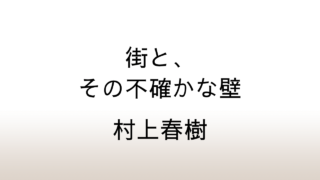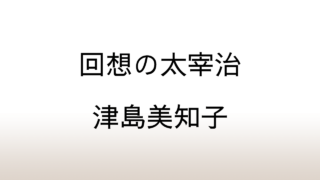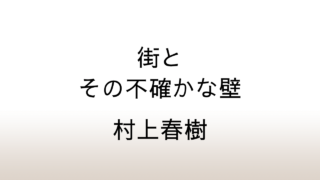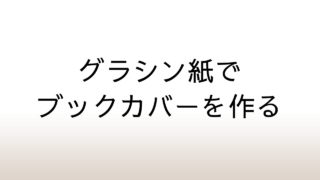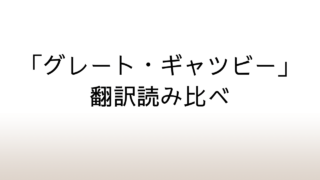庄野潤三「卵」読了。
本作「卵」は、長篇随筆「エイヴォン記」の連載第八回目の作品であり、「群像」1989年(平成元年)3月号に発表された。
単行本では『エイヴォン記』(1989、講談社)に収録されている。
現在は、小学館 P+D BOOKS から刊行されているものを入手することが可能。
「きれいだなあ」私は妻と二人で見とれた。
『エイヴォン記』の連載八回目となる「卵」では、庄野家の家族日誌という色合いが、ますます濃くなっている。
連載の最初から読んでいなければ、庄野家の日常の話の中に、なぜ、突然、古い文学作品の紹介が出てくるのかと、いぶかるかもしれない。
季節は十一月の半ばで、ご近所の清水さんが薔薇の他に野菜を持ってきてくれるところから、話は始まっている。
薔薇は、全部で八本、あった。その翌々日の朝。書斎の机の上の花生けのバレンシアが大きく開く。「きれいだなあ」私は妻と二人で見とれた。うすいオレンジ色。妻が持って来た「ばら目録表」には、「黄銅色」と書いてある。(庄野潤三「卵」)
まるで詩のように短いフレーズが並んでいるところが、庄野さんらしくていい。
さらに続く部分も。
夜、台所で、妻からバレンシアの名前を聞いたとき、昔、「バレンシアー」という歌い出しの曲があったのを思い出して、話したら、妻も知っていて、口ずさんだ。あれは、いつ頃だろう。子供の頃であったような気がする。家にレコードでもあったのだろうか。亡くなった長兄が音楽が好きであったから、この兄がレコードをかけていたのかも知れない。(庄野潤三「卵」)
薔薇の名前が、昔聴いた音楽の記憶へとつながり、亡くなった長兄の思い出へとつながっていく。
連載当初は「孫娘の文子の行状報告」という形であったのが、いつの間にか、庄野夫妻の日常のエピソードが中心となりつつあるようだ。
図書室からおもちゃの籠を自分で担いで来て、六畳へやっこらさと下す。
もっとも、祖父母の生活というのが、孫と密接に関わっているものだとしたら、フーちゃんの日常と庄野夫妻の日常とは、重なるところが大きくても不思議ではない。
孫娘の文子に妻が買って来たジャンパーを渡したのは、書斎の机の上の花生けのバレンシアが満開になったその日であった。妻はミサヲちゃんに電話をかけて、昨日買って来たフーちゃんのジャンパーを渡すから、午後来て頂戴といった。(庄野潤三「卵」)
フーちゃんを描きながら庄野夫妻を描く。
もうこの頃には、庄野さんとしては、文学作品の紹介よりも、フーちゃんを主軸に据えた庄野家の家族日誌という構想が、頭の中にあったのではないだろうか。
そうした構想が、この後の『鉛筆印のトレーナー』(1992)や『さくらんぼジャム』(1994)へとつながっていったのかもしれない。
ちなみに『エイヴォン記』は、1986年(昭和61年)7月生まれのフーちゃんが2歳になったところから始まっているから、1988年(昭和63年)当時の庄野家の様子を描いたものである。
作品中で、庄野夫妻は、墓参りや親戚の結婚式のために大阪へ出かけているが、さすがに旅行中の様子には触れられていない。
庄野夫妻の日常スケッチも、あくまでフーちゃんを主人公として描かれているからだろう。
図書室からおもちゃの籠を自分で担いで来て、六畳へやっこらさと下す。それから赤いボールを投げ(あつ子ちゃんを相手に)遊ぶ。暫くボール投げに熱中する。図書室へ行って、籐の「お馬」に乗る。妻と窓際のベッドへ上って、、電気スタンドのスイッチを押してつけたり消したりする。お茶をいれて、山形のラ・フランスとメロンを食べる。(庄野潤三「卵」)
特別の出来事はない、まさに日常のスナップである。
書き留めておかなければ、やがてみんな忘れてしまうだろう小さな出来事にこそ、庄野さんは着目する作家だった。
なお、今回紹介されている文学作品は、シャーウッド・アンダスンの短篇「卵」である。
以前に紹介されているキャンフィールドの「情熱」と同じく、『アメリカ短篇集』(西川正身編・市民文庫)に収録されているものだ。
訳者は、吉田甲子太郎だった。
書名:エイヴォン記
著者:庄野潤三
発行:2020/2/18
出版社:小学館 P+D BOOKS