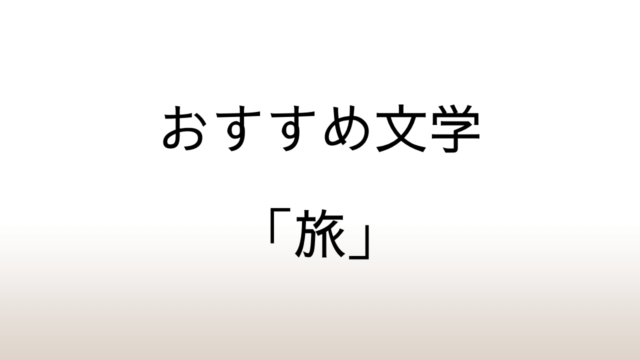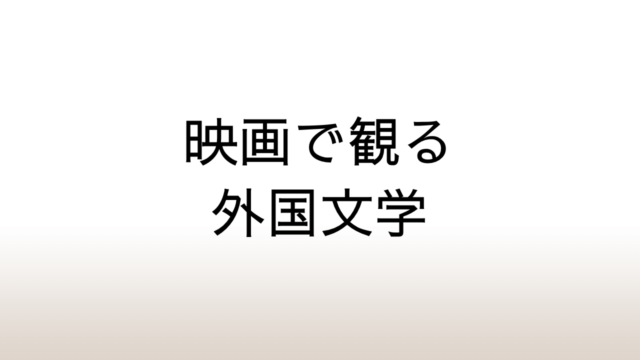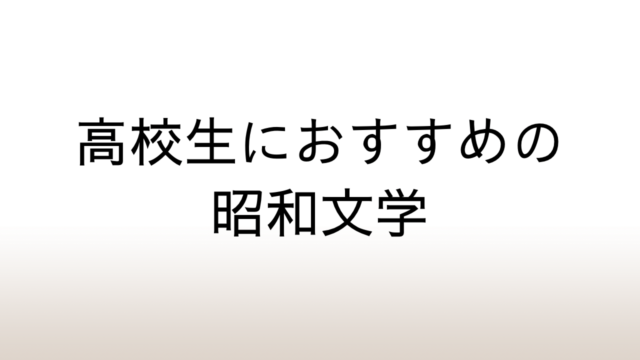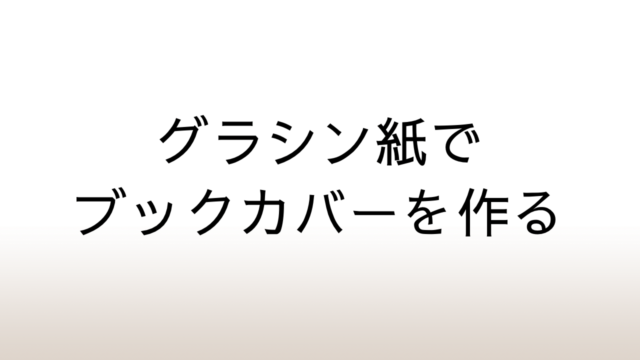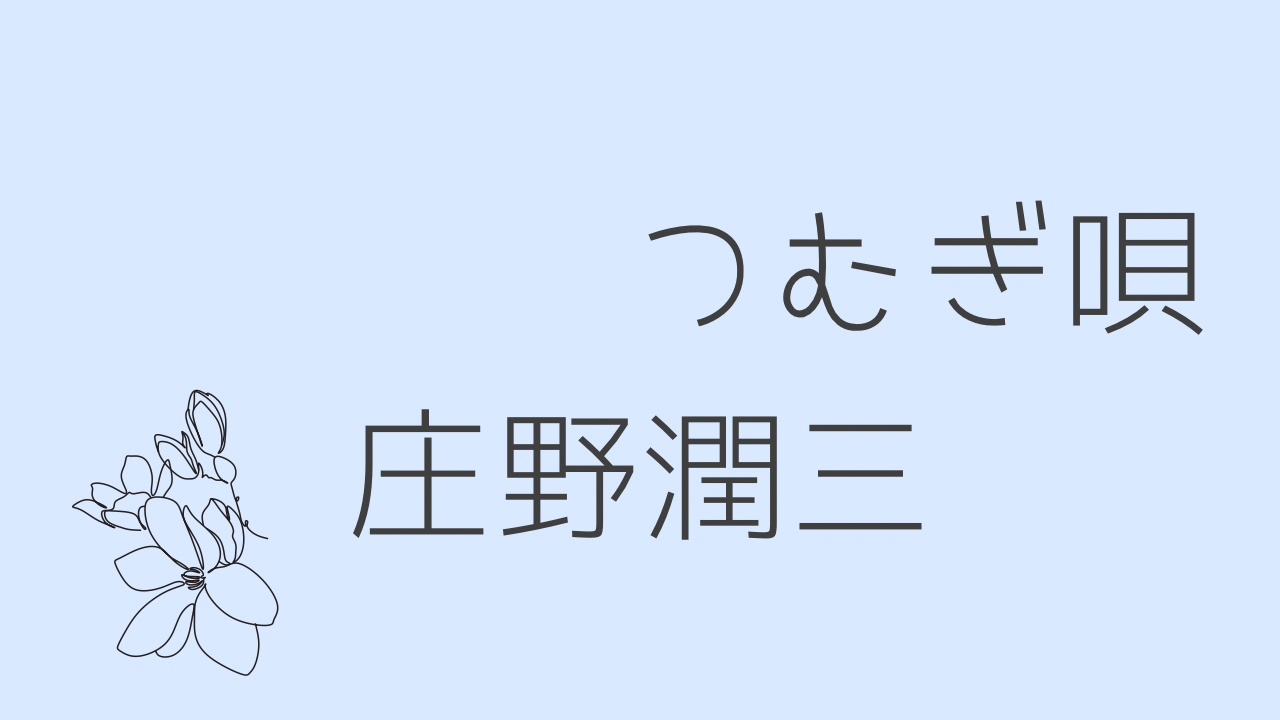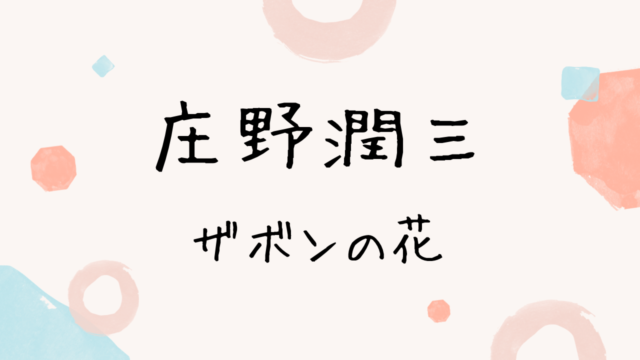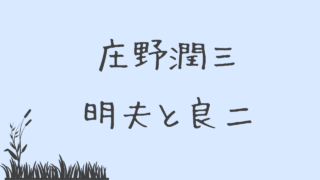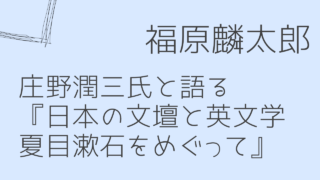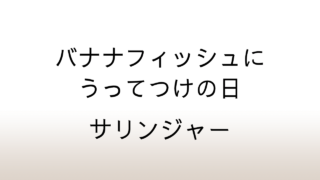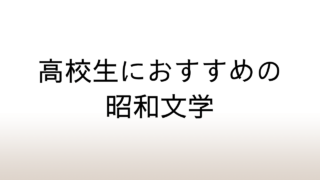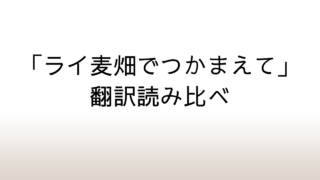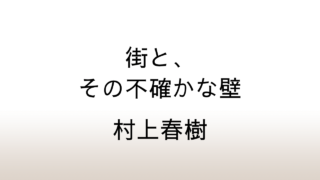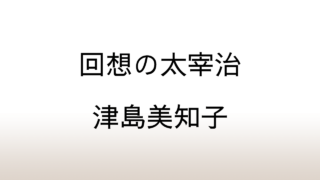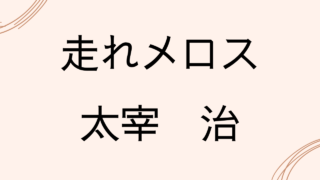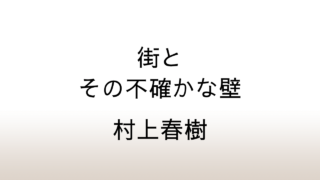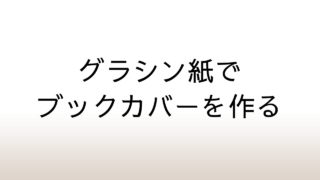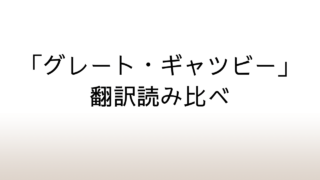庄野潤三の「つむぎ唄」は、3人の中年男性の物語である。
毛利、大原、秋吉の3人は、同じ町内会に住む40代の男たちで、それぞれが妻と子どもたちに囲まれた幸せな家庭を持っている。
特別な事件が起こらない代わりに、彼らはそれぞれの日々の暮らしの中に、味わい深い人生を感じていて、それが、この物語の大きなテーマとなっていく。
3人が揃って登場するのは、一番最初の毛利の娘の音楽会と、一番最後の毛利家で開かれた「町内会」だけで、基本的に、それぞれのエピソードは、それぞれの男性の家庭に焦点を当てて描かれている。
ピアノの発表会、庭の樹木、海水浴の家族旅行、テレビの野球観戦、子どもたちの受験勉強、差出人のないラブレター、初めての飛行機旅行、掘り炬燵、散髪、ラジオから流れる「カプリ島」、庭木用の鶏糞、父親参観日、高校受験の附き添い、宝塚観劇、合格祝い…言葉で並べてしまうと他愛のない、こうした出来事のひとつひとつが、案外、人生を豊かにしているのではないだろうか。
例えば、ピアノの発表会で娘が失敗をした時、毛利は「とちったところでどうということはないさ。人生にはとちって取返しのつかないこともあれば、笑って済むこともある。僕はちっとも心配なんかしていないよ」と言ってみせる。
あるいは、家族で海水浴に出かけた秋吉が「このときめきは、小学生の頃の夏休みにいつも待ちうけていてくれたあの喜びのかすかな名残であろうか。父も母もとうに死んでしまって、もうこの世の中にはいない。昔のあの賑やかだった家は、どこへ行ってしまったのか」と感慨に耽ったりする。
何気ないように思われる些細な出来事の積み重ねが、実は人生の励みになってくれるものだということを、この物語は教えてくれているようだ。
暮らしが穏やかであるほど感情に敏感になれる
われわれの毎日の暮しというものも、生活している当人に取っては、いやなことや情ないことや腹の立つことばかりで詰っているように思えるけれども、もう二度とそこで生きることが無くなって、はるか遠くから眺めるようになれば、こんな風にごく穏やかな、いい色をして見えるのかも知れないな。(「つむぎ唄」)
娘と飛行機旅行に出かけた大原は、飛行機から見下ろした地上の風景が「ふっくらとした、穏やかな、あたたかみのあるいい色になって見える」ことに気付いて、そこに人々の暮らしというものを重ね合わせてみる。
逆説的に言えば、遠くからは一見平板のように思われる日々の暮らしも、実際に日々を生きている本人によっては、案外いろいろなことがあったりするもので、そこに人生の面白さとか楽しさといったものがあるということだろう。
暮らしが穏やかであるほどに、喜びや悲しみや驚きといった感情に、人は敏感になれるのかもしれない。
ライフ・イズ・バット・ア・ドリーム(この世は夢に過ぎない)
「さあ、そろそろ輪唱だ。ロウ・ロウ・ロウヤ・ボートだ」毛利が云い出すと、食卓のまわりにいる者が四つの組に分けられた。(略)これは「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート(漕げ漕げボート)」で滑り出して、「ライフ・イズ・バット・ア・ドリーム(この世は夢に過ぎない)」という終りの句まで来ると、また始めに戻るのだが(略)(「つむぎ唄」)
物語のラストシーンは、毛利家に集まった大原と秋吉が、毛利家の五人家族と一緒に輪唱をする場面である。
散々、みんなで唱歌を合唱して盛り上がったところで、いよいよフィナーレの輪唱に入っていくところは、いかにも庄野文学にふさわしい賑やかな場面である。
著者(庄野潤三)は、人生のこうした楽しい瞬間を描き出すのが、本当に好きだったのだろう。
ここで歌われる「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート(漕げ漕げボート)」は、「ライフ・イズ・バット・ア・ドリーム(この世は夢に過ぎない)」というフレーズで終わりとなるが、「この世は夢に過ぎない」という言葉は、まさしく、この物語を象徴している。
ほとんど小説らしい感じのしない、あたかも日記や随筆を読むかのような作品の多いのが庄野文学の特徴で、本書「つむぎ唄」もまた、それぞれの男たちが書いた随筆のような物語に思われるが、至る場面でさりげない仕掛けがあるところに、文学作品としての充実感があるのだろう。
男たちの「つむぎ唄」を、いつまでも聴いていたいと思った。
書名:つむぎ唄
著者:庄野潤三
発行:1963/7/20
出版社:講談社