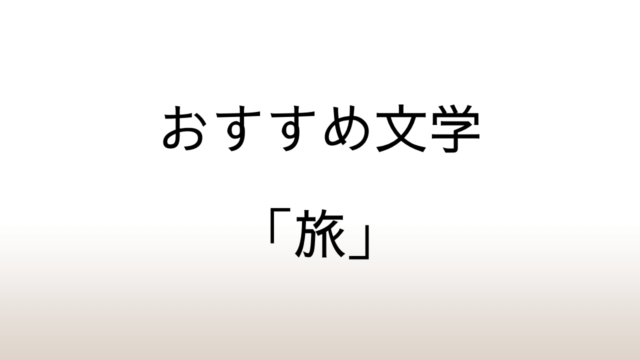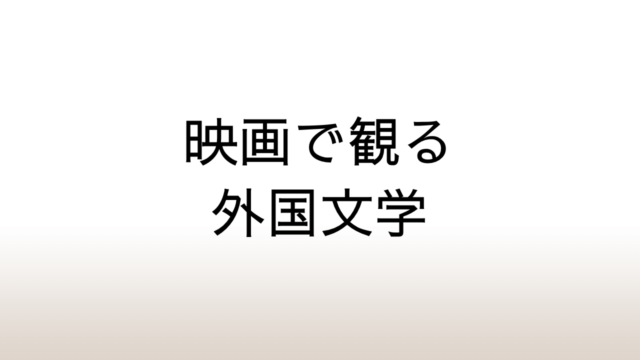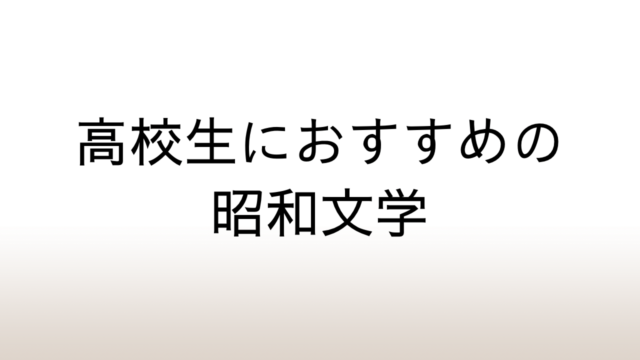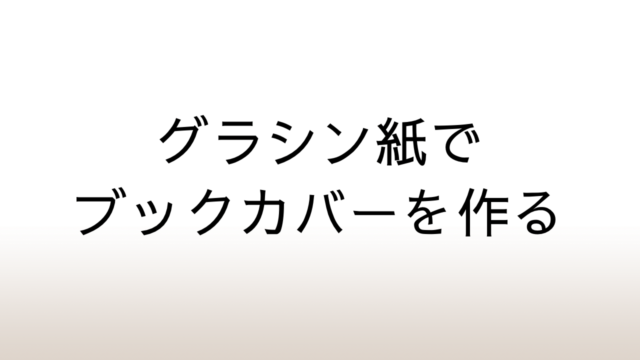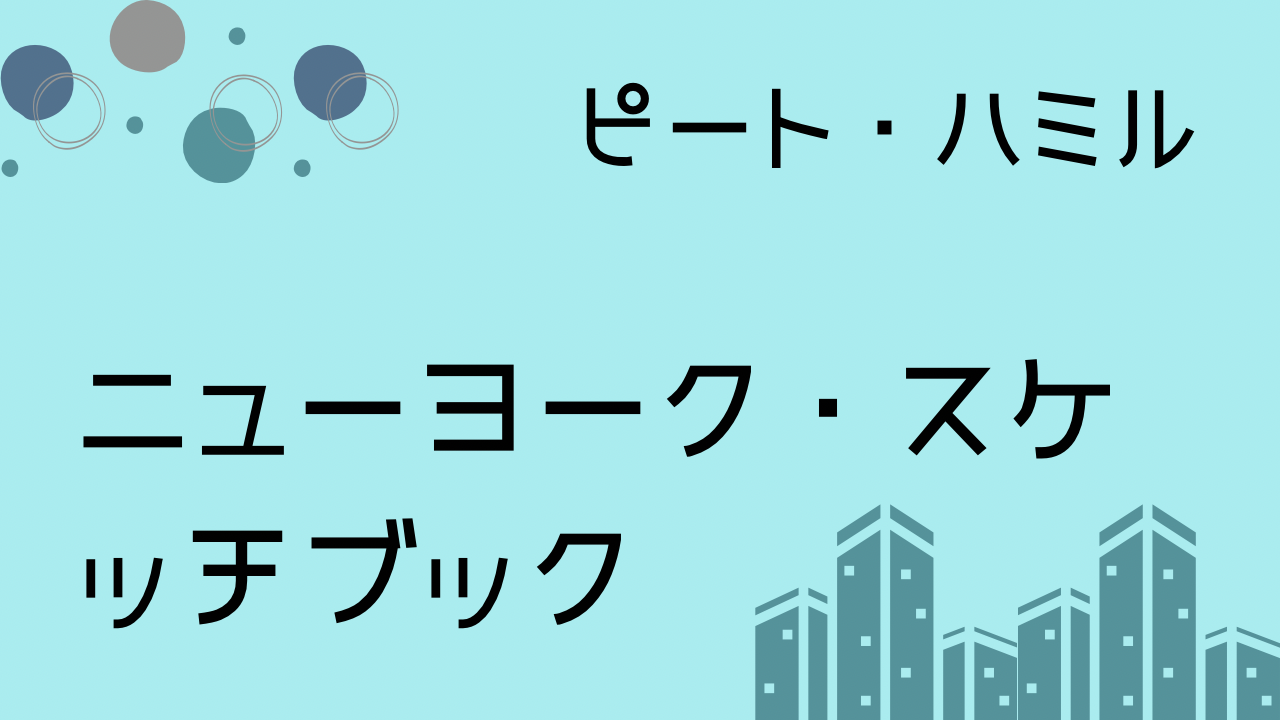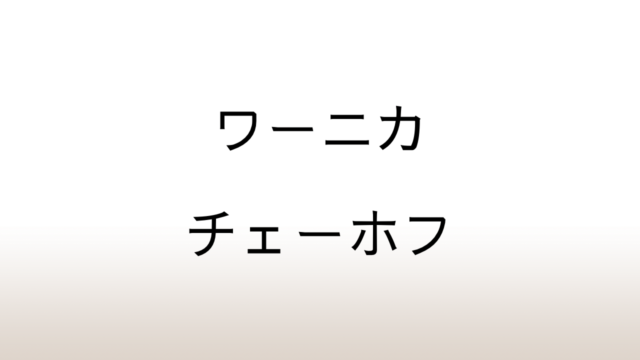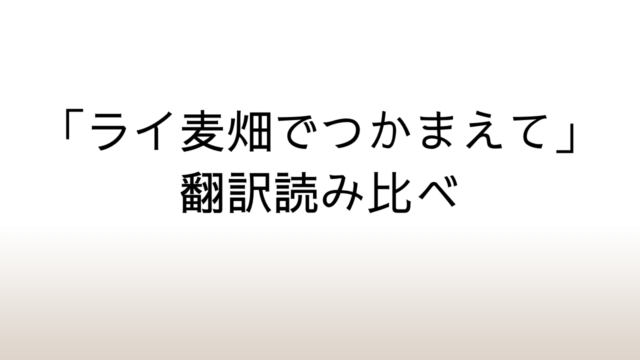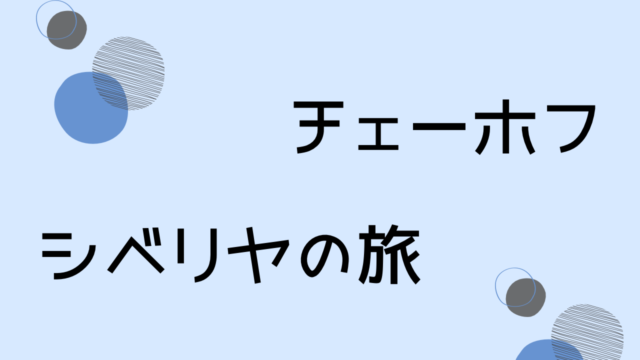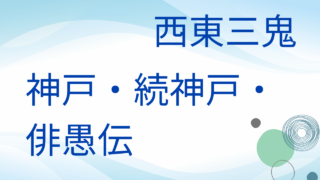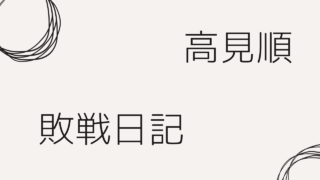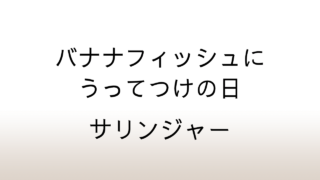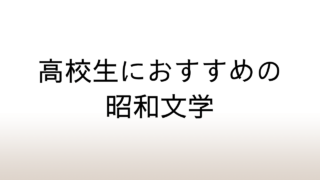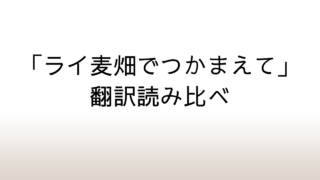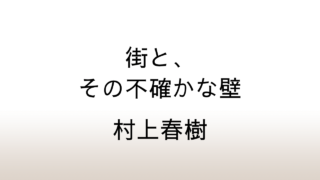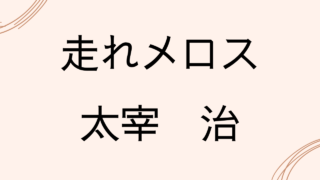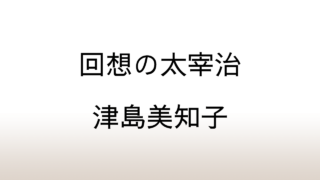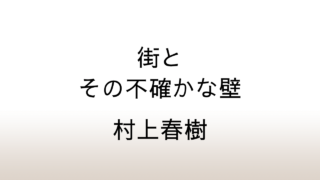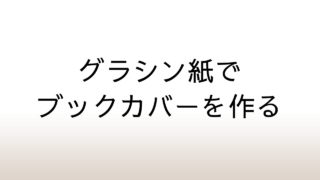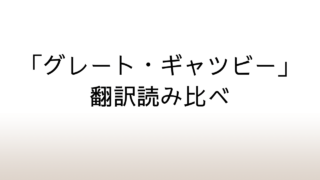ピート・ハミルさんが亡くなりました。
久しぶりに「ニューヨーク・スケッチブック」を読みました。
書名:ニューヨーク・スケッチブック
著者:ピート・ハミル、(訳)高見浩
発行:1986/4/4
出版社:河出文庫
作品紹介
「ニューヨーク・スケッチブック」は、アメリカのジャーナリストであるピート・ハミルのコラム集です。
著者は「ここにおさめた各編はいずれも新聞のために書いたものだが、言葉の厳密な意味での報道記事ではない。あくまでも物語であり、しかも短編である。といって、ふつう”短編小説”という言葉から理解される、首尾結構の整った作品でない」と言います。
「ここにおさめた物語は単なるスケッチにすぎない」のだと。
「1960年代に入って書きはじめた」短い物語は、ニューヨークの街に生きる普通の人々の暮らしを通して、人生とは何かを問いかけています。
全34編の物語に、文庫版の付録として「黄色いハンカチ」を収録。
原作の「The Invisible City」は、1980年にランダムハウス社から刊行されました。
なれそめ
僕は、アメリカのジャーナリストが書くコラムが好きです。
多くの場合、そうしたコラムは、街で出会った普通の人々を主人公としていて、彼らや彼女らの生きざまを通して「人間とは何か」「社会とは何か」「人生とは何か」ということを、読者に問いかける内容のものが多かったような気がします。
アメリカの新聞コラムを読み始めたばかりの頃に出会ったピート・ハミルも、そんなジャーナリストの一人でした。
もっとも、映画「幸福の黄色いハンカチ」の原作がピート・ハミルだったことを知ったのは、この文庫版「ニューヨーク・スケッチブック」を読んだときが初めてです。
あれ、日本の物語じゃなかったんだ?って、すごく不思議な感じがしました。
あらすじ
おれはこのニューヨークで生まれたんだよ。
ここがおれの故郷なんだ。
ここが好きで、どこよりも好きで暮らしてるんだ―
ニューヨークを誰よりも知りつくし愛しつづけている作家ピート・ハミルの<孤独と喪失に彩られた、見えない街>の物語。
巨大な街にくりひろげられる多様な人生―その<愛と喪失>の凝縮された一瞬のドラマを、絶妙な語り口で浮きぼりにした異色の短編34。
付録=新訳「黄色いハンカチ」(映画「幸福の黄色いハンカチ」原作)
(背表紙の紹介文より)
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
いいから、おっぱいが目立つように胸を張って。
いいから、おっぱいが目立つように胸を張って。おっぱいは誇示するためにある、ってのが、あたしの説なんだから。誇示するっていうのは、見せびらかす、ってことなんだからね。(「ニューヨーク・スケッチブック11」)
今年33歳になるシングルマザーのカーメンは、とある土曜日の夜、友人のネレイダと一緒にブロードウェイのダンスホールへ出かけます。
周囲の若い男女の「珍奇な動物を見て面白がっているような笑み」を感じながら、カーメンはネレイダに促されながら、店へと入っていきます。
いつまでも躊躇しているカーメンに、ネレイダは「あんたは素晴らしいよ。十年前と変わらないくらい美人だし。別れた亭主なんかよりいい男を見つけなくちゃ」と励ましながら、「さあ、おなかを引っこめて、胸を突きだすんだよ」とせかします。
やがて、踊りの輪の中へ入ったカーメンへ送られた称賛の拍手。
彼女の青春は、まだまだこれからなんだということが、ダンスホールの夜の中から、確かに伝わってきていました。
ちょうど1953年という年そのものが消えてしまったように
二人は黙ってリヴィングストン・ストリートのほうに曲がった。が、彼の記憶にあったレストランは消えていた―ちょうど、<ナムズ>や<ローザーズ>や1953年という年そのものが消えてしまったように。(「ニューヨーク・スケッチブック13」)
中年になった男性が、学生時代に愛し合っていた元カノと再会するというストーリーは、新聞コラムでは、もしかすると、良くある筋書きなのかもしれません。
大抵の場合、若い二人は理由あって別れた経緯があり、それぞれに家庭を持ちながら、それぞれの人生を生きています。
奇跡的な再会は新しいドラマの始まりを予感させますが、現実社会の中で、それほど簡単に起こりうるものではありません。
「クレア…できたら、これからもときどきどこかで会ってもらえないだろうか、どこかで一杯やるとかして」と彼が言った瞬間、彼女は無表情になって「ロバート、私は夫がある身なの―」と冷たく言い放ちます。
男は、人生にいつまでも夢を追いかけるロマンチストなのです。
ただ、きみを抱きたいだけなんだ。セックスをしたいんじゃない。
「今晩、きみと寝たいんだ」マロイは唐突にそう言った。「ただ、きみを抱きたいだけなんだ。セックスをしたいんじゃない。君の体を抱いているだけでいい」(「ニューヨーク・スケッチブック12」)
百貨店の紳士服売り場で、別れた妻が新しい恋人と一緒にいる場面を目撃したマロイは、その晩、15歳年下のスチュワーデスを高級イタリア・レストランへ連れ出します。
「彼女は実際の歳より若く見えた。髪もあの頃より長くしている」
スチュワーデスと食事をしながらも、別れた妻の姿を思い出してしまうマロイは、食事の席を抜け出して、元嫁へ電話をかけます。
「どうしてもきみを抱きたいんだ、今晩だけでいい」
マロイは懇願しますが、元嫁は「今夜わたし、約束があるの」と、冷たくマロイを拒絶しました。
なんといっても男は、人生にいつまでも夢を追いかけるロマンチストなんですね。
こんなさりげない人生の物語がたっぷりと詰まった「ニューヨーク・スケッチブック」。
大都会の片隅で繰り広げられている普通の人々の普通のドラマにこそ、人生が込められているのではないでしょうか。
読書感想こらむ
「ニューヨーク・スケッチブック」は、小説ともエッセイとも区別の付けようがない物語です。
フィクションなのかノンフィクションなのかさえ分からない。
それはニューヨークという大都会の片隅で、いかにも毎晩のように起こっているような普通の人々による普通のドラマだからです。
ピート・ハミルといえば「幸福の黄色いハンカチ」の原作者として有名ですが、僕はむしろ、名もなきコラムのひとつひとつにこそ愛着を感じてしまいます。
主人公は、遠い昔に別れた恋人と再会する中年男であったり、新しい人生を歩み始めようとしているアラサーのシングルマザーであったり。
都会で生きる普通の人々の暮らしを通して、ピート・ハミルは「人生とは何か?」という普遍的な問題を、僕たちに問いかけてきます。
答えを探すのは読者であり、人生を生きるのも読者である。
ピート・ハミルのコラムを読みながら、僕も街へ出て探してみたくなりました。
誰かの「人生」っていうやつを。
まとめ
「ニューヨーク・スケッチブック」は、誰かの人生の断片を綴ったコラム集。
それは、まるでスケッチブックに描かれたラフ・スケッチのように、自由で鮮やかな物語だ。
ひとつの人生の中に、無数のドラマがある。
著者紹介
ピート・ハミル(ジャーナリスト)
1935年(昭和10年)、ブルックリン生まれ。
ニューヨーク・ポスト紙の記者として活躍。
「ニューヨーク・スケッチブック」刊行時は45歳だった。
高見浩(翻訳家)
1941年(昭和16年)、東京生まれ。
雑誌「宝石」編集者として活躍。
「ニューヨーク・スケッチブック」翻訳版刊行時は41歳だった。