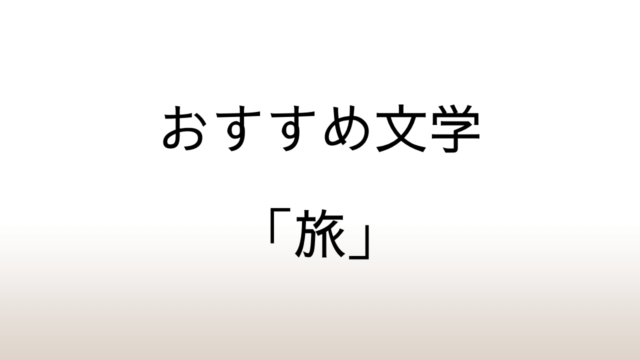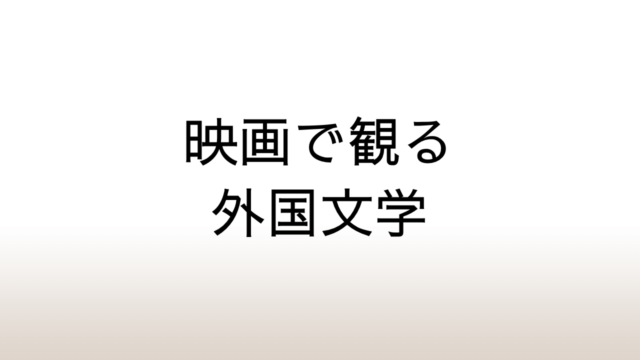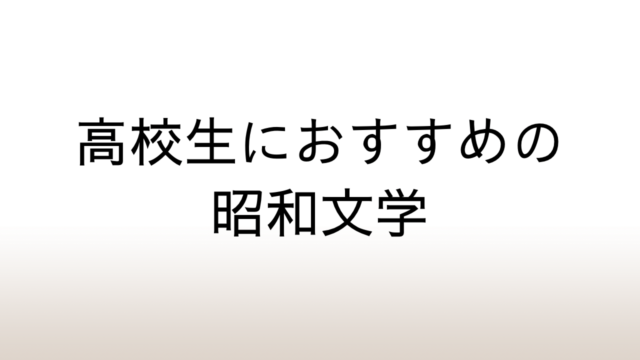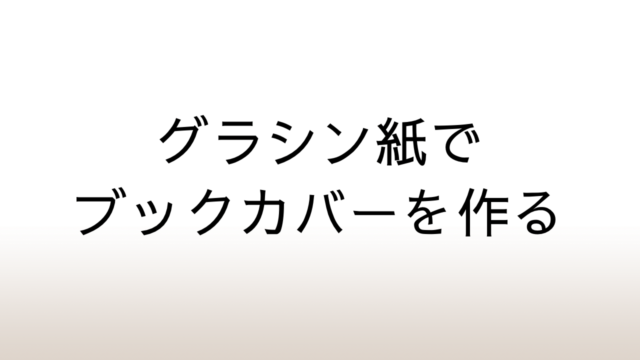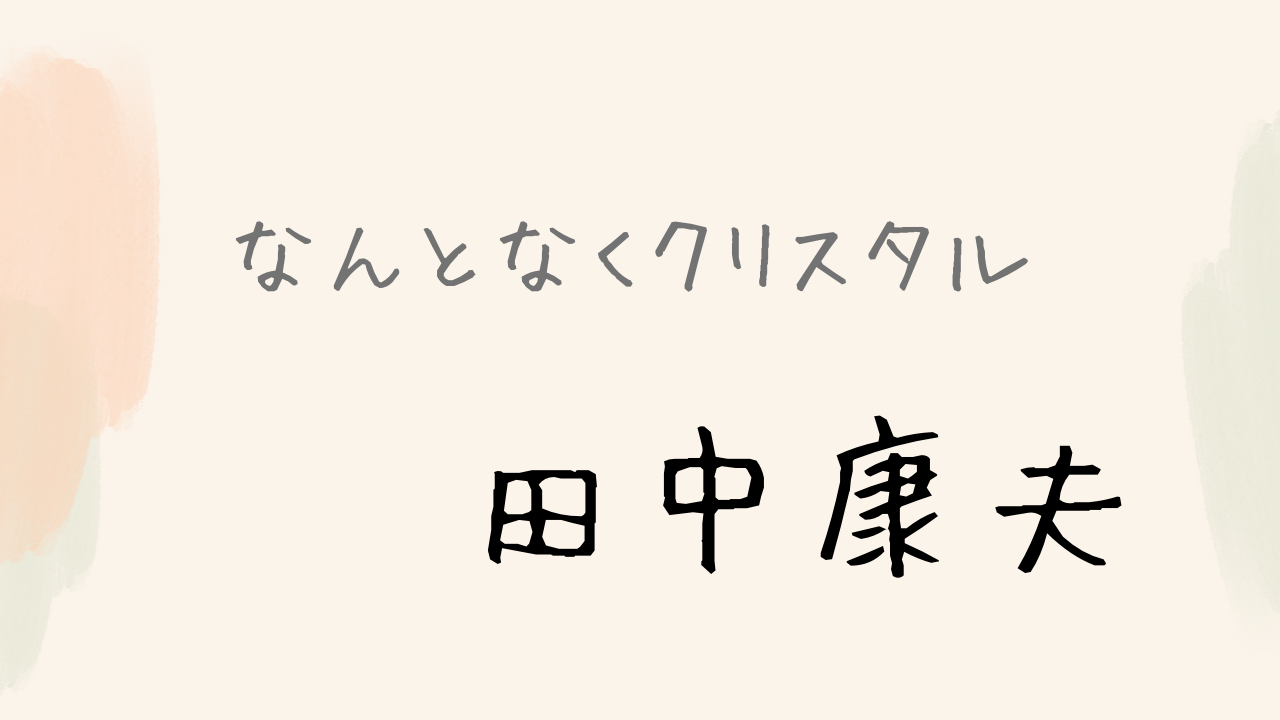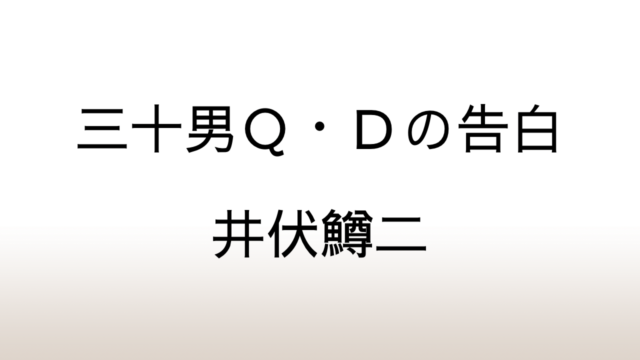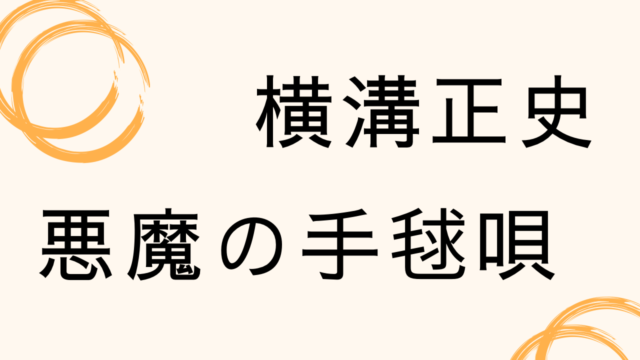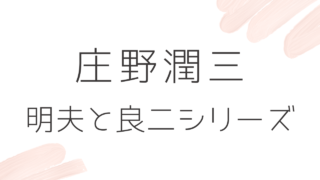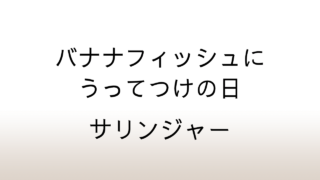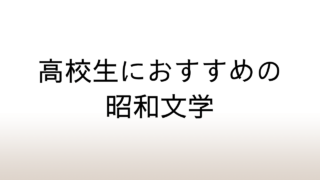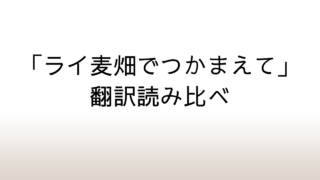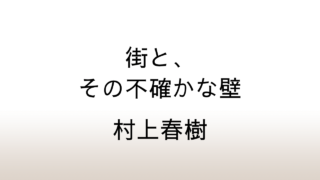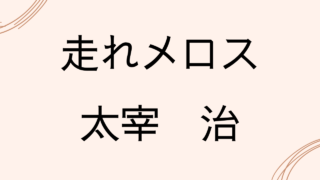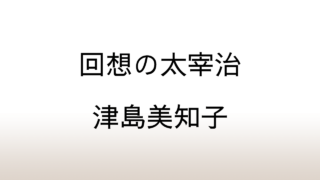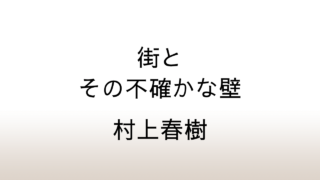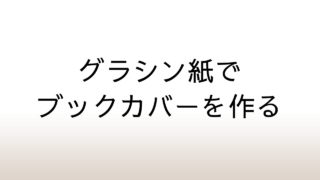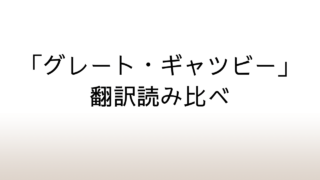横浜市長選の候補者の中に、田中康夫さんの名前がありました。
「元・長野県知事」という肩書ですが、何と言っても『なんとなく、クリスタル』の作者として忘れることのできない存在です。
1980年代冒頭、日本中を席巻した名作『なんとなく、クリスタル』は、一体何がすごかったのか?
今回は、社会現象ともなったベストセラー『なんとなく、クリスタル』の魅力をご紹介します。
概要
『なんとなく、クリスタル』は、作家・田中康夫さんのデビュー作となる長編小説です。
新潮文庫版『なんとなく、クリスタル』のあとがきによると、1980年(昭和55年)5月、当時、一橋大学の学生だった田中さんは、この作品を大学の図書館で書き上げ、5月31日の朝、河出書房の文芸誌「文藝」に郵送で応募し、10月16日夜の選考会で、見事に昭和55年度文藝賞入選作に決定しました。
ちなみに、当時の「文藝賞」選考委員は、江藤淳、小島信夫、島尾敏雄、野間宏の四氏でした。
作家・田中康夫のデビュー作となる『なんとなく、クリスタル』は、11月7日発売の「文藝」12月号に掲載され、翌1981年1月20日、単行本が発売されます。
単行本の奥付の発行日には「1月25日」と記載されているものの、都心部の書店など一部の書店では1月20日の夕刻に店頭に並んだということらしいのですが、初版2万部の『なんとなく、クリスタル』は、なんと当日のうちに完売してしまいました。
すぐに増版が重ねられ、夏を迎える頃にはミリオンセラーとなった『なんとなく、クリスタル』は、1981年では総合3位となる大ベストセラー作品となりました。
ちなみに、1981年のベストセラーの1位は黒柳徹子の『窓際のトットちゃん』、2位は青島幸男の直木賞受賞作『人間万事塞翁が丙午』でした。青島幸男は後の東京都知事、田中康夫は後の長野県知事、なんだかすごい時代です。
多くのマスコミが、現役大学生が書いた、この斬新な文学作品を取り上げ、まさにブームがブームを呼ぶ形で『なんとなく、クリスタル』は当時の日本社会に定着し、「クリスタル族」なる言葉が流行語となりました(「クリスタル族」については、後ほど詳しく解説します)。
ちなみに、1981年には「コンタック600」のTVCMで、女優の中原理恵が使った「えぐいんじゃないの~」から「えぐい」が流行語となっています。鳥山明の大人気漫画『Dr.スランプ』で、主人公のあられちゃんが使った「んちゃ」が流行ったのも、この頃です。
社会現象ともなった『なんとなく、クリスタル』は、1981年(昭和55年)下半期の芥川賞候補となりますが、惜しくも受賞とはなりませんでした。
この時の芥川賞受賞作は、尾辻克彦『父が消えた』(「文学界」掲載)で、他の候補作としては、高樹のぶ子『その細き道』(「文学界」掲載)などがあります(高樹のぶ子『その細き道』は、1984年にTBSでドラマ化されました。伊藤麻衣子主演)。
ちなみに、当時の芥川賞選考委員は、井上靖、遠藤周作、大江健三郎、開高健、瀧井孝作、中村光夫、丹羽文雄、丸谷才一、安岡章太郎、吉行淳之介。
さて、芥川賞受賞は逃したものの、どうして『なんとなく、クリスタル』は、社会現象となるほどにヒットしたのでしょうか?
あらすじ
『なんとなく、クリスタル』は、主人公の女子大生「由利」が自分の暮らしぶりを語る独白の形式で書かれた小説ですが、ストーリーとして際立った物語があるわけではありません。
フランス語の授業をさぼった由利は、同棲相手(淳一)が留守の日に、前夜にディスコで知り合ったばかりの男の子(正隆)とデートして、一夜限りの関係を結んでしまいますが、絶頂に達することはできません。
「愛情がなければいけない」ということを悟った由利は、淳一のことが、なおさらに愛おしくなってしまいます。
ストーリーとしては以上で、概略を説明してしまうと「なんのこっちゃ」という感じになってしまいますが、『なんとなく、クリスタル』は、たったこれだけの物語の中で、1980年当時の若者が持っていた価値観を見事に包括しています。
最大の特徴は登場人物のキャラクター設定が完璧なことで、この小説は「キャラクターを読ませる小説」だと言っても過言ではありません。
例えば、主人公の由利は、どんな女の子なのか。
由利は、昭和34年生まれの神戸出身。
「渋谷四丁目にある”七人の敵がいた大学”」(青山学院大学のことと思われます)に通う女子大生で、大学では英文科に学び、テニス同会に所属しています。
彼女は、神宮四丁目にあるマンション(十畳の洋間と八畳のダイニング・キッチンがある)で、恋人の淳一と一緒に、お互いに縛られない大人の関係を築きながら暮らしています。
シドニーにいる彼女の両親から仕送りはありますが、贅沢な暮らしを望む彼女は、モデルの仕事をして毎月40万円以上を稼ぎ、「三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい」と考えています。
彼女は「野菜や肉を買うなら、青山の紀伊国屋がいいし、魚だったら広尾の明治屋か、少し遠くても築地まで行ってしまう」くらいにライフスタイルにこだわりをもっていて、パンを買うのは代官山のシェ・リュイ、ケーキは六本木のルコントか銀座のエルドール。
テニスの練習がある日には、朝からマジアかフィラのテニス・ウェアを着て、学校まで行ってしまいますが、普段の日は、気分によってボート・ハウスやブルックス・ブラザーズのトレーナーを着ることにして、スカートは原宿のバークレーで買ったものを合わせます。
着ていて一番気分がいいのは、サン・ローランやアルファ・キュービックで、六本木へ遊びに行く時には、クレージュのスカートかパンタロンに、ラネロッシのスポーツ・シャツの組み合わせ、ディスコ・パーティにはサン・ローランかディオールのワンピース。
洋楽の好きな彼女は、青山のパイド・パイパー・ハウスで輸入レコードを買い、ローラースケートは駒沢公園で、スカッシュをするなら等々力の伊勢丹スポーツ・クラブまで出かけ、有栖川公園から元麻生の西町インターナショナル・スクールを通って、オーストリア大使館の横の暗闇坂を下って麻生十番まで散歩をしたりします。
これは、彼女のライフスタイルの一部ですが、ご覧のように『なんとなく、クリスタル』では、登場人物たちの生活が具体的な固有名詞によって表現されていることが大きな特徴で、作品には、この固有名詞を解説するための注釈が、全部で442個も付されています。
あまりにも多数のブランドが登場するため、この小説は「ブランド小説」などと揶揄されましたが、この「ブランド」の存在こそが、『なんとなく、クリスタル』という小説の本質でもありました。
それは一体、どういうことだったのでしょうか?
ちなみに、ディスコで知り合った男の子の名前「正隆」は、松任谷正隆と同じ字です。作品中にも「ユーミンのダンナ様として知られる、アレンジャーの松任谷正隆さんと、同じ字をかく彼は、、、」と紹介されています。恋人の「淳一」は、小説家の渡辺淳一と同じ字ですか、、、
読書感想と解説
「なんとなく、クリスタル」は「ブランド小説」なのか
新潮文庫版『なんとなく、クリスタル』のあとがきの中で、著者の田中康夫さんは「どういったブランドの洋服を着て、どういったレコードを聴き、どういったお店に、どういった車に乗って出かけているかで、その人物が、どういったタイプの人物かを、今の若者は判断することが出来るのです」「人は、年齢に関係なく、みな、そうした他の力を借りて、自分自身を証明しているのです」と語っていますが、『なんとなく、クリスタル』という作品において、ブランドとはまさに個を証明するための記号でした。
ブランドという記号(あるいはレッテルと言ってもいい)を貼り付けることによって、パーソナリティを語ることのできる時代が到来したと言えるのかもしれませんね。
それでは『なんとなく、クリスタル』は、ブランド讃歌の「ブランド小説」だったのでしょうか。
作品中で、由利は一夜限りに関係を結んだ正隆と、こんな会話を交わしています。
「結局ね、ブランドに弱いんだよね。僕らの世代って。ま、僕らの世代というより、日本人全体がそうなのかな」「多分、そうなんじゃない」「向こうのブランド名がついていると、アンダー・ライセンスの日本製でも、なんとなくいいものに見えてきちゃうじゃない。でも、そこに付いているタグを取っちゃったら、こりゃ絶対売れないよね」
この後、由利は「ブランドにこだわることは、バニティーなのかな、と考えてしまう」「でも、それで気分がよくなるのならいいじゃないか、とも思えてくる」「ブランドが、ひとつのアイデンティティーを示すことは、どこの世界でも同じなのだから」と考えます。
一方で著者は「ブランドに弱いんだよね」という言葉の注釈として「この小説の登場人物はマネキン人形で、中身が空洞だ、という「文芸」評論家だって、学歴や肩書にこだわる人です」「この小説には生活がない、という「文芸」記者だって、新聞社のバッジというブランドを取りはずしたら、タダの人です」と、皮肉的なコメントを寄せています。
『なんとなく、クリスタル』は、あまりにも斬新過ぎたということで賛否両論があり、評価の分かれる文学作品だったようですが、そうした評価も含めて、1980年代冒頭という時代を表しているような気がします。
「クリスタル族」とはどんな人たちか
ベストセラー小説『なんとなく、クリスタル』は社会現象ともなり、「クリスタル族」という流行語まで生まれましたが、「クリスタル族」とは、一体どのような人たちを言うのでしょうか。
「クリスタル族」とは『なんとなく、クリスタル』に登場する若者たちの表面的なライフスタイルをとらえた言葉で、都市部の大学に通う女子大生全般を示す言葉として、幅広く使われる形で流行しました。
世代的には、由利と同世代の1960年(昭和35年)前後生まれで、都市部で大学生活を送っていた方々ということになるので、1960年生まれで青山学院大学英文科を卒業した川島なお美さんなんて、もろ「クリスタル族」という感じです(イメージ的にもぴったり)。
バービーボーイズの杏子さん(1960年生まれ、大妻女子大)もクリスタル族、山下達郎夫人の竹内まりやさんは1955年(昭和30年)生まれなので、世代的には「クリスタル族」よりも少し上になるでしょうか。
ところで、「クリスタル族」のクリスタルって、どんな意味で使われているのでしょうか。
そして、どうして「なんとなく」なのでしょうか。
クリスタルとは透明感のあるライフスタイル
ディスコで知り合った正隆と一夜限りの関係を結んだ後で、由利は「クリスタルなのよ、きっと生活が。なにも悩みなんて、ありゃしないし…」とつぶやきます。
その時、正隆が答えた台詞は、次のようなものでした。
「クリスタルか…。ねえ、今思ったんだけどさ、僕らって、青春とはなにか! 恋愛とはなにか!なんて、哲学少年みたいに考えたことってないじゃない? 本もあんまし読んでないし、バカみたいになって一つのことに熱中することもないと思わない? でも、頭の中は空っぽでもないし、曇ってもいないよね。醒め切っているわけでもないし、湿った感じももちろんないし。それに、人の意見をそのまま鵜呑みにするほど、単純でもないしさ」(田中康夫「なんとなく、クリスタル」新潮文庫)
おそらく、この部分で「クリスタル」という言葉の意味がすべて語られているようです。
全共闘世代のように熱く燃え上がることもなければ、吉田拓郎みたいに「人間なんて…」と自己追求をするわけでもないけれど、シラケ世代のように醒め切っているわけでもない。
「クールっていう感じじゃないよね。あんましうまくいえないけど、やっぱり、クリスタルが一番ピッタリきそうなのかな!」という正隆の言葉のように、ホットでもクールでもない、温度感のない世代を表す言葉、それが「クリスタル」だったんですね。
それでは、どうして「なんとなく」なのでしょうか。
作品中で由利は「なんとなく気分のよいものを、買ったり、着たり、食べたりしている」「なんとなく気分のよい音楽を聴いて、なんとなく気分のよいところへ散歩しに行ったり、遊びに行ったりする」と考えながら、「(淳一と)二人が一緒になると、なんとなく気分のいい、クリスタルな生き方ができそうだった」と感じます。
「クリスタルな生き方」というのは、曲げることのできない主義主張という強固なではなく、「なんとなく」そんな生き方をしていくのだといった程度の、柔らかい自己主張を持った言葉だということでしょう。
「自分はクリスタルに生きるんだ!」と言った瞬間に、それは「クリスタル」ではなく「ホット」な生き方になってしまいます。
こだわりの生き方を持っているけれども、それは「なんとなく気分の良いものを選ぶ」ことであって、そんな無味無臭で乾燥した生き方が、「なんとなく、クリスタル」というライフスタイルだったのではないでしょうか。
なんとなくクリスタルなライフスタイル。
それが、この小説の本当に伝えたかったことだったように思います。
「なんとなく、クリスタル」は注釈で楽しむ小説だった
ところで、この小説の醍醐味は、何と言っても、欄外に設けられた(だけど、本文と同じくらいのボリュームがある)数々の注釈です。
例えば「髪型をサイド・グラデェイションにきめた」は「髪を四分六分に分けながら、サイドの髪を後ろへ流してサイドから後ろへの髪の毛の流れを強調したヘヤ・スタイル」などと説明があって、1980年代冒頭の風俗を知る良い手がかりとなってくれます。
注釈を読んでいくだけでも、80年代カルチャーに関心のある方にとっては勉強になりそう。
せっかくなので『なんとなく、クリスタル』に登場するファッション・ブランドと、その注釈を並べてみましょう。
リバティ・プリント
ロンドンにある名門百貨店。リバティのテキスタイル。花柄プリントのテキスタイルは『くまのパディントン』を生み出す、イギリスの雰囲気を伝えてくれます。なぜか日本では、「西武」百貨店が販売してくれています。
アルファ・キュービック
シックで上品な商品を出すといわれている、日本のファッション・メーカー。
バラクータ
イギリスのブランド。トラッド少年に人気があります(ちなみに「スィング・トップ」は「手っ取り早く言えば、たかがジャンパーのこと」との解説あり)。
レノマ
本来は、フランスの小さなブチック。日本では、ライセンス物のバッグ、化粧品等を出す、スエードのバッグは、手あかが付きます。
ボート・ハウス
渋谷二丁目にある、異常人気のトラッド・ショップ。人が多すぎて、アーア。品物も、美的感覚ゼロの山積みでアーア。
ブルックス・ブラザーズ
米国の有名なアイビー・ショップ。日本では、北青山三丁目に支店があります。それにしても、今どき、あのロング・ポイント・カラーのボタン・ダウン・シャツを、アイビー少年気取りに、一体、誰が買っていくのでしょう。
サン・ローラン
二十一歳でクリスチャン・ディオールの主任デザイナーとなり、1966年には自らのメゾンを持った、イヴ・サン・ローランのブランド。アンダー・ライセンスの日本製婦人服は、アルファ・キュービックの製品です。フランスものには、リヴ・ゴーシュの表示があります。
エルメス
馬具商からスタートしたのに、今や超高級ブランドになりまして…
エスティ・ローダー
このブランドを扱っているかどうかが、即、その百貨店の格付けに使われるブランド。
シップス
銀座にあるトラッド・ショップ。バークレーや、この店をはじめ、原宿にあるクルーズ、シーズ、カヌーといったトラッド・ショップのローマ字入りトレーナーは、トラッドな服装をしない少年少女諸君も、しばしば後生大事に着ていることがあります。
ミハマ
横浜は元町にあるくつ屋さん。カッター・シューズと呼ばれるカカトがペッチャンコな”ペチャぐつ”によって、今や、全国津々浦々のJ・Jガール志望の少女に熱烈人気。
『なんとなく、クリスタル』は80年代ファッションに興味のある方にもお勧めの教科書となってくれそうですね。
まとめ
ということで、以上、今回は田中康夫さんの『なんとなく、クリスタル』について全力で語ってみました。
大ベストセラーとなった『なんとなく、クリスタル』は、当然映画化の流れとなり、1981年、かとうかずこ主演で松竹から映画化されましたが、こちらの方は小説のようなヒット作とはならなかったようです。
また、著者の田中康夫さんが作詞した『なんとなく、クリスタル』という曲(作曲は近田春夫)を、柴田恭兵さんがシングルで出していますが、こちらも小説のようにバズることはありませんでした。
近田春夫のロックンロールを柴田恭兵が熱唱すると、全然「なんとなく」でも「クリスタル」でもないように思います。透明感のある徳永英明あたりにミディアムナンバーを歌ってもらった方が「らしい」ような、、、ちなみに、徳永英明は1961年生まれのクリスタル世代。柴田恭兵は1951年生まれでした。
『なんとなく、クリスタル』は、やはり文学作品としての小説の持つ魅力が大きな作品だったのではないでしょうか。
次に気になるのは、横浜市長選挙ですね!
書名:なんとなくクリスタル
著者:田中康夫
発行:1985/12/20
出版社:新潮文庫