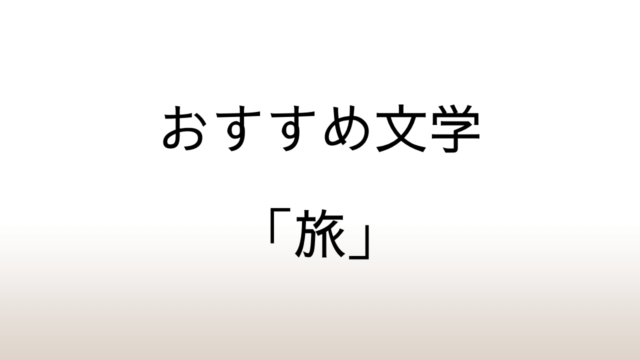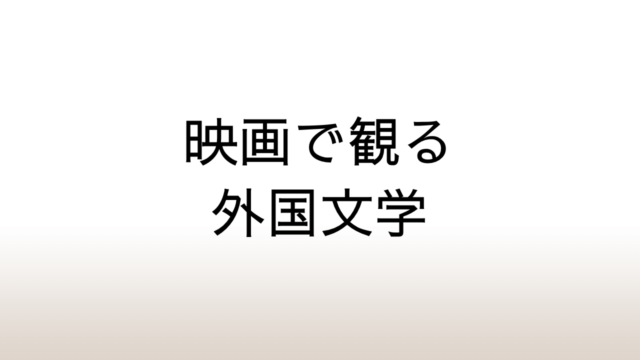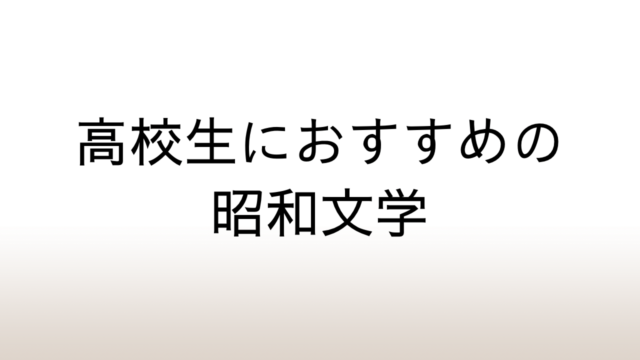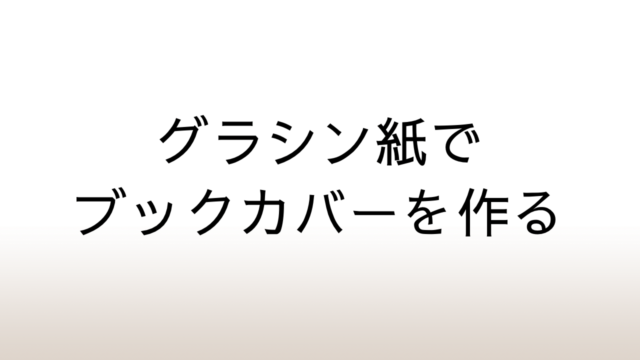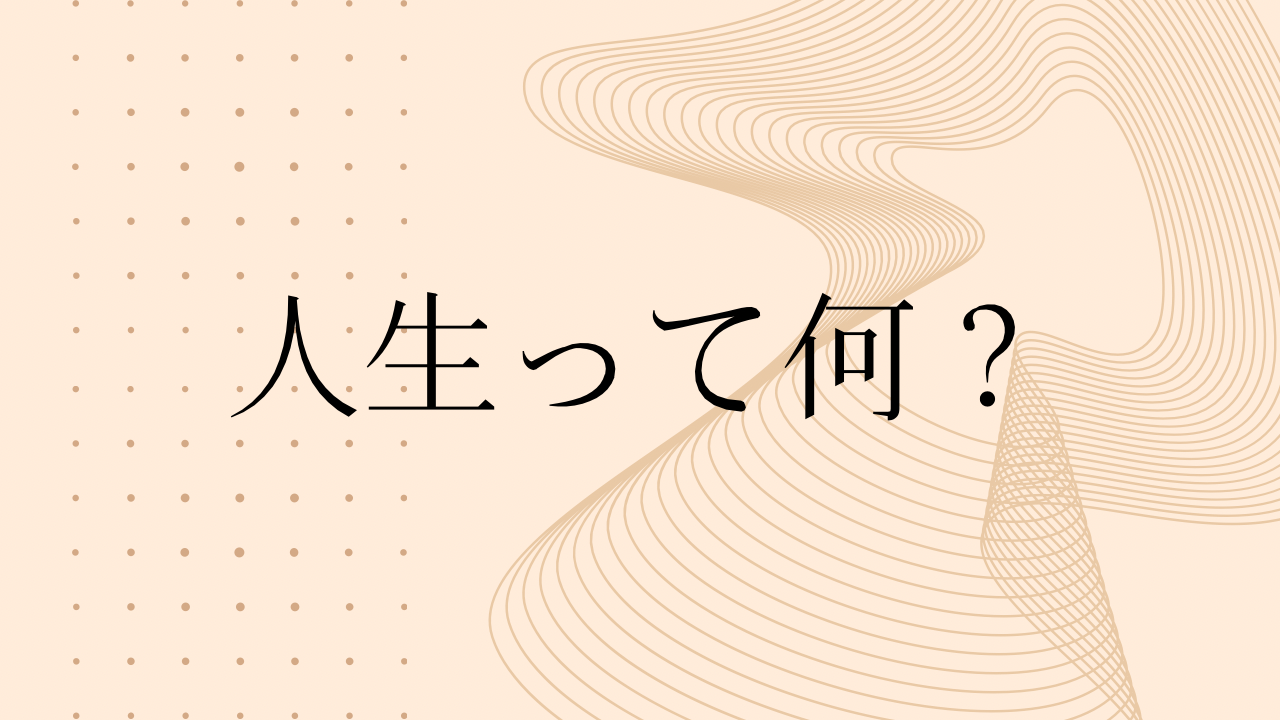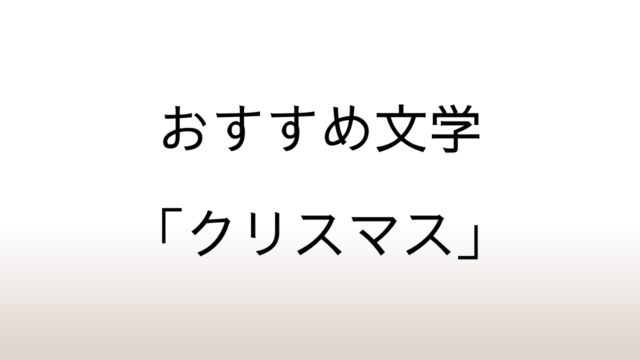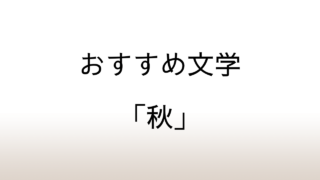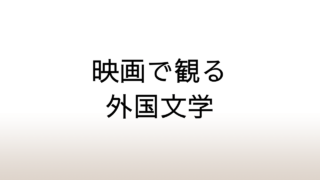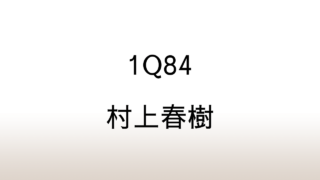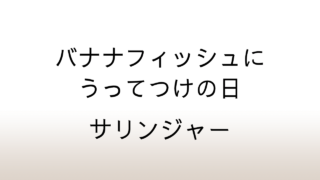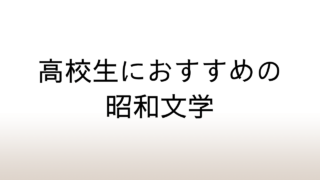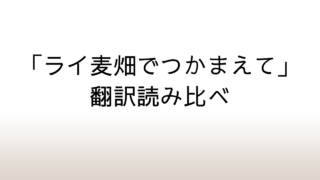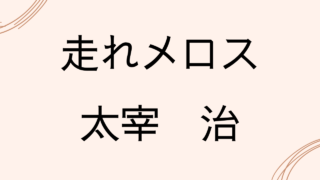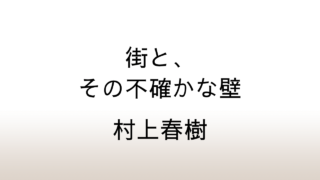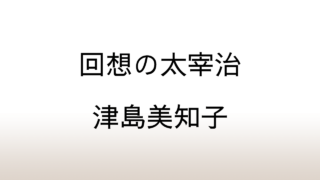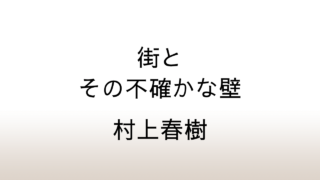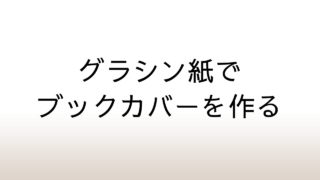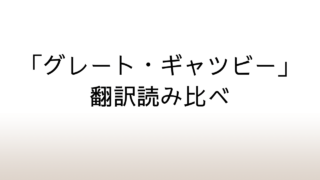「人生って何だろう?」と、深く考えさせられる文学作品を集めてみました。
秋って、いろいろと物思いに耽りたくなる季節ですよね。
小説を読んで、人生と向き合ってみてはいかがでしょうか。
チャールズ・ラム「エリア随筆」(1823年)
イギリスのエッセイスト、チャールズ・ラムの代表作です。
ラムはロンドンをこよなく愛したサラリーマンでした。
「エリア」とは架空の人物の名前で、作品名には「エリアが書いたエッセイ」という意味があります。
ロンドン市民の人生が、繊細な感覚で綴られた作品です。
私たちは、アリスの子供でもなければ、あなたの子供でもありません。いえ、子どもでもなんでもないのです。アリスの子供たちは、バートラムをお父さんと呼んでいます。私たちは空(くう)なのです。そう言うにさえあたらないものなのです。幻なのです。(チャールズ・ラム「幻の子供たち」山内義雄訳)
島崎藤村「破戒」(明治39年)
詩人として有名な島崎藤村が書いた長編小説です。
被差別部落に生まれた出自を隠して生きる男の数奇な運命。
日本の自然主義文学を代表する作品としても知られています。
文豪・夏目漱石からも高い評価を得ました。
一生の秘訣とは斯の通り簡単なものであつた。『隠せ。』――戒はこの一語(ひとこと)で尽きた。(島崎藤村「破戒」)
夏目漱石「こころ」(大正3年)
文豪・夏目漱石の永遠の名作です。
親友を裏切って女性(妻)を手に入れた男の一生の後悔。
その罪は、生きている限り、永遠に彼の心につきまとってくるのです。
罪から解放されようと、男の選んだ道とは?
「精神的に向上心のないものは、馬鹿だ」私は二度同じ言葉を繰り返しました。そうして、その言葉がKの上にどう影響するかを見詰めていました。「馬鹿だ」とやがてKが答えました。「僕は馬鹿だ」(夏目漱石「こころ」)
有島武郎「生まれ出づる悩み」(大正7年)
札幌農学校出身の小説家、有島武郎の代表作品です。
芸術と生活の間で苦悩する男たちの物語。
夢を追い続ける生き方って、永遠のテーマかもしれませんね。
絵描きのモデルは漁夫画家として知られる<木田金次郎>でした。
あの少年はどうなったろう。道を踏み迷わないでいてくれ。自分を誇大して取り返しのつかない死出の旅をしないでいてくれ。もし彼に独自の道を切り開いて行く天稟(てんぴん)がないのなら、どうか正直な勤勉な凡人として一生を終わってくれ。もうこの苦しみはおれ一人だけでたくさんだ。(有島武郎「生まれ出づる悩み」)
小熊秀雄「焼かれた魚」(大正14年)
北海道出身の詩人、小熊秀雄の書いた童話です。
焼かれたサンマが、故郷の海へ戻るために旅をします。
遠い海まで運んでもらうために、動物たちに自分の<身体>を提供しながら。
夢を追いかけて、ボロボロになっていくサンマの姿は、僕たちの姿でもあるのです。
『あゝ、海が恋しくなつた、青い水が見たくなつた。白い帆前船をながめたい』と、この丘の上で秋刀魚は口癖のやうに言ひました、ふと何心なく耳を傾けますと、この丘の下のあたりで、どうどうといふ岸をうつ波の音が聞えるではありませんか、なつかしいなつかしい波の音が、そして遠くのあたりからは賑やかな潮騒がだんだんと近くの方へひびいてきます。(小熊秀雄「焼かれた魚」)
魯迅「故郷」(昭和7年)
中国の小説家・魯迅の短編小説です。
懐かしい故郷を訪ね、少年時代に一緒に遊んだ幼馴染と再会した主人公。
時の流れは、二人の少年に「身分の違い」という変化を与えていました、、、
古い友人との再会は、人生を考えさせられる瞬間でもあります。
私は身を横たえて船底にじゃぶじゃぶと当る水音を聴きながら、私はひとり自分の行手を行きつゝあることを感じた。私は思った、私と閏土とは竟(つい)にこんなにかけ隔てられてしまったのだ、だが私たちの後輩にしてもやはり同じようで、現に宏児はいま水生のことを思っているのだが私は再び彼らが私に似ないように、また、お互に隔膜(へだて)が出来ないようにと希望する……(魯迅「故郷」佐藤春夫訳)
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」(昭和9年)
詩人にして童話作家、宮沢賢治の代表作品です。
我が身を犠牲にしてまで友だちの生命を救ったカンパネルラ。
宇宙を疾走する銀河鉄道の旅で、ジョバンニは何を悟ったのでしょうか。
本当の幸いとは何か?と考えさせられる名作ですね。
「ぼくはおっかさんが、ほんとうに幸(さいわい)になるなら、どんなことでもする。けれども、いったいどんなことが、おっかさんのいちばんの幸なんだろう。」カムパネルラは、なんだか、泣きだしたいのを、一生けん命こらえているようでした。(宮沢賢治「銀河鉄道の夜」)
サマセット・モーム「かみそりの刃」(昭和19年)
イギリスの人気作家、サマセット・モームの長編小説です。
第一次世界大戦の戦場で親友を失った男は、人生探求の旅に出た。
様々な非難を浴びながらも、男は自分の人生を歩き続けていくのです。
ストーリー・テラーのモームらしい結末にも注目。
ところが、ついさっきまで朗らかに人生を楽しんでた奴が、あっという間に死んじまってるんだよ。なんという残酷、なんという無意味なんだい。いったい人生とはなんだ? 人生なんて、いったい意味があるのか?(サマセット・モーム「かみそりの刃」中野好夫訳)
(2024/04/25 12:53:15時点 Amazon調べ-詳細)
太宰治「人間失格」(昭和23年)
太宰治の代表作です。
生きづらさを抱えながら生きてきた男の生き様を描いています。
酒、煙草、売春婦、左翼思想、人妻との自殺。
「狂人」と呼ばれた男が、最後に出した結論とは?
恥の多い生涯を送って来ました。自分には、人間の生活というものが、見当つかないのです。自分は東北の田舎に生れましたので、汽車をはじめて見たのは、よほど大きくなってからでした。(太宰治「人間失格」)
J・D・サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」(昭和26年)
サリンジャー永遠の名作。
社会から弾き出されていく17歳の少年の独白で綴られています。
どこにも居場所がない、という生きづらさ。
社会を拒否していたのは、少年の方だったのかもしれませんね。
ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ。たしかにかなりへんてこだとは思うけど、僕が心からなりたいと思うのはそれぐらいだよ。かなりへんてこだとはわかっているんだけれどね。(サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹訳)
(2024/04/24 22:01:51時点 Amazon調べ-詳細)
ジャック・ケルアック「路上」(昭和32年)
アメリカのビート派作家、ジャック・ケルアックの長編小説です。
自らの放浪体験を綴ったロード小説。
マリファナ、セックス、モダン・ジャズ、、、
既成の価値観を吹き飛ばした、若者たちの新しい感性が描かれています。
「新規まきなおしかい?」僕は大声でいった。「新規まきなおしだよ、君。おれは自分の生活に戻るんだ。君と一緒に残れたらなあ、また戻って来たいものだよ」(ジャック・ケルアック「オン・ザ・ロード」福田実訳)
庄野潤三「浮き燈台」(昭和35年)
芥川賞作家・庄野潤三の中編小説です。
何をやってもついてない、不運な男が、遠い海辺の村を訪れます。
死と隣り合わせに生きる漁村の人々との出会いと気付き。
傾いたままで浮いたり沈んだりしている「浮き灯台」は、不運に振り回されながら生きる「私」自身の姿だったのでしょう。
われわれはまあこの世に間借りしているようなもので、何もムキになることはない。いいことがあると云ったって夢かと思うようなことは起らないし、悪くなると云ったところで滅茶苦茶に悪くなることもまあないだろう。これから先のことは分らないが、大体今までに経験して来たことと大同小異というところになるのではないか。(庄野潤三「浮き灯台」)
ボブ・グリーン「街角の詩」(昭和51年)
1980年代に日本でも大人気だったコラムニスト、ボブ・グリーンの精選コラム集。
小説ではない、短いコラム。
その中に、街角で出会った人たちの、人生の一瞬が切り取られています。
人間の数だけ、人生がある。
誰でも見たことがあるだろう。どこにでもいるグラウンドの花形プレーヤー。バスケットのボールとコンヴァースのオールスター・スニーカーだけでウエスト・サイドの地獄から這い上がろうとしている黒人の若者たちを。トニー・ウイリアムズは、その中でもずば抜けて目立っていた。彼は知っていたのだ。こんな惨めな生活から抜け出したいのなら、何かしなくてはいけないのだと。(ボブ・グリーン「街角の詩」香山千加子訳)
スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」(昭和57年)
映画「スタンド・バイ・ミー」の原作小説です。
3人の仲間たちと「死体探し」の冒険に出かけた12歳の夏の終わり。
秋になれば、彼らは別々の道を歩いていくことになります。
映画よりも原作小説の方が「深い」と思わせてくれますよ。
「おまえの友達はおまえの足を引っぱってる。溺れかけた者が、おまえの足にしがみつくみたいに。おまえは彼らを救えない。いっしょに溺れるだけだ」(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子訳)
村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」(平成6年)
1990年代の村上春樹を代表する長編小説です。
失踪した妻を探す男の物語。
国際的にも高い評価を得た名作ですね。
夫婦関係から戦争まで、壮大な世界が綴られています。
「かわいそうなねじまき鳥さん」と笠原メイは囁くように言った。「きっとあなたはいろんなものを引き受けてしまうのね。知らず知らずのうちに、より好みすることもできずに。まるで野原に雨が降るみたいに—」(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」)
(2024/04/25 11:45:32時点 Amazon調べ-詳細)
まとめ
以上、今回は、「人生って何だろう?」と深く考えさせられる文学作品をご紹介しました。
秋って物思いに耽りたくなる季節です。
たまには、思い切り自分の人生と向き合ってみるのも悪くないかもしれませんね。