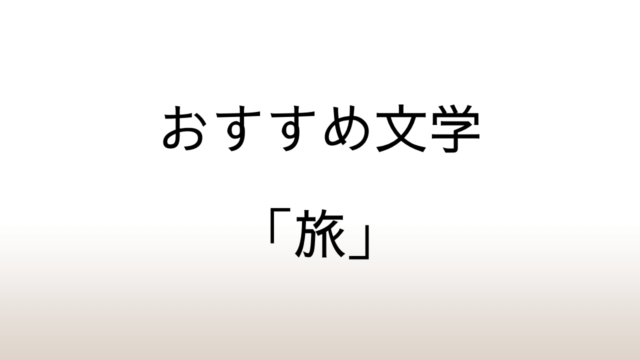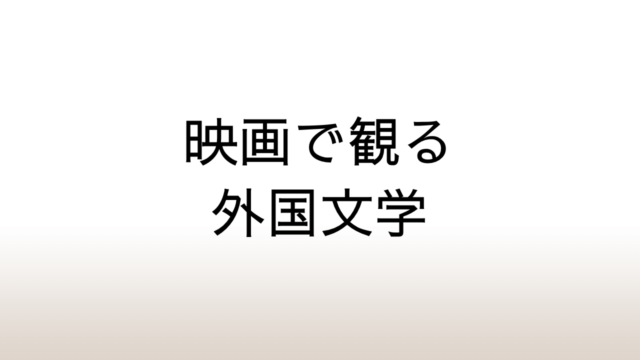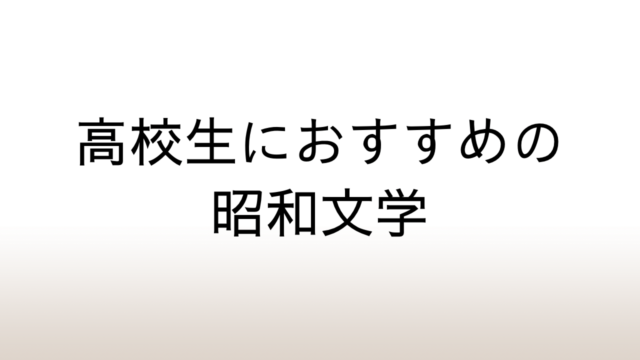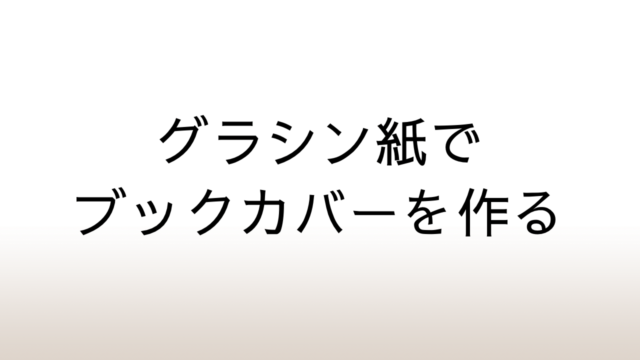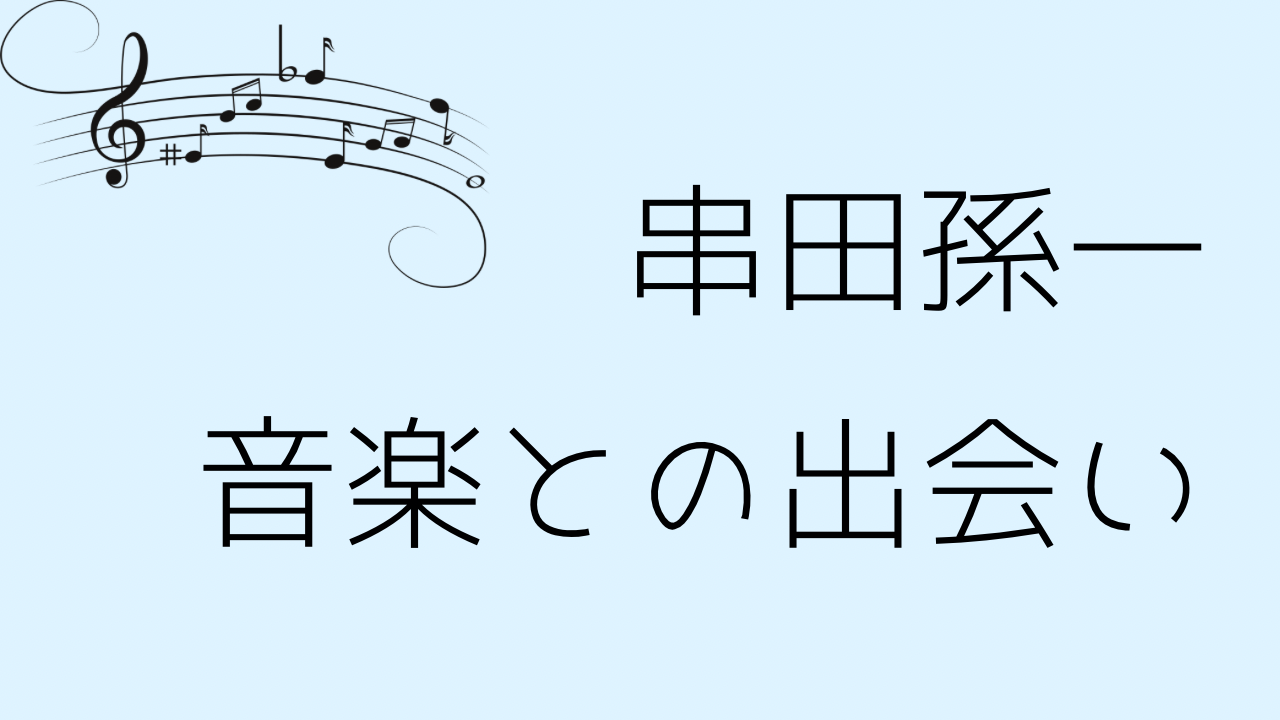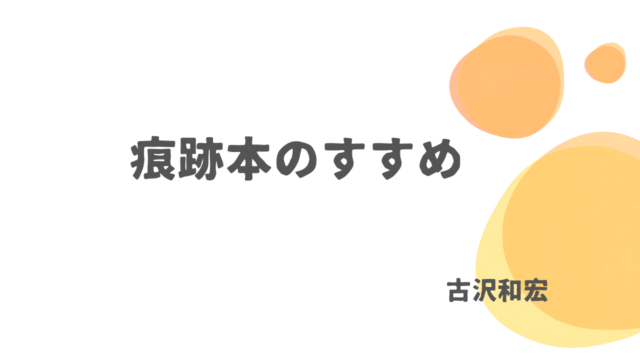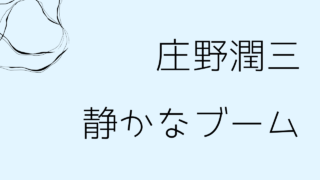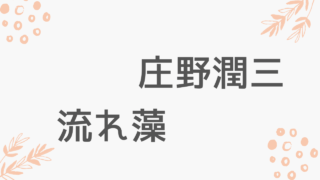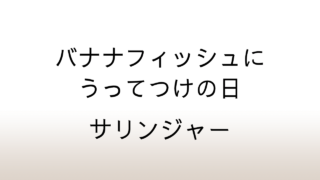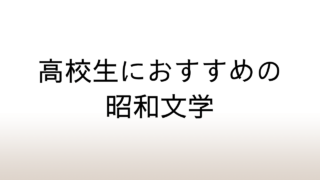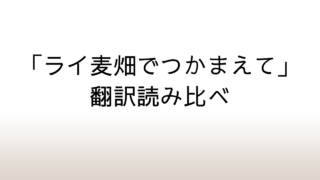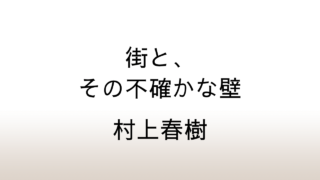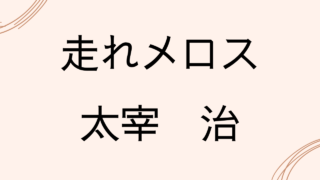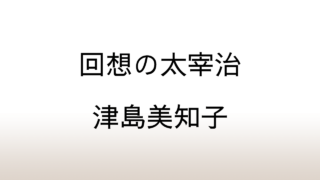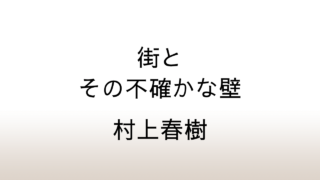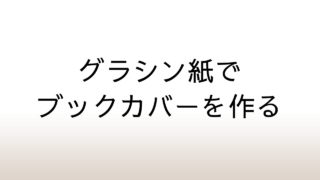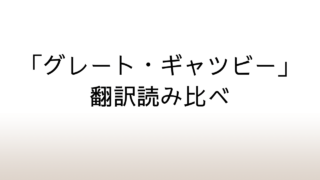「死んだ私の友人は、死ぬ一週間ほど前から、レコードでグレゴリオ聖歌ばかり聴いていたそうで、その栄光の讃歌を聴きながら死んだということだった(「青く澄む憧れ」)」と書いたのは、本書「音楽との出会い」の編者である串田孫一である。
本書には、串田のチョイスによる26人の音楽エッセイが収録されている。
立原正秋は「モーツァルトをきいているとき、魚を食べていることが多い」そうで、「朝の九時に起きて秋刀魚を焼いてビールをのんでいたら、NHKのFM放送がモーツァルトの嬉遊曲を流していた」「八月にもたしか鮭の頭をかじっていたときにモーツァルトをきいた記憶がある」「前夜の残り物の鮟鱇鍋をあたためて酒をのんでいたら、裏の家からモーツァルトの<ピアノ協奏曲ニ短調>」がきこえていた」などと、日常生活の中に溶け込んでいるモーツァルトの魅力について綴ってみせる。
星新一は「モーツァルト。ブラームス、『新世界のドヴォルザーク』。こういった名に接すると、反射的に中学時代を思い出す」ほどの音楽少年で、東京空襲が盛んとなった戦争末期には「私は毎日のようにこのレコードをかけ、聞いていた。いつ死ぬかわからぬ状勢。しかし、生きているあいだに、このような名曲にであえたのだと思うと、ひとつのなぐさめにもなった」と回想しているが、終戦とともにクラシック音楽との付き合いも終わりになってしまった。
青山次郎や河上徹太郎、小林秀雄、中原中也といった仲間たちとともに音楽を楽しんだ大岡昇平は、「十四歳の僕もベートーヴェンを通じて、春夫龍之介など大正の感傷主義にあきたらなくなり、外国文学に惹かれて行ったのである」として、文学と音楽との大きな関係性について論じてみせる。
秋山ちえ子は、「指導困難な要保護女子の、長期収容施設」で「元売春婦で大方が知恵遅れや性格的に欠陥のある女性たちが約一〇〇人いる」という「かにた婦人の村」の責任者である牧師が苦心して手に入れたオルガノに関する貴重なエピソードを披露しているし、清水脩は「二〇・五世紀を十九世紀のロマン主義時代にかえせないのと同じで、四十を越したぼくを二十代にかえす訳にはいかない。二〇・五世紀+四十歳代の恋愛詩を作曲すればよい」と名文を残している。
一人一人の回想の中に音楽との出会いがあり、それぞれの人生の中に音楽が確かな足跡を刻み込んでいる。
優れたエッセイに触れて、新しい音楽の世界へと踏み出していこう。
もはや若くはないことの幸福に似ている
灯の下で、妻の頭に幾筋かの白毛が銀いろに光っていたが、顔には若々しい静かさがあった。私たちに、一つの成熟がめぐみ与えられた。結婚生活の十年の試練が、もう過去のものになったと、謙遜な気もちでなら、言ってもいいような気がした。ああ、夫婦生活の幸福は(少なくとも私にとっては)もはや若くはないことの幸福に似ていると、私はいくらか悲しい。(片山敏彦「永遠に母なるもの」)
著者(片山敏彦)にとって音楽の思い出は、最愛の妻である愛子との思い出につながっている。
結婚したのは「私は一高と法政大学とへ教えにいっており、愛子はお茶の水にあった上野音楽学校の分教場へ歌唱を教えにいっていた」頃で、結婚を記念する旅行で芦ノ湖へ出かけたときに「妻がうたったベートーヴェンの『アデライデ』を聴いて私は涙ぐんだ」とある。
「或る朝、食卓の上に顔を伏せて、娘が声をあげて泣いているので私はおどろいた。わけを聞くと、今ラジオが放送したシューベルトの歌は、「ママがいつでもうたっていた歌だ」と娘は言った」というのは、愛妻を亡くした後のエピソードだが、母に死なれた直後には、やや蒼ざめた顔つきをしながらも、人前で涙を見せなかった大学生の娘の号泣の理由を知ったとき、著者は「安心すると同時に涙ぐんだ」という。
本作「永遠に母なるもの」は、本エッセイ集の中でも、ひときわ胸を強く打つ作品である。
観念的である必要はさらさらない
それは実に、明るくて、しかももの悲しい音楽だった。カーテンごしの柔らかい昼の光、ゆうべ飲みのこしたグラスもそのままに、三人の女の眠った小さな室内のけだるいいきれ、そしてお酒に爛れた胃袋に滲みわたるリンゴの実の爽やかな酸味。それらにぴったりとマッチした、もの悲しいくせに妙に幸せな、透明な音楽だった。(吉原幸子「朝のリンゴ」)
このとき、著者(吉原幸子)の聴いていた音楽は、アルビノーニのオーボエ協奏曲だった。
あるいは、定番のホリガーとイ・ムジチの演奏だったかもしれないが、その時の著者は、まだ曲名も演奏家も知らなかった。
その後、アルビノーニを集め始めた著者は、「「イ・ムジチ合奏団」その他に較べ、私はあまり装飾音のない、そしてあまり早すぎない「ザール室内管弦楽団」—オーボエはジャック・シャンポン—のものがいちばん好きだ」と考えるようになる。
そして、著者にとって「アルビノーニとリンゴの味とが奇妙な連想作用を持つようになってしまった」という。
エッセイが人生を綴る文学であるとしたら、良い音楽エッセイとは、音楽を通して人生を語る、そんなエッセイのことだろう。
観念的である必要はさらさらない。
音楽とは、そもそも体験のことなのだから。
書名:音楽との出会い
編者:串田孫一
発行:1989/6/30
出版社:音楽之友社