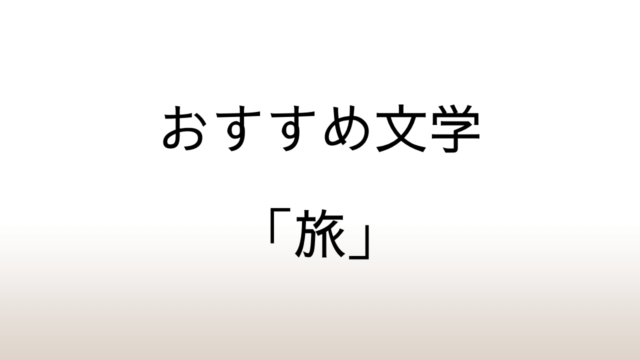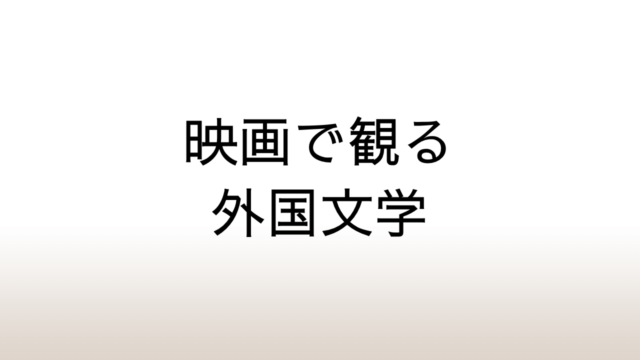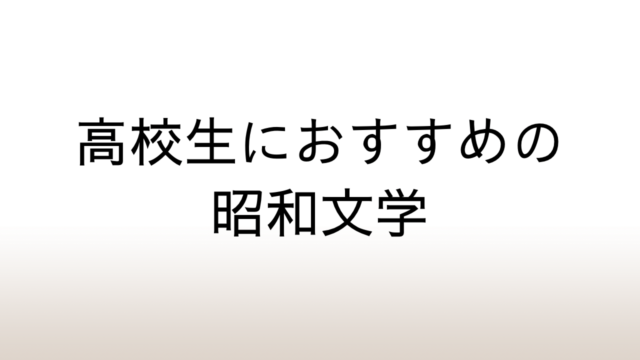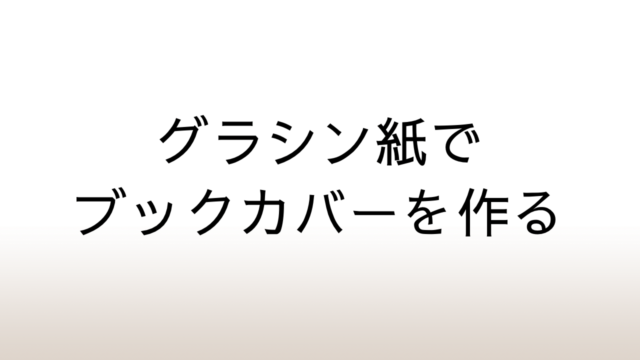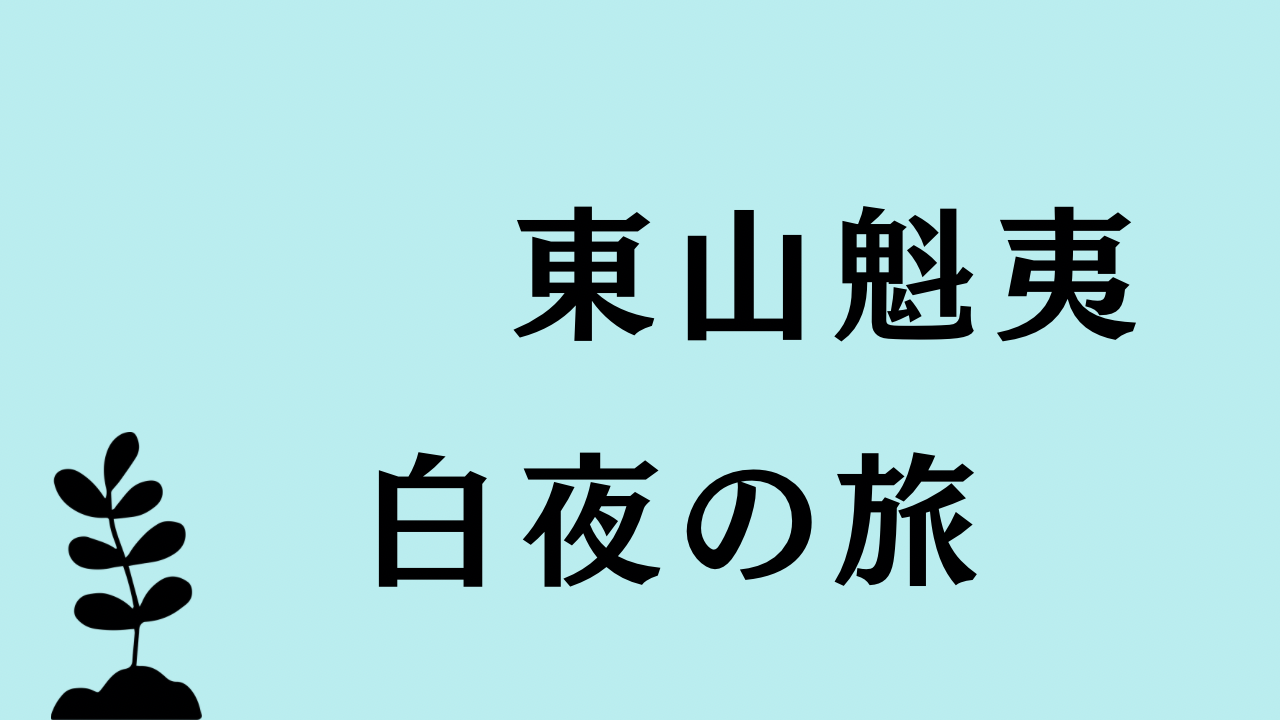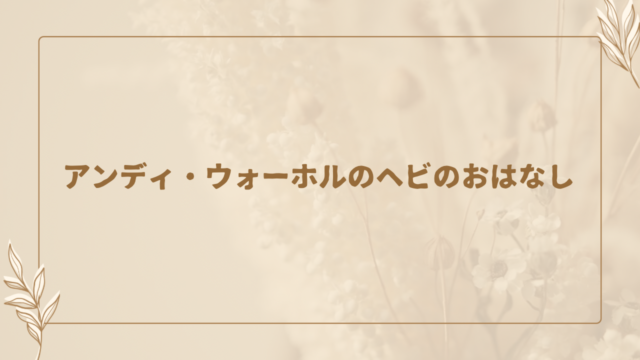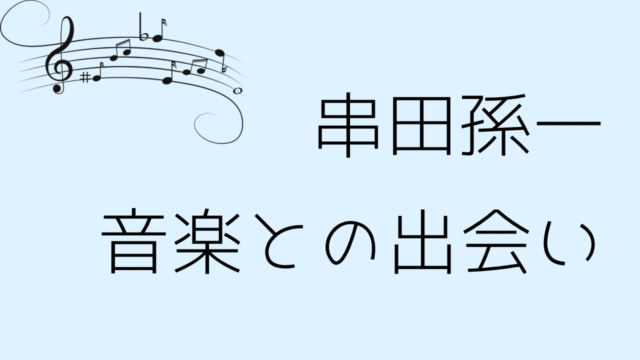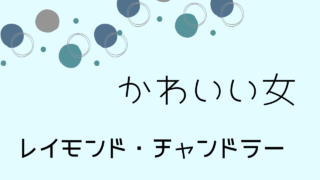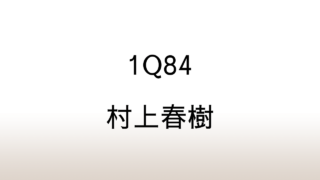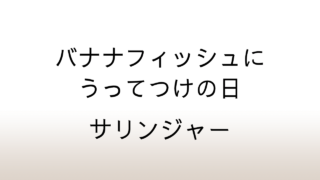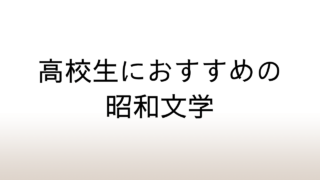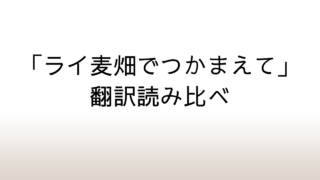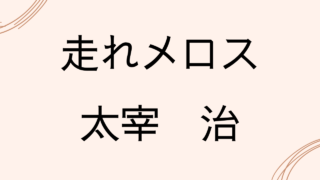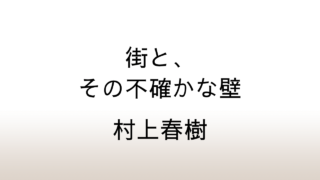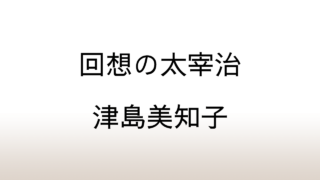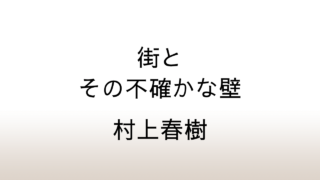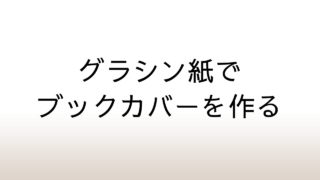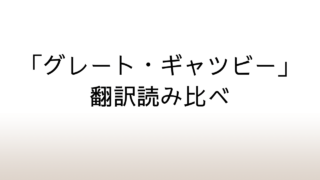東山魁夷さんの北欧旅行記「白夜の旅」を読みました。
海外旅行が珍しかった時代の、貴重な旅コラムです。
書名:白夜の旅
著者:東山魁夷
発行:1980/10/15
出版社:新潮文庫
作品紹介
「白夜の旅」は東山魁夷さんの書いた北欧旅行記です。
あとがきによると、この「昭和37年春から夏の終りへかけての北欧の旅は、私には戦後最初の海外旅行」であり、「妻にとっては、生まれて初めての経験」でした。
当時は「まだ国外への旅行が不自由であった時代」で、そんな時代に「未知の国々を巡って、かなり長い旅をしたことも不思議である」と、東山さんは回想しています。
東山さんの北欧旅行は、デンマークに始まり、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドを経て、再び訪れたデンマークの地で終わります。
(目次)デンマーク/スウェーデン/ノルウェー/フィンランド/デンマーク///あとがき
単行本は、1963年(昭和38年)5月に新潮社から刊行されました。
デンマーク、スェーデン、ノルウェー、フインランド―静かな森と湖、尖塔の林立する古い街、甦る春と短い夏、夏至祭の夜の炎、そして、深夜の太陽。久しくあこがれを抱いていた北欧の国々。自然を愛し、自然に親しむ画伯が、“私の芸術の歩みの上で、かなり大きな意義を持つものとなった”と語る、生命の輝きに満ちた北欧の風景への旅の記録。口絵カラー8点、本文中カット11点挿入。(カバー背表紙)
なれそめ
僕は旅行記を読むのが好きです。
殊に、自分の見たことのない街の風景を描いた旅行記を読むと、まるで自分が旅をしているかのような気分を味わえるのが楽しいと思います。
ポイントは、古い時代に書かれた旅行記であること。
と言っても、古すぎる紀行文は記録的要素がなりすぎるので、少し時代遅れに感じられるくらいの旅行記がいちばん好きです。
そういう意味で、昭和時代(特に戦後)に書かれた旅行記は、僕の大好物と言えるようです。
現在のような北欧ブームが起こる、ずっと昔に書かれた東山魁夷さんの『白夜の旅』は、「北欧の旅」と「1960年代の旅」というふたつの旅行を、僕に楽しませてくれるものでした。
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
デンマークの人は本当の幸福を知っているのかもしれない。
「デンマークの人は本当の幸福を知っているのかもしれない。元来、幸福ということは消極的な喜びだけを意味するのだろうからね」この時、復活祭の鐘が遠く近く響き渡ってきた。そばを赤と黒の対照を見せて自転車を走らせてゆく二人、真赤な上着の制服の郵便配達夫と、黒いシルクハットに黒い服装、顔まで真黒な煙突掃除夫である。(「デンマーク」)
東山さんの北欧旅行はデンマークからスタートします。
デンマークの旅はコペンハーゲンから始まりますが、東山さんにとってデンマークは「少年の頃読んだ雪の女王や人魚姫の美しい物語を書いた作家」アンデルセンと強く結び付いていました。
「人間の幸福は、最も素朴な愛によることを繰り返し書いたその詩人の心」は「この国の多くの人々の心でもあるように思える」と、東山さんは綴っています。
コペンハーゲン最大の名物の一つは「海辺の通りランゲリニエにある小さな人魚姫の像」でした。
そんな街だからこそ、「真赤な上着の制服の郵便配達夫」や「黒いシルクハットに黒い服装、顔まで真黒な煙突掃除夫」まで、街の何もかもが、東山さんには童話的に見えていたのかもしれませんね。
ストックホルムの街は、何かしら冷厳なものを感じさせる。
ストックホルムの街は、灰色の空を突き刺す尖塔といい、渋い色調の壁や、四角な窓の羅列といい、何かしら冷厳なものを感じさせる。コペンハーゲンのような人間の体温の感触はない。ここは、まさしく北の都である。(「スウェーデン」)
コペンハーゲンからストックホルム空港へ着いたとき、「丈高い針葉樹に、白樺の交る森の寒々とした風景」に、東山さんは「いよいよ北欧へ来たと感じた」そうです。
「車で一時間位の距離にあるモーラ」という町には、「スウェーデンの国民画家ソルンの墓」があり、東山さんは、その近くにある「ソルンの作品を集めた美術館と、彼の生前住んでいた家」を訪れています。
また、ある晩にはホテルの「サロンでコーヒーを飲みながら、このホテルのリディアという夫人に『ヴェルムラント』の歌を歌ってもら」います。
ヴェルムラントは「スウェーデンの湖と森に恵まれた地方」の名前で、この「単純で素朴ではあるが、やや憂鬱な響きを持つ」民謡のメロディを聴きながら、東山さんは、いつか北欧の風景を見たいと考えていたのだそうです。
東山さんの旅行記は、画家の鋭い観察眼によって描かれる北欧の街並みの描写が見事なのですが、美術や文学、音楽などの芸術分野に高い感度で接するあたりも、この『白夜の旅』の読みどころだと、僕は思いました。
フィンランドの夏―いったい私達の夏というものが、この国にあるのだろうか。
フィンランドの夏―いったい私達の夏というものが、この国にあるのだろうか。空は晴れて、明るい砂地の道に松林の影が濃い。しかし、空気は冷く澄んで、勿論、蝉の声など聞こえない。春の夏と、秋の夏があって、本当の夏を知らない国。ホテルの部屋へ入ると、うっすら暖房がしてあって、それが快く感じられるのである。(「フィンランド」)
ヘルシンキの街で、東山さんは「美しい白夜」を見ます。
それは「欧州大陸の最北の首都であるこの市街の夏の夜は、夜といっても一向に暗くなってゆかない」夜で、「月が、空と水の上の二つあ」り、「冴えてはいるが、穏やかな光」を見せていました。
また、「ここからタムペレに至る水路が『詩人の道』と名付けられ、数あるフィンランドの船旅の中で、もっとも美しいとされている」ヴィラットの町で、東山さんは夏至祭を見学しています。
あえて雑踏から離れて、湖畔から遠い運河のはずれまで移動した東山さんは、「向うの湖畔の狭い砂地に集まっている人々の群れ」を遠く眺めます。
「音楽も歓声も遠いが、まさしく、それは美しい舞台であった」と思ったその時、「対岸にぱっと火が燃え上った」瞬間を、東山さんの眼がとらえます。
もう真夜中に近いというのに、それは人々の踊りが最高潮に達したことを示す火柱であり、その時の様子について、東山さんは「暗い森の帯を赤い焔は真二つに切断した」と綴っています。
60年近くも昔に、一人の日本人西洋画家が見た北欧の伝統的な風景の数々。
果たして、今でも見ることができるのでしょうか。
読書感想こらむ
フィンランドの船旅の船中で、東山さんは「美しいメロディ」の曲を聴きます。
 東山魁夷さんの描いた「北ヨーロッパの地図」が素敵すぎる
東山魁夷さんの描いた「北ヨーロッパの地図」が素敵すぎるシベリウスの生家があるヘーメンリンナという町のレコード屋で訊ねると、店の主人は、EP盤を一枚取り出しながら「それはカンガサーラの夏の日でしょう。カンガサーラはタムペレの東方にある美しい風景の村です。マウノ・クーシストォの歌っているものがあります。ちょっとかけてみましょうか」と言います。
果たして、昨日、船で聞いたメロディが、テノールの歌で響いてきて、東山さんはそのレコードを買って帰ります。
調べてみると、マウノ・クーシストの歌う「カンガサラの夏の日」はApple Musicで聴くことができたので、そこから先の部分を、僕はマウノ・クーシストのテノールを聴きながら、おしまいまで読みました。
マウノ・クーシストが登場するまでBGMは、ノルウェー生まれの作曲家、エドヴァルド・グリーグの「抒情小曲集」でした。
素敵な旅行記を読む時には、素敵なBGMを聴きながら読むのがお勧めです。
まとめ
東山魁夷さんの北欧旅行記「白夜の旅」を読むと、なんとなく感傷的な気持ちになります。
本を読みながら僕は、1960年代の異国で少し孤独になりました。
著者紹介
東山魁夷(画家)
1908年(明治41年)、横浜市生まれ。
本作をはじめ、著作も多いことで知られている。
北欧旅行をしたのは54歳のとき。