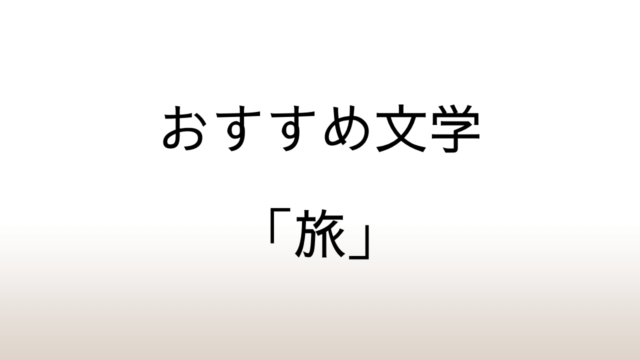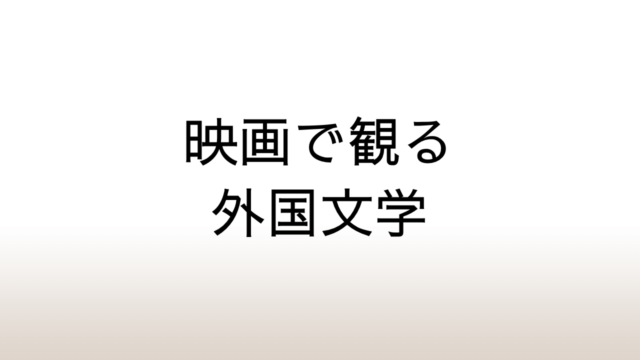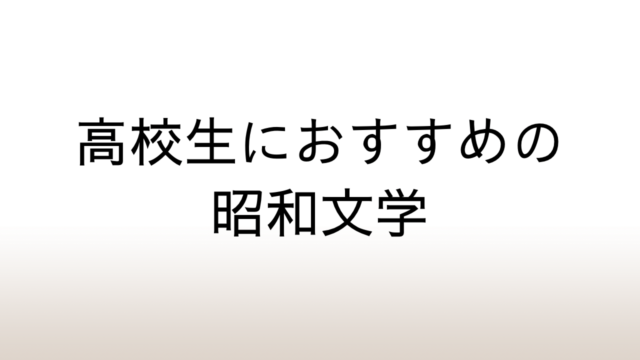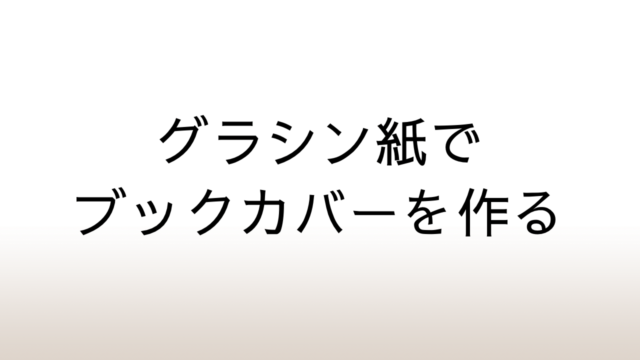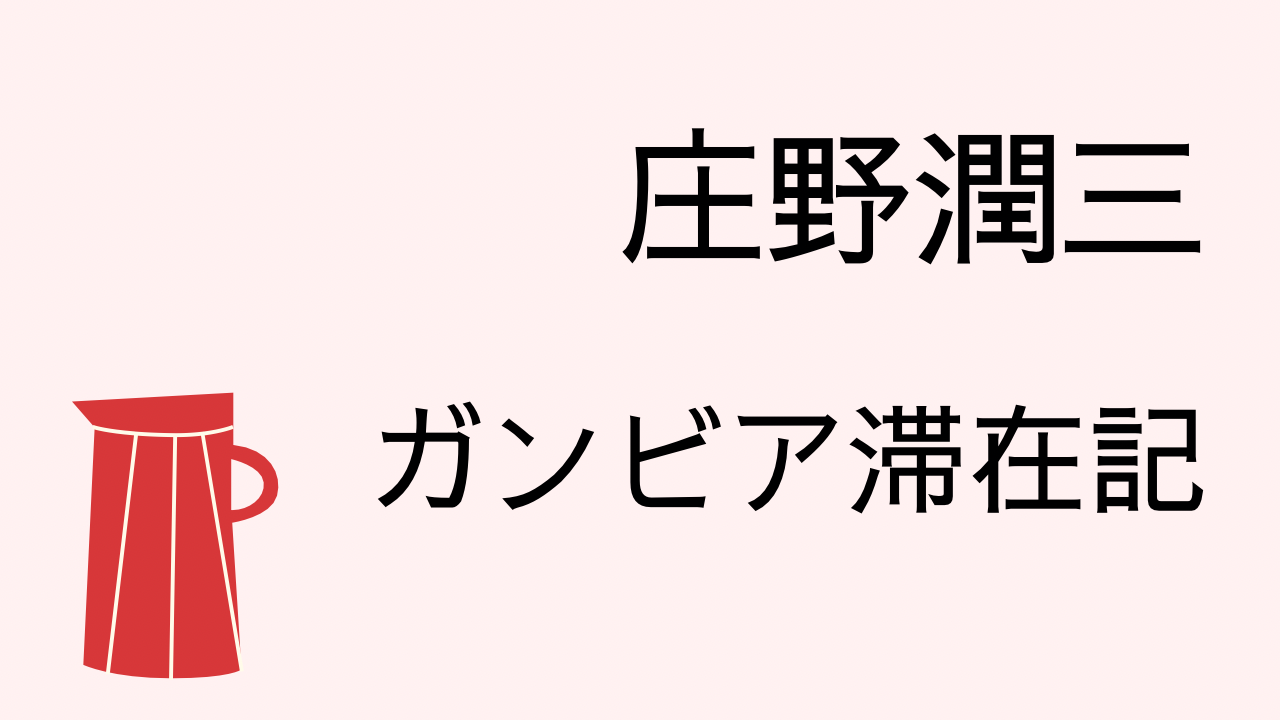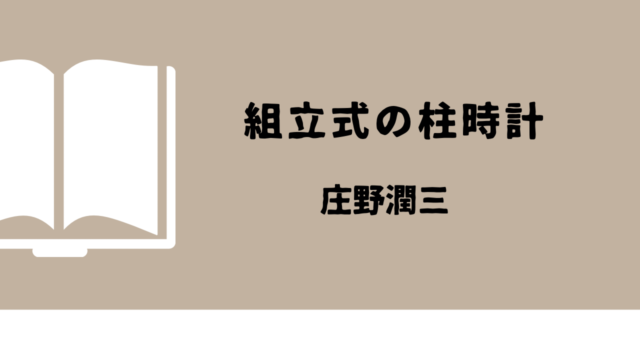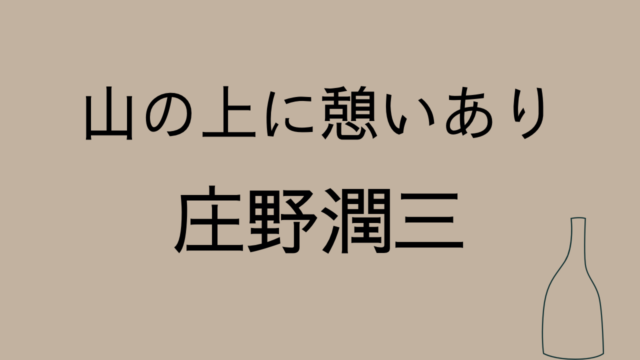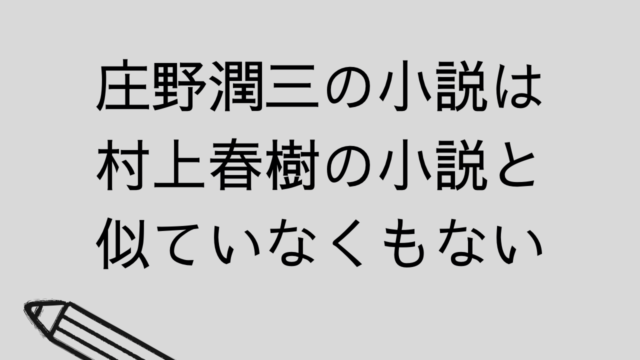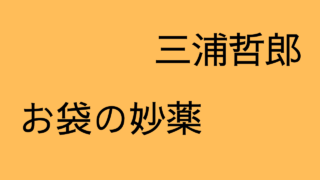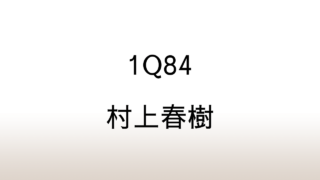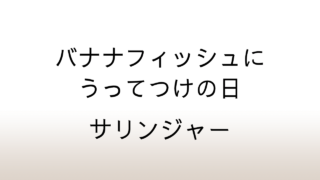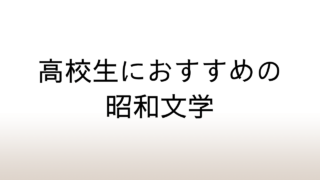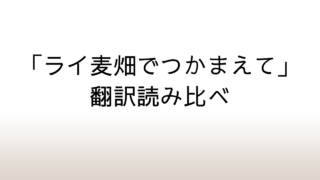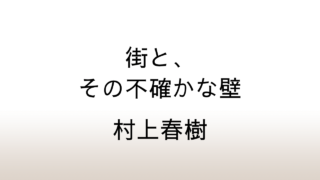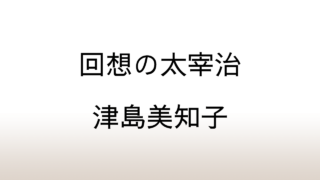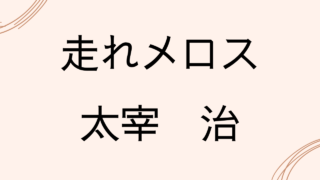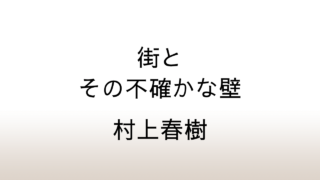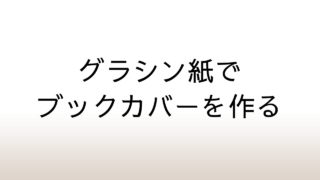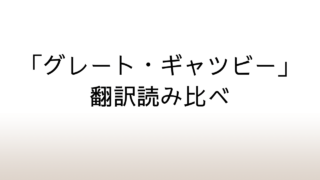ここでは、庄野潤三の長篇小説「ガンビア滞在記」について紹介しています。
庄野夫妻がアメリカ留学した際の滞在記録です。
概要
「ガンビア滞在記」は、庄野潤三の長篇小説である。
書き下ろし作品であり、単行本は、1959年(昭和34年)3月5日、中央公論社から発行された。
装丁は高橋忠弥。
帯には「この澄明な世界、この清純な感受性を愛さない小説読者は稀であろう。芥川賞作家の書下ろし長篇!」とある。
帯裏にある推薦文は井上靖によるものだった。
氏は詩人である。氏が詩を書かれたかどうか私は知らない。しかし、氏の作品について語る時、梶井基次郎の作品に対すると同様に感受性の純粋化という言葉を使っていいのではないかと思う。勿論、庄野氏の作品は梶井基次郎の作品とは違って、ずっと小説的構成を持つものであるが、しかし、氏の作品の持つ澄明度はさしずめそうした言葉を使う以外にないと思う。(井上靖/庄野潤三氏について)
1975年(昭和50年)7月10日、中公文庫として文庫化された。
2005年(平成17年)10月7日、みすず書房「大人の本棚シリーズ」から復刻刊行されている。
執筆の背景
1957年(昭和32年)9月から翌1958年(昭和33年)8月まで、ロックフェラー財団の奨学資金「フェローシップ」による日本の文学者たちのアメリカ留学の一環として、ケニオン・カレッジに留学することとなった庄野さんは、夫人帯同でアメリカオハイオ州ガンビア村に滞在した。
当時、ロックフェラー財団との間で日本側の窓口となっていた坂西志保が、庄野さんの書いた『ザボンの花』を読んで感銘を受けたことがきっかけだったという。
アメリカ留学にあたって庄野さんの出した「田舎の出来るだけ小さな町に行って、その町の住民の一員のようにして暮らすことが出来たら」という希望を受けて、ロックフェラー財団が選定した大学が、人口600人、戸数200戸という小さなガンビア村にあるケニオン・カレッジだった。
この留学で特別の任務も与えられていなかった庄野さんは、とにかく日々の出来事を克明にノートに記録することを自分に課し、このノートに書かれた記録を元にして執筆された作品が、本作『ガンビア滞在記』である。
なお、留学中に書かれた「ガンビアノート」は膨大なものであったため、『ガンビア滞在記』では書ききれなかったエピソードを中心に、庄野さんは後に『シェリーと楓の葉』『懐しきオハイオ』という二つの長編小説を発表している。
また、このアメリカ留学の体験は、多くの短篇小説としても作品化されている。
あらすじ
『ガンビア滞在記』は全部で三十五の章から構成されている。
1 オハイオ州ガンビア
ある朝、私が郵便局から帰って来ると、私たちが入っているバラックの前の道の電信線の上を栗鼠が一匹、木の実を大事そうに口にくわえて渡っていくのが見えた。栗鼠の家であるガンビアの林は、いま冬に向ってその色を変えつつある。
2 郵便局
ガンビアの町の人々は大通りにある郵便局の中に各自のボックスを持っていて、毎朝郵便物を取りに出かける。郵便局では局長以下四名の人が働いていた。ガンビアの郵便局にはひとつ変ったものがある。それは入口の右手の壁にある壁画だ。
3 ミノーとジューン
今後の我々の生活で何かにつけて関連を持って来るのは、ミノーとジューンの二人である。ミノーはボンベイで生れた印度人で、ジューンは彼がアメリカ留学中に結婚したアメリカ人の奥さんだった。
4 ガンビアの動物
ガンビアには栗鼠のほかに重要な動物がもうひとつあった。ラックーンである。綴りを尋ねると、RACCOONであった。エリオットさんは、ラックーンは顔にブラックマスクがあると云って、指で眼のまわりをくるりと撫でてみせた。
5 「村の宿屋」とドロシイズ・ランチ
ガンビアには食堂が二軒ある。「村の宿屋」と「ドロシイズ・ランチ」である。しかし、この二軒は全く性格の違うものだった。大通りにある「村の宿屋」は立派なレストランで、ケニオンの教授をはじめ、ケニオンを訪問したお客さんはみなここで食事をする。ドロシイズ・ランチは大通りから外れたところにある。
6 結婚式の写真
十月十六日の夕方、ミノーに誘われてペトリ(シェリー酒)を飲みに行った。ペトリを飲みながら、ミノーはジューンとの結婚式に写したカラーの写真を見せてくれた。
7 ガンビアのスポーツ(1)
私たちがガンビアに来たときは新学年が始まる一週間前で、カレッジは空っぽであった。私は早く休暇が終って、ガンビアの町に学生が溢れるところを見たいと思った。ランサムさんの話では、ケニオンでは水泳部が一番強く、オハイオ州で度々優勝している。テニスも、比較的強い。その次がサッカーで、これはフットボールよりはいいということだ。
8 ブラウン氏の銀行
ブラウン氏はガンビアに古くから住んでいて、ずっと銀行に働いている。銀行は「ピープルズ・バンク」という名前だが、私にはむしろ「ブラウン氏の銀行」のように見えた。
9 ディンショウ来る
私たちがミノーとジューンに会う回数が次第に多くなってきた頃、突然ボンベイからミノーのお母さんのディンショウが来た。ミノーのお母さんは小さくて円い、子供のような顔をした人であった。
10 ホームカミング・フットボール
十月二十六日の朝、私は妻と二人で二時から始まるケニオンのホームカミング・フットボールの試合を見に出かけた。ホームカミングはアメリカの学校の秋の行事で、この日に卒業生が母校へ帰って来て週末を過ごすというのが、その言葉の意味である。
11 ヘイズ食料品店とウィルソン食料品店
ガンビアへ来た人は、最初のうち二軒の食料品店のどちらで買うべきか迷うそうである。大ざっぱに云って、どちらの店も似たり寄ったりだから、特に一方を選ぶ理由がなくなるのだ。
12 万聖節前夜
十月三十一日のハローイーン(万聖節前夜)が近づくと、急に子供の落書きが現れた。マウント・ヴァーノンでは、大通りの商店の窓という窓に蝋を融かしたようなものでなぐり書きしてある。ハローイーンには子供は落書きしてもいいことになっているのだそうだ。
13 嵐
その日は朝から風が音を立てて吹いていた。私は空の低いところを雲が非常な速さで走って行くのを見上げ、「日本でもアーリイ・オータムにはこんな嵐の日がある」と云った。家に帰ると、妻はあんまり帰りが遅いので風に吹き飛ばされたのではないかと心配していた。
14 ジューンとディンショウ
ミノーの家では、ジューンとディンショウがシリーンを連れてイリノイのジューンの家へ一週間出かけることになった。私は出発の前日の午後に家の前でミノーからそのことを聞いた。彼は、「いま荷造りしているところだ」と云った。
15 ミノーとベンジャミンの一週間
火曜日の夕方、歴史のソロモン教授の家で呼ばれる前に、ミノーは私の家へちょっと来て、「今晩は何を食べるか?」と聞いた。彼はその時、昨夜私たちが帰ってから急に淋しくなり、ヘインズへ車を走らせてライス一箱とシェリーを買い、帰って米を炊き、肉とまぜて食べたと話した。
16 ガンビアの周囲
ある午後、私たちはココーシング川にかかった橋を渡って、マウント・ヴァーノンへ行くのとは違った方向へ歩いて行ってみた。ガンビアの方を振り返ると、オールド・ケニオンが木立の上に半分だけ建物を現して、陽に明るく映えていた。
17 感謝祭
十一月の最後の週の木曜日がサンクスギビング・デイ(感謝祭)だ。ミノーの家ではエバンストンから大学の時の友達を呼んで、四日続きの休暇を一緒に過した。ミノーが私たちをドリンクに呼びに来たので行くと、友達はレコードでクリスマス・キャロルをかけて聞いていた。
18 雪の日
十二月四日の朝、雪が止んだ。私たちはすぐに家の前から道路へ出るまでの雪かきをした。その雪は前の日の朝から降り出して、夕方までに目分量で十五センチほど積ったのである。
19 せり売り
「来週の火曜日の十二時半からオークション(せり売り)をやる。もしよかったら見にいらっしゃい」と、ウィルソン氏が云った。せり売りのある家は、ワインバーグ氏の家と地続きの廃屋のようになった家であった。
20 クリスマス ディンショウ帰る
クリスマスの晩、独身のベーリー教授と一緒に私たちは、ミノーの家へ呼ばれた。その前の日、私が手紙を書いているところへディンショウが来て「金曜日にボンベイへ帰る」と云った。
21 引越
イングリッシュ教授の家族が一年間の休暇を終えて英国から帰って来る日が近づいたので、カレッジ当局の立てた移転計画に基づいて、ミノーの家族が私たちのいるバラック一号へ、私たちはバラックの端の三号へ移ることになった。私たちは一月二日に引越しをした。
22 ガンビアのスポーツ(2)
マウント・ヴァーノンまで出かけた翌日、雪が降った。二時半からケント大学との水泳の試合があるので、雪の中を見に出かけた。ケニオンの選手はプールの左側に、紫に白くケニオンと抜いた上着に下が白のトレーニングパンツを着て、真赤なスリッパーを穿いて並んでいる。右側に白いジャンパーを着たケントの選手が並んでいる。
23 肥沃なるガンビア
バーボンを飲むことにしたが、ジューンは気分がよくないと云って飲まない。「そうかしたのか」とミノーに聞くと「どうも妊娠らしい」と云う。ミノーは「ガンビアでは五人も妊娠している奥さんがいる」と云ってから「肥沃なるガンビア」と笑った。
24 ココーシングの氷
二月二十五日の午後、ニコディム夫人がガンビアから三十八マイル東に離れたコショックトンの町にある小さな博物館へ私たちを連れて行ってくれた。コショックトンへ行く道の両側に、ココーシングが両側の木立と一緒にずっとついて来る。ココーシングとはインディアンの言葉で「ふくろうのいる場所」という意味なのだそうだ。
25 ジャーマン・ミーズル
二月二十六日の午後、ミノーがロレンス・カレッジの総長の手紙を持って家へ来た。それは、ノースウェスターン大学でミノーがドクターを取った時に世話になった教授が、ロレンスの総長宛に出してくれた手紙であった。
26 春の気配
ある日、ニコディム夫人が家の近くに生えているスノードロップを持って来てくれた。それは小指くらいの長さのか細い草花で、コップの中に入れると、十分も経たないうちに、小さな、白い花が咲いた。
27 戸外生活
「本当に春になるのは四月十五日からだ」と云ったミノーの言葉は的中した。ダンビルへ行った日からガンビアには毎日、よく晴れた、暑い日が続いた。フレッシュマンの二つの寄宿舎の間の芝生には、あちらにもこちらにも裸になって日光浴をしている学生が見られた。
28 拾う神
久しぶりのマルティニを楽しんだ日から四日目の午後であった。サトクリッフ教授のクラスが終ってからミノーのところへ寄ってみた。静かなのでノックしてみると、ミノーが出て来て「カム・イン」と云った。「悪い手紙を今朝受け取った」。
29 ガンビアのスポーツ(3)
四月三十日の午後ケニオンとウースター・カレッジとの野球の試合を見に行った。グラウンドは前にサッカーをやったところである。ケニオンの学生は五人見に来ているだけであったが、途中から野球好きのサトクリッフさん、ドイツ語のヘイウッド氏が応援にかけつけ、俄かに活気づいた。
30 ベビイ・シッター
ミノーがミシガンから帰ってから四日目にミゾーリ大学から長距離電話がかかって来て、もう一度インタヴューに出かけることになった。ミゾーリ大学はミゾーリ州のコロンビアという町にある。ジューンがミノーを空港まで送る間、私はシリーンのベビー・シッターをすることになった。
31 半旗
五月十一日の夕方、フラタニティーのシンギング・コンテストがあった。これはケニオンの年中行事のひとつで、これが終るとすぐに卒業試験が始まるのである。各フラタニティーの学生が四人ずつ腕を組み合い、列をつくって、「フィランダー・チェイス」の歌を合唱しながら行進する。大通りの真中の楓の並木の下を通ってオールド・ケニオンまで歩くのだそうである。
32 心覚え — 卒業式まで
ラックーン谷間は青葉の茂みで隠されてしまった。その奥に一軒の廃屋があって、長い冬の間、いつもの道を通る時に見えていたが、それも今は全く見えない。明日でいよいよケニオンの授業が終りになる。夕方五時にミノーの家へマルティニに呼ばれて行くと、ミノーは「もう三時間クラスに出たらおしまいだ。有難い」と云って喜んでいる。
33 散髪屋ジム
散髪屋ジムの店は、ウィルソン食料品店の一つ置いて隣りにある。私がガンビアへ来て初めてジムの店へ行った時、彼はこの店を始めてから三十四年になると云った。
34 エディノワラ家の出発
ミノーの車は中古のドッジである。何年のドッジかということは私は知らない。ミノーがまだエバンストンにいた時、知合の教授が車を売って新しいのと買い換えるという話を聞いて、譲ってもらったものだそうだ。それから間もなく、その車にジューンとシリーンと荷物を積んでガンビアへやって来たのである。
35 小鳥の巣
卒業式のあとですぐにニューヨークへ出かけた私たちが二週間ぶりにガンビアへ戻って来ると、入口の左側、ミセス・ベック寄りの方の灌木の中に小鳥の巣が作られていた。六月の終りにニコディム夫妻がロング・アイランドへ出かけ、今度はミノーの一家がコロンビアへ行ってしまったので、私たちはガンビアでの最後の一週間をひっそりと二人だけで暮らすことになった。
あとがき(抜粋)
私は昭和三十二年の秋から翌年の夏まで米国オハイオ州ガンビアに滞在した。ガンビアは電話番号帳によると人口六百、戸数二百と記されている。
田舎の出来るだけ小さな町に行って、その町の住民の一員のようにして暮らすことが出来たらというのが、ロックフェラー財団によって一年間の米国留学の機会を与えられた際の私の希望であった。
私は教授の家族の中にも、他の職業に従事している人たちの中にも、よき隣人を発見した。「ガンビア滞在記」はこれらの隣人の話を中心に、九月に始まって六月に終るカレッジの一年と町の様子を書いたものである。
私は滞在記という名前をつけたが、考えてみると私たちはみなこの世の中に滞在しているわけである。自分の書くものも願わくばいつも滞在記のようなものでありたい。
中公文庫
『ガンビア滞在記』は、1975年(昭和50年)7月10日、中公文庫として文庫化されている。
カバー紹介文(中公文庫)
米国オハイオ州ガンビアは人口六百、戸数二百の町。昭和三十二年秋から一年間の留学で滞在した著者は、広大な山野の明け暮れの中に、庶民の友情と哀歓を見た。
 庄野潤三「ガンビア滞在記」中公文庫版
庄野潤三「ガンビア滞在記」中公文庫版解説(坂西志保)
中公文庫版『ガンビア滞在記』では、坂西志保が解説を寄せている。
坂西志保は、ロックフェラー財団の留学事業にあたって、日本側で人選を務めた人物であり、この解説の中では、本留学事業の経緯についても触れられている。
その時、ロックフェラー財団の文化部長で、基金の授与を担当していられたチャールズ・B・ファーズ博士が来日された。博士は京都大学に学ばれ、日本語が堪能で、終戦後各年毎に日本を訪れ、私たちが当面している困難な問題をよく知っていられた。そして、戦前ロ財団が日本の学術団体や大学に援助を、また教授や研究所を海外に留学させて下さったりした例に鑑み、敗戦国の日本で創作活動に従事している人たちを一年の予定で海外に派遣することにしたいといわれた。
これをきいて私は飛び上がるほどよろこんだ。当時の日本にとって海外事情を詳細に書いてくれる人たちこそ、ほんとうにこれからの日本の民主主義の手本を示してくれることになると思ったからである。そしてこれはロ財団の創作家への奨学金ということになり、期間は一年間、数ヵ月合衆国に滞在するのが望ましいが、別に制限はない。ヨーロッパに行ってもよい。報告その他は一切要求しない。私が候補者を選び、ファーズ博士が面接して最後に決める。大体こんなことで話がまとまり、その第一回に福田恆存さんと大岡昇平さんが選ばれた。
占領下にあって公務以外は外国へ行くのは許されていない時であったから、この計画は歓迎された。そして発表された新しい眼で見る西欧の鋭い観察は広く注目され、日本の進路を暗黙のうちに示唆した。そのうち占領も終りに近づき、海外留学もかなり自由になって来た。ロ財団は引き続いて奨学金を出してくれることになっていたので、出来るなら選ばれた人たちが夫人同伴というわけにいかないか、恐る恐る伺いを立てた。
夫妻で一年留学ということになると、新しい経験を分け合い、終生いろいろ効果があると私は判断してファーズ博士に懇願した。ロ財団も私の主張を認め、最初に選ばれたのが庄野氏夫妻であった。これは昭和三十二年のことで、アメリカの小さな町で住民の一員のように暮らしたいという庄野さんの希望が叶えられ、その記録が『ガンビア滞在記』なのである。
大柄の外国人の間で小柄な日本人はひどく若く見える。庄野さんは三人のお子さん持ちである。序でに私が庄野さんに奥さんを連れて一年留学の相談を持ち出した時無理だと思ったが、たってお願いした。承諾された時私はほっとした。お立ちになる前に庄野さん一家を国際文化会館にお招きしてお昼を差上げた。一番上のお嬢さんが十歳位であったろうか、弟さん二人のお世話をしているのを見守っていて私は胸が痛くなり、奥さんのお気持ちを察してつらかった。
始めてアメリカへ行く人に、老若男女を問わず、私は『ガンビア滞在記』を読みなさいと勧める。楽しい本であるし、外国へ行って戸惑う場合どうしたらよいか具体的に庄野さんは解答を与えている。
あとがきに著者の庄野さんは一年近くガンビアに暮していて「教授の家族の中にも、他の職業に従事している人たちの中にも、よき隣人を発見した」と書いている。ことばや考え方、風俗習慣の相違を乗り越えて、お互いに良き隣人を発見するコツが、誠によくこの本に書かれているといいたい。
 中公文庫版「ガンビア滞在記」紹介文
中公文庫版「ガンビア滞在記」紹介文大人の本棚(みすず書房)
『ガンビア滞在記』は、2005年(平成17年)10月7日、みすず書房「大人の本棚シリーズ」から復刻刊行されている。
帯文(大人の本棚)
帯には「親切な隣人たち、町をかけまわる栗鼠、春夏秋冬にさまざまな彩りをみせる山野。アメリカの小さな町で暮らした一年間を描き、生きる静かな歓びに満ちた名作」とある。
 庄野潤三「ガンビア滞在記」みすず書房・大人の本棚シリーズ
庄野潤三「ガンビア滞在記」みすず書房・大人の本棚シリーズ裏表紙の紹介文
米国オハイオ州ガンビアは人口600人の小さな町、「中部平原が終ってまさに東部アパラチア高地に移ろうとする」あたりに位置する。
昭和32年秋から一年間、留学のためこの町で暮らした庄野夫妻の滞在記。
よき隣人でもある大学の友人たち、町の商店の人々、気儘に走りまわる栗鼠や、ときに出没するラックーン(あらいぐま)—。
 庄野潤三「ガンビア滞在記」みすず書房・大人の本棚シリーズ
庄野潤三「ガンビア滞在記」みすず書房・大人の本棚シリーズ広大な自然を背景に、この静かな町の、静かな歓びに満ちた春夏秋冬の暮らしを描いた名作。
「庄野夫妻はガンビアについたその日から小さな町の住民になりきったのである」(阪西志保「解説」)
解説(阪西志保)
大人の本棚シリーズ『ガンビア滞在記』には、中公文庫に掲載された坂西志保による解説が収録されている(中公文庫版を参照)。