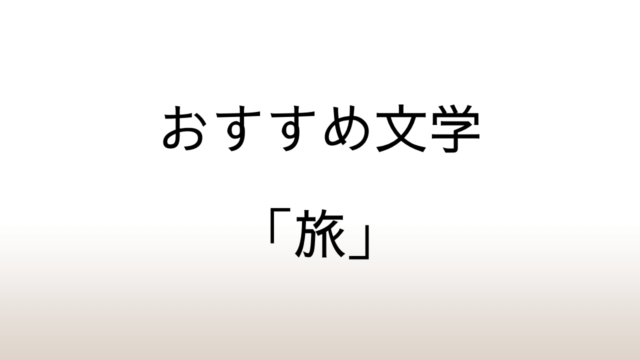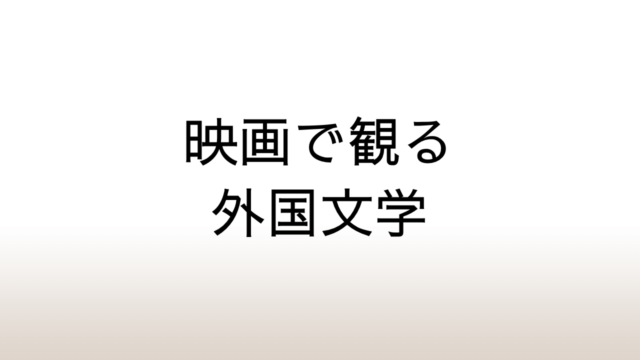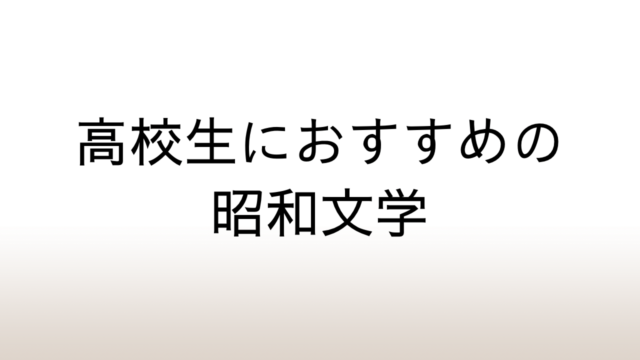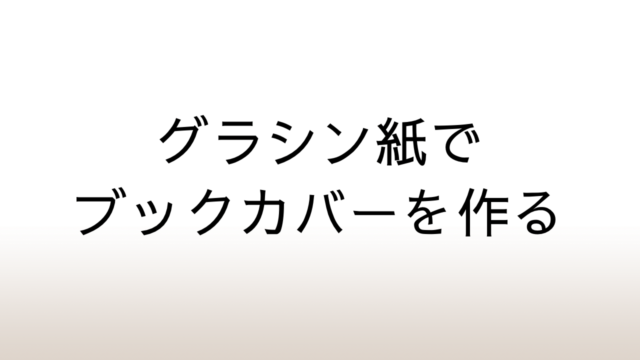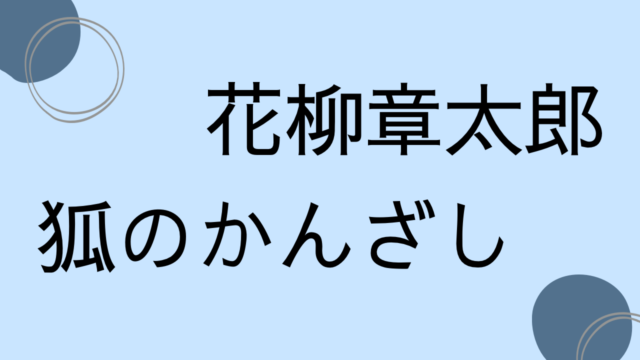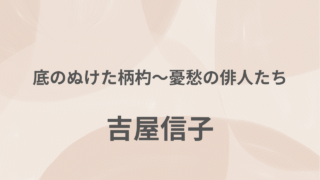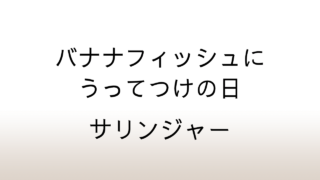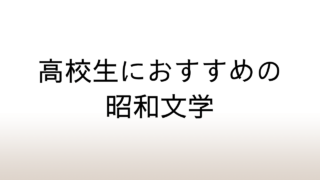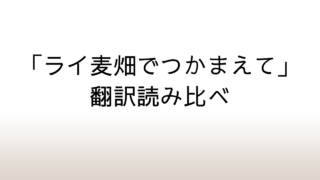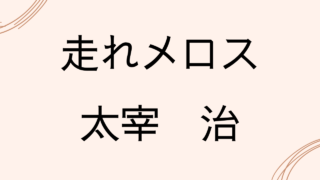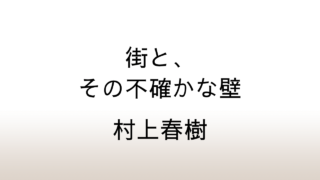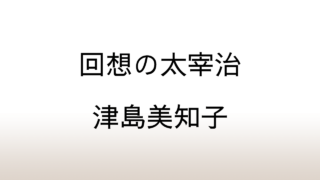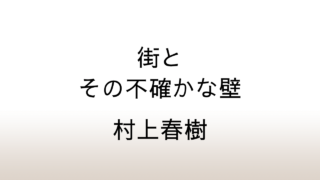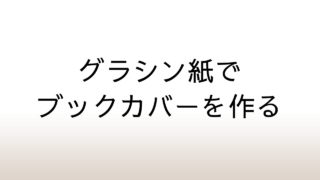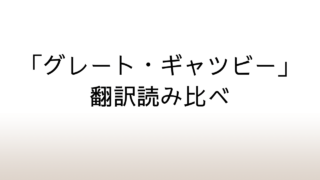渡辺淳一さんの作品「冬の花火」について紹介します。
夭折の女流歌人中城ふみ子の伝記的小説
「冬の花火」は、渡辺淳一の小説です。
角川書店が発行する短歌雑誌「短歌」で、昭和47年4月号から48年12月号にかけて連載され、昭和50年に角川書店から単行本として出版されました。
この小説は、北海道帯広市出身の女流歌人・中城ふみ子の一生を描いた伝記的小説です。
実在の歌人をモデルとしているので、多くの事実を基礎に描かれていますが、あくまでも小説であることを忘れてはいけないということを、作者である渡辺淳一は指摘しています。
それは、この小説が書かれた昭和47年当時は、中城ふみ子の没後から18年しか経過していないこと、多くの関係者がまだ存命であること、そして、小説の内容が、特に男女の性的な関係を多く含んでおり、重大なスキャンダルにも繋がりかねないことを、作者が懸念していたことを推察させます。
それほどまでに、中城ふみ子の生きざまは多くの男性と関係に溢れ、ドラマチックなものでした。
小説のタイトル「冬の花火」は、短歌雑誌に応募したふみ子の作品表題によっています。
「冬の花火」のあらすじを詳しく紹介します
ここでは小説「冬の花火」のあらすじについて、詳しくご紹介します。
(ネタばれ注意です!)
序章
作者である渡辺淳一は、歌人・中城ふみ子に関する取材のため、北海道の道東の街・帯広市を訪れます。
当時、帯広は札幌から急行で5時間を要する東の街でした。
10月末の帯広の気温は3.3℃。
東京からやって来た作家は、帯広駅に到着した瞬間「背中を風が吹き抜けるような冷気」にとらわれます。
晴れ過ぎた空と、平原の中にある低い街並みが、東京の作家に謎の「寒さ」を感じさせたのでしょうか。
第一章 蒼茫
中城ふみ子(野江富美子)は、1922年(大正11年)11月25日、帯広市内の呉服店に生まれました。
作者の渡辺淳一は、帯広で中城ふみ子の実の妹である野江敦子をはじめ、中城ふみ子を知る友人たちから直接話を聞いて、中城ふみ子に関する基本的な情報を収集していきます。
庁立帯広女学校時代のふみ子は「キュリー嬢」と呼ばれるほど痩せていて、苦手な数学で点数を稼ぐために、若い男性教師にラブレターを送ったこともあったそうです。
「庁立帯広女学校」は、1915年に設立された「十勝姉妹職業学校」がルーツ。1931年、「帯広町立姉妹高等女学校」として帯広町に移管。1933年には北海道庁に移管され、「北海道庁立帯広高等女学校」と改称されました。1950年から男女共学を機に現在の「北海道帯広三条高等学校」となります。
文芸部では部長を務め、「少女の友」に連載されていた川端康成の「乙女の港」に熱中しました。
1939年(昭和14年)に女学校を卒業した後は、東京の家政学院に進学、2年で卒業した後は、1941年(昭和16年)に帯広市へ帰郷しました。
1942年(昭和17年)4月、中城ふみ子は、北大工学部出身の鉄道官僚である中城弘一と見合い結婚、札幌に越した後、10月には夫の転勤に伴い室蘭市へと移り住みます。
そして、1943年(昭和18年)5月、長男の孝を出産。
1944年(昭和19年)5月には、夫が函館鉄道管理局施設部出張所長に栄転し、函館市での生活を始めます。
しかし、1945年(昭和20年)5月、職務上の饗応を受けた角で、夫の弘一は札幌へ戻されてしまいます。
1946年(昭和21年)3月、長女の雪子は札幌市内で生まれました。
「北国に生れし子故(ゆえ)雪子といふいとしき雪子美しくなれ」の作品が残されています。
この頃、閑職に追われた弘一は、闇物資を流すブローカーのような仕事に手を出すようになり、夫婦関係も荒んでいくようになりました。
1948年(昭和23年)の秋、三男の潔が生まれた2か月後、夫の弘一は再起を図るため、自ら望んで郷里の高松に転勤、一家五人は四国の人となります。
しかし、四国に移転して半年後、弘一は国鉄を辞職し、闇ブローカーを本職とするようになってしまいました。
1949年(昭和24年)4月、ふみ子は生後半年の潔だけを連れて帯広に帰郷、故郷で新しい生活を始めることを決意します。
戦後の混乱期に、乳児を連れて四国から北海道まで鉄道で移動することは、並大抵の苦労ではありませんでした。
手持ちの現金も底をつきかけたふみ子は、函館市内で質屋に駆け込みますが、偶然にもそこの女主人は、帯広女学校時代の同級生でした。
かつて自分よりも下に見ていた同級生に憐れみを受けながら金を借りるという屈辱を、ふみ子は全身で感じることになります。
8月、夫の弘一が2人の子どもを連れて帯広までやってきて、再び、一家5人の暮らしが始まります。
ふみ子の父親の世話で、弘一は帯広商工高校の教師となりますが、田舎教師に満足できない弘一は仕事を休みがちになり、1950年(昭和25年)3月、自ら退職してしまいました。
「帯広商工高校」は、昭和25年の共学化の際に「北海道帯広高校」と統合、現在の「北海道帯広柏葉高校」と校名を変えています。あるいは、弘一は、帯広商工高校の教員としては最後の世代だったのかもしれませんね。
弘一は友人とともに、闇物資を扱う会社を起こし、少しずつ家を空けるようになります。
そして、5月、弘一に女性の匂いを感じたふみ子は「もう帰ってこなくていいわ」と夫を追い出し、夫婦の別居生活が始まりました。
第二章 野火
1950年(昭和25年)6月末、28歳だったふみ子は女学校時代の同級生である村尾祥子に連れられて、帯広神社の社務所で開かれた短歌会に出席します。
既に、1947年(昭和22年)の春、札幌で暮らしていたふみ子は、北海道の歌誌「新墾(にいはり)」に参加をしていましたが、作品の投稿はせいぜい二、三度というごく簡単なものでした。
この日、ふみ子は30名ほどの出席者の中で二番目に多い得票を集め、一躍注目の新人歌人となります。
当時、ふみ子は3人の子を持つ人妻ではありましたが、見知らぬ人には20代前半でも通用するような若さを見に付けていました。
この短歌会の中で、ふみ子は20代後半の好男子・諸岡修平と出会います。
結核を患う諸岡は入院中の身であり、その上、病院の看護婦は彼の妻でした。
ふみ子は急速に短歌にのめり込みながら、諸岡と親しくなっていきます。
7月の短歌会の後で、二人きりで酒を飲んだとき、諸岡は妻とうまくいっていないことを告白、間もなく、ふみ子は病院へ諸岡を見舞います。
諸岡の病室に現れた彼の妻は、まるで20代前半としか思われない、美しい看護婦でした。
第三章 幻暈
1950年(昭和25年)9月、別居先の夫を訪ねたふみ子は、若い女性と暮らす弘一を発見して愕然とします。
そして、以前から札幌の中城家から強い要請を受けていたとおり、一番下の三男潔を中城家へ引き渡すことを決意します。
ふみ子との愛に熱中していた諸岡は、新しい短歌雑誌の発刊に奔走しており、昭和26年1月、十勝圏の短歌雑誌を統合する形で新雑誌「山脈」が誕生しました。
この頃、ふみ子は諸岡に対する相聞歌を数多く発表しています。
ともに独身ではありませんでしたが、ふみ子は諸岡の「愛人」という地位に酔いしれていました。
しかし、諸岡は結婚する前に付き合っていた元カノ・寺本郁代ともよりを戻しており、二人の密会現場を発見したふみ子は激怒して諸岡に絶縁を告げます。
諸岡と別れたふみ子は、帯広畜産大学の卒業記念ダンスパーティーで出会った大学生・大島と付き合い始めるようになります。
二人が毎週のようにデートを重ねていた6月、危篤の知らせを受けたふみ子は諸岡を見舞いますが、妻の道江が見ている前で、ほとんど会話をすることはできません。
結局、諸岡はその夏を乗り切ったものの、9月末、享年30歳で亡くなってしまいました。
諸岡の妻である道江や元カノの郁代と同席した通夜の夜、ふみ子は「たれのものにあらざる君が黒き喪のけふよりなほも奪ひ合ふべし」と詠んでいます。
第四章 喪失
諸岡の死を節目とするように、ふみ子は夫・弘一との離婚を決意、1951年(昭和26年)10月2日、二人は正式に他人となりました。
心機一転を図りたいふみ子は東京行きを決めて、両親の反対を押し切るようにして、11月初め、東京へと旅立ちます。
東京でふみ子は、タイプライターの学校へ通ったり、夜には喫茶店で働いたりしますが、半月と続きません。
銀座や新宿の映画館やダンスホールで、ふみ子は遊びまくります。
11月の末のこと、銭湯に入りながら、ふみ子は左の乳房に触れてみました。
実は、帯広を発つ頃から左の乳房に張った感じがあって、強く押すと鈍いような痛みを感じることがあったのです。
なんとなく左右の乳首の形が違うような気もしますが、ふみ子は「気のせい」だと自分に言い聞かせていました。
12月、金銭尽きたふみ子は、上京した母に連れられて帯広へと戻りました。
1952年(昭和27年)1月、帯広市内のダンスホールに通い始めたふみ子は、ダンス教師・五百木(いおぎ)伸介と出会います。
年下の男性を相手に、ふみ子は再び恋に落ちたのでした。
その頃、乳房の痛みは以前よりも強く頻繁になっていました。
母の勧めで近所の外科医を訪れたふみ子に、医師は「もしかすると癌かもしれない」と告げます。
当時は、癌に対する市民の意識はまだ低く、「癌かもしれない」という医師の言葉を、ふみ子はきちんと理解することができませんでした。
わが国では明治以来、死に至る病気と言えば「肺炎」「結核」「胃腸炎」などの感染性疾患が上位を占めていました。戦後、こうした感染性疾患が急速に減少し、変わって「がん」「心臓病」「脳血管疾患」といった、いわゆる生活習慣病と呼ばれる病気による死亡が上位を占めるようになります。がんが死因の1位となるのは昭和56年(1981年)から。
大学病院での検査の結果、正式に「乳がん」と診断されたふみ子は、乳房を切除するよう主治医から強く説得されます。
「お乳がなくなるくらいなら死んだ方がマシだ」と言い張っていたふみ子も、命を保つためには乳房の切除しかないということを理解して、とうとう手術を決意します。
このとき、最初に診断を受けてから、既に2か月が経過していました。
1952年(昭和27年)4月16日、ふみ子は左乳房切断手術を受け、片側の乳房を失いました。
5月中旬に退院したふみ子が一番最初に考えたことは、失われた乳房をいかにして装うかということでした。
当時、日本でブラジャーはまだ一般的ではなく、胸に当てるものとしてはブラ・パットが普通だったのです。
国内大手下着メーカーのワコール(昭和21年に和江商事として創業、昭和32年にワコール株式会社に改称)がブラパットの取り扱いを開始するのは、昭和24年のこと。翌25年、和江商事はオリジナルのブラジャーを開発・販売開始します。
退院後、ふみ子は以前と同じようにダンス教師の五百木との交際を続けました。
乳房を失ったふみ子は、十勝川温泉の旅館で、胸を両腕で抱いたままの状態で五百木に抱かれます。
若い男性と付き合うふみ子を世間は非難しますが、二人の恋はますます熱く燃え上がっていきました。
第五章 夕虹
正式な離婚を期に、旧姓の「野江」に戻すべきかどうか、ふみ子は短歌の師匠に相談しています。
師は「旧姓に戻すのが筋だろう」と言いますが、ふみ子は「中城の方が恰好いい」と答えます。
「名前の冴えない作家は歌も冴えない」というのが、ふみ子の結論でした。
1953年(昭和28年)10月、ふみ子の右の乳房に再び癌が発見されます。
左乳房を切断したとき、既にがんは右乳房へも転移していたのでしょう。
10日後、ふみ子は右乳房の切除手術を受け、両方の乳房を失いました。
11月、さらにがんの放射線療法を受けるため、ふみ子は札幌医大病院へと通院します。
ふみ子の癌は、脇や肩の淋巴腺にまで拡がっており、外科的治療は既に限界を超えていたのです。
小樽に嫁いでいた妹の家から、ふみ子は毎日札幌医大病院へと通いました。
1954年(昭和29年)1月、病室が空いたのを期に、ふみ子は札幌医大病院へ入院します。
札幌医科大学附属病院は、昭和25年に設立された道立施設です。前身は、昭和7年に設立された北海道社会事業協会附属札幌病院。なお、著者の渡辺淳一は、昭和39年から札幌医科大学の助手として勤務した経歴を持っています。
入院前日の1月3日の夜、帯広神社社務所で開かれた新年歌会に、ふみ子は北海タイムス記者である遠山良行を連れ添って登場しました。
32歳の遠山は「新墾」本誌の編集委員で、北海道短歌界の若手エースとして既に著名な存在でした。
札幌医大への通院中に遠山と知り合ったふみ子は、急速に遠山との関係を発展させていたのです。
1月4日、ふみ子は遠山に付き添われて札幌医大病院に入院します。
当時の札幌医大病院は戦時中そのままの木造モルタルの貧弱な建物で、ふみ子は「まるで牢獄のような」肌寒さを感じていました。
この年、中央歌壇の有力な短歌雑誌「短歌研究」が、一般投稿者から五十首詠を募集する新企画を開始しています。
師の勧めを受けていたふみ子も、この企画に応募するための準備を進めており、締め切りの1月15日直前だった13日、50作品をまとめ上げて東京へと郵送しました。
入院しながらも外出を続け、ふみ子は札幌での暮らしにも馴染んでいきます。
帯広の恋人・五百木とは手紙でのやり取りが続いていました。
第六章 光彩
雪が降り続く2月末のある日、ふみ子の元に東京からの電報が届きます。
五十首詠での特選を知らせる日本短歌社からのものでした。
ふみ子の特選作品は「短歌研究」昭和29年4月号に掲載され、たちまち、ふみ子は時の人となりました。
応募作品の表題は「冬の花火-ある乳癌患者のうた」でしたが、雑誌掲載時にタイトルは「乳房喪失」へと変更されていました。
刺激的なタイトルとともに、ふみ子の作品は当時の短歌界で大きな議論を巻き起こしました。
好意的な評価がある一方で、悪意に満ちた酷評や罵言も決して少なくはなかったのです。
こうした中、道内の歌人仲間は、ふみ子に歌集の出版を勧めます。
ふみ子の病気は確実に進行しつつあり、歌集を出版するなら急がなければならなかったからです。
過去の作品から300首程度が抜粋され、タイトルも「花の原型」に決定しました。
最後に残ったのは、序文を誰に依頼するかということでしたが、ふみ子は高名な作家・川端康成への依頼を提案します。
川端康成と何一つ接点のないふみ子は、川端康成に宛てて序文依頼の手紙を送りました。
当時、川端康成は55歳。長く芥川賞選考委員を務めるほか、昭和27年に芸術院賞を受賞するなど、文壇の大家でした。
周囲からは気違い沙汰としか思われない行為でしたが、川端康成は快く応じたばかりか、ふみ子の作品を雑誌「短歌」に掲載するよう、角川書店社長の角川源義に依頼します。
角川社長はふみ子の作品を宮柊二に見てもらった上で、「短歌」昭和29年6月号に掲載しました。
このときの表題は「花の原型」で、巻頭に52首が掲載され、川端康成と宮柊二の紹介文がそれぞれ添えられていました。
川端康成は後に小説「眠れる場所」で、ふみ子の作品「不眠のわれに夜が用意しくるもの 蟇・黒犬・水死人のたぐい」の一首を引用しており、ふみ子の作品に対して高い関心を抱いていたことをうかがわせます。
こうして、両方の乳房を失った薄幸の美女というショッキングで華やかなスターとして、ふみ子は戦後歌壇に登場したのでした。
ちなみに、若きエース寺山修司が登場するのは、それから間もなくのことで、中城ふみ子と寺山修司の二人によって、戦後歌壇は新たな時代を迎えることになります。
「短歌研究」に掲載された中城ふみ子の特選作品に刺激を受けた寺山修司は、本格的に短歌に目覚め、自らも「第2回五十首詠」に応募し、特選を得ます。このとき、寺山修司は早稲田大学に入学したばかりの1年生、弱冠18歳のまさしく若きホープでした。
「短歌研究」1954年(昭和29年)6月号に、再びふみ子の作品が掲載され、ふみ子を見出した編集長の中井英夫は処女歌集の出版をふみ子に勧めました。
札幌の出版社で印刷直前だったふみ子の歌稿は取り下げられて、東京の作品社から出版されることになりました。
歌集のタイトルは「花の原型」と決まっていましたが、中井の意向により「乳房喪失」へと変更されました。
なお、「花の原型」はふみ子の死後(昭和30年4月)に出版された第二歌集のタイトルとして用いられています。
この年の4月、歌人仲間の発案で、ふみ子の声が録音されていますが、このときの仲間たちとの会話は、ふみ子の通夜の席で披露されました。
第七章 装飾
5月初めの頃、ふみ子は自分の鼻の下の髭がうっすらと伸びていることに気付きます。
主治医によると、それは抗がん剤の副作用で、男性ホルモンの影響によるものだろうということでした。
男性ホルモンががん治療に効くと聞いて、ふみ子は過去に関係を持った男性たちのことを思い出します。
この頃、放射線科に回って来たインターン生の中川純と知り合ったふみ子は、この若い医師を誘い出し、性的な関係を持ちました。
まるで抗ガン治療を受けるような気持ちで、ふみ子は中川の精液を自分の体内で受け入れていたのです。
帯広時代のライバル歌人であった逢坂満里子が見舞った午後、ふみ子は重態に陥ります。
満里子からの連絡を受けて、翌朝、帯広からの夜行でやってきたふみ子の母親が到着します。
ふみ子は危篤状態であり、家族や歌人仲間が集められました。
数日、呼吸困難が続きましたが、7月1日午後、ふみ子は奇跡的に危篤状態から脱しました。
第八章 落日
小康状態を取り戻した頃、時事新聞文化部記者の高木章次が取材のために来札します。
ふみ子と関係を持った男性の中で最も美男子であった高木に、出会った瞬間にふみ子は惹かれていました。
30分のインタビューが2時間を超え、さらに翌日も高木はふみ子を見舞います。
7月6日の夜、こっそりと病院に忍び込んだ高木は、病院のベッドの上でふみ子と関係を持ちました。
その日から、高木は会社を休んで病室に泊まり込み、ふみ子の世話をすることになります。
7月8日の昼過ぎ、完成したふみ子の処女歌集「乳房喪失」が病室に届けられ、ふみ子は一冊ずつ丁寧にサインをしました。
7月10日、旧友である帯広の村井祥子がふみ子を見舞います。
この日は土曜日で、夜には豊平川で花火大会が開催されることになっていました。
友人と花火大会に出かけるという祥子に、ふみ子は「私のような病人は早く死ねばよいと思っているのでしょう」「花火でも見ながら、わたしが死ぬのを祈るといいわ」などと辛らつな嫌味をぶつけます。
振り返ってみると、この時期は、ふみ子に訪れた最後の小康の時期でした。
7月23日に来札した逢坂満里子が見舞ったとき、ふみ子の容態は一目で容易ではなく、慌てて満里子は帯広へ電報を打ちます。
会社を休んで泊まり込んでいた高木は、会社からの命を受けて25日に札幌を離れました。
最後の夜も、高木は病室の床の上で、瀕死のふみ子の体を抱きました。
26日、ふみ子の母が到着したとき、ふみ子は再び危篤状態に陥っていました。
強心剤と解熱剤を投与され、酸素吸入を受けながらも、ふみ子は短歌を作り続けていました。
面会謝絶が続く7月29日の朝、東京から千歳空港に到着したばかりの中井英夫がタクシーで札幌医大病院へ駆けつけました。
自分を発掘してくれた編集長と、このとき初めてふみ子は面会することができたのです。
終章
6月の危篤状態を脱してから、ふみ子はほとんど気力だけで生きていました。
歌の恩人である中井に出会えたことが、彼女の気持ちに一つの区切りを付けたのかもしれません。
中井と会った翌30日、ふみ子の発作はいよいよ激しいものになります。
親戚や歌人仲間が集められますが、ふみ子は必死で生き続けます。
危篤状態が続く中、中井は仕事の事情もあって8月1日夕方の飛行機で帰京しました。
8月2日、歌人仲間の宮田益子が見舞ったとき、ふみ子は枕の下にあるノートを益子に託します。
未発表の作品が収められたものでした。
翌日の8月3日の朝、激しい呼吸困難がふみ子を襲いました。
狼狽する母に、ふみ子は「騒がないで、騒がないで」と二度訴えました。
その直後、最後の発作が訪れ、10時50分、ふみ子の命は完全に尽きました。
享年31歳。
最後の言葉は「死にたくない、、、」でした。
その夜、親戚や歌人仲間が集まり、仮通夜がいとなまれました。
まるで、ふみ子の死を悼むように、午後から小雨が降り始めていました。
8月4日、小雨が降る中で告別式が行われ、ふみ子の遺体は平岸火葬場で焼かれました。
この日の夜、生前に録音されていたふみ子の会話が披露されました。
遺骨は、翌5日朝の汽車で家族とともに帯広へと向かいました。
正月に札幌医大病院へ入院して以来、初めてふみ子は故郷へ帰っていくのです。
真夏の十勝平野には藍色の亜麻の花が一面に咲き乱れていました。
生前にふみ子が残していた作品「息きれて苦しむこの夜もふるさとに亜麻の花むらさきに充ちてゐるべし」を思い出させるかのように。
ゆるゆる読書レポート
ここで管理人の感想を少し記しておきたいと思います。
フィクション小説の限界
作者も書いているように、この小説はあくまでもフィクション小説です。
多くのエピソードが事実に基づいているとは言え、存命の人たちに対する過分な配慮が働いていたことが推測されます。
特に、ふみ子最愛の恋人とも言えるダンス教師・五百木伸介との関係は、かなりふわっと描かれているような印象を受けます。
札幌の病院で多くの男性に囲まれながら、着実に死へと歩み続けるふみ子を、五百木はどのように考えていたのか。
全国誌でデビューし、一躍時のスターとなったふみ子の活躍ぶりを、帯広の恋人は何を思って見ていたのか。
仮にこの小説を五百木の視点で描いていたとしたら、また違った物語になったような気がします。
ルポタージュを基本としながら関係者に配慮するフィクション小説の限界が、作品の至るところで感じられました。
セックスは生き続けることへの祈りだった!?
ところで、中城ふみ子は多くの男性と性的関係を持った魔性の女として描かれていますが、実際に残された写真を見ると、数々のエピソードとは対象的に、素朴で地味な女性という印象を受けます。
絶世の美女と言うよりも、コミュニケーションの中で男性の心をつかむことができる、そんな人間的な魅力を持った女性だったのかもしれませんね。
それにしても、危篤状態を脱してなお、男性の肉体を求め続けたふみ子にとって、セックスとはどのような意味を持っていたのでしょうか。
乳房を切除して最初に五百木と寝たとき、ふみ子はまるで自分が殉教者になったようだと考えます。
あるいは、乳房を失ったふみ子にとって、セックスは信仰にも似た敬虔な行為だったのかもしれません。
乳がんが自分の体をむしばんでいく中、死への恐怖に襲われながらも男性と肉体関係を持つことで、ふみ子は生きることを祈り続けていたのかもしれません。
乳がんと札幌医大病院に関する描写が詳しい
この小説の特徴は、やはり医師である渡辺淳一が作者だということに尽きます。
乳癌を患うふみ子の体を、作者は医師という専門家としての視点から冷静に分析し、素人である読者にも分かりやすいように描写していきます。
小説の舞台も、ほとんどは札幌医大病院。
実は、ふみ子が亡くなったとき、渡辺淳一は札幌医科大学に通う1年生の学生でした。
当時の渡辺淳一は、中城ふみ子の存在を知らなかったそうですが、後に小説家となった作者が、自分の学び舎で死んだ女流歌人について興味をそそられないはずはありません。
ふみ子が入院する大学病院に関する描写も、必要以上に詳しいものとなっていて、当時の札幌医大病院を知るには格好の資料となっています。
中城ふみ子作品に関する詳しい解説はない
結局、この小説は面白いのかどうか。
管理人は率直におもしろいと思います。
特に、初めて中城ふみ子を知る人にとっては、中城ふみ子作品にのめり込むきっかけを与えてくれる物語だと言えるでしょう。
もっとも、作者の渡辺淳一は短歌の専門家ではないため、中城ふみ子作品に関する詳しい解説は期待できないと考えるべきです。
小説中にはふみ子の短歌が数多く登場しますが、歌の解説はほとんどありません。
短歌はふみ子の気持ちを物語るために引用されており、ふみ子の短歌が、この小説の雰囲気を創り上げていると言うことができるでしょう。
ゆるゆる文学散歩
小説を読んだ後は物語の舞台を実際に訪れるのが楽しみです。
「冬の花火」の舞台は大きく帯広と札幌とで構成されています。
今回は、ふみ子が闘病生活を送った札幌の所縁の場所をご紹介しましょう。
札幌医科大学附属病院
中城ふみ子が入院した札幌医大病院は市の西部の円山に近い南一条通りにあった。病院は戦時中、女子医専付属病院と称していたのが、戦後の学制改革で札幌医大となったもので、表玄関に近い部分を除いて大半は戦時中のままに木造モルタルの粗末な建物であった。ふみ子の入院した放射線科の病室はなかでもとくに貧弱な東病棟の一階で、木造の廊下は歩くとみしみしと鳴り、遠くからみると床が上下に波打っていた。(渡辺淳一「冬の花火」)
帯広で乳房切除手術を受けた中城ふみ子は、より専門的な放射線治療を受けるため、昭和29年1月4日、札幌医大病院に入院します。
当時の札幌医大病院は、戦前に建てられたまだ古い建物で、ここで学生時代を過ごした渡辺淳一の手によって詳しく描写されています。
ちなみに、北海道立女子医学専門学校附属病院が札幌医科大学附属病院へと変更されるのは、1950年(昭和25年)のこと。
ふみ子が入院生活を送った放射線病棟は、ふみ子の死後間もない1957年(昭和32年)3月に建て替えられています。
ふみ子が入院した頃の放射線病棟が、建替直前の本当に古い建物だったことが想像できますね。
電停「札幌医大前」
正月のせいか八時を過ぎた病棟は静まりかえり、時たま表通りを行く電車の音が流れてくるが、それが過ぎるとまた静寂が訪れる。隣の病室から患者の咳がきこえるが、それも数分続いただけで止む。夜になって冷えこんできたらしく、窓ガラスの端に氷の紋ができてくる。(中略)また遠く電車の音がする。音は雪のせいか、まるくふくらんで遠く聞こえる。仰向けになると薄汚れて灰色になった天井に丸い電気の笠が黒い影をつくっていた。(渡辺淳一「冬の花火」)
昭和29年当時、札幌医大前にはまだ市電が走っていました。
原田康子の「挽歌」にも登場する一条線の「円山公園行き」です。
小樽の妹の家から札幌医大病院へ通院していたときも、ここへ入院してから街へ外出するときにも、ふみ子は札幌市電を利用しました。
その頃は多くの患者や見舞客が、この路面電車に乗って「札幌医大前」電停で下車していたものと思われます。
札幌南一条西郵便局
一月十三日、ふみ子はようやくまとめた五十首を清書し、夕方病院の斜め向かいの郵便局に持って行った。「十五日までに東京に着きますかね」「速達だから大丈夫です」局員は原稿の入った袋を秤に乗せながら答えた。(渡辺淳一「冬の花火」)
「短歌研究」の五十首詠に応募する際、ふみ子は病院の斜め向かいにあった郵便局から発送しています。
これは現在も西18丁目にある「札幌南一条西郵便局」だと思われます。
1月15日までだった〆切直前の13日夕方に、ふみ子はここを訪れ、東京に向けて原稿を速達で郵送しました。
札幌グランドホテル
ふみ子がグランド・ホテル前で電車を降りると、中川はその前のアカシヤの樹の下で靴を磨かせている。それを見ると、ふみ子はうしろから近づき、いきなり中川の眼を両手でおおった。(渡辺淳一「冬の花火」)
昭和29年5月、入院中のふみ子は、札幌医大のインターン生である中川と密会します。
場所は札幌駅前通りにある札幌グランドホテルでした。
戦後、札幌駅前通りには靴磨きを営む女性が数多く並びました。
札幌グランドホテル、アカシヤ並木、靴磨き。
戦後の札幌駅前通りの特徴がさりげなく描写されていますが、今では失われてしまった古き時代の札幌の一こまです。
北大植物園
六月の初め、アカシヤの花が咲き乱れるころ、ふみ子は突然外出したいといいだした。その時、石塚は風邪で熱があったのに、自転車のうしろにふみ子を乗せて植物園まで行った。楡の巨木が芝生に濃い影を落し、リラの花咲く園内を、石塚はふみ子を自転車の荷台に乗せながら、ゆっくりと押して歩いた。(渡辺淳一「冬の花火」)
石塚はふみ子に恋い焦がれながら、ただふみ子の言うがままに従うだけのしもべ的な存在として登場する男性です。
肉体関係はありませんでしたが、ふみ子がまるで家族同様に心を許した唯一の男性でもありました。
豊平川の花火大会
花火は北海道新聞社の主催で、豊平川の川原で開かれ、豊平橋から幌平橋までの両側の堤は、見物客で溢れていた。みな白い半袖や浴衣姿で、短い北国の夏を惜しんでいる。祥子は夜空に打上げられる火の輪を見ながら、また病室に残してきたふみ子のことを思った。(中略)河原から歩いて薄野まで戻り、そこで菓子折を買うと、祥子は電車に乗って、医大病院前で降りた。夜の病院は黒く静まりかえり、花火の歓声はもうここまでは聞こえない。(渡辺淳一「冬の花火」)
豊平川の花火大会は、札幌の短い夏を盛り上げる風物詩のひとつです。
最盛期には一夏に3回の花火大会が催されていましたが、バブル景気破たん後の縮小で、現在は1回だけの貴重なものとなっています。
平岸火葬場
翌四日も、相変らず小雨が続いたが、仮装し、九時から告別式を挙行した。ここにも、通夜に出席した歌人達はもとより、新聞で知って駆けつけた一般の会葬客も数多かった。このなかを遺体は午前十時に出棺し、札幌の平岸火葬場へ向かった。(渡辺淳一「冬の花火」)
昭和29年当時、札幌の火葬場は豊平区平岸にありました。
豊平霊園が手狭になったため、昭和16年に造成された平岸霊園の中に建てられたものです。
平成6年までは地下鉄南北線に「霊園前駅」という駅も存在しましたが、現在は「南平岸駅」と名称を変えています。
平岸火葬場も、昭和59年に里塚霊園へと移設され、現在は平岸プールになっています。
まとめ
以上、渡辺淳一の小説「冬の花火」について紹介しました。
最後に「冬の花火」のお勧めポイントをまとめておきます。
・中城ふみ子の生涯を知ることができる
・中城ふみ子の作品も多数収録されている
・ただし、あくまでもフィクション小説
北海道の短歌史を研究する上だけでなく、日本の女流歌人を語る上でも、中城ふみ子は決して忘れることのできない存在です。
この小説を入り口にして、中城ふみ子の作品に触れてみてはいかがでしょうか。
短歌に関する知識がない人にも楽しめる小説ですよ。
書名:冬の花火
著者:渡辺淳一
発行:1979/5/20
出版社:角川文庫