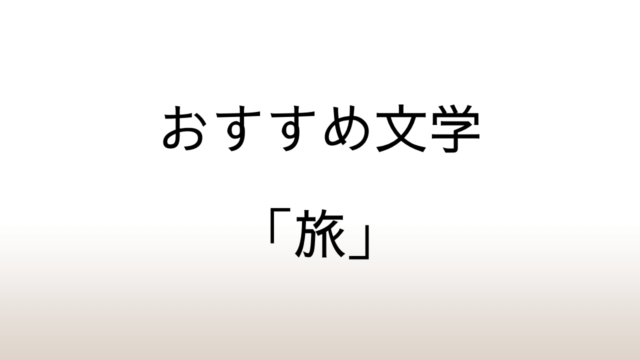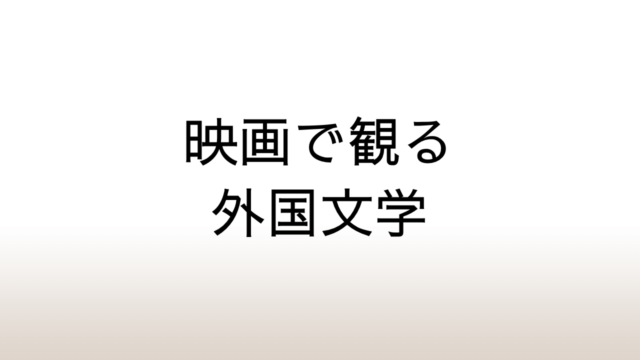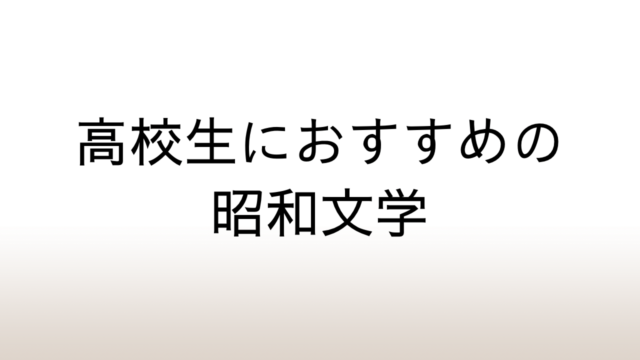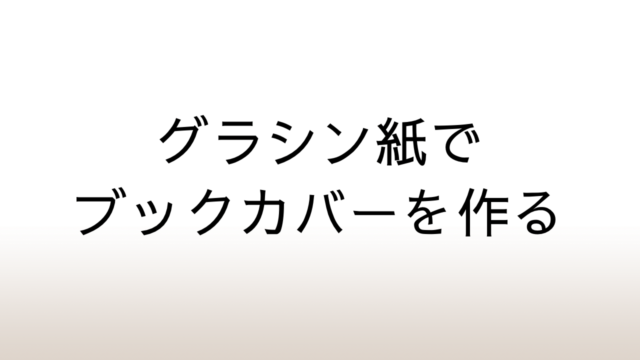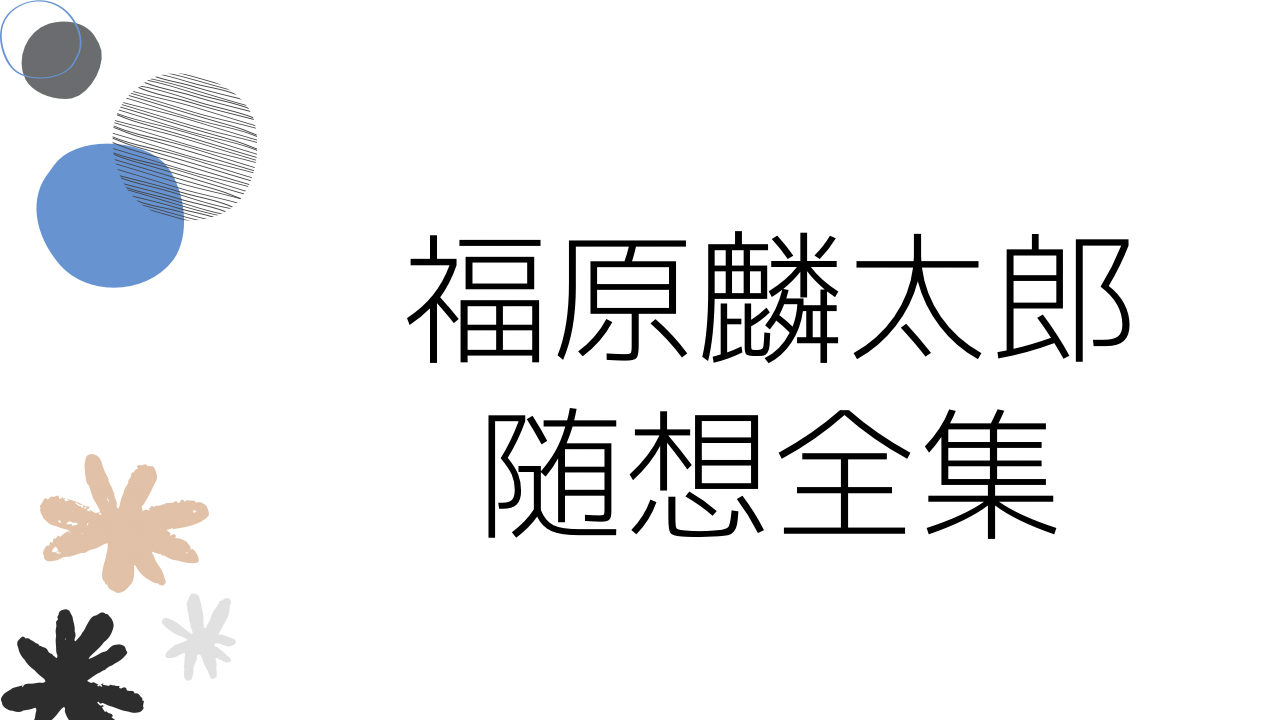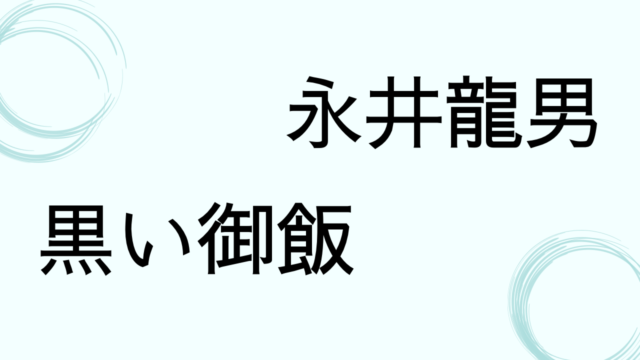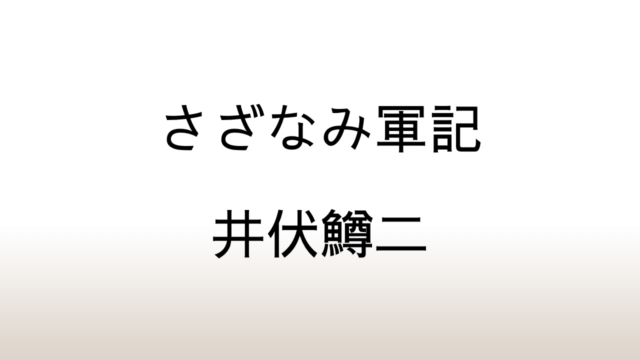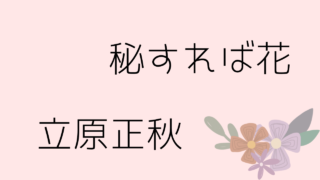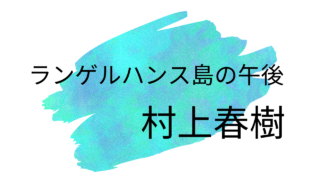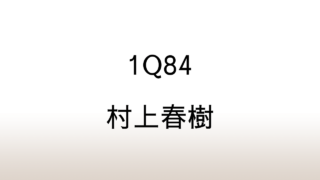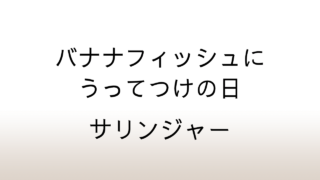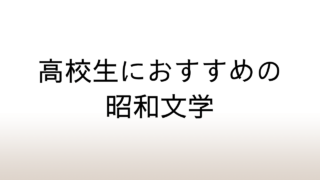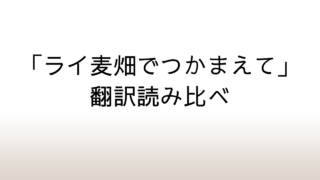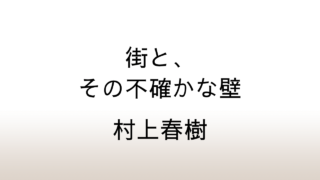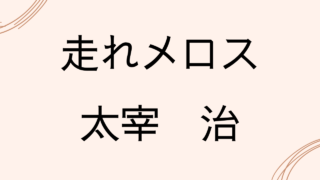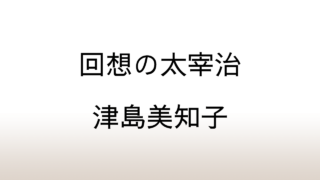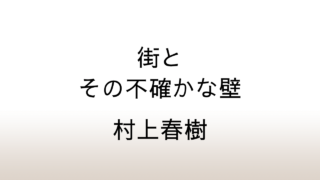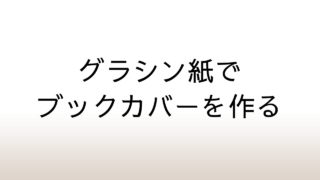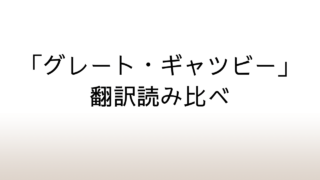福原麟太郎さんの随想全集第2巻「本棚の前の椅子」を読み終えた。
本は人生の幸せであり、読書は生きる楽しみである。
そんな幸せの、お裾分けみたいな随筆集だ。
書名:福原麟太郎随想全集「2 本棚の前の椅子」
著者:福原麟太郎
発行:1982/3/15
出版社:福武書店
作品紹介
福原麟太郎随想全集は、英文学者であり随筆家としても著名な福原麟太郎の随筆作品をまとめた、全8巻の随想集である。
第2巻「本棚の前の椅子」について、解説の河盛好蔵は「この巻には主として書物と読書についてのエッセイが収められている」と綴っている。
読書の愉しみを「生きることと共にある愉しみ」とする著者が、その深い学殖を通して、さまざまな角度から照し出した書物の世界。心から本を愛してやまなかった碩学の、広やかな魂を伝える巻。(帯文)
あらすじ
河盛さんの解説によると、本書は「三部に分けられていて」「著者の読書論と読書法を述べたⅠがその中心をなしている」「Ⅱの部には、著者の愛読し敬読した文学者や作家についての随想が収められている」「Ⅲの部には、読書余禄ともいうべき楽しく興味深い文章が集められている」ということになる。
「この巻は著者の仕事部屋をありのままに見せてくれる親しみ深く、教わる所の多い一巻である」という河盛さんの言葉が、この本を的確に物語っているのではないだろうか。
目次///<I>読書の愉しみ/読書と私/読書の目的/読書の方法/日向の読書/夏に読みたい本/読書週間に寄せて/読書有閑/雑書のヂャングル/雑誌を読む楽しみ/読書の味/人間・世間の書を/書物と人生/書斎/文学の書/古典の道しるべ/随筆について/辞書のこと/書斎にて/読書ということ/<Ⅱ>上等兵の日記/なずなとむくげ/史伝の美しさ/岩田さんのこと/太宰治/谷崎潤一郎/文体革命の時代/饗庭篁村/うしろ姿/表現の深浅/吉田健一・人と作品/<Ⅲ>わが読書/少年の日に/東京の本屋/変奏曲/本を売る/人を羨む/悲しき蔵書/自費出版/稀覯本の条件/風はなぜ吹くのだ///解説(河盛好蔵)/初出一覧///<月報>福原さんとの五十年(中野好夫)/福原先生のこと(荒垣秀雄)/福原先生の玩具箱(沼田六平大)
なれそめ
福原麟太郎さんの随筆に関心を覚えたのは、庄野潤三さんの随筆を読んでいるときのことである。
チャールズ・ラムの良き紹介者であった福原麟太郎を、庄野さんは深く敬愛しており、様々な作品の中で、福原さんのことを回想し、その言葉を紹介している。
例えば、「クロッカスの花」という随筆集に収録されている「治水」の中でも、庄野さんは「福原さんの随筆には、数え上げればいくらでも傑作が出て来る。夜空にきらめく星の中からどれがいちばんよく光るか、くらべようというようなものではないか」「シェイクスピアの云った言葉でもラムの云った言葉でも、この人の身体を通って出て来ると、もう福原さんの魅力となる」と、福原さんの随筆の魅力について、最愛の言葉を使って引用しているほどだ。
http://syosaism.com/shono-jyunzo-005/
庄野さんの影響を受けた僕は、講談社文芸文庫から出ている福原さんの随筆集「天才について」を読んで、福原さんの随筆の魅力にいっぺんでやられてしまった。
http://syosaism.com/fukuhara-rintaro/
福原さんの随筆をもっと読みたいという気持ちで、すぐに入手したのが「福原麟太郎随想全集(全8巻)」である。
どの巻から読み始めるか迷ったけれど、タイトルに惹かれたのが「本棚の前の椅子」だった。
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など。
随筆というものは、そう思われているよりは、もっと文学作品のはずだ
随筆というものは、そう思われているよりは、もっと文学作品のはずだと思う。古今の名作といわれるようなものは、何だか、ぴたっと貼りついたら、もう離れないような、芸術性を持っているようである。専門の文筆家の作であろうがなかろうが、出来上がったものはまがうかたなき文学だ、ということがあっても差し支えない。私はそのようなものを読みたい。(「随筆について」)
昭和28年3月2日「毎日新聞」掲載。
エッセイというと、素人が体験談を面白おかしく書いたものという風潮がある。
文筆業で生きている人の中にも、エッセイというのは暇潰しの原稿料稼ぎくらいに考えている人がいるのかもしれない。
自分の書いたエッセイを「文学作品」だと胸を張ることのできる作家が、現在、どのくらいいるのか。
福原さんの書いた文章からは、昭和28年当時、文学作品としての随筆が、既に軽んじられていたことを感じ取ることができる。
どんなに短くても、優れた随筆は、中途半端な短篇小説よりも深い感動を与えてくれる。
そういうものだと信じたい。
もうみんな死ぬ年なのだ、ああ君がさきに行くのか、というような感じである
平田(禿木)先生の亡くなられたとき、島崎さんはとうとう弔問に来られなかった。そのとき私は告別式にくらい来て下さればよいにと思ったが、いま私も六十を半分も越してしまってみると、島崎さんの心持がわかるような気がする。つまり、もうみんな死ぬ年なのだ、ああ君がさきに行くのか、というような感じである。焼香という儀礼など、あってもなくても友情に関係はないのである。(「変奏曲」)
昭和35年5月「サンデー毎日」掲載。
「変奏曲」は、島崎藤村の「春」にまつわる思い出を綴った回想文だ。
「春」の舞台は明治26年から28年頃で、22歳の島崎藤村をはじめ、平田禿木(21)、戸川秋骨(24)、馬場狐蝶(25)、上田柳村(20)、北村透谷(26)などをモデルとした若者たちが登場する。
平田禿木や戸川秋骨は英文学者として福原麟太郎に大きな影響を与えた人物であるだけに、「春」は福原さんにとっても思い入れを持って読むことのできる物語だった。
自分の親しい人たちが、小説の中に登場していることの興奮を、僕はまだ知らないけれど、その興奮を想像することはできる。
年老いた師にも熱い青春の時代があったことを、福原さんは島崎藤村の小説の中に発見しているのだ。
読書とは生きることと共にある愉しみというものではないだろうか
ねる前まで読んでいて、あとは明日にしようと、残り惜しくも本を閉じ、あしたの朝を待つ心境で枕につくとか、外から家に帰ってくるとき、帰ったら、あの本にすぐ取りつこうぜと心に思いながら、電車に乗っている、というようなことは、決して無くはない。私自身の経験にも、そのような時代があった。今から思うと、どんなに貧乏でも、どんなに辛いことがあっても、そういう時にその人は幸福なのである。(「読書の愉しみ」)
昭和32年1月3日、朝日新聞掲載「新潮文庫」広告文。
第2巻の一番最初に、この随筆がある。
新聞広告の文章だから、随筆と言っていいかどうか分からないけれど、ここには読書に対する福原さんの哲学が示されている。
どんなに貧乏でも、どんなに辛くても、本を読んでいる時(あるいは読みたい本がある時)、人は幸福である。
「それは生きることと共にある愉しみというものではないだろうか」という福原さんの言葉に深く共感しながら、僕たちは次の随筆へとページをめくる。
読書感想こらむ
通常、3冊の本を同時進行で読むことの多い僕が、この一週間は、ほとんどこの本しか読まなかった。
福原麟太郎の世界にどっぷりと浸かってしまいたいという気持ちがあったのかもしれない。
可能であるならば、福原さんの随筆集を同時代的にリアルタイムで読みたかった。
リアルタイムでなければ理解することのできない感覚もあったのではないだろうかと思うから。
もっとも、その代わりに僕は、70年後、80年後の時代でなければ理解することのできない感覚をもって、福原さんの古い随筆を読むことができる。
時間というフィルターを経て、なおも色褪せない。
そこに文学作品としての随筆があるように思える。
まとめ
福原麟太郎随想全集第2巻「本棚の前の椅子」は、読書の楽しみを広げてくれる。
すべての読書家にお勧め。
著者紹介
福原麟太郎(英文学者)
1894年(明治27年)、広島県生まれ。
日本英文学会会長など。
1981年(昭和56年)、86歳で没す。