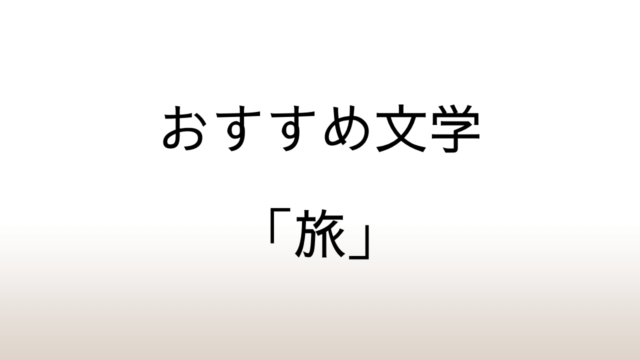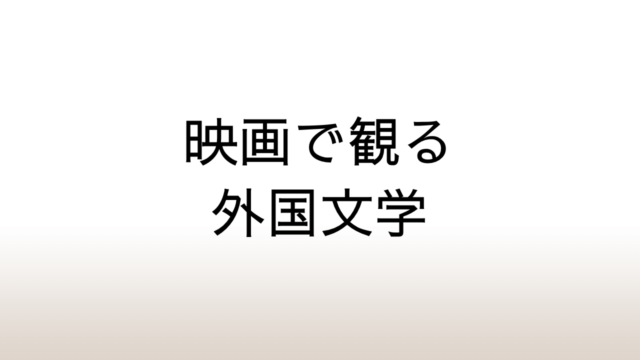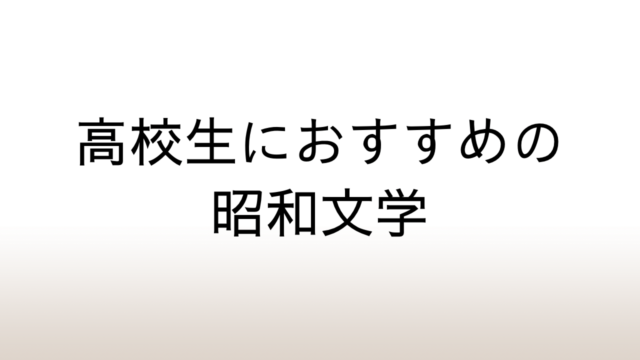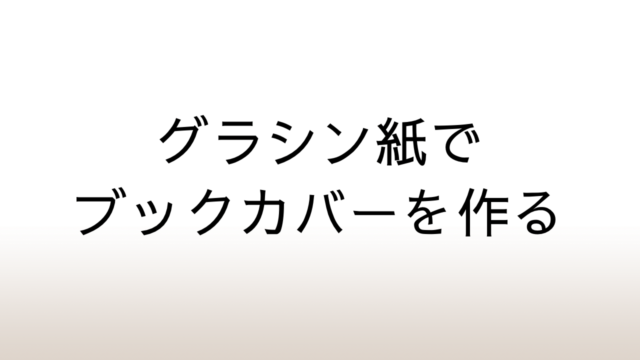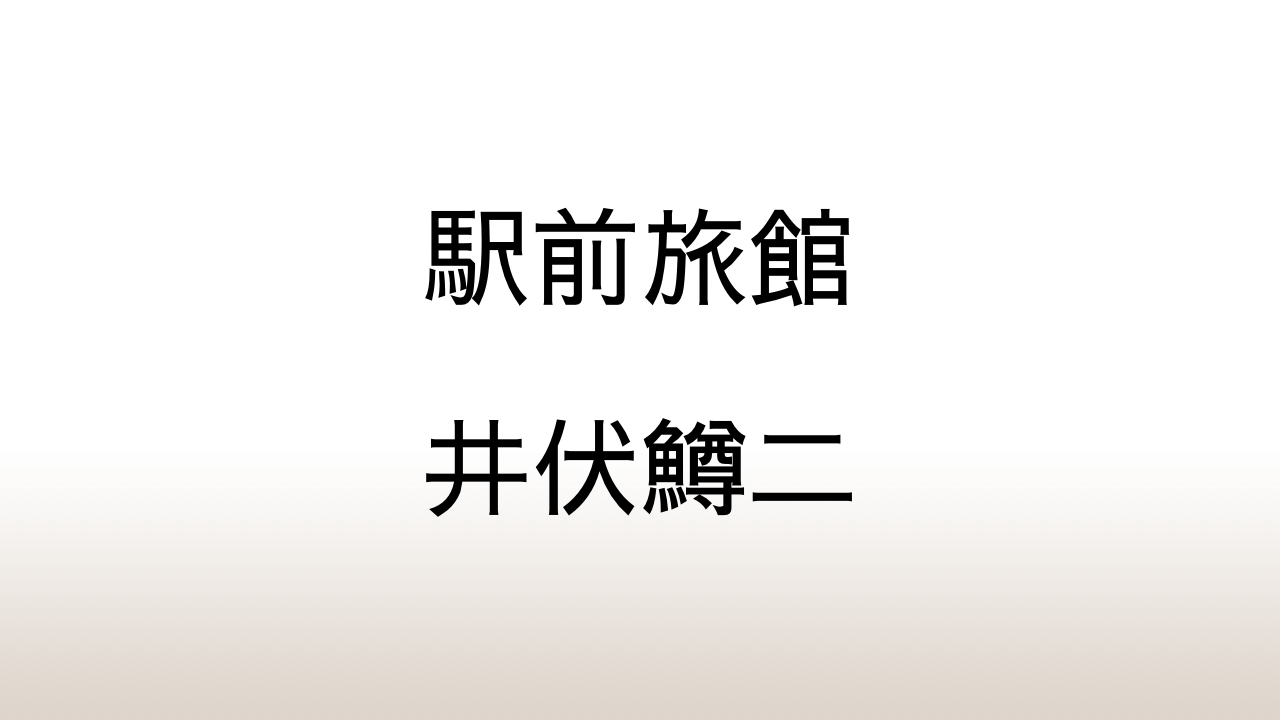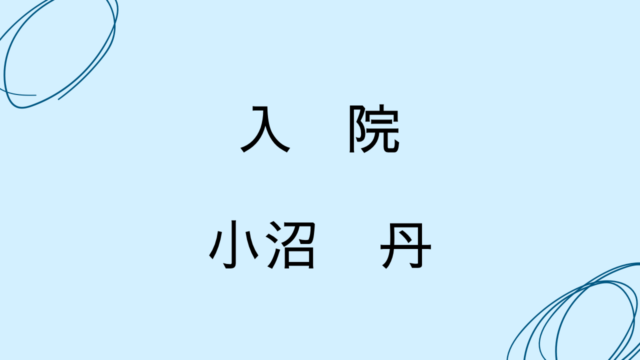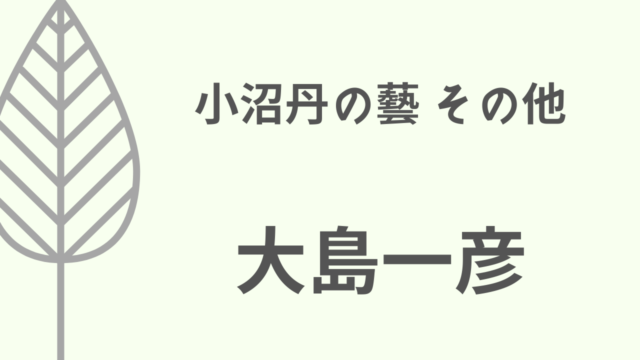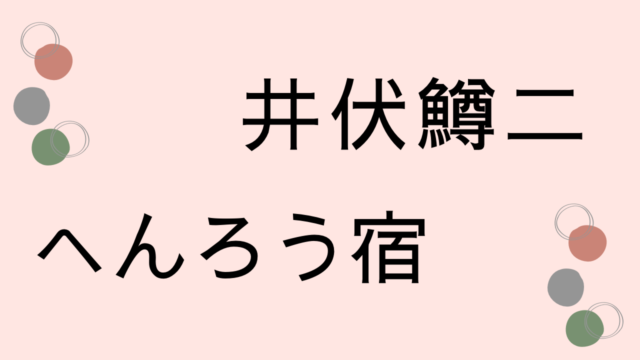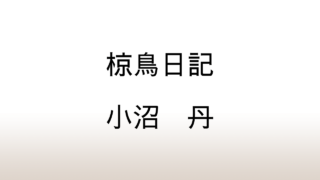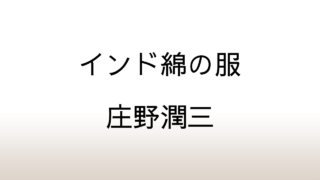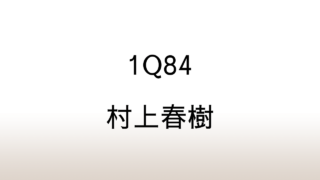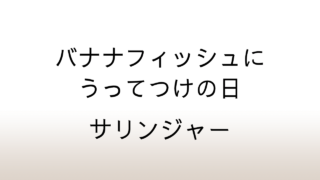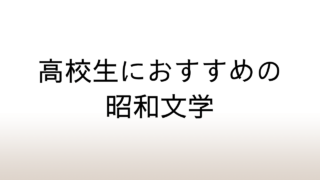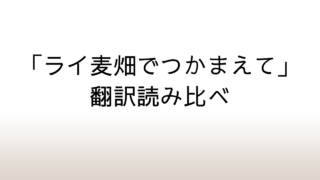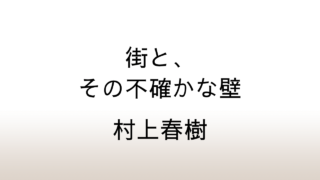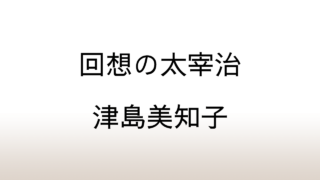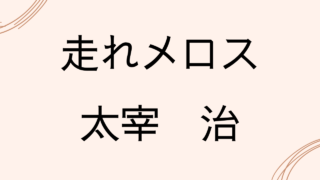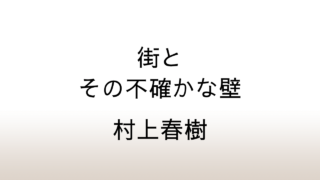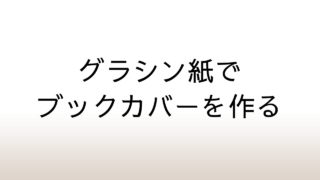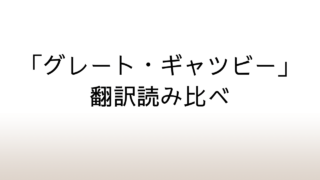井伏鱒二「駅前旅館」読了。
本作「駅前旅館」は、1956年(昭和31年)9月から1957年(昭和32年)9月まで『新潮』に連載された長篇小説である。
連載開始の年、著者は58歳だった。
単行本は、1957年(昭和32年)11月に新潮社から刊行されている。
1958年(昭和32年)、豊田四郎監督、森繫久彌・フランキー堺・淡島千景・淡路恵子などの出演により映画化された。
失われた日本の伝統
本作「駅前旅館」の楽しさは、語りの楽しさである。
その楽しさは、飲み会の席を盛り上げたという、井伏鱒二自身の語りの楽しさではなかったのか。
特別の筋書きはない。
ストーリーの骨格にあるのは、駅前旅館の番頭が、ずっと昔に縁のあった女性と再会し、怪しい雰囲気となるものの、番頭仲間の機転で深入りを逃れ、馴染みの居酒屋の女将と良い仲になるというものである。
つまり、旅館の番頭を主人公とした恋愛物語だが、恋愛物語の感じがまったくないのは、筋書きよりも、主人公の語りが中心になっているからだろう。
本作は、駅前の柊元旅館の番頭<生野次平>の独白という形で進められる。
「駅前の宿屋風景を知りたい。思い浮ぶままに語ってくれ。くだらないと思ったことでも喋ってくれ。何も彼も繕わずに話してくれ。芝居や小説のように仕組まなくてもいい。在りのままに話してくれ」という注文に応える形で、主人公は「連続独演みたいな真似」で、駅前旅館の番頭としての見聞を披露する。
最初に簡単な身の上話から始まる。
いわば私、餓鬼のときから旅館の寄生木になって来た人間です。百姓仕事や木樵の仕事では、幾ら自分で思ったって五体が言うことをききません。それに早くから生れ在所を棄てて行った人間だ。在所の人から見ると、どうせろくな者とは言われない。実際にろくな人間じゃあございません。(井伏鱒二「駅前旅館」)
主人公の母親は、旅館の女中だったから、主人公も、若い頃から旅館で働き始める。
女中部屋の女たちと遊び、女郎屋通いに身を費やした主人公は、戦争を境に気持ちを入れ替えて、まだ焼け跡だった東京へ上京する。
そこで私、決心いたしました。よろしい、東京に出てやろう。東京に出たら、焼け残った上野の五重の塔に願がけをしよう。今度からは、性根を入れかえて、いかに不時の稼ぎがあったって、博打はうつまい、女道楽も馬券買いも思いきろう、必ず思いきるんだ。(井伏鱒二「駅前旅館」)
ところが、戦後、旅館の流儀も、戦前からは大きく変わってしまった。
主人公が見つめているのは、戦前から戦後にかけて大きく変わってしまった、宿屋の流儀である。
かつてあった時代を懐かしむように、主人公は、戦前の旅館風景を思い出す。
このノスタルジーこそ、本作を通底している主旋律だろう。
例えば、明治、大正から昭和にかけて、戦前まで、江の島の片瀬の旅館街は、番頭たちが客の呼び込みの腕比べをする晴れの場所だった。
江の島へ出稼ぎに行くのは、毎年三月から八月までの夏稼ぎですが、初めて稼ぎに行く番頭は、先ず口入れ稼業の親分の前で、実際に呼込みをやってみて、それでいいとなると旅館へ振向けられる。だから関西と関東の番頭の腕くらべをするようなもので、そのつばぜりあいは実に壮観なるものでした。(井伏鱒二「駅前旅館」)
あるいは、「ソハヤマタオ一イマノタ」などという、謎の電報のこと。
これは私たち業者の間で通用する符牒の文句です。戦前には駅頭に出るほどの刑事なら、新米でもたいてい心得ていた符牒だが、戦後は疑いをかけられる怪文書に見えるんだ。(井伏鱒二「駅前旅館」)
戦後十年、時代は、まさしく移り変りつつあったのだろう。
駅前旅館の番頭の姿を通して描かれているのは、失われていく日本の伝統だったのかもしれない。
東京の駅前旅館は、日本中から客が集まってくる場所だから、番頭の目を通して描かれる地方の庶民の姿もおもしろい。
お客のうち、爺様婆様を泊めて賑やかなのは、何といっても千葉県の外房だね。飲むと、必ずやるのは盆踊や大漁節だ。みんな自分の家から踊の用意支度を持って来て、お酒のほか長襦袢から手拭一本まで準備してやって来る。(井伏鱒二「駅前旅館」)
群馬県とか千葉県は、修学旅行の団体まで金遣いが荒い。
石川県あたりの婆様だと、夕食の二合瓶をスーツケースに入れて、息子の土産にと持って帰るのがある。
昔の江の島仕込みで言えば、お客を見るには先ず履物から見る。無論、下駄の形にも地方色というのがあるが、履物が新しければ、これは山形だな、秋田だなとわかるんだ。次にお客の持ってる携行品を見る。風呂敷包みを背負ってるのは新潟県、バスケットはたいていが山形県、千葉あたりの人は袋にして背負っている。(井伏鱒二「駅前旅館」)
地方色という言葉も、戦後の高度経済成長の時代に失われてしまった言葉だろう。
経済発展の中で、全国の均一化が進み、履物や携行品を見て、地方を見分けるなんていうことはできなくなってしまった。
自選全集の覚え書きに、井伏さんは「消えて行く寸前の専門家の風儀を書いた」と記している。
現在となっては「消えてしまった」専門家の風儀が、ここにある。
つまり、風俗史的にも民俗学的にも、『駅前旅館』は価値のある作品だということだ。
庶民の姿を描き続けてきた井伏鱒二だからこその、風俗文学と言えるのかもしれない。
駅前旅館の番頭の生き様
井伏鱒二の小説では、庶民が生き生きとしている。
山形出身の学生だった松山さんは、下宿の後家に因縁をつけられるようなことを仕出かしてしまって、いやいやながら後家の姉と所帯を持つ言質を取られてしまった。
泥酔した松山さんは、土間の外で雨に濡れながら、竪樋にしがみつき、その桶に耳を押しつけている。
「さあ旦那、おやすみなさいまし。深夜の雨は、お毒でございますよ」私が松山さんの腕に手を添えると、それを振りはらって。「止してくれ。よう、聞えるんだよ。いっさいがっさい、みんな一と纏めに聞えるんだ。人生の内臓の音だ」(井伏鱒二「駅前旅館」)
「人生の内臓の音だ」という、ドキッとするような言葉が、何気ない昔話の中にひょっこりと埋め込まれている。
こういうのを読むと、井伏鱒二という作家は、やはり恐ろしいと思う。
主人公の番頭仲間でライバルでもある高沢は、主人公と並んで、この物語を盛り上げている重要な登場人物だ。
そこへ、おかみさんが帰って来て、「あら高沢さん、いやですわ。駄目です、いけません」と、招き猫を奪って胸に抱きしめました。それが、いかにも艶なるものに見え、また、どうにもナフタリン臭い恰好のようにも見えました。で、高沢が図に乗って、「春の夜や、いやです駄目です、いけません」と即吟して、やがてその意を解したおかみさんに、「ふふふふ」と恥ずかしそうな含み笑いをさせたことでございます」(井伏鱒二「駅前旅館」)
「春の夜や、いやです駄目です、いけません」という、さりげない名句が、ここで生れている。
高沢は、辰巳屋のおかみに気が合ったようだが、毎晩通っているうちに、不本意ながら「友達づきあい」の仲になってしまったらしい。
「四度も五度も通っているてえと、友達づきあいになって、もはや口説けねえ。お前さんのやりかたは、お前さんの青春のかけらというやつを、まるで味噌漬けにしてるようなもんだ。だが、俺の見るところじゃあ、十分すぎるほど脈があるね」(井伏鱒二「駅前旅館」)
同業者間の友情は、同じ苦労を味わってきた男同士だからこそ、通じるものでもあったのだろう(本作『駅前旅館』は、男同士の友情物語でもある)。
「お前さんのやりかたは、お前さんの青春のかけらというやつを、まるで味噌漬けにしてるようなもんだ」という台詞も、書き留めておきたい名言の一つである。
「高沢は猪口を持った手を伸ばしまして、受けて大きな所作で飲みほすと、ぱちりと平手で額を打つのでした」のように、酒飲みの姿も実に生き生きとしている。
その辰巳屋のおかみは、主人公に気があるような、微妙な雰囲気を漂わせている。
「あたし字が下手くそだから、履歴書なんか書けないわ。あたしの気持が通じないのと同じように、いくらじれったくても仕様がないのね。まるで宿命を背負っているみたい」(井伏鱒二「駅前旅館」)
謎かけのような言葉には、女の生々しい雰囲気がある。
きっと、辰巳屋のおかみは、主人公のことが好きなんだろうと思うが、そのあたりの深いところまでは書かれていない。
生野次平というこの俺は、色道にかけて何という雑な男だろう。於菊に会ったときも辰巳屋の前に出たときも、同じ型に嵌まったことしか言えなかった。同じ無器用な真似しか出来なかった。生れながらの雑な人間であるにしても、あちらの女こちらの女に同じ真似をしたのが儂は恥ずかしい。(井伏鱒二「駅前旅館」)
客としてやってきた、昔の女・於菊に手を出すことはできず、辰巳屋のおかみさんの前でも、膝をくっつけあって喜んでいるだけの木偶の棒だと、高沢は言った。
生野次平という男の生き様が、そこにはある。
私という人間は、番頭として、また一個の人間として何ら節操があるわけではなく、自分で自分を信用している人間ではない。しかも自分は何という女に弱い人間だろうと自分で自分の気持を持てあますことがある。ただ、自分でもよくわからない何か意地ずくのような気持から、その日その日の恰好がつくように我流で凌いでいるだけなんだ。(井伏鱒二「駅前旅館」)
こうしてみると、本作『駅前旅館』は、単に庶民の風俗をスケッチしただけのドキュメンタリーではないことが分かる。
戦前から戦後にかけて、駅前旅館という舞台で生きてきた男の、人生の物語。
新潮文庫の解説を担当した河上徹太郎は、「私はしばしば井伏鱒二御当人と酒を置いて歓談している時のようないい気持になる」と書いている。
改版後も、河上徹太郎の解説を残してくれた新潮文庫に感謝したい。
それにしても、読み応えのある小説というのは、こういう小説を言うんだろうな。
それにしても、井伏鱒二はやはり文章が上手い。
永井龍男のような美しい文章というのと違って、膨らみのある日本語の文章だ。
イケメンではないけれど、人間として魅力的な男。
そういう文章の上手さが、井伏さんの作品の、一つの特徴だと感じた。
書名:駅前旅館
著者:井伏鱒二
発行:2007/11/01
出版社:新潮文庫