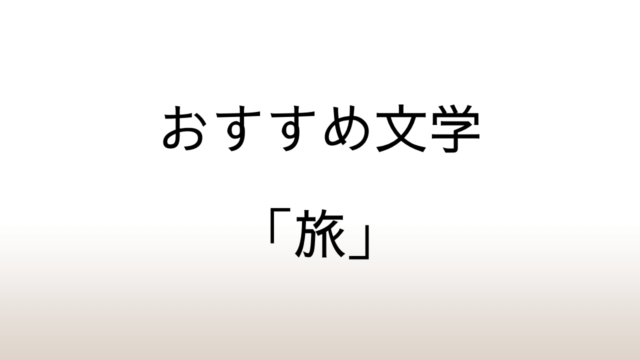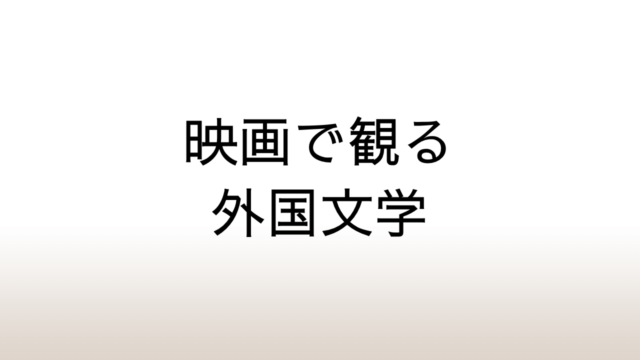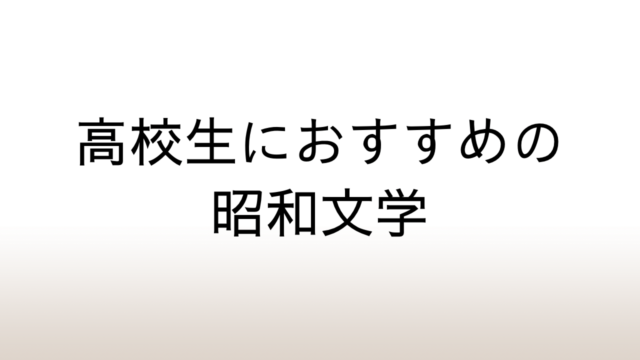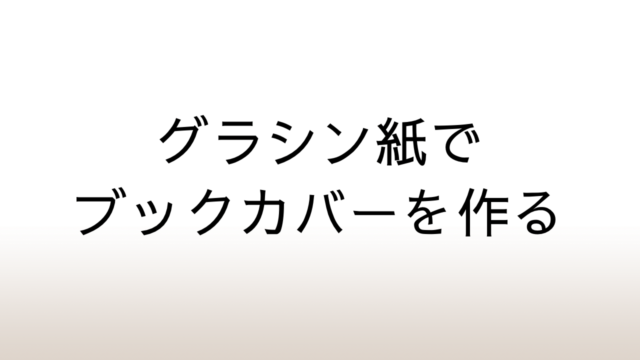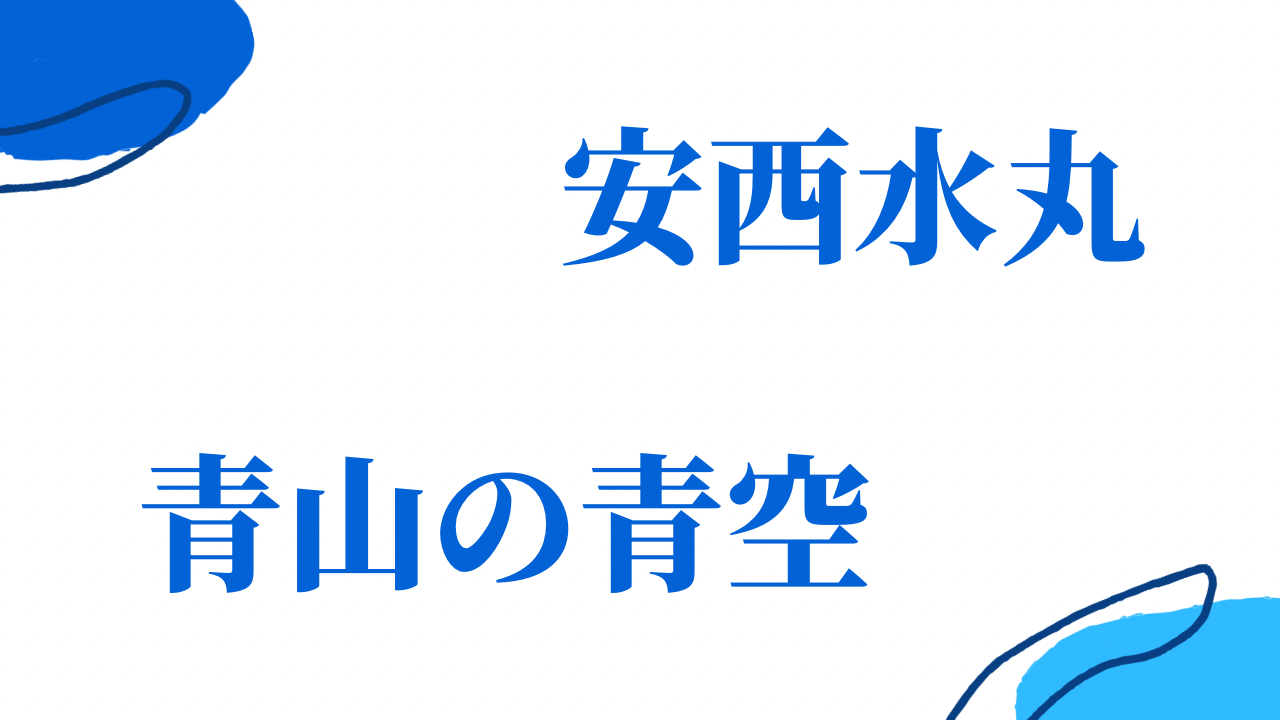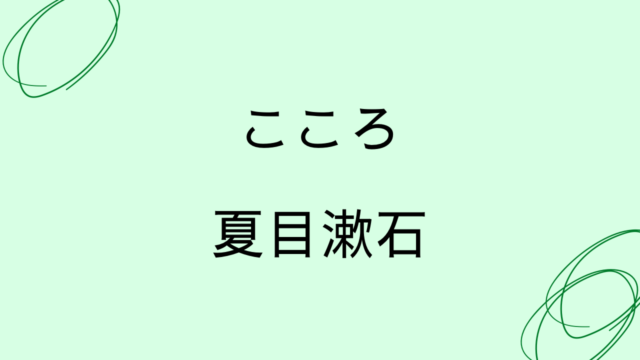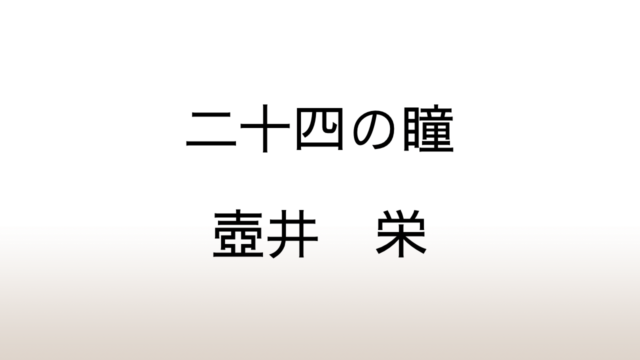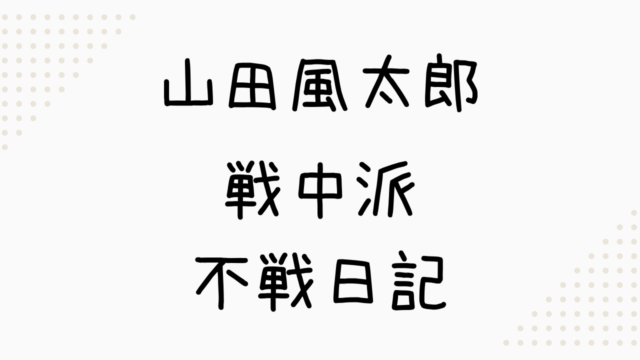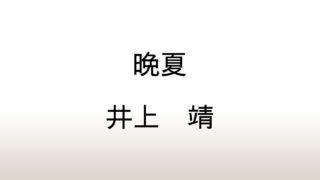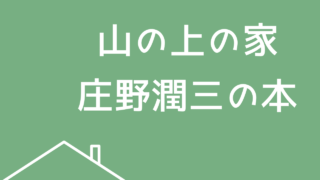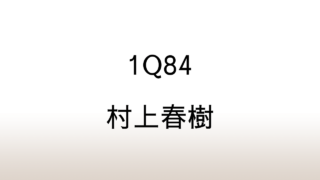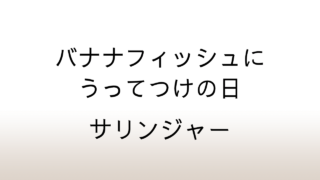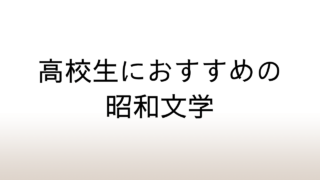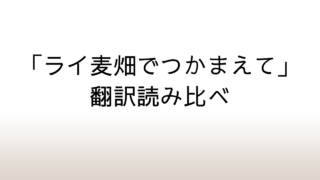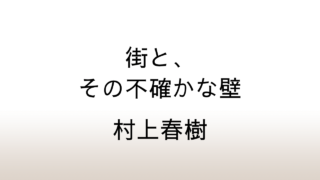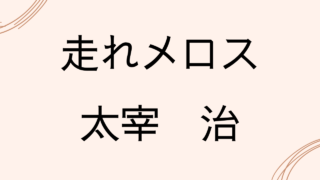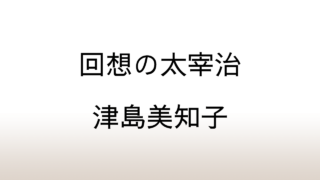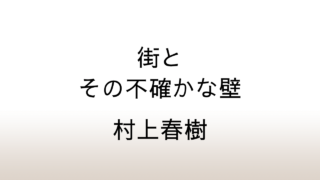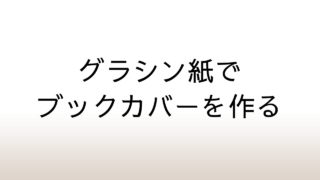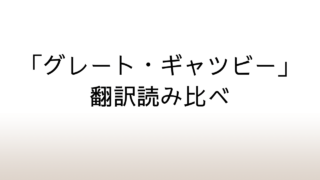安西水丸さんのエッセイ集「青山の青空」を読みました。
読書の合間の息抜きに、楽しめましたよ。
書名:青山の青空
著者:安西水丸
発行:1993/2/25
出版社:新潮文庫
作品紹介
「青山の青空」は安西水丸さんのエッセイ集です。
単行本は、1989年(昭和64年)にPHP研究所から刊行されています。
水丸さんの「まえがき」によれば「とりとめもなくあちこちに書いたもの」で、「すべてはささやかな日常の気分」であり、「青山の青空。そんな空をちらっと見上げた気持ちで目をとおしていただけたらと思っている」とあります。
(目次)まえがき///第1章 僕の風景/癌で死にたくなかったらつまらぬジェラシーなどおこすものではない/カタカナ職業にもトレンドがある/スキーは貧しいスポーツである/スポーツクラブは意外と恥しいところである/都会の言葉はポストカードで伝えたい/いいプレゼントは日頃のいい人間関係から生まれる/有名人あこがれ人間は後をたたない/アブノーマルを深く追求しよう/ぼくはきっと俳句をやめないと思う/ぼくはペットが嫌いだ/みんな猫の魔力に犯されている/「ニャーゴ」という猫の鳴き声がたまらなくいやだ/盲目的なペット愛を見ると発狂しそうになる/僕にとっての「犬の系譜」/新幹線の中ではおにぎりを食べながら三味線を聴く/きれいな空き缶はペン立てにする/二十八歳になるまで酒を飲むことを母にかくしていた/アート・ガーファンクルの声を聴いていると天使の姿がうかんでくる/もしもピアノが弾けたなら/ぼくの場合、人の好き嫌いは顔で決まる/個性とはそこはかとなくにじんでくるものだ/わがままなんてなんだかんだいうほどのことではない/カラオケが嫌いで現代を生きるのは難しい/ぼくは一年中、ほとんど同じような格好をしている/おしゃれなんて恥しい///第2章 街の風景/原宿・青山好きの若者は正直者である/湘南はカーライセンスからはじまる/ホテルの似合う女はいいものだ/銀座はごく自然にぼくの遊び場所になった/銀座はどこか外国風の匂いが漂っていた/桜散るお堀端を「美少女電車」が走っていた/人のいない遊園地には祭りの後のさみしさがある///第3章 時の風景/イラストレーションはおいしそうかまずそうかで決まる/ポルトガル海岸とデンマーク山のある風景/ぼくは女の歴史の中で生きてきた/絵を描くことは楽しい遊びだった/桜の色がいいね―その一言で絵を描きつづけようと思った/「少年王者」に夢中になり何度も模写をくり返した/「とんがり帽子」のべんとう箱が凶器になった/五人の姉にかこまれて「君の名は」を聴いていた/父の書斎には邦楽のレコードがたくさんあった/子供の頃から傍役が好きだった/ぼくはハーモニカを二本持っていた/男たちの唄声が海原の風に舞った/セピア色になった裕次郎の似顔絵/四人ひろしをおぼえていますか?/かなしみの「新安里屋ユンタ」/まず自分は何をする人になるかをはっきりとさせることだ/ジャズの話はいつもどこかできすぎだ/雪のマンハッタンに「静寂」の音が流れた/ぼくは今でもパイプを愛用している/きちんとスーツを着て仕事をするのは気持ちのいいことだ/カーラジオから「スタンド・バイ・ミー」が流れた/アズナヴールを聴くとパリを思い出す/房総の正月と京都の忘年会///あとがき///《特別対談》「プレゼント」柴門ふみ×安西水丸
あらすじ
雨が降る日も曇る日もあるけれど、ぼくの心の中の青山はいつも晴れだ。
今日はふらりと映画でも見に行こうか。
銀座に出て路地裏の居酒屋で一人酔おうか。
それとも…。
仕事場を構える青山で、著者が折りにふれ感じたこと、思ったこと、考えたこと。
そんなささやかな日常の気分を、イラストレーションと文章で綴ったエッセイ集。
巻末には、漫画家・柴門ふみ氏とのオリジナル対談付き。
(背表紙の紹介文より)
なれそめ
安西水丸さんといえば村上春樹さんと、僕の中でははっきりと繋がっています。
やはり「村上朝日堂」シリーズの中に登場する水丸さんの印象は、非常に強かったのだろうと思います。
やがて、村上さん繋がりで水丸さん本人の著作も読んでみたいと思うようになり、水丸さんのエッセイ集を集めるようになりました。
もともと僕はエッセイやコラムといった短い雑文が大好きで、とりわけ文筆を主な生業としていない、つまり「素人」の書いた随筆が大好きです。
何が飛び出すか分からない楽しさがあるし、近所のおじさんの世間話を聴いている気軽さもある。
そして、古い時代に書かれた雑文には、古い時代の空気感が宿っています。
文学書を読むのとは少し違った息抜きみたいな感じで、僕はこのエッセイ集を読むことができました。
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
サラリーマンの楽しさにはスーツを仕事着としていることがある。
ぼくはサラリーマンを15年ぐらいしていたことがあるけれど、サラリーマンの楽しさにはスーツを仕事着としていることがある。会社勤めをしているのにイキがってセーターやデニムの上着など着ていく男の愚かさを考えると、スーツをきちんと着こなしている男の格好よさを感じてならない。スーツを着こなせないということは、あらゆる意味で勉強が足りないということと同じである。(「ぼくは一年中、ほとんど同じような格好をしている」)
安西水丸さんは、本当にスーツが大好きだったみたいですね。
本書には「きちんとスーツを着て仕事をするのは気持ちのいいことだ」というエッセイも収録されていて、水丸さんのビジネス観というかスーツ観のようなものが、非常によく伝わってきます。
そんな水丸さんの好きだったスーツブランドが、あのブルックスブラザーズ。
宝島ブランドムック「ブルックスブラザーズ」では、水丸さんがニューヨークで仕事をしていたときに、初めてブルックスブラザーズと出会った話が紹介されています。
ただし、ビジネスを離れた部分でいうと「僕にとって洋服なんて、なんでもいいんだという考えがある」そうです。
もっとも、これは「自分がちゃあんとしてさえいれば、洋服なんてどんなモノでも似合うのだという考え」を持っている、水丸さん流の人生哲学のようなものでしょう。
「とにかく普通の格好がいちばんいいと常日頃思っています」という言葉は、自分に自信のある人でなければ書けない言葉なんだろうなあと思いました。
銀座という街は天井が高い。
銀座という街は天井が高い。これが僕の銀座の街に感じている印象だ。渋谷や新宿にある、あのおおいかぶさってくるようなものがない。海が近いからかもしれない。いつも風が吹き抜けている。(「銀座はごく自然にぼくの遊び場所になった」)
明治以降、多くの文化人に愛されてきた街、銀座。
安西水丸さんも、この銀座という街が大好きなのですが、そこには「ぼくは銀座という街を特別な街だと思っていない」という水丸さん流の愛し方があります。
「大学に行く時も、毎日通り抜けていたし、大学生になってはじめてアルバイトをしたデパートも銀座にある」といった感じで、水丸さんにとって「銀座はごく自然にぼくの遊び場所になった」ということのようです。
本書には比較的短い雑文が多く収録されているのですが、この「銀座はごく自然にぼくの遊び場所になった」というエッセイはページ数も多くて、水丸さんのイラストによる銀座の地図も挿入されているなど、かなり詳しい銀座案内となっています。
水丸さんお気に入りのお店が次から次へと紹介されているので、この本を片手に銀ブラするだけで、一日たっぷりと楽しめそうです。
もっとも、水丸情報は1980年代のものなので、時代の移り変わりを感じる銀座散策になるかもしれませんね。
村上春樹さんも大の猫好きで、やはり奇妙な猫を二匹飼っている。
怖かった。ぼくはつい恥しさも忘れて悲鳴のような声で村上さんを呼んでしまった。村上さんが出てきて、どうしたんですか、と言うのでこの猫がぼくにとびかかろうとしたんだと言ったところ、村上さんはなんと言ったと思います…「なんだそんなことですか。ぼくは今忙しいんだから、そんな熊に襲われたような声出さないでくださいよ」だって。何もわかっていないんだから困る。(「ぼくはペットが嫌いだ」)
安西水丸さんが村上春樹さんの家へ遊びに行った時に、猫に驚いて叫んでしまったエピソードは、村上春樹さんのエッセイにも登場します。
水丸さんの受け止め方によれば「彼の飼っている二匹のうち、一匹の方(あれはたしかシャムだ)がぼくを襲おうとした」「そいつは上体を低くかまえ、腰をあげ、ヒョウやトラが獲物をねらう時のような体勢をとった」そうなので、猫が苦手な人にとっては、確かに恐ろしい体験だったかもしれませんね。
それにしても、村上さんの「なんだそんなことですか。ぼくは今忙しいんだから、そんな熊に襲われたような声出さないでくださいよ」という反応は、あまりにも予定調和なので、思わず笑ってしまいました(笑)
「青山の青空」には、この他にもとりとめのない雑文がたくさん収録されています。
日曜日の午後に、頭の中を空っぽにして楽しみたいエッセイ集ですね。
https://syosaism.com/murakami-harukido/
読書感想こらむ
「青山の青空」は1989年(昭和64年)刊行なので、いわゆるバブル景気真っ盛りの時代に出版された本ということになります。
エッセイの随所には、1980年代後半のバブル時代らしいキーワードがポツポツと登場するので、そういう時代性を楽しむことも、こういった古いエッセイ集の味わい方の一つかもしれないと思いました。
「カーラジオから「スタンド・バイ・ミー」が流れた」なんかは、映画館で観た「スタンド・バイ・ミー」がとてもいい映画で思わず感動したなんて話が紹介されていたりします。
https://syosaism.com/standbyme/
「あとがき」の中で水丸さんは「ぼくは四十まではいちおう前向きに生きようと思っていた」と書いています。
40歳まではイラスト一本で勝負をしてきて、40歳を超えた頃から「雑誌やPR紙から短いエッセイのような仕事の依頼が多くなった」のだそうです。
いくつも著作を出すほどなので、文筆業も決して嫌いではなかったんでしょうね。
1980年代後半の空気に触れたいと考えている人にお勧めしたいなあと思いました。
まとめ
安西水丸さんの「青山の青空」はリラックスしたい時にお勧めのエッセイ集です。
雑誌やPR紙の囲みコラムみたいにとりとめのない雑文を、いろいろと楽しむことができます。
全体にバブル時代の空気が漂っているのも特徴。
著者紹介
安西水丸(イラストレーター)
1942年(昭和17年)、東京都生まれ。
大学卒業後は電通でアートディレクターとして勤務をしたこともある。
「青山の青空」刊行時は47歳だった。