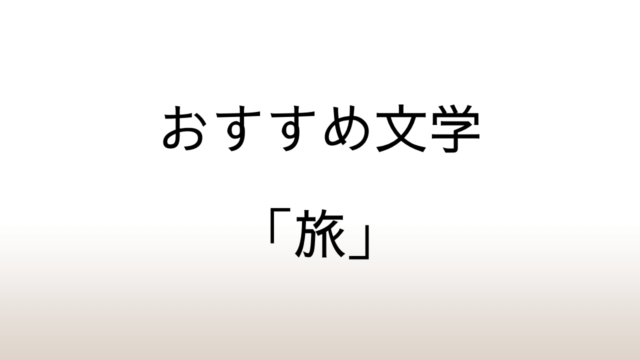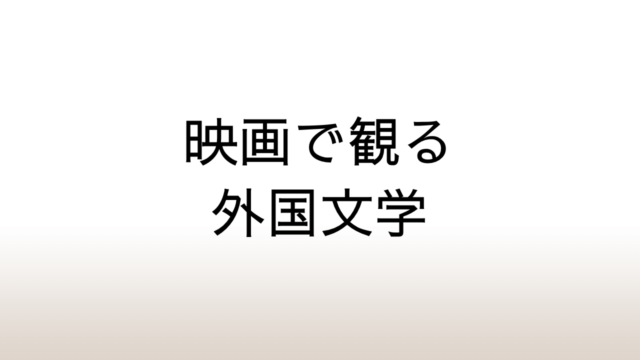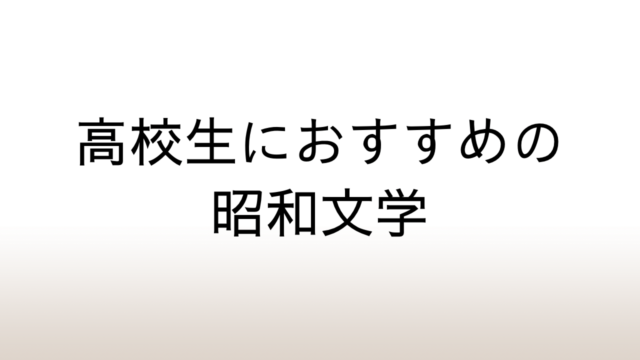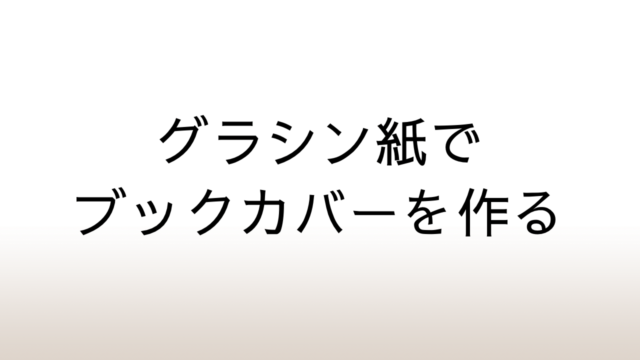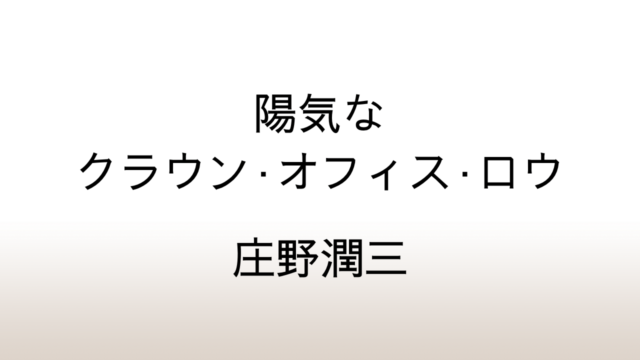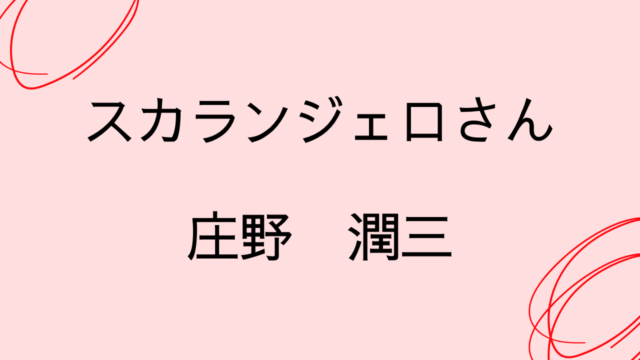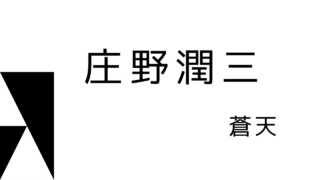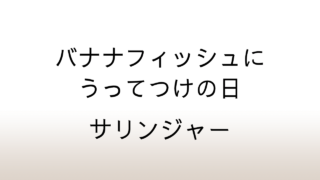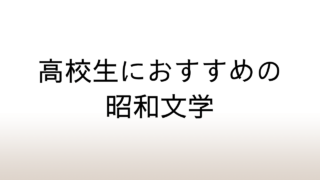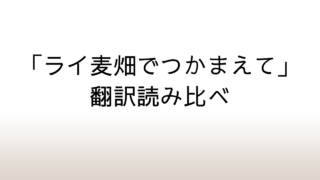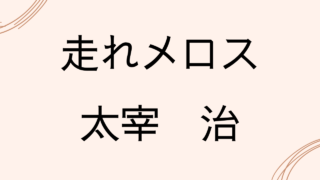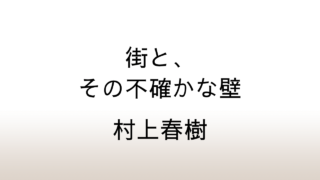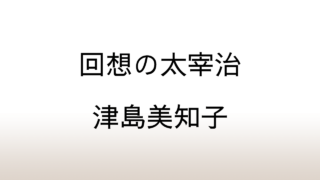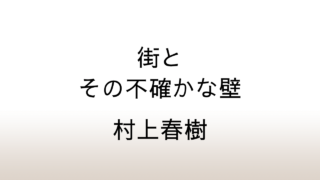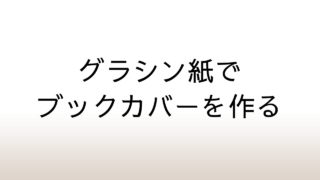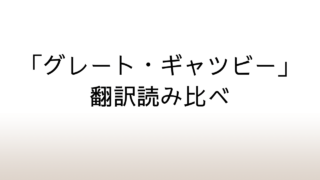庄野潤三の代表作「静物」が解釈の難しい作品であるということは、村上春樹「若い読者のための短編小説案内」でも詳しく(詳しすぎるくらいに)指摘されている。
「静物」の解釈の難しさについて、村上さんは「まるで雨降りの日にけぶった水平線をじっと遠くから見ているようなもの」と表現している。
小説的な説明を徹底的に排除した小説「静物」
「静物」の、このとらえどころのなさの最大の要因は、この作品が、小説的な説明を究極的なまでに(ともすれば必要以上に)削って構成されている、排除の文学によるものだからだ。
読者は、全体的な流れを確信することはもとより、一つ一つのフレーズの意味やアイテムの存在意義に至るまで、ほとんど理解することなく、この小説を読み終えるだろう。
この点について、村上さんは「広告手法でいえば「ティーザー」的に書かれています」と分析しているのだが、ティーザーみたいな小説なんかを読まされたって、読者には理解できるわけがない。
だから、一方では「書いていなくたって分かるはずだ」という論法が生まれる。
庄野潤三の作品世界では、奥さんが自殺未遂をしたということは、ひとつの文学的既成事実になっている。つまり彼の作品をずっと追って読んできた読者は、それを既に知っているわけです。だからいちいちそんなことを説明する必要はないんだ、と。つまりNHKの朝の連続テレビ小説を見ているような感覚ですね。(村上春樹「若い読者のための短編小説案内」)
しかし、村上さんは、こうした見方には否定的で、「説明が不十分であるのは、作者が意識的にそれを排除し、取り外しているからでしょう」と、自分の考えを整理している。
その理由は、これは文章を加えていった作品ではなく、文章を削って削って削り抜いた作品で、作者は推敲に推敲を重ねたはずであり、「たまたまそうなりました」というようなレベルのものでは到底あり得ないから。
この徹底的な排除の姿勢で書かれた「静物」には、排除の姿勢からしか生まれない、都会的な格好良さがあることは事実だ。
「静物」という題名について、村上さんは「still life」という英語を引用しながら、「正直に言って、僕はそういうスーパー・クールな文章の書き方が個人的には好きです」と綴っているくらいである。
崩壊しかけた家族の絆を再構築しようとしている
結局、作者・庄野さんは、この「静物」という作品で何を言いたかったのか。
作者はのちに、「『静物』を書いたあと、雑巾をしぼるようにして自分をしぼり出す小説はかなわない」というように述懐していますが、僕はむしろ「静物」にいたるまでの一連の作品を書くことこそが、「雑巾をしぼるよう」であったのではないかという風に考えています。
おそらくその従来のラインの上では、それ以上小説として書くべきことが、作者にはもはや見いだせなくなっていたのではないでしょうか。
(村上春樹「若い読者のための短編小説案内」)
「静物」を仕上げるまでに、庄野さんが相当の苦労を重ねたことは、よく伝えられているエピソードだが、村上さんは、「舞踏」のような初期の作品を引き合いに出しながら、過去の作品こそが雑巾をしぼるような作業の末に生まれたものではないかと指摘している。
そう考えると、庄野文学の中において、「静物」はひとつの締めくくりであり、初期庄野文学の総決算であると考えることができる。
それは、家庭内における父親としての、庄野さん自身の締めくくりであり、総決算でもある。
実は、「静物」では夫婦の会話がほとんどなく、子どもたちに向かって話しかけることで、夫婦の対話を間接的に成立させている。
父母と姉兄弟という五人家族は、微妙なバランスを崩さないように気を配りながら、家族的な平穏を維持しようとしていたのだろうか。
そう考えると、この小説は、崩壊しかけた家族の絆を再構築しようとしている経過を描いた作品であるととらえることが可能だ。
再構築された家族の絆は、やがて「夕べの雲」以降に続く一連の家族小説へと発展していく。
夫婦の危機を描いた初期作品と、五人家族の平穏を描いた中期作品とを繋ぐものとして、「静物」はやはり忘れることのできない作品なのかもしれない。
書名:若い読者のための短編小説案内
著者:村上春樹
発行:2004/10/10
出版社:文春文庫