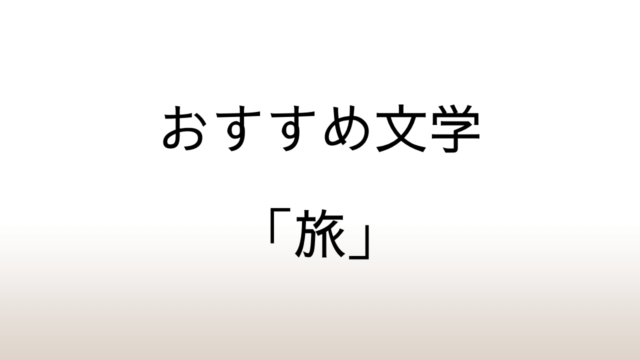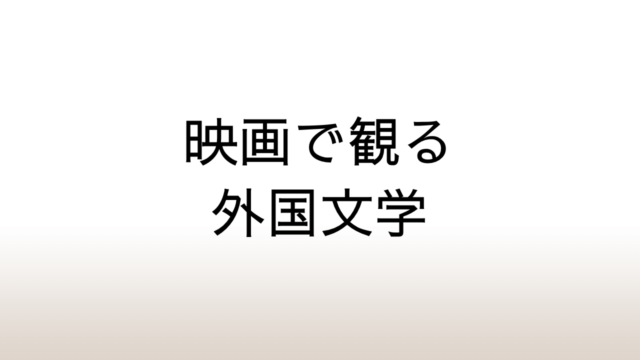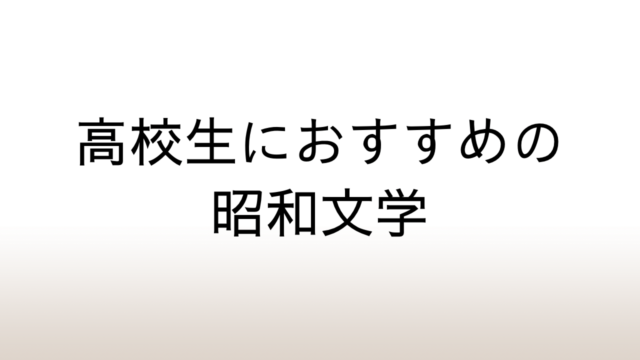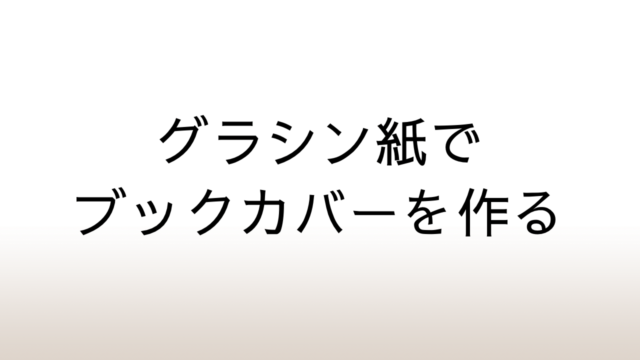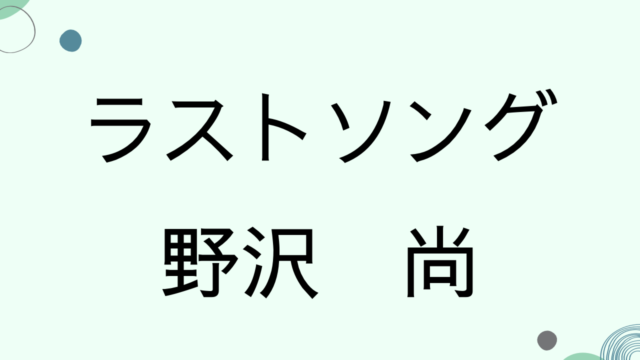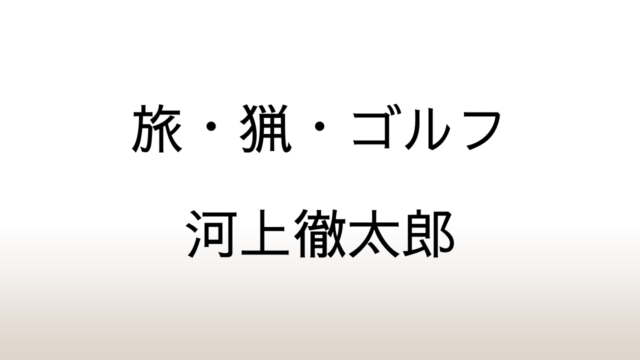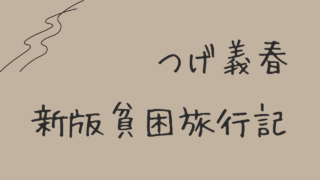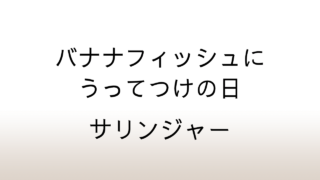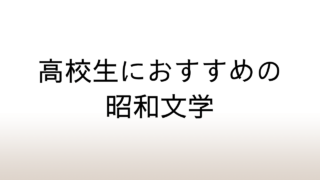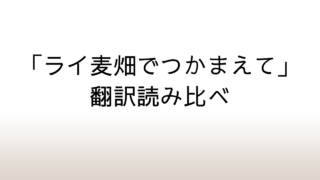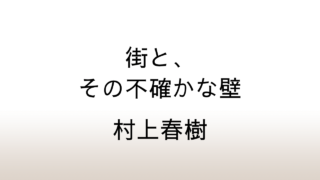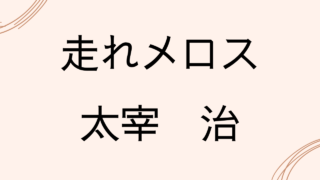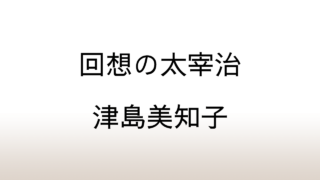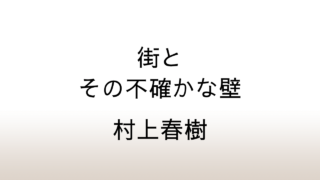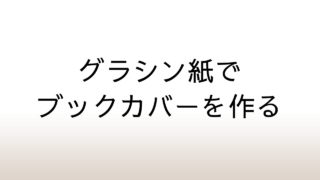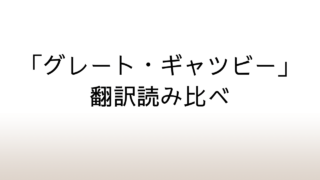(2024/04/19 15:39:25時点 Amazon調べ-詳細)
「雪女」は「文学界」(昭和51年1月号)に掲載された、和田芳恵の短編小説である。
主人公の仙一は、小樽中学2年生のときに脚気となり、両足を不自由にしてしまう。
学校を退学した仙一は、家業の荒物屋を手伝いながら、坊主山の麓にある円通寺の住職から習字を教わり、「書家の書いた字はきらいだ」「もの欲しそうな感じが、少しでも出たら、その字はいけないのさ」などと言うようになった。
同じころ、仙一は村の青年団の幹部として忙しく活動しながら、小学校の同級で、今は料理屋で働いている「さん子」と、親しく交際するようになるが、村の運動会で二人の噂は大いに広がり、間もなく、仙一は住職の斡旋で、小樽色内町の宮本印章店に住み込みで働くこととなる。
真面目に仕事と向き合っているうちに、いつしか仙一も印章を掘るようまでになり、店の夫婦は、仙一を後継ぎとしてもらいたいと思うようになっていた。
やがて、2年ぶりに故郷の国縫へ帰郷した仙一は、さん子に求婚し、二人で円通寺を訪れ、住職に結婚の許可を求めるのだが、そのとき、住職から、思いもよらない自身の出生の秘密を解き明かされることになった…
著者(和田芳江)の故郷である国縫(長万部町)と小樽を舞台とした、この短編小説は、不幸を背負いながらも誠実に人生と向き合い、前向きに人生を生き抜いていく仙一を主人公として描いた、爽やかな青春物語である。
思いやりに包まれたプロポーズの美しさ
さん子は仙一たちのところへ銚子を運んできたり、肴の誂えを聞きに来たりした。「丸大も酌婦がいたころはおもしろそうだったが、小娘が座敷へ出るようではね」酌婦というのは私娼のことで、北海道では後家、白首ともいった。(和田芳恵「雪女」)
仙一とさん子との交際は、決して濃密なものではなかったが、さん子には仙一の足の不自由なところを自然体で支えようとする優しさがあった。
互いに飾り気のない付き合いだったからこそ、2年ぶりに再会したときの求婚も「さん子は、私と結婚する気があるだろうか。私が眼をつぶっているうちに考えて、どっちか決めて、返事をしてくれないか」だった。
そのとき、「私は、こんなからだになってしまったし、ことわられても、仕方がないと思っているのさ」と付け加えたのは、やはり、仙一のさん子に対する思いやりだっただろう。
さん子は「仙一さんが、あたしのようなものでもいいなら…」と、仙一の求婚を即座に受け入れながら、「あたし、小樽へ行くことになるのね。いなか育ちだから、仙一さんが笑いものにされるかもしれませんね」とつぶやくところは、とても印象的な場面である。
互いに互いを思いやる美しさが、この物語を中心から支えているのだろう。
雪の上で交わされた愛の祝福
さん子は、ふと、思いついたように、雪のなかを歩きまわって、下駄へやわらかな雪をつけて、仙一と同じくらいの背になった。さん子は、小作りだが、肉づきがよかった。仙一の前にたったさん子は、目をつぶって、唇を突きだした。(和田芳恵「雪女」)
雪の中で口づけを交した二人が、そのまま雪の上に倒れて埋もれてしまうラストシーンは、北海道の冬の美しさを強く印象づける、素晴らしい名場面だ。
積もった雪の上に顔を押し付けたさん子の顔の跡が残り、さん子は「この雪の面てに、仙一さんの面てを重ねてごらんなさいよ」と仙一を誘う。
仙一は、雪の上に残ったさん子の顔の跡に自分の顔を押し付けながら、「さん子はまるで雪女のようだ」と思ったところで、物語は終わるのだが、雪の上で互いの顔の跡を重ね合うという演出は、さすがに北海道だという感じがする。
北海道の中でも札幌や小樽といった都市部ではなく、国縫という郡部の小さな町で生まれ育った二人にふさわしい、愛の祝福の風景と言うべきだろう。
そして、その愛の祝福は、人生と真摯に向き合い、日々を誠実に過ごしてきた二人だからこそ与えられるべき祝福であったということを忘れてはならない。
それは「歩いたところが道になる」と色紙に綴った著者自身の、紛れもない信念のようなものだったに違いない。
人生は決して裏切ったりしないのだと。
書名:おまんが紅・接木の台・雪女
著者:和田芳恵
発行:1994/3/10
出版社:講談社文芸文庫