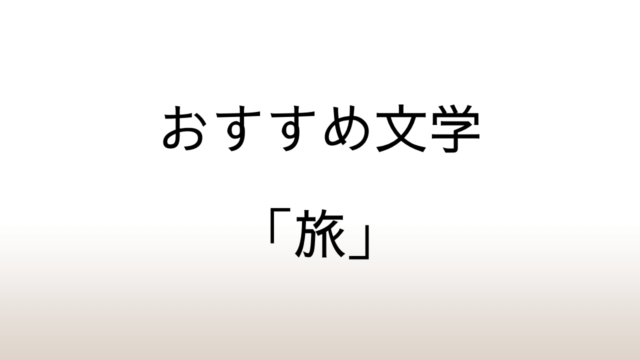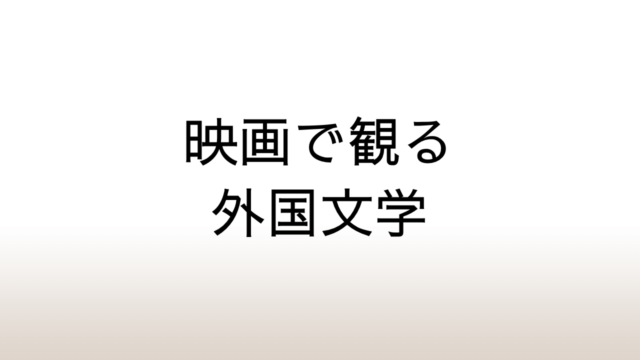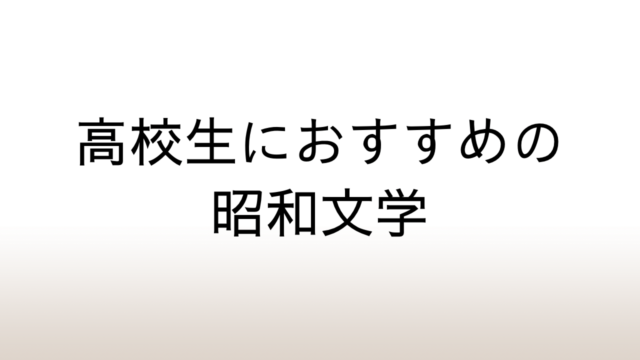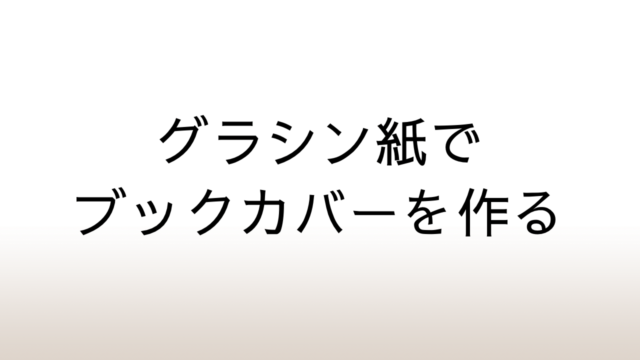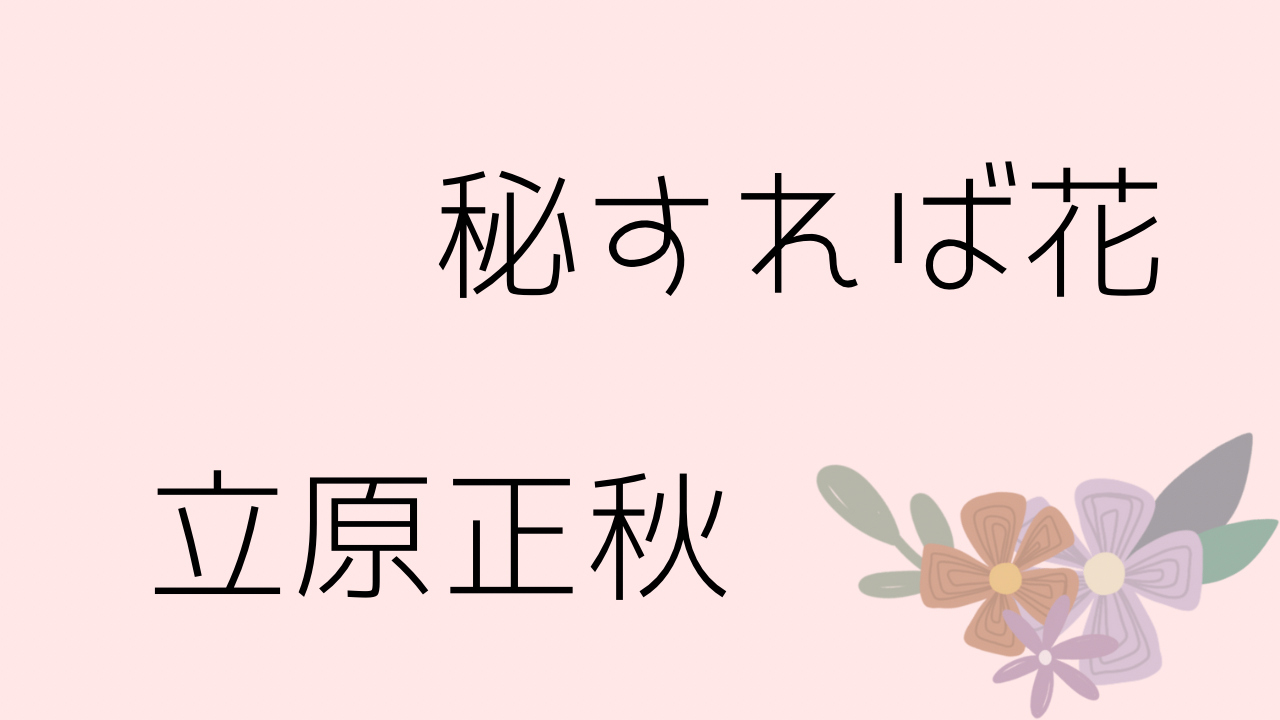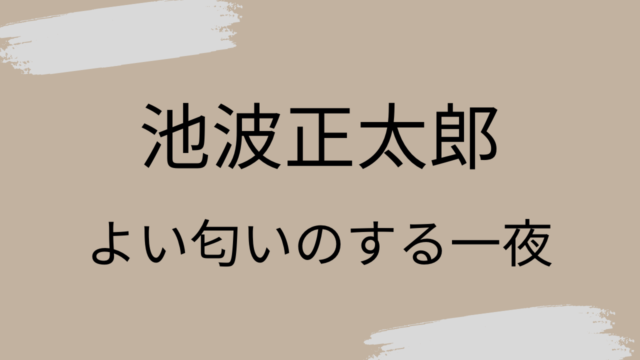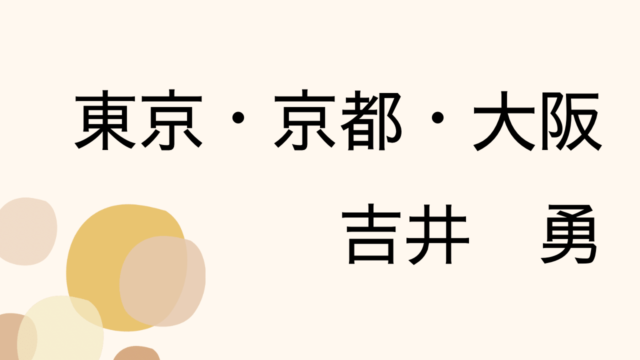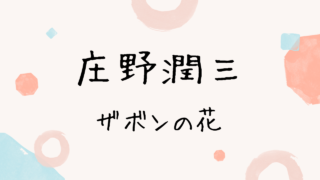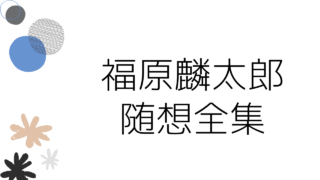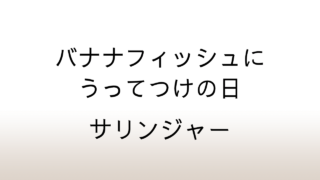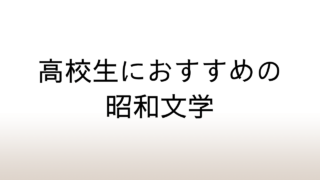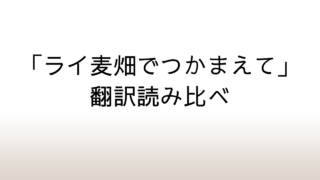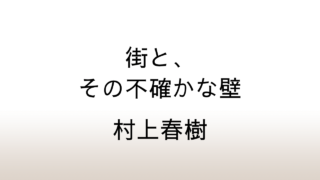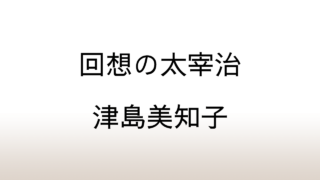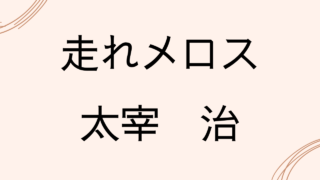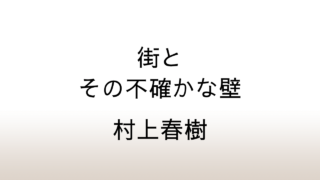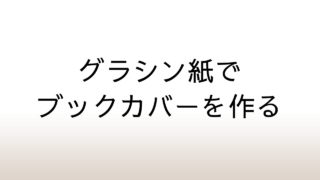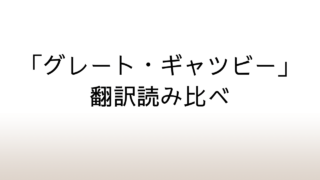立原正秋さんの随筆集「秘すれば花」を読みました。
自我を貫くためには軋轢をも恐れない、孤高の人間性に震えました。
書名:秘すれば花
著者:立原正秋
発行:1982/8/25
出版社:新潮文庫
作品紹介
「秘すれば花」は、立原正秋さんの第一エッセイ集です。
あとがきの中で、立原さんは「ここ五年ちょっとのあいだに、あちこちに書いた雑文がこんなにあったとは思わなかった」と書いています。
「昭和45年暮」とあるので、昭和40年から45年くらいまでの間に書かれた随筆をまとめたものと言っていいようです。
「本の題は私の心づもりでは<雑文集>であった」そうですが、「編集を担当してくれた大門武二氏から、<雑文集>では困る、と言われ、<秘すれば花>ではどうか、との提案があった」「もっと砕けたいい題はないものか、と考えたが、なかなか思いつかず、けっきょくこれにきまってしまった」そうです。
単行本は、昭和46年1月に新潮社から刊行されています。
あらすじ
「秘すれば花」は、新聞や文芸誌、女性誌、同人誌などに掲載された随筆やコラムを収録しています。
紅野敏郎さんの解説には「「雑文集」とはいいながらも、この本には、立原の文学的姿勢がなまなましいかたちで提出されており、立原文学のなりたち、その人、その魅力を随所に発見することができる」「このエッセイ集の読みどころは、立原自身が、なつかしくも、切なくも感じたであろう文学上の真の友人のワンスケッチ、あるいはその著書について語った部分であろう」とあります。
また、紅野さんは「この文庫本では、初版本の配列を入れかえ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅰ、Ⅱの順となっているが、私自身は初版本の配列のなかに、立原の第一エッセイ集の志の真の姿を見ることが出来ると思っている」「出来得べくば、初版の配列に従って読んで頂きたい」とも綴っています。
湘南鎌倉の四季折りおり、旅の風物や思い出、好きな酒と肴、自ら包丁の腕をふるった自慢の料理、他に音楽との出逢い、自作の背景、同人雑誌「犀」や「早稲田文学」の編集話、敬愛する作家や同世代の文学者の風貌姿勢等々、早世を惜しまれる著者が、日本の風土と伝統をいつくしみ、美しいものへの憧憬と、人の心のあわれを率直に語る。爽やかで気品にあふれる第一エッセイ集。(カバー文)
(目次)「Ⅰ」漁師町にて/住みにくい鎌倉の夏/早春/鎌倉薪能/暗い風景の金沢/夏と秋のあいだ/鉢植蜜柑/旅のこぼれ話/山桜のこと///「Ⅱ」二十年来の酒/新関脇の酒/酒中日記/長夜の酒/酒有別腸/正月三ケ日/ギネスと平和/魚と酒/天下一品の店/わたしの包丁書/小さな海/魚の街/あさめし/食道楽/鮟鱇とモーツァルト/蛙とすっぽんと海鼠///「Ⅲ」鎌倉の寺/思いがけない発見/匿名のはがき/面を藉りて舞う/講演について/非行について/蝮と朝食/素振り/表札泥棒/殴り逃げ/酒と剣の効用/旅先での本屋/ひとつの行為/借家を追われる/転居記/数学の思い出/モーツァルトとの出逢い/私のなかの言葉/元漁師と魚屋のおやじ 湘南日記①/衣替え 湘南日記②/春の漬け菜 湘南日記③/鰯 湘南日記④/男の着物 湘南日記⑤/来訪者 湘南日記⑥///「Ⅳ」《犀》創刊の辞/《犀》創刊雑録/《犀》編集後記/《犀》終刊の辞/『剣ヶ崎』について/ひとつの感想/純文学と大衆文学/私小説的発想を排す/不毛の世代/一小説家の感想/庭を眺めている日々/実作者の所感/《早稲田文学》編集長就任に際して/第七次《早稲田文学》復刊の辞/《早稲田文学》編集後記/編集室から去るにあたって/十四本の白髪/文学は変っているか/『花伝書』の教え/秘すれば花/わが愛する歌/『冬の旅』あれこれ/『冬の旅』を終えて/川端康成氏覚え書/ジュネとミラー/小川国夫との出逢い/懐かしい顔/大岡昇平氏について/田久保英夫氏の脱出/吉田知子さんのこと/『白痴』の美しさ/宗谷真爾著『なっこぶし』/寺田透著『現代日本のことばと詩』/平尾靖『少年非行』/李恢成著『またふたたびの道』/後藤明生著『私的生活』/能と新劇の交流を/中村光夫作『汽笛一声』/「Ⅴ」刃物/山川方夫の思い出/都会人の感覚/吉行さんの時計/高井有一の艶めいた声/にぎやかにしてさびしき男 野坂昭如/十八年ぶりの同窓会/会ってみたい人///あとがき/解説(紅野敏郎)
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
日々これ酒に明け酒に暮れる。
酒中日記を書きはじめる。文壇人とのつきあいがないのに、こんなものを書いてもしょうがないではないか、とことわったのに、つきあいがない日記を書けと編集者が言う。日々これ酒に明け酒に暮れる。酒を飲みながら書いているこの文章、すなわち酒中日記である。(「酒中日記」)
「小説現代」昭和42年8月号掲載。
文壇きっての酒豪として知られる立原さんには、酒について書いた多くの随筆があり、本書「秘すれば花」の大項目のひとつも、酒と美食について書かれた作品を集めたものになっています。
どのくらい強いかと言うと「私の酒はお茶と同じだから、日本酒に換算して四升から五升までなら、常と渝らない。五升を越したら少し酔ってくる(「二十年来の酒」)」というからすごい。
「長の酒」という作品では、高井有一さんを自宅に泊めて二人で飲んだとき、高井さんが途中で眠ってしまったので、仕方なく酒を飲みつつ原稿を書きながら朝を迎え、高井さんを送り出した後は、一人でゆっくりと酒を飲んだというエピソードが紹介されています。
しかも、ひと眠りした後に、再び目覚めの酒と称して飲んでいるのですから「とにかく私の酒はこんな四六時中酒びたりのことが多い」というのももっともです。
「酒を飲んでからむ人がいる。私はこんな男が嫌いである」「私は酒の上で女を口説くのも嫌いだ。好きなら好きと素面ではっきり言えばよい」(「二十年来の酒」)など、立原さんは乱れる酒を嫌いました。
「酒の上での失敗はひとつもない。失敗した人は、たぶん酒にのまれてしまったのだろう」という一文には、お酒が好きな立原さんの、お酒に対する真摯な姿勢が表れているかのようです。
死後五十年ほどたってから、ひとつ作品がのこれば幸いだ、と私は思っている。
私は、ここに越してきたら、なるべき文壇づきあいをしないようにしたい、と決めていた。これからは東京にもあまり出ないようにしたいときめている。今月はあの作品が良かった悪かった、だれがどうした、というような文壇独特のサロンとはもう縁を切りたい。そして、死後五十年ほどたってから、ひとつ作品がのこれば幸いだ、と私は思っている。(「転居記」)
「読売新聞」昭和45年8月3日掲載。
本書「秘すれば花」には、立原さんの文学仲間が多く登場しますが、同じくらいに、当時の文壇に対する、あまり友好的ではない姿勢を示す文章もたびたび登場します。
「ある作家と会ったとき、新人がでればそれだけ俺達の原稿が売れないことになるから俺は決して新人の原稿を推さないよ、と酒席で言われた(《犀》終刊の辞)」などの経験が、立原さんを文壇から少しずつ遠くしていったのかもしれません。
私達の世代は、不毛の世代とひそかによばれているらしい。
第三の新人達の受賞作と石原、大江氏の受賞作のあいだに、私達世代の作品をおいてみると、私達の生きる場所がないということがはっきりするだろう。私達には『太陽の季節』や『飼育』は書けない。といって『驟雨』も書けない。しかしどちらも理解はできる。理解できるがどちらも書けない、という事実のために、私達の世代は宙ぶらりんの状態にあるといってよい。(「不毛の世代」)
「新潮」昭和42年6月号掲載。
自分たちの世代が文壇において「不毛の世代」と呼ばれることに、立原さんは割り切れぬ思いを抱いていたようです。
いわゆる「第三の新人」と呼ばれた世代(吉行淳之介、安岡章太郎、小島信夫、庄野潤三など)と、石原慎太郎や大江健三郎らの世代の間に挟まれて、自分たちの世代があると、立原さんは言います。
「終戦とともに一応自分のなかで戦争を消化できた」第三の新人と、戦後に青春を享受した石原慎太郎世代とも違い、「いずれも青春のいちばん大切な季節を青春を知らずに過してきた」世代、それが立原さんたち、いわゆる「不毛の世代」でした。
立原さんたちの世代は「二つの世代にはさまれ、殻を閉じることで自分の活路を見出しているとしか思えない情態」であり、「得体の知れない無力感のうちに自ずと築きあげた世界が、他人に迷惑をかけず自分も表には出ない小さな殻であった」と、立原さんは考えていたのです。
そのひとつの象徴が突然の交通事故で亡くなった山川正夫さんで、立原さんは「山川氏が亡くなったとき、私は、自分の軀の一部が崩れ去ったような感じを受けた」「山川氏の死は、私達世代のかなしみであると言ってもよい」「山川氏はこの不毛の世代から脱けでようとして脱けでられなかった」と綴っています。
この「不毛の世代」に関する一連の随筆は、本書「秘すれば花」の中で、とりわけ興味深く読むことができました。
ちなみに、立原さんが「不毛の世代」と称している作家には、山川方夫、田久保英夫、阿部昭、宮原昭夫、林峻一郎、高井有一、後藤明生などがいたようです。
読書感想こらむ
久しぶりに「本の壺」で抜きどころの多い随筆集でした。
僕はいつも本を読みながら、琴線に触れた部分に付箋紙を貼り付けていくのですが、本書「秘すれば花」は、読み終わった後に付箋だらけになっていたほどです(ほとんど付箋がつかない本も多い)。
「不毛の世代」を始めとして、ついつい文壇に関する部分にばかり注目してしまいがちですが、何気ない日常の一こまをスケッチしたような随筆にも、良いものが多かったです。
「地方を歩いていていちばん心惹かれるのは民家である。そしてそこに息づいている主婦達の生活である。さっぱりした木綿の着物に駒下駄などをはいている女に出あうと、それだけで心が和んでくる。木綿の着物と駒下駄は、その女の約やかな日常を想像させてくれる。木綿の肌ざわり、木綿のあたたかさ、木綿の光沢、そんな味を、戦後の日本人は忘れてしまっている(「旅のこぼれ話」)」とか、「漁師達の貧しい暮しには、胸にしみる生活の匂いがあり、現実感があった。漁から戻った夫と睦みあっていたあの若い女房にも、そんな生活の匂いがあった。(略)私は、毎日、海を眺め、漁師達の生活の匂いをかぎ、ときには釣糸をたれながら、作家には書くことだけが残されている。そんなことを思っている(「漁師町にて」)」などの文章も、ぜひ書き留めておきたいと思います。
まとめ
「秘すれば花」は、立原正秋さんの最初の随筆集。
昭和40年前後の文壇の様子や、酒と美食、鎌倉の四季など、読み応えのある随筆がたっぷり。
秋の夜長に日本酒を飲みながら読みたい。
著者紹介
立原正秋(小説家)
1926年(大正15年)、朝鮮生まれ。
1966年(昭和41年)、「白い罌粟」で第55回直木賞を受賞。
「秘すれば花」刊行時は44歳だった。