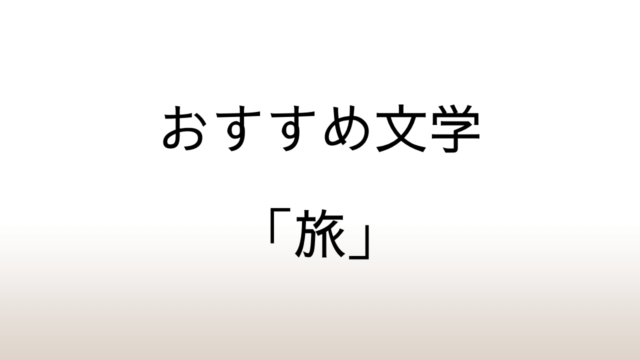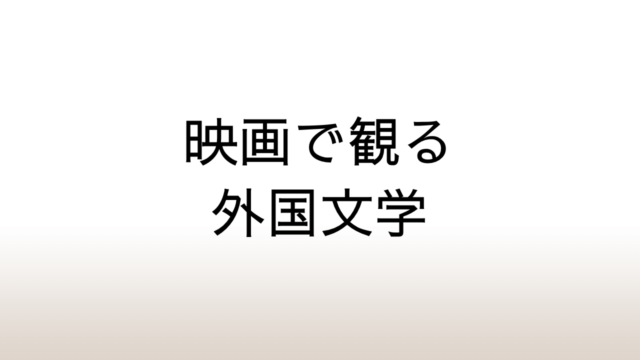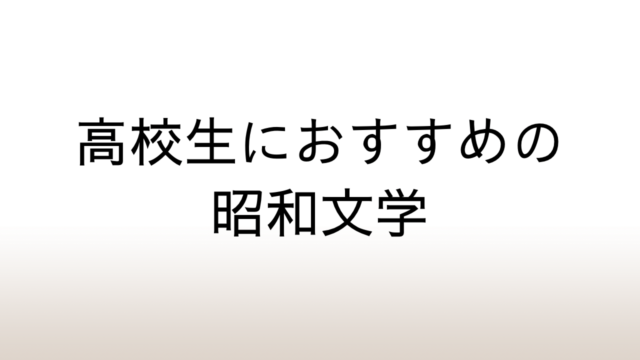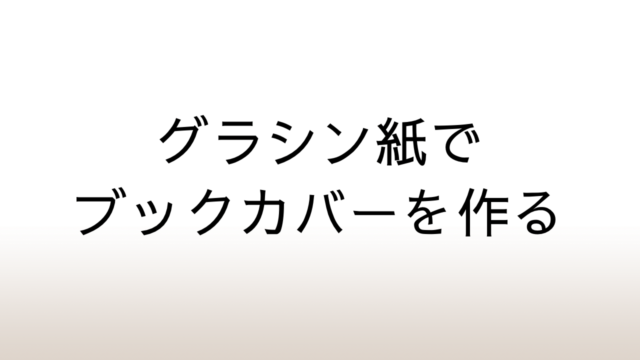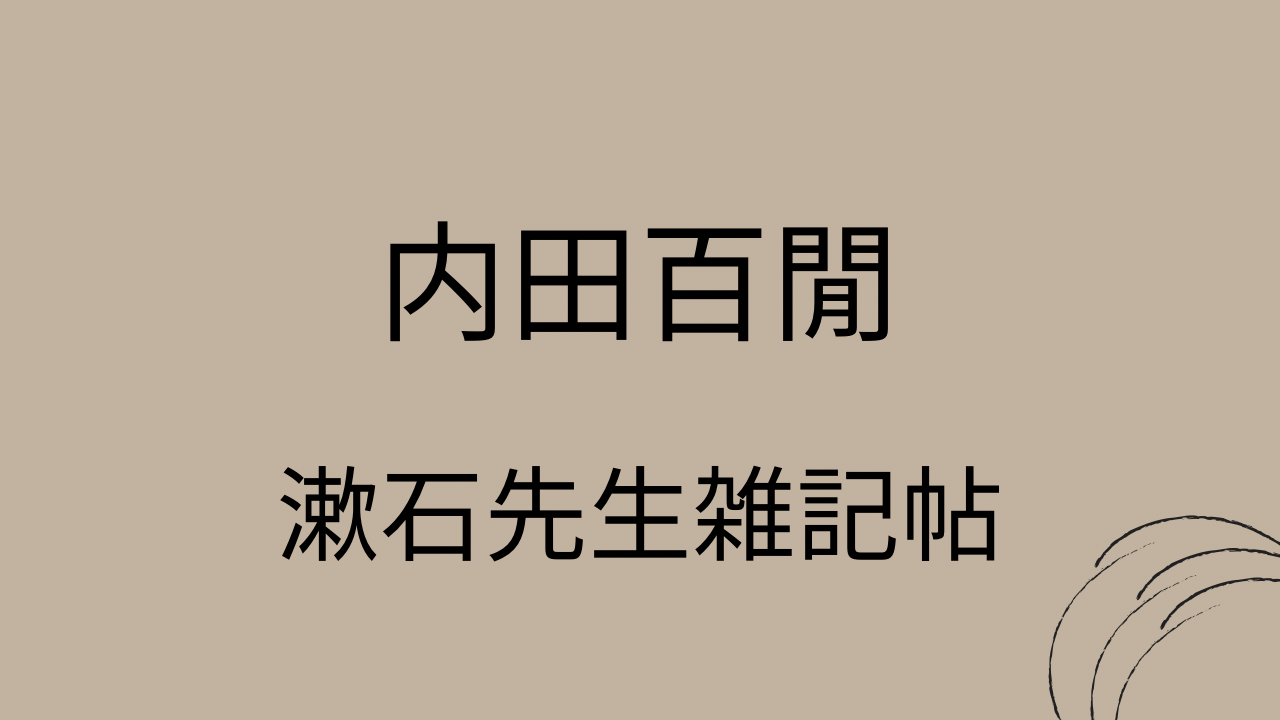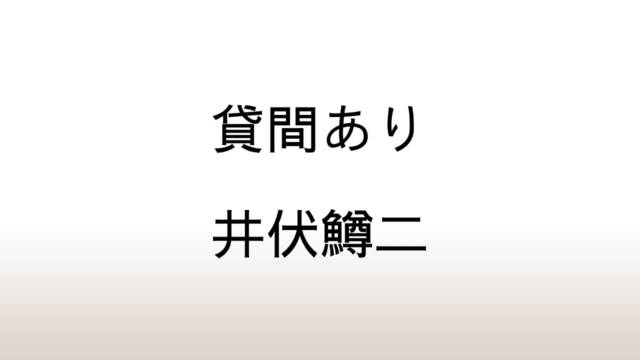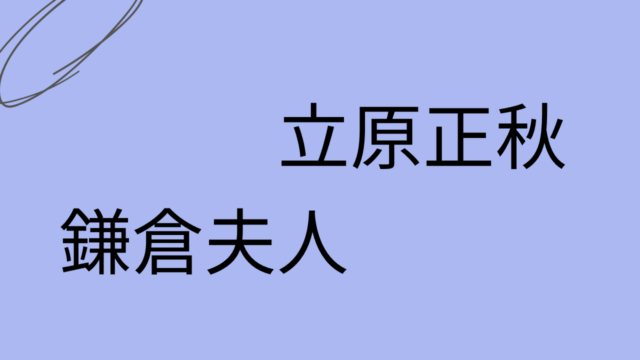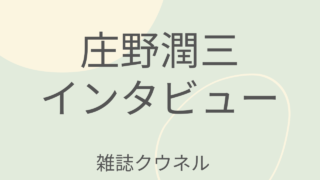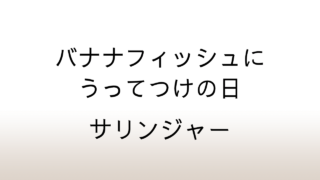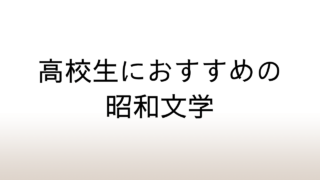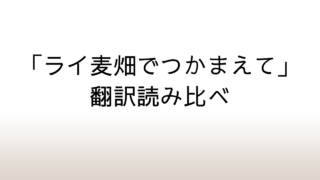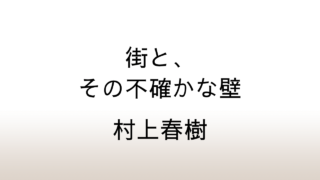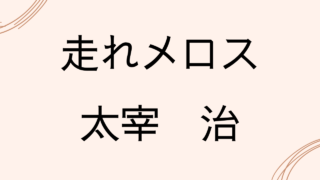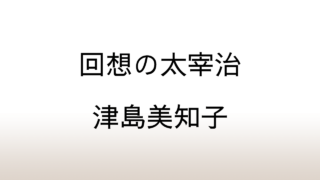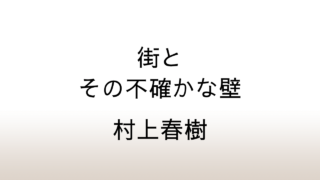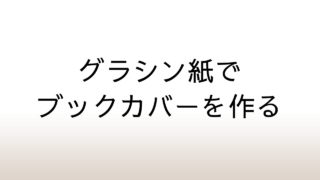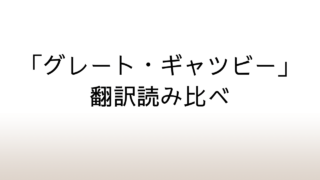内田百閒の随筆「漱石先生雑記帖」を読みました。
何かとエピソードの多い、文豪の夏目漱石ですが、弟子の目から見た日常の中の漱石が丁寧に描写されています。
夏目漱石の本をもっと読みたくなりそうです。
書名:漱石先生雑記帖
著者:内田百閒
発行:1985/12/25
出版社;河出文庫
作品紹介
「漱石先生雑記帖」は、内田百閒が書いた随筆集です。
河出文庫「今月の新刊」の帯には「百閒全エッセイ中の金字塔」「深い哀惜にユーモアをこめ、生涯を通して語り伝えた人間漱石の追憶と師弟交流の記」とあります。
また、平山三郎の「編纂者のあとがき」では「本誌は、内田百閒が、師・漱石について語り、書いた文章を蒐めて、だいたい執筆した年代順に編纂した」と書かれています。
なれそめ
夏目漱石が書いた夏の小説「それから」を読み終えた後も、読後の余韻がなかなか消えないままで、無性に夏目漱石に関するものが読みたい気持ちが続いていたので、内田百閒が書いた夏目漱石に関する随筆集を読むことにしました。
数多くの随筆を遺した内田百閒ですが、本書は師である夏目漱石について書いたものだけを収録した書籍で、端から端まで夏目漱石に関するエピソードで埋め尽くされています。
良い文学作品に出会ったとき、その作者について深く知りたいと思う心は、極めて自然のものであり、特に夏目漱石のような大文豪ともなると、知っているようで知らない常識も、きっと多いのではないでしょうか。
本書は「夏目漱石についてもっと知りたい」と思う人が最初に手にする、そんな随筆集みたいです。
あらすじ
毎週木曜日、漱石の書斎に門下生が集う木曜会―錚々たる学者文人が揃う仲で最も若いメムバーとして漱石に愛された百閒は、生涯を通して師への敬愛を語り続けた。
愛読者となった中学時代の挿話から、文通、初めての出会い、門下生としての交流、漱石の臨終まで、深い哀惜にユーモアをこめて綴られた漱石追憶の本書は、百閒の代表的エッセイであり、また人間漱石を浮彫りにする名著である。
(背表紙の紹介文より)
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、本の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
丸善からくれたのが漱石先生の万年筆、オノトであった
丸善に「学燈」という雑誌があって、内田魯庵さんが丸善にいて、漱石先生に万年筆の宣伝文を書いてくれといったので、先生が書かれたらしい。そのお礼に丸善からくれたのがつまり右に云った漱石先生の万年筆である。オノトであった。(「インキ・ペン・原稿用紙」)
内田百閒は「先生が亡くなられてから形見として貰った」万年筆をとても大切にしていたらしく、このオノトの万年筆についても、いろいろな場面で紹介しています。
夏目漱石は丸善が献上したオノトの万年筆を愛用し、「たしか『彼岸過迄』から『明暗』の前まで使われたと思う」のですが、「亡くなられる少し前、ペンの先が折れてしまった。そこでその次は先生が自分で買われて、前のはそれきりになっていたのを僕が貰ったのだ」と、内田百閒は述懐しています。
百閒は、その後「僕に取っては非常に大事な万年筆だから丸善へやって直させた処が、ペン先を取替えて使えるようにしてくれた。直し賃が五円だった」と、万年筆を修理しますが、友人から「壊れたペン先の方が漱石先生の記念ではないか」と指摘され、交換した壊れたペン先を返すよう、丸善に交渉しました。
「丸善へ行って、折れたペンを返してくれと云ったらいい工合に見つかって返してくれた。その代わりまた五円とられた」と綴っています。
ちなみに、漱石は「セピヤ色のインキを使った」そうで、弟子の小宮山豊隆も同じ「セピヤ色のインキ」を使っていたそうです(「前掛けと漱石先生」)。
漱石先生は下戸で、盃を舐めただけでも真赤になった
漱石先生は下戸であって、盃を舐めただけでも真赤になった様である。(「漱石断片」)
夏目漱石の小説では、主人公がお酒を飲む場面がたびたび登場しますが、作者の漱石はまったくの下戸で、一滴のアルコールも受け付けない体質だったようです。
ある夏の午後、来客に冷たいビールを振る舞っているとき、ふと気が付くと「漱石先生が真赤な熱そうな顔をして」いました。
どうやら「どうかしたはずみでちょっと一杯飲んでみたのであろう」と百閒は推察していますが、「『吾輩ハ猫デアル』の中の苦沙弥先生が味醂の盗み飲みをした時の顔はその様であったろうと思われた」「その顔を思い出すと少々可笑しくもある」と、百閒は懐かしく回想しています。
文豪と言えば酒飲みというイメージが強いですが、日本を代表する大文豪がお酒を飲めなかったなんて、ちょっと意外で楽しいエピソードだと思いました。
このときの話は「『つはぶきの花』より」の中の「残り鬼」という随筆でも紹介されています。
ちなみに、漱石を慕う文学者が集う「漱石山房の木曜日の晩」に「紅茶を出されたこと」があったそうですが、紅茶の味の味の分からぬ百閒は、漱石から「どうだ?」と訊かれて、曖昧な返事をしたと言います(「紅茶」)。
仲間たちはみな「紅茶の風味を賞嘆した後であった」ので、「こういう先生にかかっては、このどこやら産の紅茶も台無しだねえ」と言われて、百閒先生は「大いに面目を潰した」のだとか。
お酒が大好きな百閒ですが、紅茶の味にまでは知識が及ばなかったようですね。
夏目漱石の蓄音機はビクター9号だった
その漱石先生が蓄音器を買ったのは、どう云うものを聴く為であったか、あるいはお子さん達のために買われたのか、それは知らないが、先生の名声大いに揚がり、身辺に余裕が出来てきたから求められた物であると云う事は、先生の生前に聞いた事がある様な気がする。(「漱石先生蓄音器」)
漱石の死後、内田百閒に譲られたこの蓄音機は「ヴィクターの九号であって、勿論古い型であるけれども、古い為に非常にいい機械である様に思われる」「私の家で聴いた客は皆口を揃えて素敵な機械だと褒めるのである」と紹介されています。
もっとも、漱石を慕う文学仲間の集まりで、漱石が音楽に関する話をすることはほとんどなく、「小宮豊隆氏の『夏目漱石』を読んでいると、随所に絵に関する話はあるが、音楽の事はちっとも出て来ない」と指摘している場面も。
「上野音楽学校の秋季演奏会を聴きに行ったら、漱石先生も来ていて、帰りに一緒になったことがある」「当日のヴァイオリン・コンチェルトが面白かったように思ったので、私からその事を云うと、先生は面白いと思うけれど結局器楽では物足りない。器楽の妙味は人の声に及ばないと言われたことを覚えている」という回想は、漱石の音楽観を端的に表現しているものかもしれないなと思いました。
文学を離れたところで、こうして夏目漱石という人物に関するエピソードを読むと、文学作品に対する読み方も、もっと深いものになるのかもしれませんね。
読書感想こらむ
創元社「夏目漱石作品集」の推薦文の中で、内田百閒は「夏目漱石は日本人の先生であり、その作品は日本人の教科書である」「若い人人が成長して本を読む様になれば必ず夏目漱石を読み、漱石の作品は若い人人に読まれる為に年々新しく若返っている」と書いています。
「『夏目漱石作品集』は古典ではない」という百閒の言葉を読みながら、僕は「なるほど」と思いました。
どうして夏目漱石が古くないのか、時代を超えて普遍性があると感じられるのか。
漱石の作品が古くないのではなく、いつの時代も若い人々に読まれてきたからこそ、漱石の作品も時代とともに新しく若返ってきたということなのでしょう。
「我我が自然や人生や自分の事に就いて感じたり、考えたり、迷ったりする時、自分の内にいる夏目漱石が共に迷ったり考えたり感じたりする」だとか「夏目漱石という偉大な作家がその作品を読んだ者の中に溶け込むのである」などという百閒先生の端的な推薦文も、非常に的を得ているものだと思います。
「夏目漱石は我の今日に生存する」「未だ読まない人人に必ず読む事を薦める」。
ここまで弟子に愛された夏目漱石という作家は、やはり素晴らしいなあと思わざるを得ないし、ここまで師を愛した内田百閒だからこそ、こんな素晴らしい随筆を残すことができたんでしょうね。
夏目漱石の小説を読んで満足した後に、ぜひとも読んでいただきたい随筆集です。
まとめ
「漱石先生雑記帖」は、内田百閒が夏目漱石について書いた散文だけを収録した随筆集です。
文学評論ではなくて、夏目漱石という一人の人間に関する回想記で、夏目漱石の人となりを知るためのエピソードがたくさん紹介されています。
漱石が愛用した文房具や好きだった紅茶の話など、文士マニアが喜びそうな話も満載。
著者紹介
内田百閒(小説家)
1889年(明治22年)、岡山市生まれ。
東京大学の学生時代から漱石門下生となる。
1971年(昭和46年)、81歳で亡くなった。