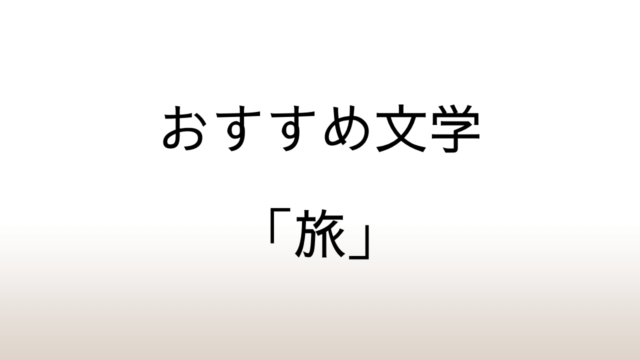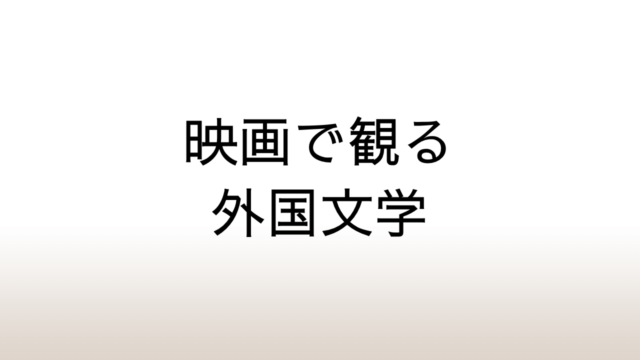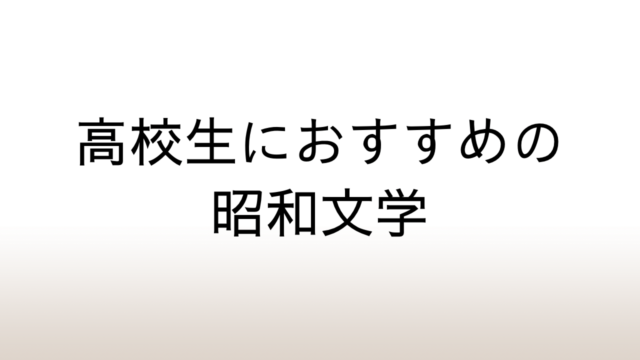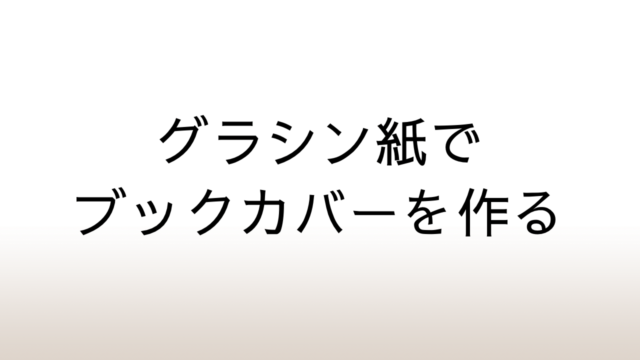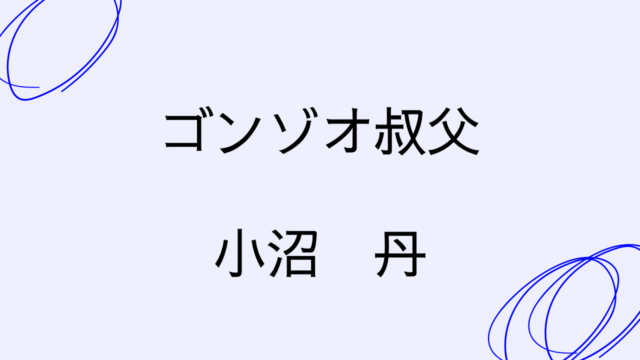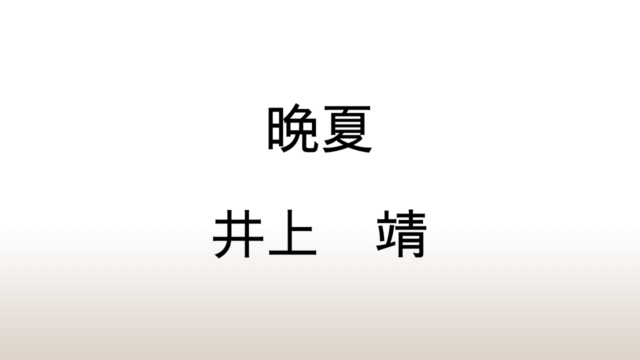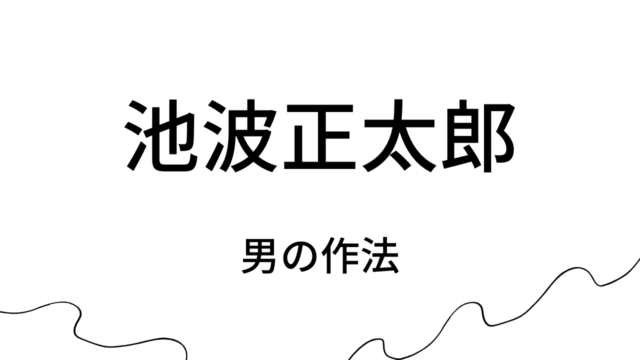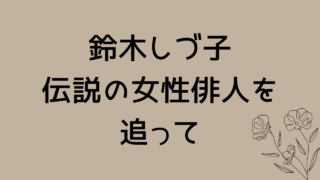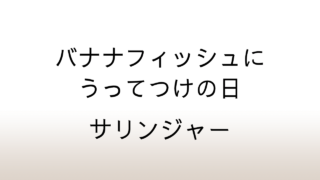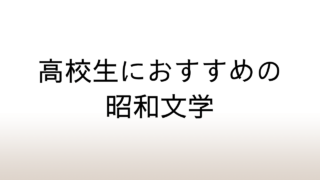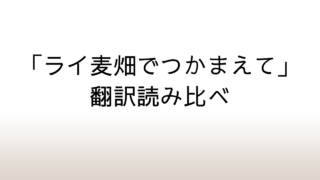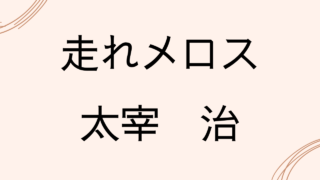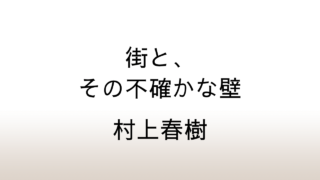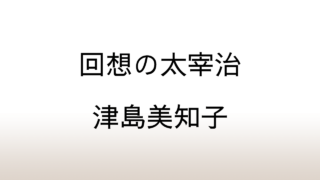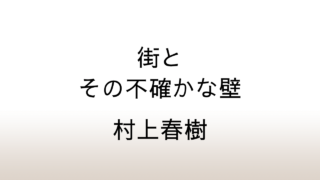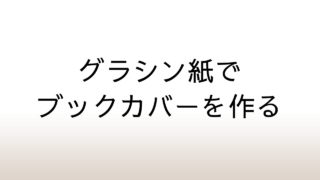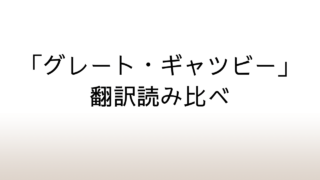書評というよりも、書評をきっかけとして自分を語る。
小川洋子の「博士の本棚」は、そんなエッセイ集だ。
全体は「図書室の本棚」「博士の本棚」「ちょっと散歩へ」「書斎の本棚」の四章で構成されていて、その中でもっともボリュームの少ない「博士の本棚」が本書のタイトルとなっている。
しかし、小川洋子という一人の女性を最も身近に感じることができるのは、古い小学校の図書室で読んだ本が次々と登場する「図書室の本棚」だろう。
「どのお話が一番好きか、と考えるのは、たいして意味のないことかもしれないが、何か一つ買って帰ろうと決心して骨董屋さんをのぞくのと同じくらい、楽しいことではある」と綴る彼女は、少年少女向けの外国文学について熱く語る。
彼女は、インタビューで子ども時代の読書について聞かれるたびに、図書室で一緒にコッペパンを食べた先生のことを懐かしく思い出すという。
「そこに本があるならば、私の出番などありません。子供たちは自分一人で、自分のための本をちゃんと選べます」とでもいうかのように、黙ってカウンターの向こう側に座っていた先生の姿を、コッペパンの焼ける匂いとともによみがえらせながら。
やがて、回転本棚に並んだ少年少女向けのシリーズに夢中になった小学生の女の子は、クラフト・エヴィング商會に憧れる大人の女性になった。
粗筋を説明し始めると途端につまらなくなる小説は、いい小説だ
『中国行きのスロウ・ボート』は、もしかしたら自分にもいい小説が書けるんじゃないだろうか、という錯覚を呼び起こした。錯覚と希望を混同するくらい愚かにならなければ、誰も小説など書けないだろう。デビュー作が文芸誌に載るまで、そこから三年かかった。そして私は今でも書き続けている。あの時呼び起こされた錯覚を、ずっと変わらず抱き続けている。(「死の気配に世界の深み知る」)
本エッセイ集には、たくさんの文学作品が登場するが、村上春樹の「中国行きのスロウ・ボート」は、計3篇のエッセイに登場しているほど、著者お気に入りの短編集であり、中でも「午後の最後の芝生」という作品を、小川洋子はこよなく愛している。
「処女作にはすべてが含まれる」とはよく言われるところだが、村上春樹最初の短編集である「午後の最後の芝生」には、現在にまで至る村上春樹のあらゆる要素が含まれていると、彼女は指摘している。
「粗筋を説明し始めると途端につまらなくなる小説は、いい小説だ」と断言する彼女の言葉に従うと、大学生の男の子がアルバイトで芝を刈るだけの短い物語である「午後の最後の芝生」は、間違いなく良い小説の部類に入るものだろう。
そこには一切の啓示も教訓もなく、なにものをも象徴しているわけではないのに、彼女はこの作品によって小説家への道を導かれたらしい。
やがて彼女は、村上春樹のデビュー作「風の歌を聴け」の舞台となった海辺の街に住み、「村上作品を読む時にいつも感じる、じめじめとしていない風の感触や、どこからともなく流れてくる海の匂い」を実感できるようになった。
「中国行きのスロウ・ボート」は、「死の床に就いた時、枕元に置く七冊」にも選ばれている。
平凡な日常生活の中で見つける温かな暮らし
作家、庄野潤三さんが、子供たちが巣立ったあとの平凡だが心穏やかな夫婦の暮らしを、シリーズで書きはじめられてから、もうどれくらいたつだろうか。(略)『貝がらと海の音』『ピアノの音』『せきれい』『庭のつるばら』…等々の作品群を読みついでいるうち、自分が庄野家の遠い親せきになったような気さえしてくる。(「なぜか出せない親への手紙」)
僕が、小川洋子の「博士の本棚」を買ってきた理由は、庄野潤三に関する短いエッセイが収録されていたからである(見開きでわずか2ページに満たない)。
「庄野潤三さん」の前に、わざわざ「作家」と職業を前置きしているところに、庄野潤三という小説家の持つ一般社会の中での立ち位置が理解できるような気がして、強く共感できるものを感じた。
何かの雑誌か新聞かで掲載されたのだろう、この短いエッセイは、庄野文学についての書評というよりは、庄野さんの小説では頻繁に登場する「長女からのお礼状」を持ち出して、「当たり前のようでも、実の両親に礼状を出すというのは、なかなかできそうでできないものだと思う」などと、親子の関係のあり方について、ふんわりと考える読み物となっている。
著者は、子を持つ一人の親として、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」の作品と向き合い、そこで描かれている平凡な暮らしの中の家庭生活に、幸せな親子の姿を見つけ出していたのかもしれない。
振り返ると本書は、古い小学校の図書室で「小公女」や「秘密の花園」に胸ときめかせていた文学少女が綴る、読書感想文のようなものであった。
もしかすると、芥川賞を受賞して長い年月が経つ今も彼女は、あの頃の文学少女のままなのかもしれない。
書名:博士の本棚
著者:小川洋子
発行:2010/1/1
出版社:新潮文庫