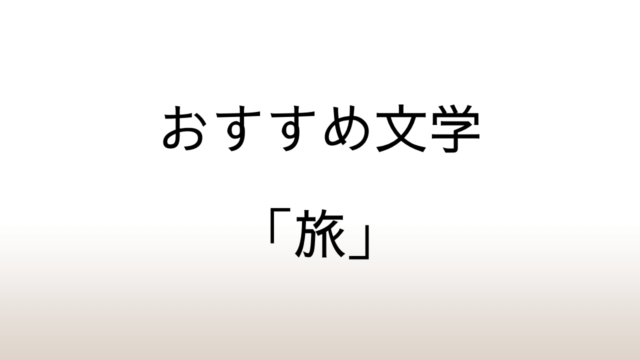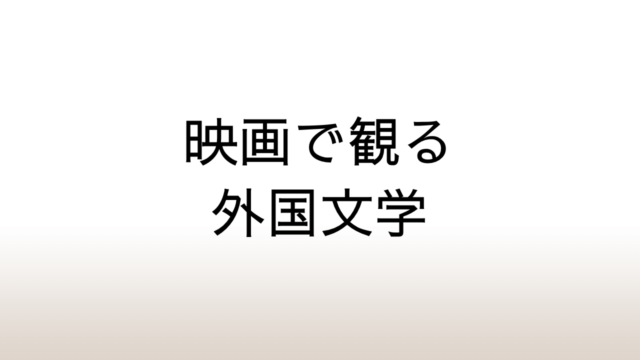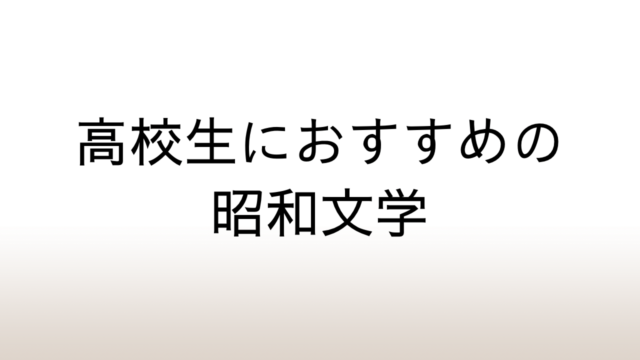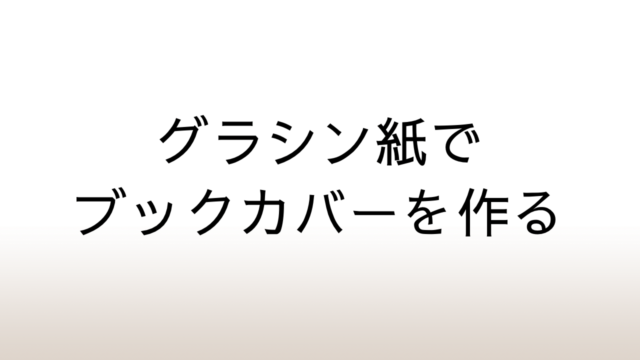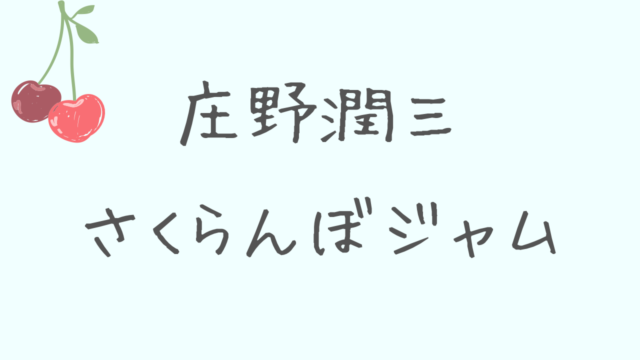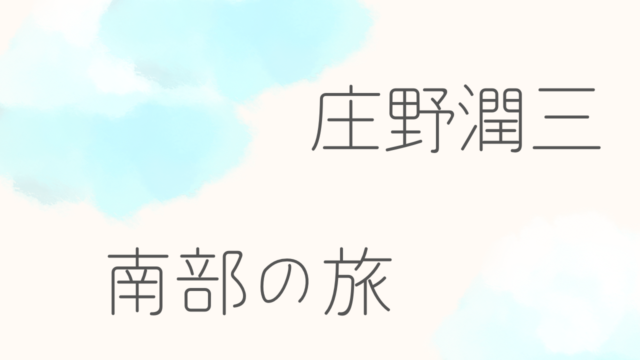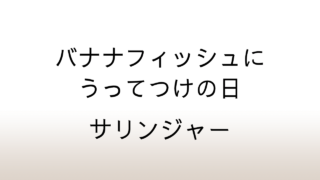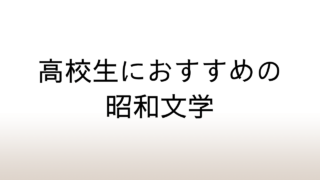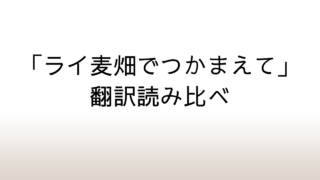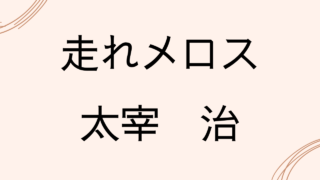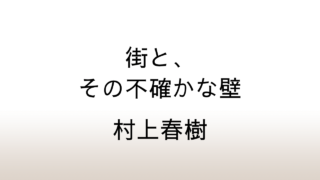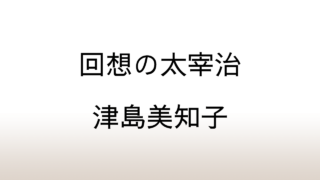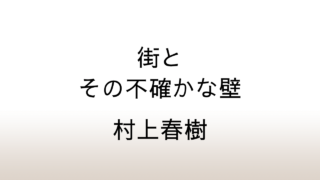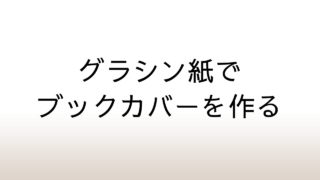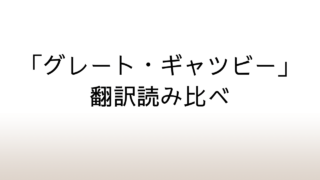庄野潤三『野鴨』の<十三>から<十五>まで。
全十回の連載で、三十章まである小説だから、連載の五回目、ちょうど前半の半分が終わることになる。
ひとつひとつの章が独立しているところが読みやすさのポイントだろう。
「そうか。要するに、ロング・ロング・アゴーだ。あれを吹いてくれ」
『野鴨』の<十三>は、雉鳩の話から始まる。
この雉鳩が「牛乳ちょうだい」と鳴いているように聞こえるという話から、井村は、十八世紀のロンドンの牛乳売りのことを思い出す。
これも耳学問で、英国の一人の画家について書かれた評伝の中に出て来る。「いい本だから読んでごらん」といって、教えてくれた友人がいなかったら、井村はそんな本が出ていることも知らずにいただろう。感謝しなくてはならない。(庄野潤三「野鴨<十三>」)
この評伝というのは、桜庭信之の『絵画と文学 ホガース論考』のことである。
次に話は、黍坂にいる和子の子どものことへと移る。
なかなか生えないと心配していた歯が二本生えてきた。
みんなでだるま市へ行ったときには、まだ生えていなかったというところから、話題はだるま市へと発展していく。
晩年の連作の中にも登場する「柿生のだるま市」の始まりが、ここにある。
次に<十四>は「てけし」の話。
「てけし」というのは、和子の大家さんの長男で、良二の中学の同級生であり、同じ陸上競技部で練習をしてきた友だちである。
良二は、たて笛を買いに出かける途中で、てけしと会ったのだが、最後に井村は、たて笛を吹くように良二へ言う。
良二がたて笛を買って来た日の晩、井村は、「あれを吹いてみてくれ」といった。「何でありますか」「あれだ。語れめでし昔を、というのがあるだろう」「まごころ、だよ」と明夫がいった。「語れめでしまごころ、久しき昔を、でしょう」「そうか。要するに、ロング・ロング・アゴーだ。あれを吹いてくれ」(庄野潤三「野鴨<十四>」)
それは井村の家族の愛唱歌の中に入っている曲だったが、井村は歌詞を覚えるのが面倒で、いつまでたってもひとりで歌えない。
それでも、昔のままの、古風でいくらか堅苦しいような歌詞が家の中から聞えて来るのは、好ましい気がする。
「変らないということに、かえって生き生きしたものを覚える」と、井村は感じていた。
呆気ないような夢ではあったが、兄がひとりだけ出て来る夢は珍しかった。
続いて<十五>は、亡くなった兄の夢を見た話から始まる。
朝がた、亡くなった長兄に会って、何かひとこと、ふたこと話す夢を見た。どういう場所で、どういうふうにして会ったかということも、何を自分がいったのかということも、覚えていなかった。呆気ないような夢ではあったが、兄がひとりだけ出て来る夢は珍しかった。滅多に見なかった。目を覚ましたあとには、兄の夢をみたという懐しい心持だけが尾をひいていて、せっかく夢で会ったのに、中身が消えてしまって、どこにもあとかたが無いのを物足りなく思った。(庄野潤三「野鴨<十五>」)
「目を覚ましたあとには、兄の夢をみたという懐しい心持だけが尾をひいていて、せっかく夢で会ったのに、中身が消えてしまって、どこにもあとかたが無いのを物足りなく思った」という一文が、夢のはかなさをうまく表現している。
兄が亡くなる直前、井村は兄の病室に泊まりこんで、不寝番をしたことがあった。
彼が兄の病室に泊ったのは、その晩一回きりで、次に妹と交替する番が来る前に、兄は亡くなった。
つまり、彼が付き添いで泊まった、その翌日に、長兄は亡くなったのだろう。
兄の思い出は、映画を観に連れていってくれたときのことへと繋がっていく。
あれは、中学二年くらいのときだっただろうか、、、
庄野さんが、亡くなった家族を素材にしたときの作品には、名作が多いような気がする。
書名:野鴨
著者:庄野潤三
発行:1973/1/16
出版社:講談社