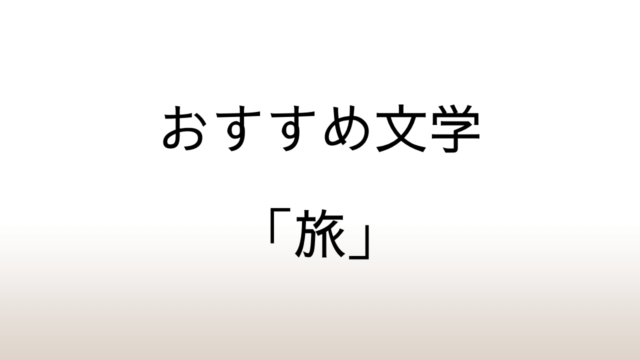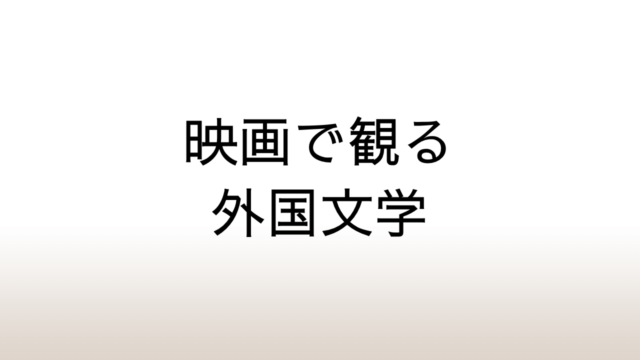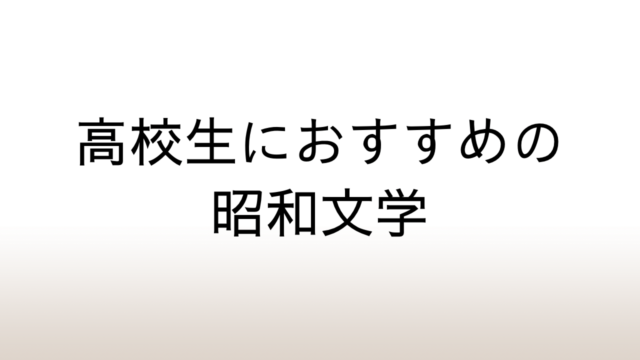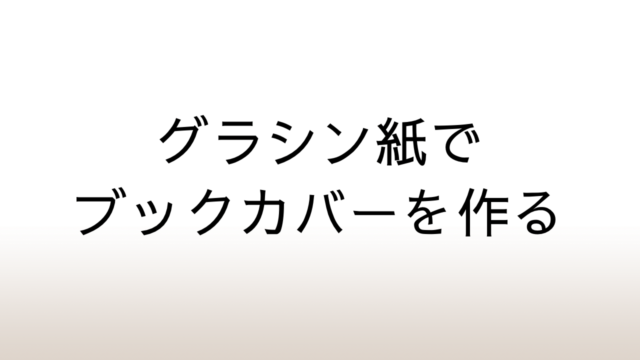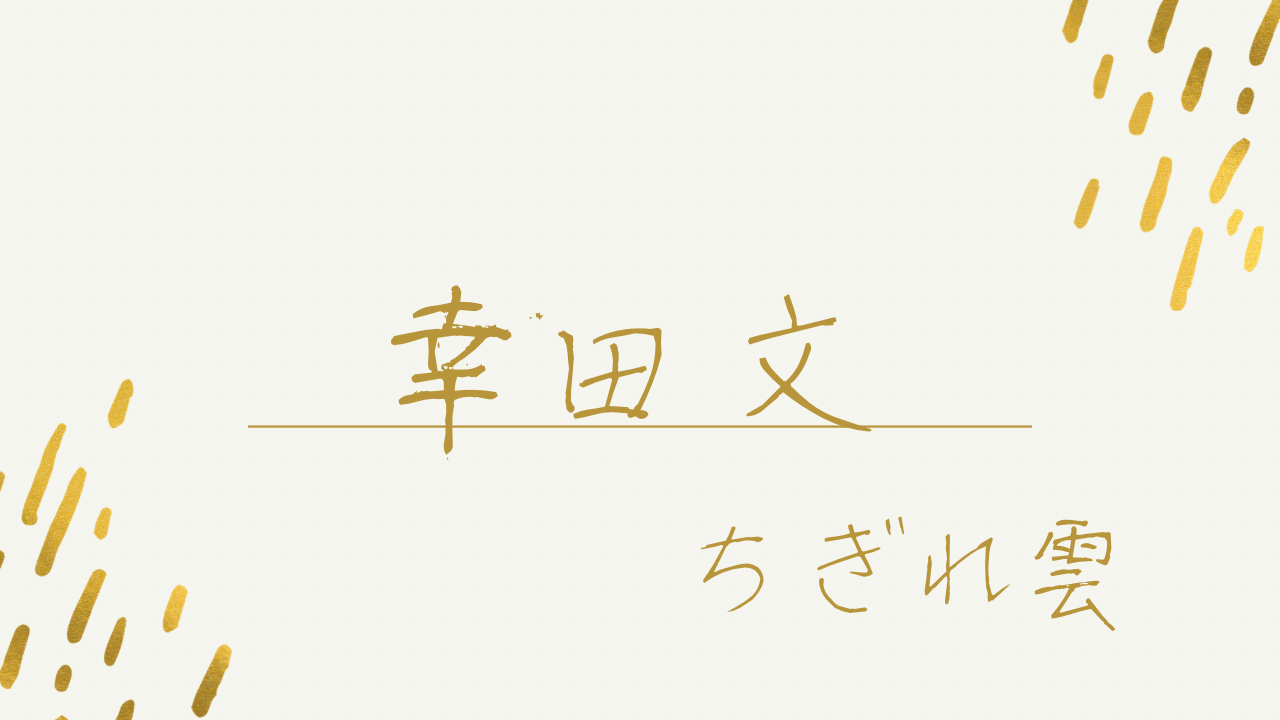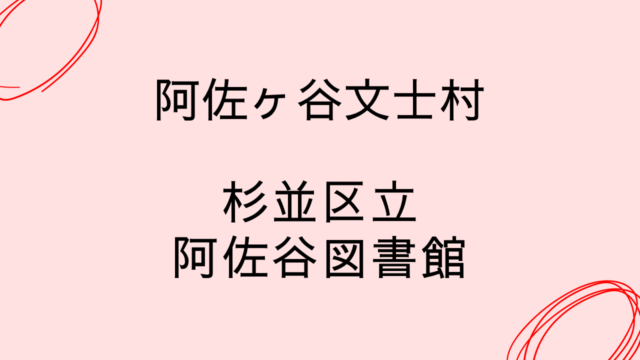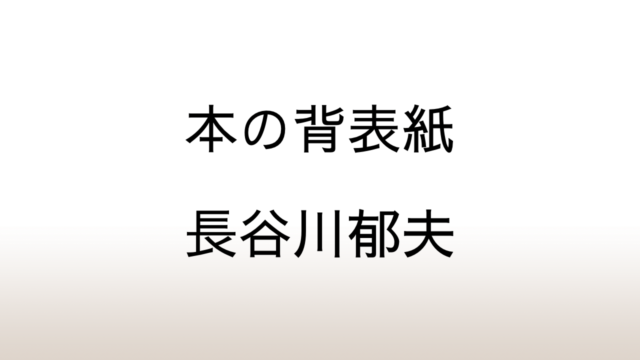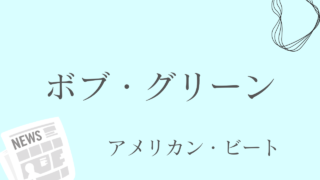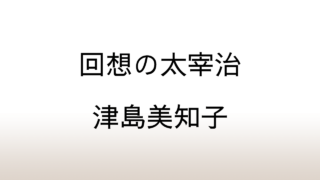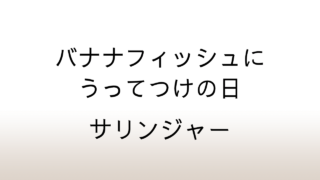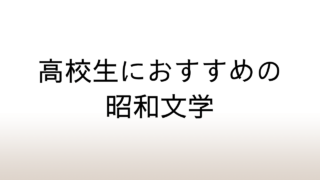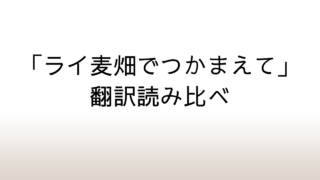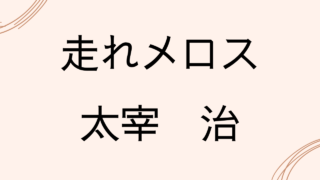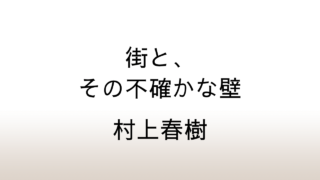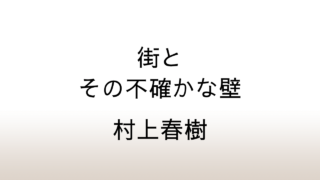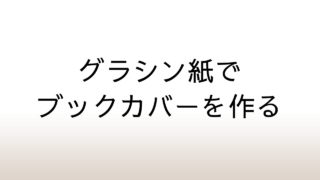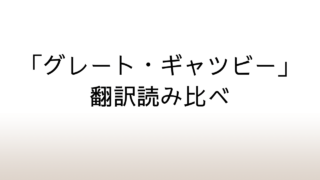「おれが死んだら死んだとだけ思え、念仏一遍それで終る」死の惨さ厳しさに徹し、言葉を押さえて話す病床の父露伴。十六歳の折りに炊事一切をやれと命じた厳しい躾の露伴を初めて書いた、処女作品「雑記」、その死をみとった「終焉」、その他「妹をおもう」「父の七回忌に」「紙」等二十二遍。娘の眼で明治の文豪露伴を回想した著者最初期の随筆集。(背表紙の紹介文より)
書名:ちぎれ雲
著者:幸田文
発行:1993/2/10
出版社:講談社文芸文庫(現代日本のエッセイ)
作品紹介
「ちぎれ雲」は、明治の文豪として知られる幸田露伴の娘、幸田文が書いた随筆集です。
随筆の題材は父親である幸田露伴が多く、厳粛な明治の男親の生き方を伝える名作として知られています。
収録作品は、昭和20年代に新聞や文芸雑誌に掲載されたものがほとんどで、それぞれページは多くないものの、幸田文の美しい日本語で綴られる極上エッセイと言って良いでしょう。
(目次)雑記/終焉/すがの/かけら/手づまつかい/造語家/鴨/れんず/旅を思う/水仙/膳/父の七回忌に/このごろ/てんぐじょう/紙/結ぶこと/ほん/ぜに/二百十日/在郷うた―在郷うた/塔の影/片びらき―/対髑髏のこと///人と作品/年譜/著書目録
本書は『幸田文全集第一巻』(1958年12月・中央公論社刊)を底本として使用し、多少ふりがなを加えて編集されています。
なれそめ
近年の僕の趣味は、講談社文芸文庫の「現代日本のエッセイ」シリーズを読むことです。
講談社文芸文庫の帯には多きな文字で「文学の復権」とか「本物の衝撃」とか書かれていて、実際、文学好きなら一度は読んでおきたい良書名作がラインナップされています。
幸田文の『ちぎれ雲』も講談社文芸文庫の棚に並んでいるものを購入しましたが、幸田文の随筆作品は昔から好きで、「精選女性随筆集」(文藝春秋)なんかでも楽しく読ませてもらっていました。
いずれにしても、随筆好きとして幸田文の随筆集は必ず手許に置いておきたい良書に間違いなく、講談社文芸文庫で揃えられるというのは、とてもうれしいことだと思います。
本の壺
心に残ったせりふ、気になったシーン、好きな登場人物など、僕の「壺」だと感じた部分を、3つだけご紹介します。
突然「おとうさん死にますか」と訊いた
ふと親一人子一人という感情が走って、突然「おとうさん死にますか」と訊いた。「そりゃ死ぬさ」と変に自信のあるような云いかたをし、「心配か」と笑った。(「雑記」より)
幸田文の随筆は、幸田文の生きざまを語りつつ、父である幸田露伴の生きざまを綴っているものがほとんどで、男の生き方を学ぶ上で、非常に多くのヒントを得ることができます。
死の直前まで、幸田文は父・露伴の介添えをしていましたが、病床で吐血する父を看病しながら、幸田文は父の死に面しながら、二人で生きてきた父と子の関係を意識します。
父が亡くなれば、文はたった一人になってしまうという当たり前の事実と、嫌が上でも向き合わざるを得なかったからです。
そんな娘に対して、露伴は「そりゃ死ぬさ」と何事もないかのように、自分の死を淡々と受け入れようとしているところに、露伴の死生観が具現されているように感じました。
おれが死んだら死んだとだけ思え。念仏一遍それで終る。
「おとうさんが殺されるなら文子も一緒の方がいいんです。そこの子だって親と一緒にいたいんです」「いかん。許さん。一と二は違う、粗末は許さん」「いいえ大事だからです」「それが違う。おれが死んだら死んだとだけ思え。念仏一遍それで終る」(「終焉」)
首都空襲を受ける東京都内、爆音が響き渡る中、高齢の父を連れて逃げようとする娘に、露伴は「馬鹿め、そんな処にいて、云っておいたじゃないか、どこへでも行ってろ」と、一人で避難するよう怒鳴りつけます。
父一人置いて逃げることはできないと、文は父を説得しますが、既に死を淡々と受け入れようと覚悟を決めている露伴は「おれが死んだら死んだとだけ思え。念仏一遍それで終る」と、娘の要求をはねつけます。
そして「では、おとうさんは文子の死ぬのを見ていられますか」と問うと、父は、顔を少し崩しながらも「かまわん。それだけのことさ」と言い切ります。
娘を愛さない親はいないことは当然の中、露伴は露伴の死生観をあくまでも通して生きようと、あるいは死のうとしているのです。
父自らも生前、さびしい葬式を予告していた
葬儀の朝、「もし会葬者が百五十あったら、おれは世をひがむ心を撤回する」と、ながく父を知る一人が云った。百五十人はおろか、私の勘定はその三分の一にも足りなかった。父自らも生前、さびしい葬式を予告していたのである。(「すがの」)
幸田露伴は昭和22年7月30日、79歳で亡くなりますが、その葬儀は、近親者によって静かに行われたことが、幸田文の『すがの』には書かれています。
「すがの」とは、国府台の裾にある「菅野」(千葉県市川市)のことで、露伴と文の幸田父子は、戦後、この地の借家で暮らし始めます。
ある雨の夕方のこと、幸田文は「人がすっと擦れ違って行った。かわしたとたんに、ちかっと見られたという気がした。大きな洋服の男が駒下駄に素足で、すぐ曲がって行ってしまった。傘をささず、きつい背なかだった。風に吹きぬけられたようなものが残った」という体験をします。
実は、このときすれ違った男性こそ、当地で暮らす人気作家の永井荷風でした。
同じ地域で暮らしながら、結局、会って話をすることもなかった幸田露伴と永井荷風でしたが、露伴の寂しい葬儀のとき、荷風は斎場の前まで来て黙礼をして去っていたことが分かります。
露伴の回想の中で、永井荷風についても書くことについて許可を得ようと訪れた幸田文に、永井荷風は「そんな固い挨拶なんぞあなた、何でもどんどんお書きなさいよ」と快く応じます。
戦後日本のちょっとした文壇史が、こんなところにも綴られているんですね。
読書感想こらむ
幸田露伴と幸田文は、いわゆる「複雑な家庭」の中で生きてきますが、父と子の愛情の強さは、幸田文の随筆を読んでいると、いろいろな場面で感じることができます。
娘の躾にもひどく厳しい露伴は、真の意味で男が男らしかった時代の「明治の父親像」として映りますが、男というのは、自分にも他人にも厳しくなければならないという、最低限の流儀があったのかもしれません。
日常生活の中で、常に自分を厳しく律しながら、露伴は娘の文をも厳しく律して育てますが、彼らの暮らしの中には、現代の我々が失ってしまったものが、あちこち綴られています。
時代が違うと言ってしまえばそれまですが、少なくとも終戦直後まで、日本人は日本人らしく生きていたんだなということを思い出させてくれます。
そして、そんな日本人らしさを、僕たちは決して失いたくはないものだと、つくづく考えてしまうのです。
まとめ
幸田文の随筆には、幸田露伴の生き方が余すところなく綴られている。
幸田露伴を知らなくても、ひとつの美しい随筆集として間違いなくおすすめ。
昭和20年代を生きる日本人の姿から学ぶことは少なくありません。
作者紹介
幸田文(小説家・随筆家)
1904年(明治37年)、東京生まれ。
父は明治時代に活躍した文豪の幸田露伴。
父の死後、文筆業を開始、処女作『雑記』(昭和22年)を発表したとき、幸田文は43歳だった。