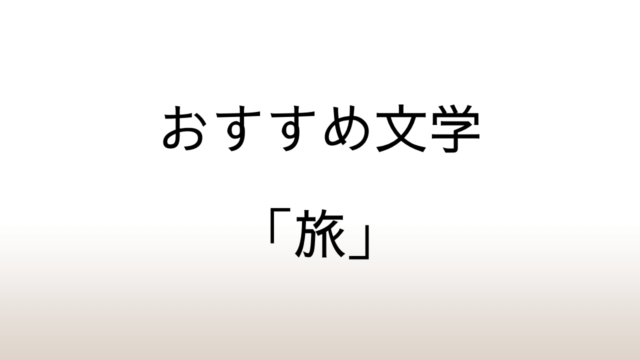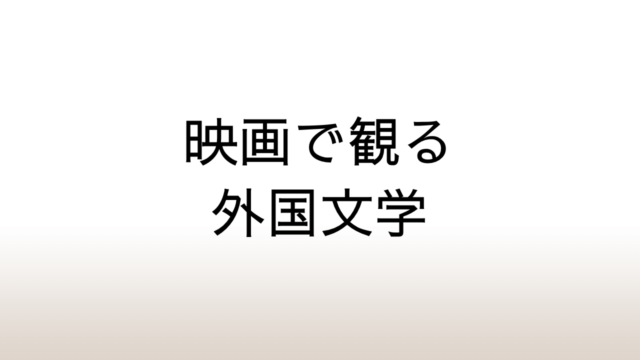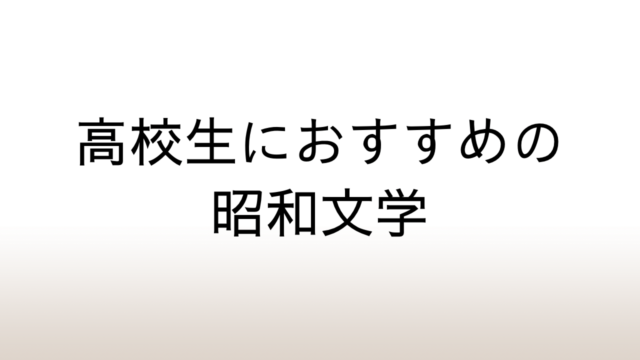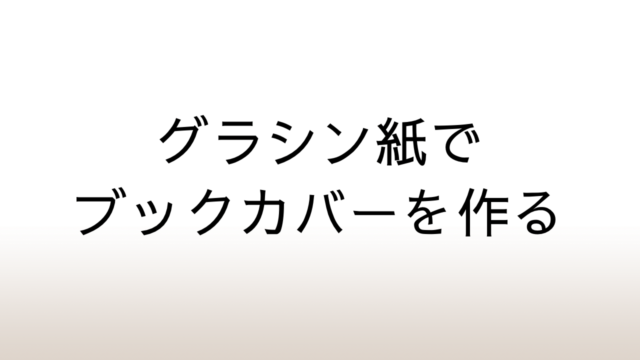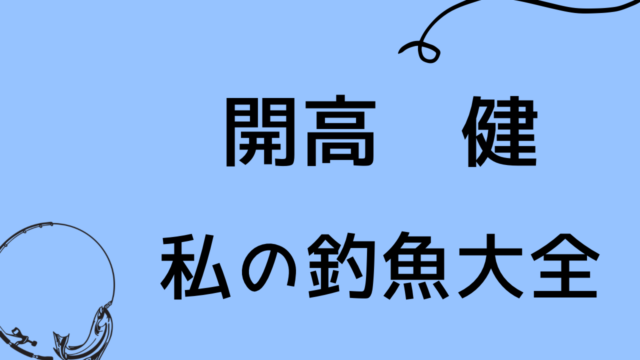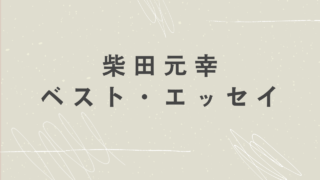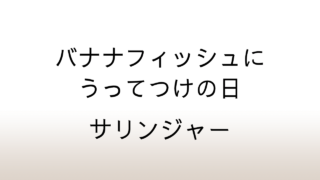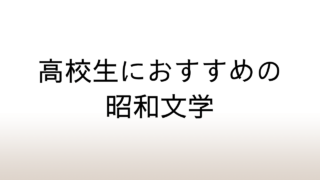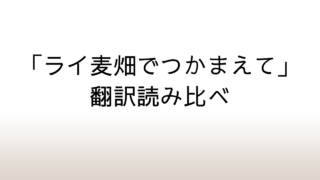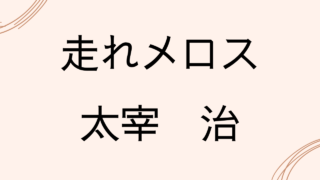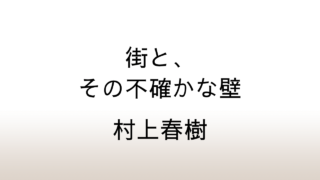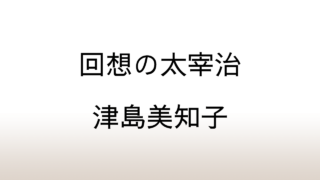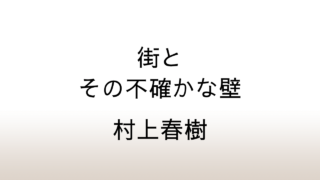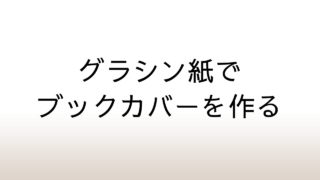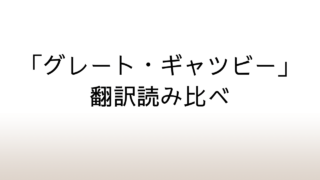志賀直哉が弟子たちに宛てた真情あふれる手紙、伊藤整が講演旅行のときに見せた素顔、府話芸の名人徳川夢声のスピーチの秘訣……。エスプリとユーモアをもって知られる著者が、その長い文学生活のなかで出会った作家たちの思い出と愛読する数々の書物について静かな情熱をこめて語る文学随想集。
書名:回想の本棚
著者:河盛好蔵
発行:1982/12/10
出版社:中公文庫
作品紹介
本書はフランス文学研究家として著名な河盛好蔵が書いたエッセイ集で、文学エッセイ集としては『文学空談(1965年・文藝春秋)』に続くものとなります。
構成として「文学巷談」と「コーズリー」の大きく二つに分かれていますが、「文学巷談」は1972年(昭和47年)に雑誌「新潮」に連載されたもので、「コーズリー」は1975年(昭和50年)に同じく「新潮」に連載されたものから一篇を省いた上で、雑誌「世界」1974年(昭和49年)6月号に掲載された「献辞の話」が追加されています。
<「文学巷談」目次>宇野浩二と象徴派/アンニュイの文学(宇野浩二)/腰の低い文学(宇野浩二)/文学の我鬼(宇野浩二)/やさしいひと(広津和郎)/「子をつれて」の作者(葛西善蔵)/太宰治の文章/文学者夢声(徳川夢声)/伊藤整の詩/梶井基次郎と音楽/梶井と「冬の日」/パリ通信<「コーズリー」目次>志賀さんの手紙/さまざまの証言/私の戦争協力/知らぬが仏/緑雨のアフォリズム(斎藤緑雨)/藤村の勉強(島崎藤村)/フランス語の名人/百年祭そのほか/外国語五十年/献辞の話
1976年(昭和51年)に新潮社から発行されたものを文庫化したものです。
解説は庄野潤三、表紙カバーは吉田勝彦。
なれそめ
僕は「文壇史」というやつが好きです。
「文学史」ではなくて「文壇史」。
文学者たちの公私に渡る活動の記録が文壇史ということになりますが、ありていに言えば作家先生の「ゴシップ」。
どこそこの作家が誰それの嫁を寝盗ったとか、誰それは睡眠薬中毒になって自殺したとか、作家の誰と誰が仲良しで、誰と誰とは仲が悪かったとか、誰それは酒癖が悪かったとか、誰それは酒が飲めない代わりに甘いものに目がなかったとか、そういうどうでも良いゴシップが、僕は好きです。
中学生から20歳くらいまでの間に、日本の近現代の作家の作品を文字どおり乱読していく中で、どうして作家はこんなことを書いたのだろうか、ここに書かれていることは事実なんだろうかというように、作品を深く知りたい一心で調べていった末にたどり着いたのが「文壇史」でした。
その後は、小説を読むよりも作家研究の方が好きになってしまったくらい。
河盛好蔵さんの『回想の本棚』は、河盛さんが見てきた作家たちの素顔が書かれていて、文壇史好きな方にはかなりお勧めです。
明治末期から戦争直後までの、いわゆる「文士の時代」の作家たちがたくさん登場しているところが、近現代の文学好きにはたまりません。
本の壺
全体に非常に内容の濃い作品となっていて、絞り込むのが大変なんですが、今回は僕の好きな作家3人の貴重なエピソードを拾い集めてみたいと思います。
太宰治からの手紙
まずは、みんな大好き、大定番の太宰治から。
河盛さんも太宰治の才能を高く評価していて「あんなつまらない時代に、あれだけの才能を持ちながら、自ら生命を絶つとは全く勿体ないことをしたもので、世のなかのことは思うようにはならないものである」と綴っています。
「僕は太宰さんの文学は嫌いなんです」と言うために、わざわざ太宰治を訪問したのは三島由紀夫。
『道化の華』で第1回芥川賞候補になったとき、この作者には「才はあるが徳がない」と言ってダメ出ししたのが川端康成。
三島も川端も最期は太宰と同じく自殺で亡くなっており「この三人には不思議な因縁があるのではないかとさえ思われてくる」という河盛さんのつぶやきには納得です。
ただし、著者の河盛さんは太宰治の文学作品の熱心な読者ではなかったらしく、「あまりに華々しいジャーナリズムの寵児になってしまったために、ゆっくりと話をする機会もないうちに彼は死んでしまった」と述べています。
河盛さんの手元には太宰治からの2通の手紙と5枚の葉書が残されていますが、太宰らしいなかなか楽しい文面です。
このごろのまた軽薄な騒ぎ方はどうでしょう。私はいっそ保守党に加盟し、第一ばんにギロチンにかかってやろうかと考えています。文化もへったくれもありやしません。馬鹿者どもばっかりです。(太宰治からの手紙、昭和21年1月19日)
手紙の冒頭には「お逢いして、一緒に飲みたく」とあり、井伏鱒二の贔屓の店で一緒に飲んだときのことを思い出したのだろうと、著者は回想しています。
太宰が『斜陽』を書き始める頃、新潮社の応接室で偶然に会った時、夕陽が窓から差し込んでいるのを見ながら「ぼくこんど『新潮』に連載を書きます。題名は『斜陽』というんです」。これです」と言って、窓の外を仰ぐように見たそうです(かっこいい)。
太宰文学の若い読者は彼に十字架ばかりを背負わせたがっている。それも結構だが私は還暦を過ぎた太宰君と馬鹿話をして腹をかかえて笑いたかった。いまの時世は徹底的に笑いのめしたい事象に充満しているからである。(河盛好蔵『回想の本棚』)
仮に太宰が生きているとすれば、この年で63歳だったと、著者は考えていたのです。
洋楽大好きな梶井基次郎
代表作『檸檬』で知られる梶井基次郎は、大の洋楽好きだったそうです。
大正末期から昭和初期にかけての時代、「洋楽」と言えば「クラシック音楽」のことでした。
本書では、河盛さんの愛読書からの引用が多く見られるのが特徴ですが、この章においても、中谷孝雄『梶井基次郎』からの引用が数多く含まれていて、その中には梶井基次郎のクラシック好きについても紹介されています。
「イタリーの歌劇団がやって来たのと前後して、その頃は続々とヨーロッパから音楽家や舞踏家が来演した。提琴のエルマンやハイフェッツを初め、セロのホルマン、ピアノのゴドウスキー、それからロマノフ王朝時代の帝室技芸員であったパヴロウなどであったが、梶井さんはほとんど一つ残さず聞いたり観たりしていた」とあるくらいに、音楽好きだったことが分かります。
著者の河盛さんも同じくらいクラシック好きだったようで、当時の音楽シーンを回想していますが、昭和初期のクラシック音楽には僕も興味があって、一時期ずいぶん熱中したことがあります。
いわゆる「エルマン・トーン」のフレーズで知られるエルマンのヴァイオリンは、いかにも大正浪漫とか昭和モダンの香りがプンプンしていて、当時の小説を読むときのBGMとしては最高にお勧めです。
梶井基次郎も大正10年3月3日に友人の島田敏夫に宛てて「二日夜エルマンと握手す。ああ此感激に過ぐるものなし」と書いています。
こうした梶井基次郎の音楽好きを踏まえて、著者は『城のある町にて』を構成する「ある午後」「手品と花火」「病気」「勝子」「昼と夜」「雨」の各篇はそれぞれ独立していることから、音楽でいうところの「組曲」を、梶井は文学作品として再現してみようとしたのではないかと推測しています。
文士らしいままで逝った葛西善蔵
一連の文学随筆の中には、令和の現在では、あまりその名を聞かなくなってしまった作家も含まれていて、葛西善蔵もおそらくその一人と言って良いでしょう。
「その作品よりも言行録のほうがよく知られていた」とあるように、当時、文壇ではかなりの有名人だったようで、「葛西は小説を書くとき、二行三行一日に書いて、そして「アア調子がついてきた、やめる」といって筆を置くという」話は、かなり有名なエピソードだったみたいです。
戦前の文壇では「調子がついてきたらやめる」とか「一日に二、三行しか書かない」とか「あの作家は遅筆である」といったようなことが、何か作家として尊敬すべき心構えのように考えられていたんですね。
もっとも、佐藤春夫は著書『退屈読本』の中で「寡作もとより結構。遅筆もまた結構。しかし、それは世人の方からこそ珍重すべきことで、作家自身で吹聴すべきことではあるまい」と指摘しているのですが。
葛西善蔵の貧乏な暮らしぶりも、また有名で、山本健吉との対談の中で谷崎精二は「細君が明日の米がないといっても、葛西は平気なんです。一日や二日、水を飲んでも生きてられるというんです。細君が気が変になっちゃったんです。子どもに食べさせるお米がないんですからね。売れるものは売りつくして、硯箱を二十銭で屑屋に売ったというんです。それで細君は国へ帰ったんですね。そのとき葛西は、いっしょに飢え死にしてもいいじゃないかと言った」そうです(『対談・日本の文学』中央公論社)。
こうした暮らしぶりに、長男も「一生おやじのことは考えるのもイヤだ」とこぼしていたそうで、小学生時代に父親と二人きりで暮らしていた鎌倉時代には、一晩家出をしたことさえあったそうです。
もっとも父親の葛西は、そのことを『不良児』(大正10年7月)という小説に仕立て上げていて、「葛西は自分が加害者であると考えては小説の書けない男で、いつも自分が被害者であるという想定の上に立って筆を進めているが、この『不良児』でも自分が少年の上にどういう打撃を与えているかということは書いていない。そこでは『不良児』を持った父の被害しか彼は書かないのである。何の不良であるはずはない。少年は誰にも訴えられない父からの被害に、一人苦悶しながら夜中の海辺をさまよっていたのではないか(広津和郎)」と指摘を受けています。
広津和郎といえば、友人の広津から女性関係の悩みについて打ち明けられたとき、葛西は親身になって相談に乗ってあげたそうですが、後日、この広津の苦悩を題材にした小説が発表されて、広津が激怒するという事件がありました。
一度は和解した二人ですが、葛西が全集の中にこの作品を収録すると知って、広津は再び激怒し、死ぬ間際の葛西を訪れ抗議したそうですが、葛西はほとんどかまっていなかったようです。
葛西善蔵の死の二日前の午前、前日の『読売新聞』に大きく出た「絶望の葛西善蔵」という自分の危篤を報じる記事を読んだとき、当の本人の葛西は「割合に、よく書いてある」と評価したそうです。
芥川龍之介が自殺したとき、「おれは東洋人だから、自殺は絶対にしない。天命を待って死ぬ」と言った葛西善蔵は、41歳のとき、その短い天命を終えました。
読書感想こらむ
河盛好蔵の『回想の本棚』は非常に読みどころの多い随筆集である。
幅広い交友関係をベースに、豊富な読書体験を重ねて書かれているので、それぞれの作家に関する文章が思わぬ意外性を持って描かれている。
いわゆる「文壇よもやま話」ではあるが、日本の近代文学史を学ぶ上で、非常に丁寧な参考書になっていると感じた。
「本の壺」では紹介しきれなかったエピソードがいくつもあって、テーマの作家に関わって様々な作家がひょこひょこと顔を出すから安心できないし、そういう意味でも飽きない随筆集だと言える。
タイトルが『回想の本棚』とあるように、作家の回想文を綴るにあたって、著者の蔵書から取り出してきた書籍を引用して、あの作家はこんなことを言っている、この作家はこんなことを書いているといった紹介が非常に豊富なので、次は、その引用元の本を読みたくなってしまう。
実際に、この随筆集を読み終えた後で、本書の中に登場している書籍を、実際に僕は少しずつ買い足してきているが、なにしろ古い本も多いので、そう簡単に集まるものではないと思った方が良いだろう。
文壇史は文学史の脇の知識ではあるが、作家に対する理解を深めることによって、作品に対する理解を深めることができることは確か。
作家の私生活に関心のある方にお勧めしたい。
まとめ
有名な文士に関わるよもやま話が盛りだくさん。
意外な作家の素顔に触れている貴重な書籍も、本書では数多く紹介されている。
文学好きなら一度は読んでおこう。
著者紹介
河盛好蔵
1902年(明治35年)、大阪生まれ。
雑誌『新潮』編集部顧問のほか、東京教育大学教授としても活躍。
本書執筆時は70歳だった。